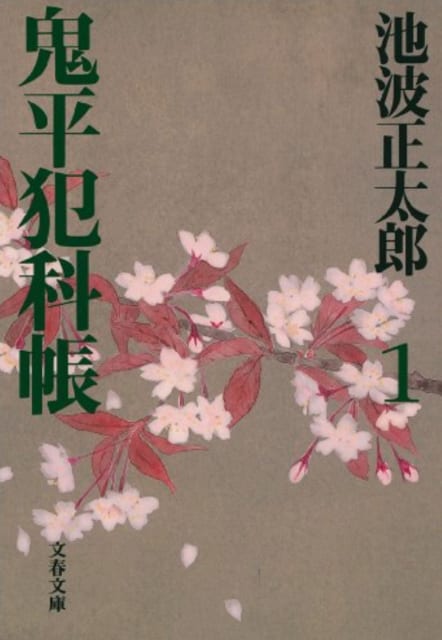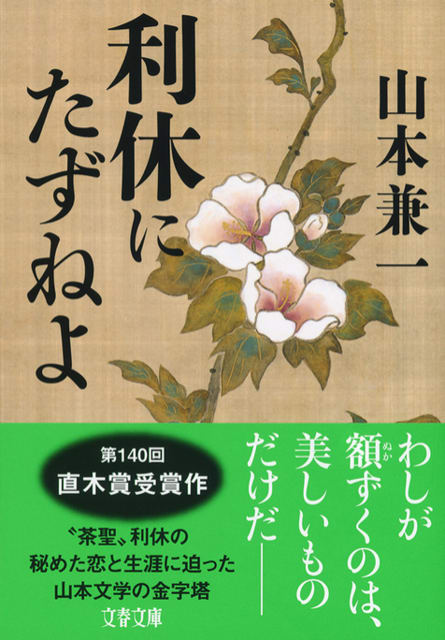@著名な捕物小説「鬼平犯科帳」は実に読みごたえがある。続々と続く事件に対し巧みに解決していく。「鬼」の仕業で盗人犯人等を怖らせ、悪行に走らないように見回る。解決の糸口が悪の一味の一人二人を奉行所側に引き込み密告させることであった。 この江戸時代の盗人任侠の掟(金科玉3か条)として1、盗まれても難儀するものは手を出さぬ事 2、盗みに入るときには人を殺傷せぬ事 3、女子を手篭めにせぬ事 があったらしい。だが、江戸後期になると盗人が変貌し皆殺し、女手篭めにするのは当たり前となり残忍な殺人事件へと繋がっていった。生きていくための租税・身分世相が厳しく、逆に商人が大儲けで贅沢三昧する世の中になった事(格差が広がった)による仕業だったかもしれない。雇われ殺屋浪人には「切り捨て御免」、それは「獣には人間の言葉が通じない」とある。正に現代でも社会の仕組みを乱し、壊し、誰が犠牲となっても自分が正しいという考えを持った人間もいる。社会の変化はある程度認めながら前に進む事が必要だが、人(国)が人(国)の作った掟(約束)を破ることは「切り捨て御免」で社会の秩序を守ることを優先にしても構わないかもしれない。
『鬼平犯科帳』池波正太郎
- 切り捨て御免の権限を持つ幕府の火付盗賊改方の長官長谷川平蔵。盗賊たちには鬼の平蔵と恐れられている。しかし、その素顔は義理も人情も心得た苦労人である。彼を主人公に様々な浮世の出来事を描き出し、新感覚の時代小説として評価高く。
- 「啞の十蔵」
- 盗人の妻が夫婦喧嘩で夫を殺した。その女を庇い、恋仲に。秘密を隠し同心の捜査に協力できなかった事で自刀する。
- 「本所・桜屋敷」
- 平蔵の故郷で恋憧れた女、実は妾子が犯罪の一味になっていた。
- 「血頭の丹兵衛」
- 松平定信は続く天災や飢饉で起こった人心の荒廃と経済危機を武家と農村との結具による(質実剛健)な武家政治を戻すごとく一旦離れた平蔵と組み、盗賊改め役にかえり咲きさせた。
- 「浅草・御厩河岸」
- 同心の密偵になった元盗人が昔の盗人頭から声をかけられ計画を知る。だが盗人同士での行き違いで頭と仲間がお互いに殺戮であい計画は無くなる。
- 「老盗の夢」
- ある若い女と恋仲になった老盗人が目覚め、最後の盗人を江戸で計画を立てる。だが、女が盗人の仲間と恋仲になりそれを恨んだ双方が殺しあう。
- 「暗剣白梅香」
- 仇討ちを目的に江戸に出たが敵討ちが見つからず殺し屋になる。ある日平蔵殺しを頼まれ平蔵の居る飲み屋に入るが、実はそこの主人が敵討ちで逆に殺される羽目になる。
- 「座頭と猿」
- 「むかしの女」
- 鬼の平蔵と言われる所以は盗賊で刃向かう者を容赦なく切って捨て、拷問を常として白状させるやり方で江戸の盗人事件は減った。だが昔ながらの人殺しをしない盗人から皆殺しを仕掛ける盗人は増えた。いくつかの盗人の頭等の住処を探し出す、それは拿捕した盗人仲間を味方に引き入れ密告させる方法で事件を解決する方法を採用した。だが、盗人仲間かあら恨まれ狙われた。切り捨て御免の言い訳で「浪人崩れには打つ手がないんだよ。おそらく大店へのゆすりをかけたのもこいつらだろうが、そのゆすり一つ見てもわかる。まるで獣だよ。世の中の仕組みが何もわかっていねえのだ。獣には人間の言葉が通じねわさ。刈り取るよ理他に仕方はあるまい。」