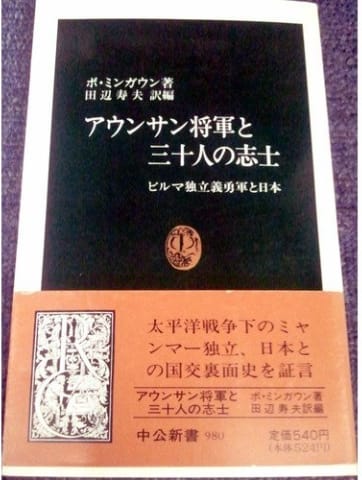@健康医療で処方箋・・「薬浸け」の患者が増えている。日本は稀に見る「薬浸け」国民になっているという調査報告書(日本では世界の薬の40%を消費、一人当たりの消費は世界一・トップは降圧剤、睡眠薬に精神安定剤だと言う) 最近薬を止めて「全てサプリメントに変えた」と言う人に出会ったが何と1日8種類を服用すると言う。「効用・効果はどうですか」と聞くと「サプリメントだから即効は認められないが効用を信じて長期服用するんだ」と言う。薬より体にはましだと言う意見だったが、この書にもある「気は病から」もあるように1、病気の誤認識 2、体の不調は気持ちと精神ストレス 3、自愛・愛情欠如等が原因で「安心」材料としての薬は特効薬だが、最近は副作用も多いと聞く。なるべく「薬」は服用しないほうがいい、人の体は自然に回復できる治癒力も持ってると信じている。
『仁術先生』渡辺淳一
- 東京下町の個人病院に勤務することになった円乗寺優先生。堅苦しい大学病院から逃れてやってきた。専門は外科だが、内科、婦人科、なんでも診る事となる。酒好きな先生は、ある晩近くの寿司屋さんに入ったが、店の青年が自分の患者であることに気づく。彼は他人には言えない病気の持ち主だった。人情味あふれる仁術先生の診察と活躍を描く。大学病院を辞めた理由は、1、学会戦隊としては、研究論文筆頭者の名の名誉は全て教授に吸い取られる 2、人間関係の複雑さに「大学なんかにいると人間はだんだん馬鹿になるだけさ」
- 「梅寿司の夫婦」(医療の誤認識)
- 寿司屋の青年が独り立ちし結婚するというストーリー、だが、梅毒で彼女にも、お客にも話せない理由があった。 実は彼女も梅毒であった事で互いの病気を隠し通すことにした。結果、血液検査のマイナス結果が出るまで何もしないことを約束させる。梅毒は手からの伝染等をはないと説得させ、マイナスになれば問題ないと双方に心配事を無くさせた。
- 「特効薬」(愛情欠如)
- 「妻が倒れた」と往診に出かけ診察、ところが原因がヒステリー。それには薬はないと判断したが、その原因は子供がいない事だった。夫婦ともに5分5分の理由があり夫婦の営みが無い所為だと分かった。
- 「保険ききません」(精神的ナイーブ)
- 若い夫婦に子供ができない。できない理由は、男はナイーブだから精神的にインパクトある言葉、事をしないように妻に伝える。看護婦の努力によりなんとか回復させ、薬は不要となった。
- 「医は仁術」と言っても
- 明治・大正次代の医者は「自分は人の命を預かる選ばれた少数ものだという自負と矜持を持っていた事」
- 法が不備な時代の義理人情として人々を助けるが金持ちと貧乏との差をつけ奉仕した。現代、開業医はあまりに儲け主義だし、大学病院は技術偏重と学問的興味に走りすぎている。かなりわがままな怠け者医者もいる。合理主義、即物主義の波が渦巻いて、医療におけるモラルの欠如が見られる。医学の祖ヒポクラテスは「医者が直すのは病気ではなく、患者である」と言った。