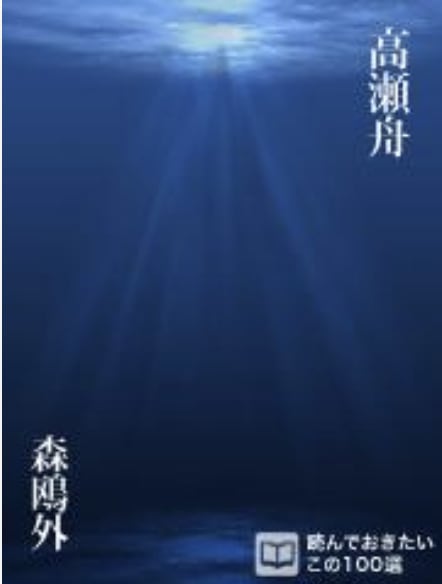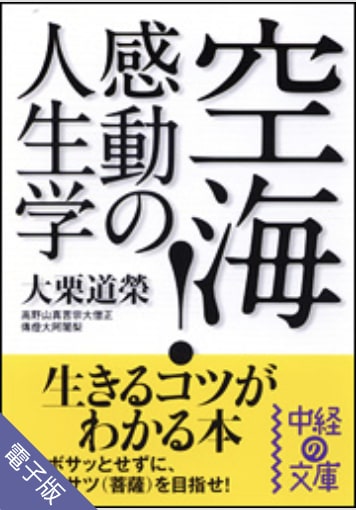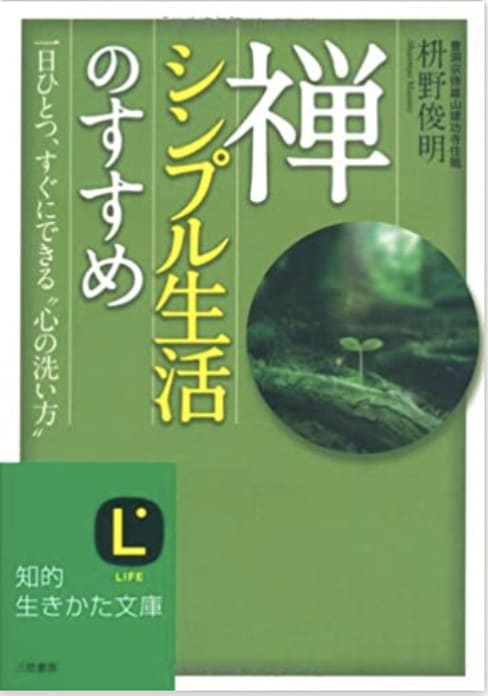@「生活をシンプルに」とは自分を如何に変えるか、変わるかである。「禅」に多くのヒントがある。ここに100項目列記してみた。 今の時代、自分にないものを求め、変わりたいと望むことが多いが、「自分にないものを求めない」とか、「変わることを恐れない 、変化するから美しい」。 どれもシンプルで今すぐにもで出来る、だが「継続」が課題になるかもだ。
『禅、シンプル生活のすすめ』枡野俊明
変化に「気づく」―すべては、この「気づき」から始まる、息をゆっくりと吐いてみる―マイナスの感情を退治する方法、脱いだ靴を揃える―すると、生き方が美しくなるなどなど、一日ひとつ、すぐにできる“心の洗い方”
●「習慣」をちょっと変えてみる
・ボーッとする時間を持とう 慌てず、焦らず、あるがままの自分で
・15分、早く起きてみる 忙しいとは「心をなくす」事
・朝の空気をしっかり味わう 1日として同じ日はない
・脱いだ靴を揃える 心の乱れは足元に現れる
・要らないものを捨てる 「得る」よりも「手放す」ことが先 (洗心)
・デスクの上を整える あなたのデスクは、あなたの心を映し出す鏡
・一杯のコーヒーを丁寧に淹れる 労力を省くのは、人生の楽しみを省く事
・字を丁寧に書く 他人に向けている目を、自分に向ける
・大きな声を出してみる お腹から声を出す事で、脳が目覚める
・食事を疎かにしない 喫茶喫飯・一心に食べること
・食事では、一口ごとに箸を置く 禅の修行とは、座禅を組むことだけではない(五観の偈)
・野菜断食のすすめ 高僧の居住まいが美しい理由
・好きな言葉を探す 本来無一物・元々何ももっていない
・持ち物を減らす 物の命を「使い切る」という発想
・部屋をシンプルに整える 「簡素」と「質素」の違い
・ベランダに小さな庭を作る どこにいても心を磨くことはできる
・裸足で生活してみる なぜ修行僧は裸足で生活するのか
・息をゆっくり吐いてみる 呼吸を変えれば心も変わる (吐く行為が先)
・座禅を組む 人は体を動かしながら思考することはできない
・立禅をする 簡単に気合を入れる方法
・考えても仕方のないことは考えない ふと「自分を忘れる」瞬間
・気持ちを上手に切り替える 「必要な無駄」もある
・ゆっくりと呼吸する 心を整えるには、まず姿勢と呼吸を整える(調身・調息・調心)
・手を合わせる 「合掌」の意味 左手は自分、右手が相手
・一人の時間を持つ 「市中の山居」のすすめ
・自分の手で自然に触れる 道端の石を拾って、匂いを嗅いでみる
・夕焼けを眺めに行く 自分の「夕焼け階段」を探してみる
・今日できることは、今日やる ある名僧に遺言に学ぶ
・眠る前は嫌いなことを考えない 自分をリセットする時間
・今できることを一生懸命やる 雲を追いかけても捕まえることはできない
●ものの「見方」を変えてみる
・「もう一人の自分」に気づく 「主人公」は無限の可能性を持っている
・起こっていないことで悩まない 不安、それはいったいどこにある
・仕事を楽しむ 喜びはいつも、自分の中にある
・ただ没頭してみる 「無念無想」心を空っぽに、心をどこにも置かず
・「目の前のもの」に囚われない 「1日作らざれば1日食らわず」
・人のせいにしない その仕事も一つの「出会い」です
・人と比べない 物事は、続けて行くことだけが難しい
・自分にないものを求めない 「結果」を出す一番の近道
・時には、考えるのをやめてみる 「心の間」から生まれるもの
・けじめをつける 心の中に「けじめ」という門を作る
・座禅会に参加してみる 悩みもストレスもお寺に置いて帰ればいい
・一輪の花を育てる 自然の世界は、毎日が新しい
・スタートを正す 「いいこと」を周りにたくさん起こす法
・自分自身を大切にする お守りは自分の分身
・シンプルに考える 一見、魅力的に見えても・・・(1行三昧=一つのことに邁進)
・変わることを恐れない 変化するから美しい
・変化に「気づく」 自分を「定点観測」する効果
・「考える」よりも「感じる」 「小さな変化に気づく人」の強み
・「もったいない」と言う心を忘れない 「禅の心」とは何か
・一つの見方に囚われない 「見立て」という考え方
・自分の頭で考える 「知識」と「知恵」は似て非なるもの
・自分を信じる 可能性は信じる心が生み出すもの
・悩むより動く 自分で心配の種を作り出している
・しなやかな心を持つ 強い心とは、しなやかな心
・体を動かす 体を動かして初めてわかること
・時を待つ 日本人の「マイペースの心」
・物との縁を大切にする 物を大切にするのは、自分自身を大切にすること
・ただし静かに座ってみる 庭を前にすると無意識に座りたくなる理由
・頭の中を空っぽにしてみる 「足す」のではなく「減らす」効用
・「禅の庭」を楽しむ 禅のにはには「癒しの力」がある
●人との「関わり方」を変えてみる
・人に尽くす 悩みはどこから生まれるのか (無常無我)
・「三毒」を捨てる 欲張らない、イライラしない、物事の道理を知る(貪・瞋・痴)
・「おかげさま」の気持ちを持つ たった一言に温かい心が詰まっている
・理屈を押し付けない 「門の前の打ち水」に心を感じる
・言葉でなく、心を伝える なぜ禅画は墨で描かれるのか
・相手の長所に目を向ける 庭も人間関係も「調和」が大事
・一人の人と深く付き合う 一つの出会いに集中して (一期一会)
・タイミングをよくする 急ぎすぎても、のんびりすぎてもいけない(啐啄同時)
・皆に好かれる必要はない 囚われない、偏らない、拘らない
・無理に白黒つけない 「白か黒か」にこだわると「灰色」の美しさを忘れる
・「あるがまま」をみる 好き嫌いで悩まない一番の方法
・上手に距離を置く 「八風吹けでも動ぜず」
・損得を考えない ウマが合う人、合わない人
・言葉だけに囚われない 相手の言葉に「心」を寄せるということ
・人の意見に振り回されない 決断力とは、自分を強く信じる力
・信念を持つ お年寄りの話の中に「生きるヒント」を見つける
・庭と会話する 「わび・さび」ってこういうことです(思いやりの心を持つ)
・人を喜ばせる 日本人のもてなし・食卓に「時間の流れ」を演出する(旬な食材)
・家族が集まる日を作る 「本当に大事なもの」に気づく場所
・お年寄りの話を聞く ご先祖がひとりかければ自分は存在しない
●「今」「この瞬間」を変えてみる
・「今」を生きる 「過去」より「今」に目を向ける
・平凡な1日にこそ、感謝する 「親死に、子死ぬ」これが一番幸せ
・「守られている」ことを意識する だから勇気を持って前に進みなさい
・前向きに受け止める せっかく今日も生きているのだから
・欲張らない 「それは本当に必要なものですか」(足るを知る=知足)
・物事を「善悪」で分けない 呼吸するのに好き嫌いもありません
・事実は事実として受け止める 「諦める」のでなく「覚悟を決める」
・「答え」はひとつではない なぜ、禅問答をするのか
・「方法」もひとつではない たとえ同じ答えに行き着くとしても
・ひけらかさない 黙っていても伝わるのが「本当の魅力」
・お金に縛らなれない お金の悩みから自由になる言葉
・不安なときほど、自分を信じる 不安にも表と裏の顔がある
・季節の移ろいを感じる これが世の中にある「唯一の真理」
・何かを育ててみる 「人生で大切にすべきこと」を知る
・「自分の声」に耳を傾ける 「枯山水」は隠遁生活の象徴
・1日1日を大事に生きる 自分らくしない時間は空っぽ
・命を大切に生きる 「自分の命」でもあなたの所有物ではないのです
・準備を怠らない チャンスを手にする人、逃す人
・死に様を考える 幸せはすぐ近くにある
・「今」「このとき」に力を出し切る 見事に「今日」を生き切った私の父