富山県から石川県七尾に入った。本州の日本海のほぼ中央。富山、石川、福井で北陸三県を構成している。
県名は、廃藩置県後一時的に県庁が置かれ加賀国石川郡美川町の群名を取ったという。
能登と加賀の旧国名は、現在でも二分した地域として広く親しまれている、七尾は、県北部七尾南湾に面する市で、七尾城山の連なる七つの
尾根に由来する。
718年能登国が誕生し、741年越中国に併合されたが、757年戻っている。室町時代には、能登護「畠山」氏の居城があり畠山文化が栄えた。
1582年前田利家公が港に近い小丸山に城を移して、七尾市街地の基礎が出来上がったという、藩政時代には、北前船の寄港地、海坊の中心として栄え、
七尾軍艦所が置かれている。
現在も、能登半島最大の商圏地で、造船、製材、コンクリート、等の工業郡があり、七尾港のカキ養殖は知られている。
湾には小島、青島、机島、松島、など能登島一帯は、国定公園に属している。
朝の静かな七尾湾 大漁の漁船帰り船


「石動山」は、紀元前の崇神天皇とも717年とも言われ、延喜式に伊須流岐比古神社として登場する歴史ある山で、加賀、能登、越中の山岳信仰の
拠点霊場として 栄え、石動山に坊院を構えた天平寺は、天皇の御撫物の祈祷をした勅願所であった。太平記や太閤記にも記されている。
南北朝時代には宮方の越中国司中院定清をかくまったため、足利尊氏の命を受けた同国守護普門俊清に焼き討ちされてている。
越後の上杉方についていた能登畠山氏旧臣が蜂起し、天平寺衆徒と共に石動山に立て籠った為、前田利家、佐久間盛政、長連龍らの織田軍に焼き討ちされ、
再び全山焼亡した。このときの焼き討ちは、主君織田信長の比叡山延暦寺焼き討ちに似ているともいわれ、数百人の法印のみならず児童子まで撫で斬りにしたとか
、千六十の首を山門の左右に掛け並べたなど、凄惨な弾圧がなされたとある。
国道から石動山へ



難攻不落の「七尾城跡」は、山の380mにある山城跡、1406年畠山満則が能登国の守護職に任ぜられた事により始まり、9代義春で約170年続いた。
数代にわたって拡張され、急斜面の地形の城も1577年、上杉謙信の侵攻で落城している。
後に、前田利家が石垣、土塁などの整備し七尾の海、町など眺望がすばらしい。
国府のあった七尾 800年以上さかのぼって


七尾城を追放された、畠山義綱・徳祐父子は越後の上杉氏を頼り、度々能登に侵入するが、七尾方の反撃にあい、ついに能登入国は果たせなかった。
1574年になると19歳に達していた義慶は、遊佐続光や温井景隆ら重臣たちに毒殺されてしまう。
義慶の後は弟義隆が継ぐが。義隆はわずか2年で、これも重臣連に暗殺されてしまう。(義慶と義隆は同一人説もある)
越中は1573年にそれまで越中の一向一揆衆が頼みとしていた武田信玄が没したことにより、上杉謙信が一気に攻勢に出て平定してしまっていた。
一方越前の朝倉氏は織田信長に滅ぼされ、信長軍は柴田勝家を大将にして加賀南部まで進出してきていた。
加賀の地では謙信、信長の両雄に加えて一向一揆が絡み、複雑な様相を呈していた。
1575年になると謙信は、加賀進軍の前に後方の安定を図るために能登を平定する作戦に出た。七尾城に対して開城して謙信旗下に加わるよう使者を派遣して説いた。
事実上の降伏勧告である。七尾城の重臣たちはこれを拒絶、上杉謙信は七尾城を囲んだ。
ぽつんと一人の古城 七尾の街 熊が出ないかと不安

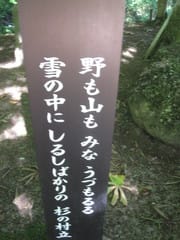

畠山義続の子義春は、上杉家に人質に出されており、その後謙信の養子となり、上杉一門の上条氏を継ぎ上条政繁と名乗っていたが、のちに上杉家を去り、
秀吉次いで家康に仕えた。
義春の子景広は関ヶ原後再び上杉家に仕え、畠山に復姓し上杉家中で最上席を有した。
土塁 石垣


「山の寺院群」は、七尾市にある寺院の総称で、1581年、前田利家が奥能登地域からの七尾城の防御を目的に、浄土真宗を除く各宗派の寺院を防御陣地
として移転配置した。設置当初は29の寺院が存在したが、現存する寺院は16寺、寺院間を結ぶ山道は「瞑想の道」と呼ばれ、観光・散策コースとなっている。
毎年秋に「山の寺まつり」が開催される。
北陸の特徴は、お寺を城の守城の一部に この一画、寺、寺である



能登の国府があった七尾の町・寺院群を歩くと、古きを感じる。
森に囲まれた参道、山道



前田利家が能登の領主になった約400年前、 それまで拠点であった七尾城から小丸山城に移し、その際に、 能登地域からの攻撃を防ぐため、桜川を
内堀として29ヶ寺を 防御陣地としたところから山の寺寺院群の歴史が始まった。
古寺が多いが ジーンズ姿の住職が説法する寺も



一寺に時間をかけていると回りきれない


「能登島」は、市の七尾湾を塞ぐ形で浮かぶ島。面積46.78km²。周囲長71.9km。一島で一町(能登島町)だったが、2004年合併により七尾市の一部になった。
能登半島国定公園に含まれる。
島によって隔てられた島の三方の海を、それぞれ七尾北湾、七尾西湾、七尾南湾とよび、大口瀬戸によって穴水町と、三ヶ口瀬戸、屏風瀬戸及び小口瀬戸
によって七尾市の半島本土側と対する。能登島大橋が屏風瀬戸に、中能登農道橋が三ヶ口瀬戸に架かる。また、小口瀬戸の対岸には観音崎がある。
能登島の中央に、「須曽蝦夷穴古墳」がある、一風変わった古墳として有名で、一辺20m弱の四角い墳丘には2基一対の石積み墓室(横穴式石室)があり、
板石を巧みに積み上げてドーム型の墓室をつくる技法は、朝鮮半島の古墳にも通じるとされ、全国的にも珍しいもの、古墳が造られたのは7世紀中頃、
東アジア社会の激動期であった。出土品や発掘中の写真、島内の遺跡出土品なども展示してある。
初めての能登島に


遺物は、 土師器+須恵器+銀象嵌円頭大刀+ほぞ穴鉄斧+刀子。銀象嵌円頭大刀装具+ほぞ孔鉄斧+須恵器など。
島内でも、ここは、湾内、内浦が一望出来る。島内には、道の駅、ガラス工房、水族館、ゴルフ場などがある。
島か見る湾と和倉温泉街



「先崎神社」能登島須曽町に鎮座、神社は、七尾湾に浮ぶ能登島・南側に鎮座しており、七尾湾を見下ろす景色の良い神社で、遠くに能登半島と島を
結んでいる能登島大橋が見る。祭神は、天太玉命、創立の年代不詳であるが、往古より産土神として篤く崇敬されてきたと思われる。
能登島の鎮守 先崎神社 拝殿



「能登島大橋」は、市の石崎町と能登島町須曽を結ぶ全長1,050mの大橋、1982年に開通した。
橋のデザインには、能登半島国定公園の恵まれた自然景観との調和し、七尾湾のおだやかな風景にとけこんだ優美な曲線が印象的であった。
公園から見た能登島大橋 向かいが能登島


「能登半島国定公園」は、石川県・富山県を跨ぐ、能登半島の海岸を主体に指定されている国定公園。
日本海側の“外浦”と富山湾側の“内浦”で対称的な景観が見られる。指定面積は9,672ha。1968年に指定された。
七尾湾 港の住宅街


次回は、石川県輪島方面へ。
県名は、廃藩置県後一時的に県庁が置かれ加賀国石川郡美川町の群名を取ったという。
能登と加賀の旧国名は、現在でも二分した地域として広く親しまれている、七尾は、県北部七尾南湾に面する市で、七尾城山の連なる七つの
尾根に由来する。
718年能登国が誕生し、741年越中国に併合されたが、757年戻っている。室町時代には、能登護「畠山」氏の居城があり畠山文化が栄えた。
1582年前田利家公が港に近い小丸山に城を移して、七尾市街地の基礎が出来上がったという、藩政時代には、北前船の寄港地、海坊の中心として栄え、
七尾軍艦所が置かれている。
現在も、能登半島最大の商圏地で、造船、製材、コンクリート、等の工業郡があり、七尾港のカキ養殖は知られている。
湾には小島、青島、机島、松島、など能登島一帯は、国定公園に属している。
朝の静かな七尾湾 大漁の漁船帰り船


「石動山」は、紀元前の崇神天皇とも717年とも言われ、延喜式に伊須流岐比古神社として登場する歴史ある山で、加賀、能登、越中の山岳信仰の
拠点霊場として 栄え、石動山に坊院を構えた天平寺は、天皇の御撫物の祈祷をした勅願所であった。太平記や太閤記にも記されている。
南北朝時代には宮方の越中国司中院定清をかくまったため、足利尊氏の命を受けた同国守護普門俊清に焼き討ちされてている。
越後の上杉方についていた能登畠山氏旧臣が蜂起し、天平寺衆徒と共に石動山に立て籠った為、前田利家、佐久間盛政、長連龍らの織田軍に焼き討ちされ、
再び全山焼亡した。このときの焼き討ちは、主君織田信長の比叡山延暦寺焼き討ちに似ているともいわれ、数百人の法印のみならず児童子まで撫で斬りにしたとか
、千六十の首を山門の左右に掛け並べたなど、凄惨な弾圧がなされたとある。
国道から石動山へ



難攻不落の「七尾城跡」は、山の380mにある山城跡、1406年畠山満則が能登国の守護職に任ぜられた事により始まり、9代義春で約170年続いた。
数代にわたって拡張され、急斜面の地形の城も1577年、上杉謙信の侵攻で落城している。
後に、前田利家が石垣、土塁などの整備し七尾の海、町など眺望がすばらしい。
国府のあった七尾 800年以上さかのぼって


七尾城を追放された、畠山義綱・徳祐父子は越後の上杉氏を頼り、度々能登に侵入するが、七尾方の反撃にあい、ついに能登入国は果たせなかった。
1574年になると19歳に達していた義慶は、遊佐続光や温井景隆ら重臣たちに毒殺されてしまう。
義慶の後は弟義隆が継ぐが。義隆はわずか2年で、これも重臣連に暗殺されてしまう。(義慶と義隆は同一人説もある)
越中は1573年にそれまで越中の一向一揆衆が頼みとしていた武田信玄が没したことにより、上杉謙信が一気に攻勢に出て平定してしまっていた。
一方越前の朝倉氏は織田信長に滅ぼされ、信長軍は柴田勝家を大将にして加賀南部まで進出してきていた。
加賀の地では謙信、信長の両雄に加えて一向一揆が絡み、複雑な様相を呈していた。
1575年になると謙信は、加賀進軍の前に後方の安定を図るために能登を平定する作戦に出た。七尾城に対して開城して謙信旗下に加わるよう使者を派遣して説いた。
事実上の降伏勧告である。七尾城の重臣たちはこれを拒絶、上杉謙信は七尾城を囲んだ。
ぽつんと一人の古城 七尾の街 熊が出ないかと不安

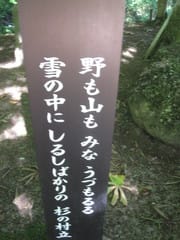

畠山義続の子義春は、上杉家に人質に出されており、その後謙信の養子となり、上杉一門の上条氏を継ぎ上条政繁と名乗っていたが、のちに上杉家を去り、
秀吉次いで家康に仕えた。
義春の子景広は関ヶ原後再び上杉家に仕え、畠山に復姓し上杉家中で最上席を有した。
土塁 石垣


「山の寺院群」は、七尾市にある寺院の総称で、1581年、前田利家が奥能登地域からの七尾城の防御を目的に、浄土真宗を除く各宗派の寺院を防御陣地
として移転配置した。設置当初は29の寺院が存在したが、現存する寺院は16寺、寺院間を結ぶ山道は「瞑想の道」と呼ばれ、観光・散策コースとなっている。
毎年秋に「山の寺まつり」が開催される。
北陸の特徴は、お寺を城の守城の一部に この一画、寺、寺である



能登の国府があった七尾の町・寺院群を歩くと、古きを感じる。
森に囲まれた参道、山道



前田利家が能登の領主になった約400年前、 それまで拠点であった七尾城から小丸山城に移し、その際に、 能登地域からの攻撃を防ぐため、桜川を
内堀として29ヶ寺を 防御陣地としたところから山の寺寺院群の歴史が始まった。
古寺が多いが ジーンズ姿の住職が説法する寺も



一寺に時間をかけていると回りきれない


「能登島」は、市の七尾湾を塞ぐ形で浮かぶ島。面積46.78km²。周囲長71.9km。一島で一町(能登島町)だったが、2004年合併により七尾市の一部になった。
能登半島国定公園に含まれる。
島によって隔てられた島の三方の海を、それぞれ七尾北湾、七尾西湾、七尾南湾とよび、大口瀬戸によって穴水町と、三ヶ口瀬戸、屏風瀬戸及び小口瀬戸
によって七尾市の半島本土側と対する。能登島大橋が屏風瀬戸に、中能登農道橋が三ヶ口瀬戸に架かる。また、小口瀬戸の対岸には観音崎がある。
能登島の中央に、「須曽蝦夷穴古墳」がある、一風変わった古墳として有名で、一辺20m弱の四角い墳丘には2基一対の石積み墓室(横穴式石室)があり、
板石を巧みに積み上げてドーム型の墓室をつくる技法は、朝鮮半島の古墳にも通じるとされ、全国的にも珍しいもの、古墳が造られたのは7世紀中頃、
東アジア社会の激動期であった。出土品や発掘中の写真、島内の遺跡出土品なども展示してある。
初めての能登島に


遺物は、 土師器+須恵器+銀象嵌円頭大刀+ほぞ穴鉄斧+刀子。銀象嵌円頭大刀装具+ほぞ孔鉄斧+須恵器など。
島内でも、ここは、湾内、内浦が一望出来る。島内には、道の駅、ガラス工房、水族館、ゴルフ場などがある。
島か見る湾と和倉温泉街



「先崎神社」能登島須曽町に鎮座、神社は、七尾湾に浮ぶ能登島・南側に鎮座しており、七尾湾を見下ろす景色の良い神社で、遠くに能登半島と島を
結んでいる能登島大橋が見る。祭神は、天太玉命、創立の年代不詳であるが、往古より産土神として篤く崇敬されてきたと思われる。
能登島の鎮守 先崎神社 拝殿



「能登島大橋」は、市の石崎町と能登島町須曽を結ぶ全長1,050mの大橋、1982年に開通した。
橋のデザインには、能登半島国定公園の恵まれた自然景観との調和し、七尾湾のおだやかな風景にとけこんだ優美な曲線が印象的であった。
公園から見た能登島大橋 向かいが能登島


「能登半島国定公園」は、石川県・富山県を跨ぐ、能登半島の海岸を主体に指定されている国定公園。
日本海側の“外浦”と富山湾側の“内浦”で対称的な景観が見られる。指定面積は9,672ha。1968年に指定された。
七尾湾 港の住宅街


次回は、石川県輪島方面へ。









