1477年,山内家家臣・長尾景春が主君上杉顕定に反乱を起こし山内顕定を上野に追い、1478年、には長尾景春に味方した古河公方・成氏と山内顕定の間に和睦が成立。
「長尾景春の乱」は扇谷家の領国武蔵において展開されているが、扇谷家家宰太田道灌は乱の平定を主導しており、扇谷家でも山内家と同様に当主と家宰との対立関係が発生し、1486年に太田道灌は、主君上杉(扇谷)定正により暗殺される。
その後は、関東の領有をめぐり山内家との対立が顕在化し、堀越公方・政知を擁した山内家に対し扇谷家は古河公方・成氏に接近して、両家は対立する。
「長享の乱」。
1493年、には扇谷定正の命で伊勢宗瑞(後の北条早雲)が堀越公方・政知を攻撃しているが、伊勢宗瑞(北条早雲)は伊豆において自立し子孫は、
後北条氏となる。同盟関係にあった古河公方成氏は分裂により衰亡していたほか、山内方の相模の領地は伊勢宗瑞(北条早雲)に次第に切り取られて
支配権を失い「大森藤頼の小田原城等」、藤頼は、山内上杉に寝返っていたため、扇谷上杉家が宗瑞に派兵を依頼したものを、宗瑞がそのまま領国化したものである)、上杉朝良(上杉定正の甥で次の扇谷家当主)は伊勢宗瑞(北条早雲)と宗瑞の甥で主君である駿河守護今川氏親の軍事支援で立河原の戦いは勝利する物の、自らは積極的な対応策を打たず河越城を包囲されて扇谷側の降伏の形で「長享の乱」は、収束。
しかし、山内家・扇谷家・古河公方それぞれの家が内紛状態に入り「永正の乱」が発生してしまう。
この騒動に付け入られる形で相模を後北条氏に浸食され、1516年には、相模における扇谷家の重鎮・三浦道寸の滅亡を招いてしまう。
やがて後北条氏は武蔵への侵攻を開始し、1524年に上杉朝興(上杉朝良の甥で次の扇谷家当主)は江戸城から川越へ逃れる。
甲斐の武田信虎(信直)は両上杉氏と同盟して後北条氏と対決。
扇谷朝興は、1533年に信虎嫡男の武田晴信(後の信玄)に娘を嫁がせて婚姻を結んでいたが、武田信虎は扇谷朝興死去の1538年、に後北条氏と和睦して離反。扇谷朝興の子上杉朝定は山内家と和解して後北条氏との戦いに臨むが、1546年「河越夜戦」で戦死(異説あり)し、扇谷家は滅亡した。
もし、上杉(扇谷)定正が太田道灌を暗殺していなければ歴史は変わっている。道灌は死の目前に「当方滅亡」と叫んだと伝わる。

「扇谷上杉家」・山内上杉家・犬懸上杉家・宅間上杉家とともに鎌倉公方を補佐する関東管領職を継承する家柄。
実質は山内上杉家がその地位を独占、そのため、室町時代の前半には、さほど大きな勢力ではないが、しかし、鎌倉公方と関東管領は次第に対立するようになり、1416年には、前関東管領の上杉禅秀(犬懸上杉家)が鎌倉公方の足利持氏に対し反乱を起こし(上杉禅秀の乱)、
1438年、関東管領の上杉憲実(山内上杉家)と持氏が対立し、持氏が自害する事件が起こっている(永享の乱)。
扇谷上杉家は、上杉禅秀の乱では鎌倉公方方に、永享の乱では関東管領方について活躍し、鎌倉公方は持氏の死で一時途絶えたが、
1449年、に持氏の遺児成氏が鎌倉公方に就任すると、成氏と関東管領の憲忠(山内上杉家)の対立が激化。
1453年、成氏が憲忠を謀殺し、享徳の乱が勃発、この乱で成氏は古河に退くが、「古河公方」と称して上杉氏と対立した。
この間、扇谷上杉家は、武蔵国に江戸城、岩槻城、河越城を築き、河越城を拠点としている。
1475年、山内上杉家の家宰だった長尾景春が反乱を起こすが、扇谷上杉家の家宰太田道灌がこれを鎮圧し、扇谷上杉家は山内上杉家と並ぶ勢力を持つようになっていく。
「七人塚」 太田道灌の首を守った家臣達



「七人塚」
1486年、糟屋の上杉館で、太田道灌が上杉定正のだまし討ちに会って非業の最期を遂げたとき、九人の家臣が道灌の首をもって洞昌院へ駆けこみ、
上杉勢が道灌の首を取り返しに来たが、九人は断固として拒否し、そこで腹を切ろうとした。
そのとき、道灌遭難の一部始終を後世に伝えるために、二人の家臣は生き残ることになり、一人家臣の子孫が、七人塚の近くに住み、代々「七人塚」の墓守をしていたと聞く。
「七人塚」は、往時、上粕屋神社の境内にあり、発掘したところ六基は盗掘された後、一基のみ現在地に移された。
「上粕屋神社」
近江の国の日吉神を当所に移し勧請したと伝わる。風土記によれば天平年中(9世紀頃)に僧侶良弁の勧請なりとも云う。
元禄に、社殿を再建し、山王権現と称したとある。 明治に入り、日枝神社と改称し、競馬神事神楽を奉納、宇和田内鎮座の熊野神社と 字石倉上鎮座の白山社を合祀し、「上粕屋神社」と改称したと云う。
良弁ー持統天皇の689年 - 宝亀774年。
奈良時代の華厳宗の僧。東大寺の開山、通称を金鐘行者といった。相模国の柒部氏の出身で、鎌倉生まれと言われ義淵に師事。
別伝によれば、近江国の百済氏の出身で野良作業の母が目を離した隙に鷲にさらわれて、奈良の二月堂前の杉の木に引っかかっているのを義淵に助けられ、僧として育てられたと言われる。
東大寺の前身に当たる金鐘寺に住み、後に全国を探し歩いた母と30年後、再会したとの伝承もあが、史実であるかは定かでない。
ただし、幼少より義淵に師事して法相唯識を学んだのは事実と云う。
祭神ー大山咋神,大穴牟連命と14神。



上粕屋・大山旧道には、いろいろと道祖神が建てられている。



大山に降った雨は湧水となって地中から湧き出し、いくつもの流れとなって斜面を下り、深い谷を刻む。
ふもとの日向や上粕屋地区に見られる扇状地は、こうした川が運び込んだ土砂により数万年前に造りあげられたと云う。


「洞昌院」-曹洞宗・山号 蟠龍山公所寺
太田左衛門大夫持資入道道灌を開基として、崇旭ー長禄二年卒が開山・創建。
天正19年寺領 3石の御朱印状を拝領している。中本寺格の寺院と云う。



太田道灌の墓がある洞昌院は、道灌が関東管領上杉憲実の弟道悦和尚のため建てた寺と伝えられている。

「太田道灌」1432-86 太田資清の子・上杉(扇谷)定正の執事を務める。武将、上杉勢力拡大に尽力。
古今無双の名将として天下にその名を轟かせた。反面、妬みの敵も増え、主君定正は、讒言を信じてしまい謀殺された。
道灌は、江戸城を「武蔵国経営」に拠点とした。道灌が舟に乗っていると一匹の魚が飛び込み「瑞祥・めでたい」とみて「千代田村」とし城を築いた。
神社の「神木」・樹齢600年以上の古木のケヤキは、根元、穴が開いて、

太田道灌は、扇谷上杉家に仕えた戦国名武将、父資清が、ここ相模国の粕屋に本拠を置いていたため、伊勢原市で生まれたと考えられている。
江戸城を築いたことで知られる道灌は、和歌にも秀でた文武両道を備えた知的武将であった。
晩年は、山内上杉家と扇谷上杉家との争いに巻き込まれ、1486年、その才能を恐れた主君上杉定正(扇谷上杉)の粕屋の館におびき出され謀殺。
道灌は、死の間際に「当方滅亡」と言い残した。自分が死ねば扇谷に未来はないという予言だという。
のちに、関東は北条早雲によって攻められ、早雲の孫氏康によって扇谷上杉家は滅ぼされる。

宗祇は,心敬の心情を思うやり、その歌心に和して、句を詠んだ。時を経て、芭蕉は、宗祇の悲しみと、風雅を追い求める心に和して、掲句を詠んだ。

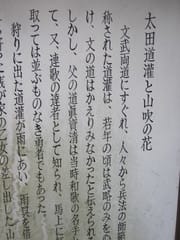

道灌が父を尋ねて越生の地に来た。
突然のにわか雨に遭い農家で蓑を借りようと立ち寄った。その時、娘が出てきて一輪の山吹の花を差し出した。
道灌は、蓑を借りようとしたのに花を出され内心腹立たしかった。後でこの話を家臣にしたところ、それは後拾遺和歌集の
「七重八重 花は咲けども 山吹の実の一つだに なきぞ悲しき」
兼明親王の歌に掛けて、山間の茅葺きの家であり貧しく蓑(実の)ひとつ持ち合わせがないことを奥ゆかしく答えたのだと教わった。
古歌を知らなかった事を恥じて、それ以後道灌は歌道に励み、歌人としても名高くなったという。
豊島区高田の神田川に架かる面影橋の近くにも山吹の里の碑があり、1kmほど東へ行った新宿区内には山吹町の地名があり、伝説の地に比定されている。埼玉県越生町にも「山吹の里」と称する場所が存在し、この地が伝説の地であるという説もある。ただしいずれも真偽は不明。

道灌は刺客に槍で刺された。
道灌が歌を好むことを知っている刺客は上の句を読む。「かかる時さこそ命の惜しからめ」
道灌は致命傷に少しもひるまず下の句を続けた「かねてなき身と思い知らずば」
これは新渡戸稲造著書「武士道」(1899)に紹介。
勇気ある真に偉大な人物が死に臨んで有する「余裕」の一例としている。


川崎市幸区の「夢見ヶ崎」
という地名は、道灌の見た夢に由来しているという。
多摩川と鶴見川に挟まれ、近くを鎌倉街道が走るこの場所は、築城するのにとても適した場所であったが、この地に宿営していた道灌が「一羽の白い鷲が私の兜を掴んで南西の地へ持っていってしまった」という夢を見て不吉だと感じ、築城を断念した。
そのため、兜を南西の地へ埋め、新たに築城する場所を探したと云う。
現在は、川崎市立夢見ヶ崎動物公園の東端にある9号古墳跡地に太田道灌碑と八幡宮・横浜市鶴見区に兜塚の碑が。

「長尾景春の乱」は扇谷家の領国武蔵において展開されているが、扇谷家家宰太田道灌は乱の平定を主導しており、扇谷家でも山内家と同様に当主と家宰との対立関係が発生し、1486年に太田道灌は、主君上杉(扇谷)定正により暗殺される。
その後は、関東の領有をめぐり山内家との対立が顕在化し、堀越公方・政知を擁した山内家に対し扇谷家は古河公方・成氏に接近して、両家は対立する。
「長享の乱」。
1493年、には扇谷定正の命で伊勢宗瑞(後の北条早雲)が堀越公方・政知を攻撃しているが、伊勢宗瑞(北条早雲)は伊豆において自立し子孫は、
後北条氏となる。同盟関係にあった古河公方成氏は分裂により衰亡していたほか、山内方の相模の領地は伊勢宗瑞(北条早雲)に次第に切り取られて
支配権を失い「大森藤頼の小田原城等」、藤頼は、山内上杉に寝返っていたため、扇谷上杉家が宗瑞に派兵を依頼したものを、宗瑞がそのまま領国化したものである)、上杉朝良(上杉定正の甥で次の扇谷家当主)は伊勢宗瑞(北条早雲)と宗瑞の甥で主君である駿河守護今川氏親の軍事支援で立河原の戦いは勝利する物の、自らは積極的な対応策を打たず河越城を包囲されて扇谷側の降伏の形で「長享の乱」は、収束。
しかし、山内家・扇谷家・古河公方それぞれの家が内紛状態に入り「永正の乱」が発生してしまう。
この騒動に付け入られる形で相模を後北条氏に浸食され、1516年には、相模における扇谷家の重鎮・三浦道寸の滅亡を招いてしまう。
やがて後北条氏は武蔵への侵攻を開始し、1524年に上杉朝興(上杉朝良の甥で次の扇谷家当主)は江戸城から川越へ逃れる。
甲斐の武田信虎(信直)は両上杉氏と同盟して後北条氏と対決。
扇谷朝興は、1533年に信虎嫡男の武田晴信(後の信玄)に娘を嫁がせて婚姻を結んでいたが、武田信虎は扇谷朝興死去の1538年、に後北条氏と和睦して離反。扇谷朝興の子上杉朝定は山内家と和解して後北条氏との戦いに臨むが、1546年「河越夜戦」で戦死(異説あり)し、扇谷家は滅亡した。
もし、上杉(扇谷)定正が太田道灌を暗殺していなければ歴史は変わっている。道灌は死の目前に「当方滅亡」と叫んだと伝わる。

「扇谷上杉家」・山内上杉家・犬懸上杉家・宅間上杉家とともに鎌倉公方を補佐する関東管領職を継承する家柄。
実質は山内上杉家がその地位を独占、そのため、室町時代の前半には、さほど大きな勢力ではないが、しかし、鎌倉公方と関東管領は次第に対立するようになり、1416年には、前関東管領の上杉禅秀(犬懸上杉家)が鎌倉公方の足利持氏に対し反乱を起こし(上杉禅秀の乱)、
1438年、関東管領の上杉憲実(山内上杉家)と持氏が対立し、持氏が自害する事件が起こっている(永享の乱)。
扇谷上杉家は、上杉禅秀の乱では鎌倉公方方に、永享の乱では関東管領方について活躍し、鎌倉公方は持氏の死で一時途絶えたが、
1449年、に持氏の遺児成氏が鎌倉公方に就任すると、成氏と関東管領の憲忠(山内上杉家)の対立が激化。
1453年、成氏が憲忠を謀殺し、享徳の乱が勃発、この乱で成氏は古河に退くが、「古河公方」と称して上杉氏と対立した。
この間、扇谷上杉家は、武蔵国に江戸城、岩槻城、河越城を築き、河越城を拠点としている。
1475年、山内上杉家の家宰だった長尾景春が反乱を起こすが、扇谷上杉家の家宰太田道灌がこれを鎮圧し、扇谷上杉家は山内上杉家と並ぶ勢力を持つようになっていく。
「七人塚」 太田道灌の首を守った家臣達



「七人塚」
1486年、糟屋の上杉館で、太田道灌が上杉定正のだまし討ちに会って非業の最期を遂げたとき、九人の家臣が道灌の首をもって洞昌院へ駆けこみ、
上杉勢が道灌の首を取り返しに来たが、九人は断固として拒否し、そこで腹を切ろうとした。
そのとき、道灌遭難の一部始終を後世に伝えるために、二人の家臣は生き残ることになり、一人家臣の子孫が、七人塚の近くに住み、代々「七人塚」の墓守をしていたと聞く。
「七人塚」は、往時、上粕屋神社の境内にあり、発掘したところ六基は盗掘された後、一基のみ現在地に移された。
「上粕屋神社」
近江の国の日吉神を当所に移し勧請したと伝わる。風土記によれば天平年中(9世紀頃)に僧侶良弁の勧請なりとも云う。
元禄に、社殿を再建し、山王権現と称したとある。 明治に入り、日枝神社と改称し、競馬神事神楽を奉納、宇和田内鎮座の熊野神社と 字石倉上鎮座の白山社を合祀し、「上粕屋神社」と改称したと云う。
良弁ー持統天皇の689年 - 宝亀774年。
奈良時代の華厳宗の僧。東大寺の開山、通称を金鐘行者といった。相模国の柒部氏の出身で、鎌倉生まれと言われ義淵に師事。
別伝によれば、近江国の百済氏の出身で野良作業の母が目を離した隙に鷲にさらわれて、奈良の二月堂前の杉の木に引っかかっているのを義淵に助けられ、僧として育てられたと言われる。
東大寺の前身に当たる金鐘寺に住み、後に全国を探し歩いた母と30年後、再会したとの伝承もあが、史実であるかは定かでない。
ただし、幼少より義淵に師事して法相唯識を学んだのは事実と云う。
祭神ー大山咋神,大穴牟連命と14神。



上粕屋・大山旧道には、いろいろと道祖神が建てられている。



大山に降った雨は湧水となって地中から湧き出し、いくつもの流れとなって斜面を下り、深い谷を刻む。
ふもとの日向や上粕屋地区に見られる扇状地は、こうした川が運び込んだ土砂により数万年前に造りあげられたと云う。


「洞昌院」-曹洞宗・山号 蟠龍山公所寺
太田左衛門大夫持資入道道灌を開基として、崇旭ー長禄二年卒が開山・創建。
天正19年寺領 3石の御朱印状を拝領している。中本寺格の寺院と云う。



太田道灌の墓がある洞昌院は、道灌が関東管領上杉憲実の弟道悦和尚のため建てた寺と伝えられている。

「太田道灌」1432-86 太田資清の子・上杉(扇谷)定正の執事を務める。武将、上杉勢力拡大に尽力。
古今無双の名将として天下にその名を轟かせた。反面、妬みの敵も増え、主君定正は、讒言を信じてしまい謀殺された。
道灌は、江戸城を「武蔵国経営」に拠点とした。道灌が舟に乗っていると一匹の魚が飛び込み「瑞祥・めでたい」とみて「千代田村」とし城を築いた。
神社の「神木」・樹齢600年以上の古木のケヤキは、根元、穴が開いて、

太田道灌は、扇谷上杉家に仕えた戦国名武将、父資清が、ここ相模国の粕屋に本拠を置いていたため、伊勢原市で生まれたと考えられている。
江戸城を築いたことで知られる道灌は、和歌にも秀でた文武両道を備えた知的武将であった。
晩年は、山内上杉家と扇谷上杉家との争いに巻き込まれ、1486年、その才能を恐れた主君上杉定正(扇谷上杉)の粕屋の館におびき出され謀殺。
道灌は、死の間際に「当方滅亡」と言い残した。自分が死ねば扇谷に未来はないという予言だという。
のちに、関東は北条早雲によって攻められ、早雲の孫氏康によって扇谷上杉家は滅ぼされる。

宗祇は,心敬の心情を思うやり、その歌心に和して、句を詠んだ。時を経て、芭蕉は、宗祇の悲しみと、風雅を追い求める心に和して、掲句を詠んだ。

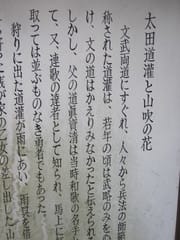

道灌が父を尋ねて越生の地に来た。
突然のにわか雨に遭い農家で蓑を借りようと立ち寄った。その時、娘が出てきて一輪の山吹の花を差し出した。
道灌は、蓑を借りようとしたのに花を出され内心腹立たしかった。後でこの話を家臣にしたところ、それは後拾遺和歌集の
「七重八重 花は咲けども 山吹の実の一つだに なきぞ悲しき」
兼明親王の歌に掛けて、山間の茅葺きの家であり貧しく蓑(実の)ひとつ持ち合わせがないことを奥ゆかしく答えたのだと教わった。
古歌を知らなかった事を恥じて、それ以後道灌は歌道に励み、歌人としても名高くなったという。
豊島区高田の神田川に架かる面影橋の近くにも山吹の里の碑があり、1kmほど東へ行った新宿区内には山吹町の地名があり、伝説の地に比定されている。埼玉県越生町にも「山吹の里」と称する場所が存在し、この地が伝説の地であるという説もある。ただしいずれも真偽は不明。

道灌は刺客に槍で刺された。
道灌が歌を好むことを知っている刺客は上の句を読む。「かかる時さこそ命の惜しからめ」
道灌は致命傷に少しもひるまず下の句を続けた「かねてなき身と思い知らずば」
これは新渡戸稲造著書「武士道」(1899)に紹介。
勇気ある真に偉大な人物が死に臨んで有する「余裕」の一例としている。


川崎市幸区の「夢見ヶ崎」
という地名は、道灌の見た夢に由来しているという。
多摩川と鶴見川に挟まれ、近くを鎌倉街道が走るこの場所は、築城するのにとても適した場所であったが、この地に宿営していた道灌が「一羽の白い鷲が私の兜を掴んで南西の地へ持っていってしまった」という夢を見て不吉だと感じ、築城を断念した。
そのため、兜を南西の地へ埋め、新たに築城する場所を探したと云う。
現在は、川崎市立夢見ヶ崎動物公園の東端にある9号古墳跡地に太田道灌碑と八幡宮・横浜市鶴見区に兜塚の碑が。










