「足利義教」 1394-1441(室町幕府第6代将軍・3代将軍義満の5男 1419年153代天台宗座主)
実権は、父義持で、死後兄弟でくじ引機で将軍に選ばれたという。鎌倉公方足利持氏を自殺に追い込む(永享の乱)さらに丹後守護一色義貫・伊勢守護
土岐持頼を誅殺している。勘合貿易再開し財政改善、狂気の独裁者といわれた。
守護に殺された独裁者ー嘉吉の乱次は自分が殺されると義教を赤松満祐が招いて殺している。
「足利持氏」 1398-1439 将軍の刃向かい続けた鎌倉公方・足利満兼の長男、12歳で4代鎌倉公方に就任。
上杉禅秀の乱鎮圧している。「足利義教」と対立ー「永享の乱」起こすが破れ自害ー鎌倉公方は、足利尊氏の3男「基氏」~関東一円を支配している。
持氏の遺児「安王と春王」は、、、、、。

「結城合戦絵詞」
1440年結城城主結城氏朝が、鎌倉公方持氏の遺子を助けて、幕府軍と戦う。(以下その絵巻)

春王・安王を女の姿に変装して逃がしたとある。
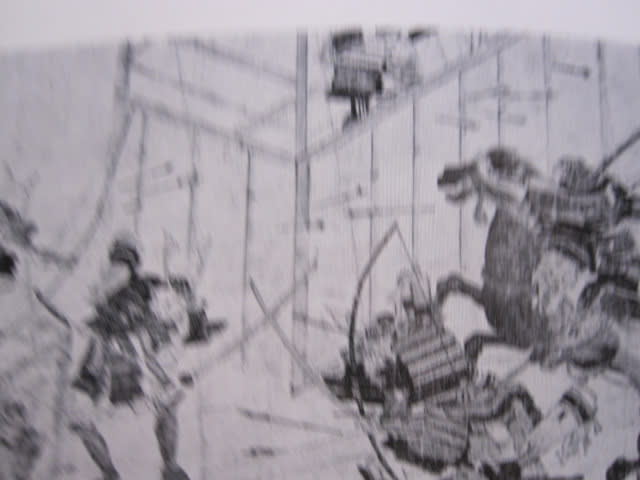
結城氏朝、春王・安王も捕らえられ戦死

「結城氏」-鎮守府将軍藤原秀郷の末裔
小山朝光(結城朝光)が平安時代後期に源頼朝の挙兵に従い、志田義広滅亡後の鎌倉時代には下総の結城(茨城県結城市)を領した事が結城氏(下総結城氏、本記事中では一部を除き単に「結城氏」と記す)の始まりであるとされ、朝光の実家である小山氏の本拠である下野国の小山(栃木県小山市)に隣接していることから、結城も元々小山氏の所領であったであろう、が、朝光自身が自分は、父の遺領を伝領せず、頼朝の配下となって初めて所領を得たと語っている。(『吾妻鏡』正治元年10月27日条)、
治承合戦期まで結城郡では古くからの郡司であったと推定される簗氏・人手氏や常陸平氏系の行方氏が支配していたと推定されることから、結城郡には元々小山氏一族の影響は及んでおらず、一連の合戦を通じて没落した行方氏らに代わって朝光が頼朝から結城郡を「新恩」として与えられたと考えらる。
家伝によれば、朝光には源頼朝御落胤説があり、北条氏のために親子の名乗りができず、その代わりに身分の上では小山氏の庶子に過ぎなかった朝光にあらゆる優遇を施した、と伝える。
伝統的に源氏を称し、代々の当主も「頼朝」の「朝」の字を通字とし、いくつもの動乱の時代を経て、鎌倉以来の名族としてその家名を後世に。

「結城伝説」
結城家の初代「結城朝光」は、
源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼしたときに従軍し、手柄を立てて平泉の黄金のほとんどをほうびにもらったと云う。
それは、代々同家に伝えられてきたが、17代の晴朝の時、徳川家康に狙われたため、現在の茨城県結城市から栃木県下野市あたりに広がる旧結城領のどこかに埋蔵されたらしいと云う。
晴朝の重臣が書き残した文書によると、財宝は重さ約8kgの金の延べ棒がおよそ2万5千本、7kg弱のものが2万5千本、それに30kgの砂金が入った樽が108個。黄金の総重量は約380tにもなる。
単純計算で1兆8千5百億円だが、
徳川家康をはじめ、大岡越前守も掘っていると云う。
さまざまな根拠によって発掘をする人は今もあとを絶たない。
結城市にある晴朝が建てた金光寺というお寺の山門には、意味不明の3首の和歌や絵が彫り込まれていて、この謎を解けば財宝のありかがわかるといわれているが・・・。
「日蓮宗 妙国寺」-開基 妙国院日宣・1345年創建 室町時代) 酒造家、俳人「早見晋我」の墓
与謝蕪村が親交の早見の死を悼んで詠んだ「北条老をいたむ」碑がある。



「時宗 金福寺」-時宗2代行上人他阿貞教が創建ー1708年ー
この鐘楼は、西之町に時を告げてきた


「真言宗 光福寺」-1558年の古寺
東寺の「亮恵」から印信を受け、中興した。


「浄土宗 弘経寺」-開基 檀秀存把
結城家18代秀康 娘「松姫」の早世に遭い、存把上人を招き建立。
与謝蕪村が兄弟子である砂岡雁宕を慕って結城を訪ね、弘経寺に長く滞在していた。
鬼瓦や植裁などが



一度も焼失していない



「禅宗 孝顕寺」-開基 独放曇聚禅師
15代政朝が開基(1515)ー18代秀康が現在地に再建



境内には、「小場兵馬自刃の碑」・三門・戒壇石・御朱印堀跡・結城家、水野家、小場家の墓
「小場兵馬」結城藩家老1818-1868 藩主を諫める事が出来ず、藩の混乱で自刃(戊辰戦争)



本堂 大将塚 結城朝光の墓・御霊屋門など



「結城七福神」
金光寺、寿老人・市杵島神社、弁財天・毘沙門堂・恵比寿神社・大輪寺、大黒天・乗国寺、福禄寿・人手観音堂、布袋。
「結城通り・路地」ー稲荷通・国府通・健田通・大町通・西之宮通・駅前蔵通・紺屋町通・亀甲通・・・-古社寺・土蔵・格子戸・商家老舗が
久保不動尊 落ち着いた街並み



「常光寺」
地元では「金仏さん」で知られているー文化財 彫刻・阿弥陀如来坐像。



「覚照寺」-真宗大谷派寺ー


「雪光稲荷神社」
結城駅に近い国府町に鎮座


「結城合戦古戦場跡」
室町幕府に抗して滅ぼされた「永享の乱」
鎌倉公方足利持氏の遺児・春王丸、安王丸は幕府軍に追われる流浪の身となって日光に、下総国の豪族ー結城氏朝、持朝ーは義によってこのかつての主君の子を擁し、天下に反旗を翻す。
押し寄せる十万余の大群を相手に、わずか一万の軍勢は果敢に闘い続けた。
「結城合戦」に続く時代が、「南総里見八犬伝」。
古河、堀越両公方や管領の上杉の扇谷・山内両氏の分裂・抗争の発端が・・・・・・。
JR水戸線を挟んむ古戦場跡

「結城酒造」-1596年創業
銘柄「武勇」「大吟醸富久福」等が



予定では、下館~水海道ー関東鉄道常総線~取手ー徳川家康重臣(本多重次居城など)でしたがパソコン故障で写真が消え、残念ながら「古河の旅」は、これで、終了します。
実権は、父義持で、死後兄弟でくじ引機で将軍に選ばれたという。鎌倉公方足利持氏を自殺に追い込む(永享の乱)さらに丹後守護一色義貫・伊勢守護
土岐持頼を誅殺している。勘合貿易再開し財政改善、狂気の独裁者といわれた。
守護に殺された独裁者ー嘉吉の乱次は自分が殺されると義教を赤松満祐が招いて殺している。
「足利持氏」 1398-1439 将軍の刃向かい続けた鎌倉公方・足利満兼の長男、12歳で4代鎌倉公方に就任。
上杉禅秀の乱鎮圧している。「足利義教」と対立ー「永享の乱」起こすが破れ自害ー鎌倉公方は、足利尊氏の3男「基氏」~関東一円を支配している。
持氏の遺児「安王と春王」は、、、、、。

「結城合戦絵詞」
1440年結城城主結城氏朝が、鎌倉公方持氏の遺子を助けて、幕府軍と戦う。(以下その絵巻)

春王・安王を女の姿に変装して逃がしたとある。
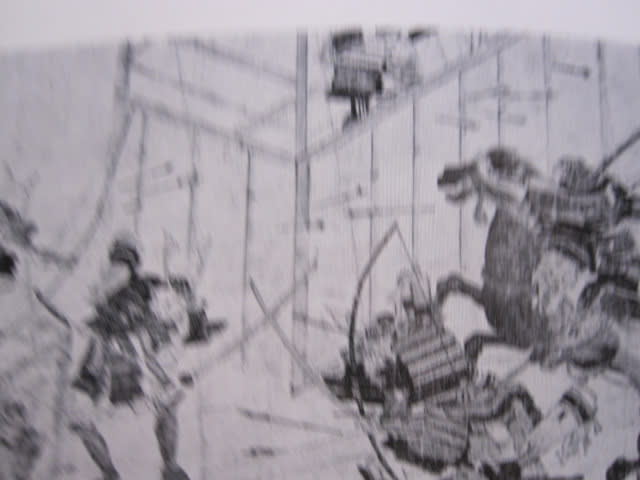
結城氏朝、春王・安王も捕らえられ戦死

「結城氏」-鎮守府将軍藤原秀郷の末裔
小山朝光(結城朝光)が平安時代後期に源頼朝の挙兵に従い、志田義広滅亡後の鎌倉時代には下総の結城(茨城県結城市)を領した事が結城氏(下総結城氏、本記事中では一部を除き単に「結城氏」と記す)の始まりであるとされ、朝光の実家である小山氏の本拠である下野国の小山(栃木県小山市)に隣接していることから、結城も元々小山氏の所領であったであろう、が、朝光自身が自分は、父の遺領を伝領せず、頼朝の配下となって初めて所領を得たと語っている。(『吾妻鏡』正治元年10月27日条)、
治承合戦期まで結城郡では古くからの郡司であったと推定される簗氏・人手氏や常陸平氏系の行方氏が支配していたと推定されることから、結城郡には元々小山氏一族の影響は及んでおらず、一連の合戦を通じて没落した行方氏らに代わって朝光が頼朝から結城郡を「新恩」として与えられたと考えらる。
家伝によれば、朝光には源頼朝御落胤説があり、北条氏のために親子の名乗りができず、その代わりに身分の上では小山氏の庶子に過ぎなかった朝光にあらゆる優遇を施した、と伝える。
伝統的に源氏を称し、代々の当主も「頼朝」の「朝」の字を通字とし、いくつもの動乱の時代を経て、鎌倉以来の名族としてその家名を後世に。

「結城伝説」
結城家の初代「結城朝光」は、
源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼしたときに従軍し、手柄を立てて平泉の黄金のほとんどをほうびにもらったと云う。
それは、代々同家に伝えられてきたが、17代の晴朝の時、徳川家康に狙われたため、現在の茨城県結城市から栃木県下野市あたりに広がる旧結城領のどこかに埋蔵されたらしいと云う。
晴朝の重臣が書き残した文書によると、財宝は重さ約8kgの金の延べ棒がおよそ2万5千本、7kg弱のものが2万5千本、それに30kgの砂金が入った樽が108個。黄金の総重量は約380tにもなる。
単純計算で1兆8千5百億円だが、
徳川家康をはじめ、大岡越前守も掘っていると云う。
さまざまな根拠によって発掘をする人は今もあとを絶たない。
結城市にある晴朝が建てた金光寺というお寺の山門には、意味不明の3首の和歌や絵が彫り込まれていて、この謎を解けば財宝のありかがわかるといわれているが・・・。
「日蓮宗 妙国寺」-開基 妙国院日宣・1345年創建 室町時代) 酒造家、俳人「早見晋我」の墓
与謝蕪村が親交の早見の死を悼んで詠んだ「北条老をいたむ」碑がある。



「時宗 金福寺」-時宗2代行上人他阿貞教が創建ー1708年ー
この鐘楼は、西之町に時を告げてきた


「真言宗 光福寺」-1558年の古寺
東寺の「亮恵」から印信を受け、中興した。


「浄土宗 弘経寺」-開基 檀秀存把
結城家18代秀康 娘「松姫」の早世に遭い、存把上人を招き建立。
与謝蕪村が兄弟子である砂岡雁宕を慕って結城を訪ね、弘経寺に長く滞在していた。
鬼瓦や植裁などが



一度も焼失していない



「禅宗 孝顕寺」-開基 独放曇聚禅師
15代政朝が開基(1515)ー18代秀康が現在地に再建



境内には、「小場兵馬自刃の碑」・三門・戒壇石・御朱印堀跡・結城家、水野家、小場家の墓
「小場兵馬」結城藩家老1818-1868 藩主を諫める事が出来ず、藩の混乱で自刃(戊辰戦争)



本堂 大将塚 結城朝光の墓・御霊屋門など



「結城七福神」
金光寺、寿老人・市杵島神社、弁財天・毘沙門堂・恵比寿神社・大輪寺、大黒天・乗国寺、福禄寿・人手観音堂、布袋。
「結城通り・路地」ー稲荷通・国府通・健田通・大町通・西之宮通・駅前蔵通・紺屋町通・亀甲通・・・-古社寺・土蔵・格子戸・商家老舗が
久保不動尊 落ち着いた街並み



「常光寺」
地元では「金仏さん」で知られているー文化財 彫刻・阿弥陀如来坐像。



「覚照寺」-真宗大谷派寺ー


「雪光稲荷神社」
結城駅に近い国府町に鎮座


「結城合戦古戦場跡」
室町幕府に抗して滅ぼされた「永享の乱」
鎌倉公方足利持氏の遺児・春王丸、安王丸は幕府軍に追われる流浪の身となって日光に、下総国の豪族ー結城氏朝、持朝ーは義によってこのかつての主君の子を擁し、天下に反旗を翻す。
押し寄せる十万余の大群を相手に、わずか一万の軍勢は果敢に闘い続けた。
「結城合戦」に続く時代が、「南総里見八犬伝」。
古河、堀越両公方や管領の上杉の扇谷・山内両氏の分裂・抗争の発端が・・・・・・。
JR水戸線を挟んむ古戦場跡

「結城酒造」-1596年創業
銘柄「武勇」「大吟醸富久福」等が



予定では、下館~水海道ー関東鉄道常総線~取手ー徳川家康重臣(本多重次居城など)でしたがパソコン故障で写真が消え、残念ながら「古河の旅」は、これで、終了します。









