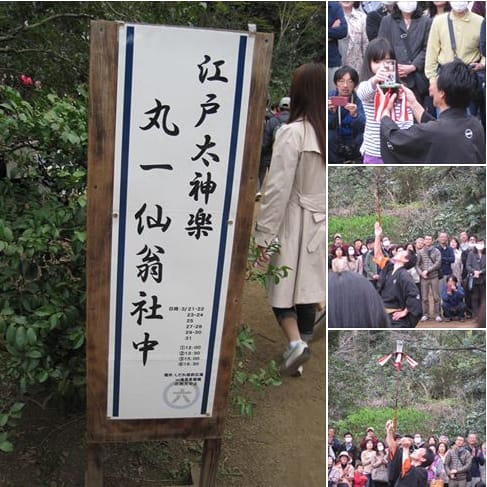あくまで自分の個人的な見解ですが、実際問題まずコウノトリの放鳥経過から言いますと、日本中に放鳥された個体の内で、雌3歳が中心になって、繁殖適地をしかもまさに日本中を放浪しています。次から次へと、1羽1羽があらゆる繁殖可能性のある箇所に訪問して現地を肌身で探っています。しかし豊岡市以外での繁殖成功例が今になっても聞こえてきません。多くはそのまま豊岡市の周辺に舞い戻ってしまっています。又一部は衰弱死もあるようです。
その行動経過から考えると、野生状態では現状では日本中に繁殖適地は存在しないとまで思われます。それは、伴侶に恵まれないこともありますが、最大は餌資源の決定的な不足です。そこで若い雌は定着して繁殖することを考えません。
オオハクチョウは、1959-60年の大移動後、着実に個体数を増やしてきていますが、その主役は人間とのかかわり方で、餌付けという「安心安全、3色昼寝付」生活を保障したことに大きな理由があると思っています。
本来冬の期間積雪や河川の凍結によって、本来自然状態では生息不可能な場所で餌付けの実質禁止によって、いずれも1960年度の大移動後、着実に個体数を増やしてきています。
その多くの箇所で何十年も継続してきた白鳥との触れ合いが断ち切られ、同時に本来の野生状態への復帰を強制された結果、オオハクチョウの子孫たちは餌を貰うことしか生きるすべをなくしたペット状態にあったために、衰弱死、あるいは春の北帰に耐えられずに落鳥し、中には秋田県などであったように鳥インフルに冒されて死亡してしまい、多くの越冬地でそこの個体群は全滅し数年後には消え失せたと考えている。
本来、海辺ではアマモなど海藻を、陸地ではマコモを主な食材としています。
それらが豊かに生育していた個所の消滅が引き起こした結果でもあります。
ハクチョウ類はオオハクチョウでは餌付けに実質禁止によって、大きく越冬地を喪失し、かつ全国的に個体数を減じています。
コハクチョウは、戦前から新潟市の佐潟を中心にして、戦後も着実に増加をしてくれています。それは餌が田んぼの落穂を主としていたからです。こちらは、餌付けを段階的に削減し、自力で水田での採餌を教育することにより、冬期間に採餌可能な個所では生き残り、個体数も回復しつつあります。
かって10年以上も前に、新潟県瓢湖で餌付けを実質取りやめた時期がありました。翌年から1万羽単位で有意義にコハクチョウの渡来数が減少したと考えます。 その結果で一番懲りたのはその地域のコハクチョウ自体です。その時を境に餌付けに依存することなく今はほぼ完全に野生化し、ハクチョウ類はファミリー単位で、その生活を楽しんでいるようです。
なぜ、このようなことが生じてしまったのか。
それは行政のあり方と密接に関連しています。
戦後の傾斜生産方式によって、エネルギーを薪や炭、石炭などから、すべてを石油に転換をした時に、旧式となったと考えて一部官僚がすべてを無価値と見做して切り捨てたことに端を発していると思います。
地方創生とは、その切り捨てられて生活手段を奪われた地域の、これからをどうするかに関わっています。
良く知られているがごとく、ドイツの森林産業は日本の1/2程度の面積でありながら、ドイツの自動車産業に拮抗する雇用数を確保しているということが大きな
ヒントであり、励みとなります。
今回はモノづくりを「なりわい(生業)」から「セルフパブリッシング(自己責任で公共財を活用)」仕組みの提言です。いくつかの農法、工法、文化など。最先端の生産手段を取り上げてみました。