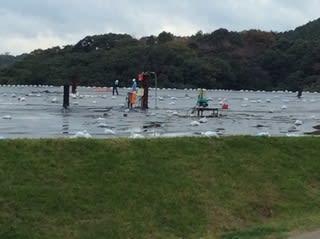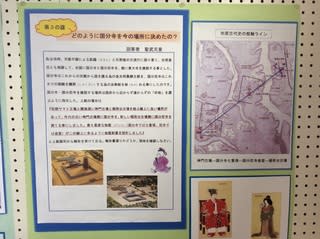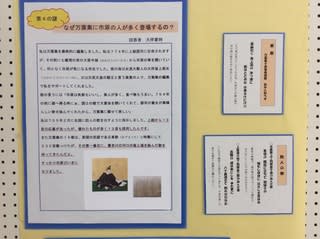昨日の議員研修会。講師は神戸にある社会福祉法人プロップ・ステーションの理事長、竹中ナミ氏。
16年前大阪にいた頃、私と同じく重度の障がいをもつ子どもさんを育てながらも、障がい者の働く場を作っている竹中さんの新聞記事を見て、ずっと会いたいと思っていた方でした。
関西では「ナミ姉(ナミねえ)」は超有名人。
やっぱり、すごいパワーの持ち主でした。

25年前に数人の仲間と共に草の根のグループとしてプロップ・ステーションを発足。
「寝たきりだから働けないんやない。満員電車の通勤ができへんからや。働きたいんや」と言う重度障がい者の声に動かされ、「重度障がい者を納税者にしよう!」との思いで活動されてきました。
そこで目をつけたのがコンピューター。
コンピューターは手指以外に足、口、瞼など、身体のどんな部分であっても、僅かでも自分の意志で動かせたなら「入力装置」を接続できるからです。
現在プロップのセミナーでは、身体障がい以外に知的ハンディあるいはLDや自閉症や発達障がい、精神障がいのチャレンジドもITCを学び、それぞれの個性と能力を発揮しています。
チャレンジド(Challenged)とは挑戦という使命やチャンスを与えられた人を示す米語で、プロップ・ステーションでは「障がい者」というネガティブな言葉を使わずチャレンジドという言葉を1995年から使っています。
ITCは日本でいう「IT」ですが国際的には「ITC」と呼ばれていて、「C」はコミュニケーションの「C」で、情報技術は本来「人と人の、あるいは人と社会のコミュニケーションに役立つこと」が大きな役割だそうです。
外に出るのが困難な重度障がい者にはピッタリ!
でも、どうやってこんな活動ができるの?って思いますよね。
「障害者年金を叩いても勉強したい!」と言われて、なんとかパソコンとソフト、講師を手配しスタート。
ある日、事務所に大きな箱が届き開けてみたら、発売1か月前のウィンドウズ94が入っていたそうな。
送り主は日本マイクロソフト社の社長。
その思いは「してあげる」というのではなく、プロップの活動に先行投資としてソフトを寄付するというもの。
ここからプロップはマイクロソフト社とつながっていくんです。
障がい者が技術を学びスキルを身に付けても、受注の壁が立ちはだかる。
仕事の幅を広げるには法人化しなくてはならない。社会福祉法人の資格を取ろう!
日本マイクロソフト社の社長がパソコンを揃えてくれ、立派な事務所も手配できたけど・・・・。
なんと、1億円の担保金がいるんですって!
この話し全てオジャン・・・。
その報告を日本マイクロソフト社に伝えると、返ってきた答えが「ビルに頼みましょう」
ええっ!? ビルって、あのビル・ゲイツですよ!
ポーンと1億円を快諾。
こうして草の根のグループが、社会福祉法人になったのです。
福祉は社会的弱者を弱者なくするために支えるものだが、人の能力を引き出せない。
人が誇りをもって生きるためには、働く場が必要。
関西弁で語るナミ姉の言葉、大阪で生まれ育った私の胸に響きました。
この議員研修会の企画をして下さった二田口議長に感謝です。
この後、ナミ姉を交えての懇親会。
2009年から「ナミねぇBAND」を結成し、ヴォーカリストとしても活動中というだけあって美声を披露して下さいました。

東京から戻った小出市長が割り箸をタクト代わりにして指揮を。
ノリノリのパフォーマンスは、ごらんの通り。

市職員と議員で市原市民歌を大合唱。

締めは前田教育長のエール。

賑やかな懇親会でした。
さて、もうすぐ議会が始まります。
明日は自宅で質問の準備しなきゃ~。