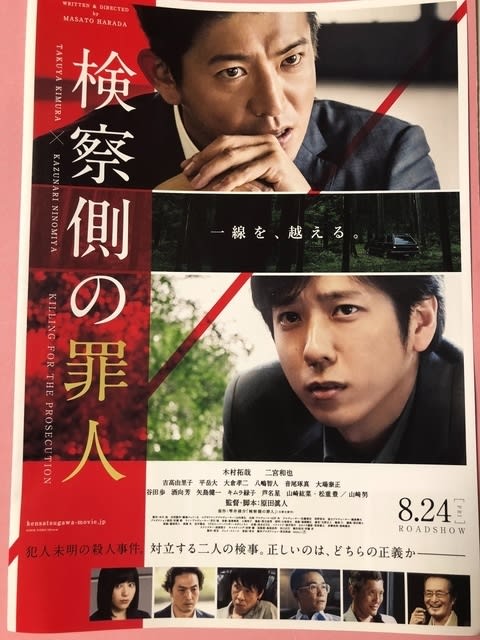今日は「すてきな終活 ~ガンになってもこわくない~」の講演会を開催しました。
主催者挨拶なんて、特別支援学校PTA連合会の会長以来のこと。

この講演会は昨年2月にも開催し、小さな会場は立ち見がでるほどの大盛況で、「もう一度聞きたい」とたくさんのお声をいただいたためPart2として企画したのですが、今回の会場は320人キャパの大ホール。どれだけ集客できるのか不安でしたが、皆で手分けしてポスター貼りやビラ配りに駆け回り、今回も客席はほぼ満席の大盛況となりました。

猛暑の中、来て下さった方に感謝です!
講師は前回に引き続き、市原市で在宅医療に携わって26年、これまでに3,000人以上の患者さんを在宅で看取ってこられた、五味クリニックの五味愽子医師。

終末医療について、どんなお話しだったかというと・・・
人が死ぬときは食欲が低下し脱水傾向になり、血液が凝固して脳の循環が悪くなり、意識がもうろうとしてきて呼吸が浅くなる。低酸素状態から、さらに意識が落ちて、脳内モルヒネ様物質βエンドルフィンが分泌して、幻覚が見えて、安らかに美しく天に召される。これは神様が動物すべてにくださる、この世で最後のプレゼントです。
ただし、自然にまかせ、あらがわず見守っていられた場合に限ります。
症状が悪化し、食べられないからといって胃ろうなどで人工的にチューブで栄養剤を流し込んだり、脱水だからといって点滴をしてしまえば、プレゼントは消えてしまいます。
「意識がなくなった」と家族が救急車を呼べば病院に搬送されて、点滴が始まると天国から引きずり戻されるのです。
この医療行為は医学的には正しいものですが、寿命が延びる分だけ先の苦しみを伴うことになります。
点滴のチューブを抜かないように手を縛られ、長くなると床ずれがでてきて痛みが増す。それでも生きていかなければならないのです。
だからこそ、患者が自分の最後をどう迎えたいかを事前に意思表示しておく必要があるのです。
在宅医療は、ここ数十年置き去りにされてきた「自然な死」を迎える、いわば医療の原点でもあると感じました。
今回は五味先生のお話の後、3名の訪問看護師さんからもお話を伺いました。

在宅医療を支える人は医師や訪問看護師だけでなく色んな職種の人がいること。関わった数々の看取りから人生の最後を安らかに迎えた患者さんの話。そして患者さんが自分の思いを勇気をもって周りの人に伝え、自分自身が主体者となってどんな医療を受けたいのかを決めることができるのが在宅医療なのだというお話をしていただきました。
写真の真ん中の渡辺ナースは、実は私の息子が8年間お世話になっている訪問看護師さんです。熱血で息子も私もだーい好きな方。冬に撮った写真ですが、ご覧のとおり満面の笑み!

訪問看護師は家族の一員でもあるのです。
医療は病気を治し症状を軽くしてくれるものであっても、人は医療を受けるために生きているのではない。
医療で最も大切なものは、医師や看護師と患者の心が通じ合うことではないでしょうか。