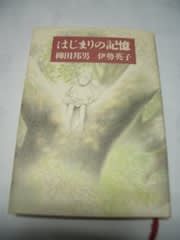しばらくのご無沙汰でしたが、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。
花から緑へ。北陸も若葉の美しい頃となりました。
花の命は短くて・・・なんて。林芙美子を想ったりしています。
ずいぶん以前のことですが、松山での講演の帰途、今治から船で尾道へ上がりました。何となく林芙美子に会えそうな気がして。(いつものパターンです)このことは昔の「通信」に書きましたが。
人生長くなりますと折々に想い出すことが多くなります。
閑話休題
先日、カウンセリング研究会事務局のMさんから、柳田邦夫さんのエッセイ集「はじまりの記憶」をお借りしたので読みました。伊勢英子さんとの共著です。
過去は現在の中にある。そして、すべての過去に意味がある。
最近、そのことをつくづく実感するようになった。
と筆者は書いています。この辺りが題名の意味するところでしょうか。
私も同様のことを思っています。私の場合「最近」ではなくて、ずいぶん以前から実感しています。このことは拙著「あのの・・・カウンセリングに学ぶ人間関係」(ぎょうせい)の中で「原体験・心象風景」として記しているところです。
柳田さんは作家であり、私はカウンセラーですが、いずれも人間の心について深く見つめてみると気付かされることだと思います。
柳田さんは息子さんを自死で亡くされています。
息子が心の病に陥り精神科に通い始めたとき
精神科医が五十二歳の私に苦言した。
「息子さんの話ですと、お父さんは一度も叱ったことがないそうですね。
父親というものは・・・」
という件があります。
柳田さんは自分の父親の影響(反面教師的な)で若い頃に、声を荒げることは決してしまいと誓ったそうです。すこぶる優しい方であったのだと思います。
この一節を読んで私は、もし(今更詮無いことですが)時には本気で息子さんを叱ることがあったならば・・・と思われて仕方ありませんでした。
私の周囲にも、このような逆縁に遭われた方も少なくありません。それは消えることの無い悲しみだと思います。
翻って、だから叱ればよいというものでもありませんが、今の親や教師を見ていて、本当の意味で叱ることや諭すことの必要性を感じます。我が子、我が生徒なればこそ。
多くの方々は「米沢先生って優しい。仏様みたい」って大いなる勘違いをされます。私は厳しい面も持ち合わせています。我が子には勿論、保護観察で面接に来る少年少女たちにも。
ある日のこと、保護観察の面接と研究会のメンバーの来所とが重なってしまいました。ある少女と3,40分の面接中、皆さんは別室で話し合いをされていました。
時折、私の大きな声が聞こえてきて皆、息を潜めていたそうです。私がその少女を「どやしつけていた」そうです。(w)
人間「ここ一番」って時は、声も荒げ、言うべきことは言わねばならないのです。特に父親なるものは。
カウンセリングや家庭訪問などをしていて感じるのですが、家に母親が2人もいるような感じがする昨今です。
四半世紀以上に亘って「親業訓練講座」なるものを提供しています。よいプログラムではありますが、前述の「ここ一番」が欠落しています。受容・共感は大切なことは言うまでもありませんが、親や教師はカウンセラー的対応のみでは絶対にダメです。
その辺りを、私の「子育自分学」や「父親業講座」或いは「コミュニケーション力開発講座」などで、しっかりフォローしてきました。
文脈がおかしくなりましたが、
一昨年、本願寺派福井別院でビハーラの会の研修に何度か招かれました。悲嘆カウンセリングについてお話とロールプレーなどをさせて頂きました。
愛する家族を失った方に「諸行無常」の言葉は冷たすぎます。それを自ら感じられるようにして差し上げるのが、私のカウンセリング・マインドです。
少し古くなりますが、高史明(こ・さみよん)さんが「一粒の涙を抱きて」-歎異抄との出会いーを上梓されたのは昭和52年です。彼は私より10歳の年長だから、当時は45歳頃です。
わたしが『歎異抄』の第五章の教えに全身をつかまれたのは、
まだやっと十二歳でしかなかったひとり子に自殺されてからの
ことであった。
と記されています。それは「危機の現代に子どもを思う」という見出しの一節です。
「危機の現代」は今もそのまま続いています。
更に、
わたしにとってそれは、亡き子にしてやれることは、すでに何もない、と
いわれたことに等しかった。
と続くのです。
数年前に、高さんの講演を東別院で聞きました。書物でのイメージで期待が大きかったせいか、お話はあまり心には残っていません。
カウンセリング研究会「あのの」で、乞われて何度か「歎異抄」を講じたことがあります。このことは拙著「あのの・・・」の後書に当時の代表であったHさんが記されています。
長くなりますので(もう既に長いですよね)、続きは別の機会に譲りますが、今の寺や宗門、いや宗教者がもっとやらなければならないことがあるように思います。
まさに、唯円が「歎異」する息づかいが耳奥に響いてくるようです。
いよいよこれから、よい季節になっていきますね。
この里に手まりつきつき子どもらと遊ぶ春日は暮れずともよし
と歌った良寛さんや、
遠流になった親鸞聖人が、海路越後に上陸されたのは、若草が萌え始める季節であったのではと、先師を懐かしく偲ばれるこの頃です。
ごきげんよう。