こんにちは。ご訪問どうも有難うございます。
通称yoーサンこと仏教者にして Counseling Supervisor の米沢豊穂です。
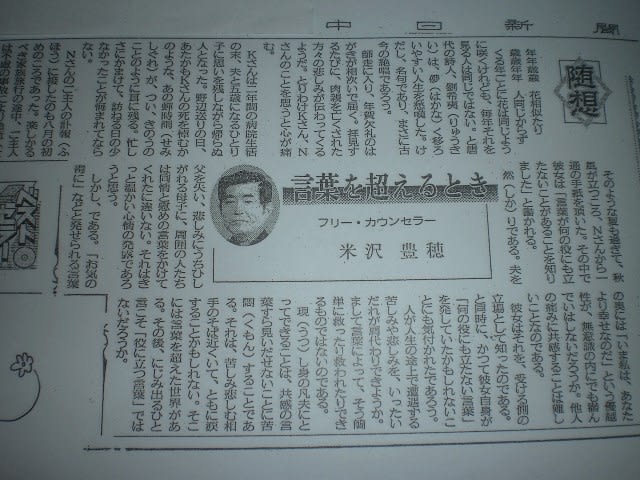
いつも交信(心)頂いている、ある方のブログ(昨年12月)に下記のような一節があった。
愛娘に先立たれた人が悲しく私に言われたのです
「生きていてもしょうがない」
咄嗟には言葉もなくて
でも言いました
「生きていてもしょうがない命なんてない」と
でも考えてしまいます
立場が変わったなら私も必死で
「どう生きよう」と問うたでしょう
悲し過ぎますね
人間長く生きて来ると、このような場面に出合うことは少なからずあると思う。全くない方もあるかもしれないが、それは人間関係の深さにもよるものである。
このブログを書かれているFさんは、当然のことながらお目に掛かったことはなく、お写真すら拝見していない。されど私は「文章は人なり」と思っている。Fさんのブログをお訪ねすると、私は必ずバックナンバーを数編は読ませて頂く。
奇を衒った言葉や画像はない。自ら感じられることを淡々と記されたものが多い。しかしそのいずれもが心に響く。それはこの方の感性の然らしむるところだろうと思う。そしてまた互いに「お念仏」に連なることも浅からざるご縁と思う。
もう一度Fさんの文章を読んでみてほしい。
>咄嗟には言葉もなくて でも言いました・・・
でも考えてしまいます 立場が変わったなら私も必死で
「どう生きよう」と問うたでしょう・・・
このところなんです。冒頭の拙エッセイ(ずいぶん以前のものですが)と読み合わせてほしい。
3段目後半にこう書いた。
【人が人生の途上で遭遇する苦しみや悲しみを、いったいだれが肩代わりできようか。まして言葉によって、
そう簡単に救ったり救われたりできるものではないのである。
現身の凡夫にとってできることは、共感の言葉すら見いだせないことに苦悶することである。それは苦し
み悲しむ相手のそば近くいて、共に涙することかもしれない。そこには言葉を超えた世界がある。その後、
にじみ出るひと言こそ「役に立つ言葉」ではないだろうか。】
Fさんが書かれるように「立場が変わったなら私も必死で・・・」。このところです。「もし、私が相手だったら・・・」
と考えるところが「共感」のスタートである。「あたかも、自分のことのように」感じられことが肝要である。
カウンセリングの第一線で、そしてまたカウンセリングスーパーバイザーとして35年余。されど、されども、自らに問うてみて、内心忸怩たる思いの私である。
今年は講演や執筆活動は少なめにして、ささやかでも「グリーフ(悲嘆)ケア(カウンセリング)」の集いを持ちたいと思っている。
つづきはまた。それでは今宵はこれにて。
通称yoーサンこと仏教者にして Counseling Supervisor の米沢豊穂です。
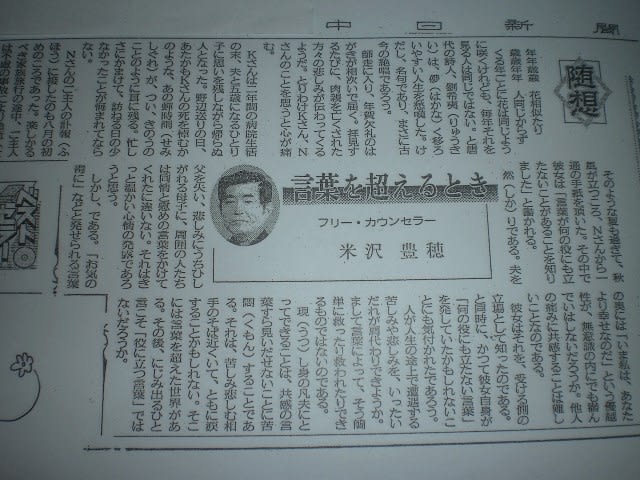
いつも交信(心)頂いている、ある方のブログ(昨年12月)に下記のような一節があった。
愛娘に先立たれた人が悲しく私に言われたのです
「生きていてもしょうがない」
咄嗟には言葉もなくて
でも言いました
「生きていてもしょうがない命なんてない」と
でも考えてしまいます
立場が変わったなら私も必死で
「どう生きよう」と問うたでしょう
悲し過ぎますね
人間長く生きて来ると、このような場面に出合うことは少なからずあると思う。全くない方もあるかもしれないが、それは人間関係の深さにもよるものである。
このブログを書かれているFさんは、当然のことながらお目に掛かったことはなく、お写真すら拝見していない。されど私は「文章は人なり」と思っている。Fさんのブログをお訪ねすると、私は必ずバックナンバーを数編は読ませて頂く。
奇を衒った言葉や画像はない。自ら感じられることを淡々と記されたものが多い。しかしそのいずれもが心に響く。それはこの方の感性の然らしむるところだろうと思う。そしてまた互いに「お念仏」に連なることも浅からざるご縁と思う。
もう一度Fさんの文章を読んでみてほしい。
>咄嗟には言葉もなくて でも言いました・・・
でも考えてしまいます 立場が変わったなら私も必死で
「どう生きよう」と問うたでしょう・・・
このところなんです。冒頭の拙エッセイ(ずいぶん以前のものですが)と読み合わせてほしい。
3段目後半にこう書いた。
【人が人生の途上で遭遇する苦しみや悲しみを、いったいだれが肩代わりできようか。まして言葉によって、
そう簡単に救ったり救われたりできるものではないのである。
現身の凡夫にとってできることは、共感の言葉すら見いだせないことに苦悶することである。それは苦し
み悲しむ相手のそば近くいて、共に涙することかもしれない。そこには言葉を超えた世界がある。その後、
にじみ出るひと言こそ「役に立つ言葉」ではないだろうか。】
Fさんが書かれるように「立場が変わったなら私も必死で・・・」。このところです。「もし、私が相手だったら・・・」
と考えるところが「共感」のスタートである。「あたかも、自分のことのように」感じられことが肝要である。
カウンセリングの第一線で、そしてまたカウンセリングスーパーバイザーとして35年余。されど、されども、自らに問うてみて、内心忸怩たる思いの私である。
今年は講演や執筆活動は少なめにして、ささやかでも「グリーフ(悲嘆)ケア(カウンセリング)」の集いを持ちたいと思っている。
つづきはまた。それでは今宵はこれにて。










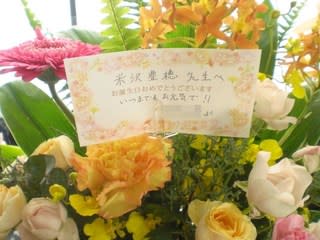
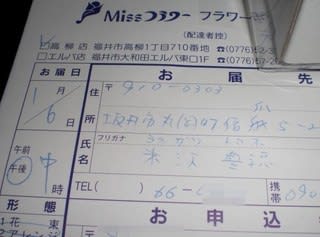
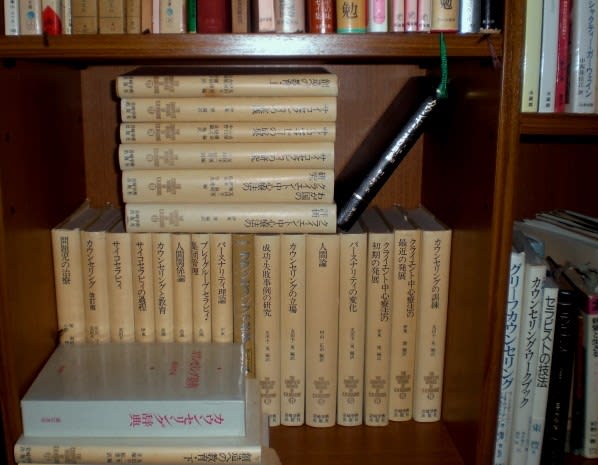
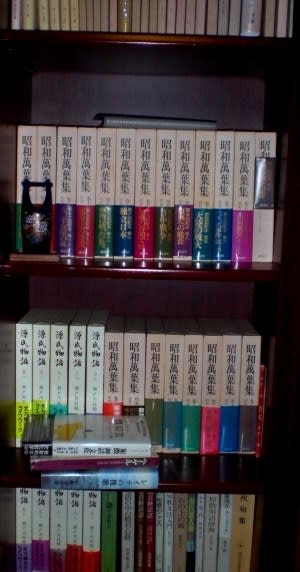
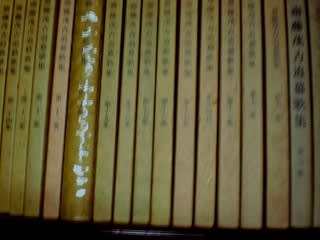
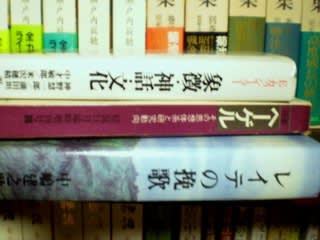
 一昨年暮れに母が身罷り、昨年は沈痛な正月だった。昨暮れに1周忌を勤めて、何となく気が抜けていたある日のこと。
一昨年暮れに母が身罷り、昨年は沈痛な正月だった。昨暮れに1周忌を勤めて、何となく気が抜けていたある日のこと。 ふつう、このように食べやすい大きさ1個ずつに切れて詰まっている。
ふつう、このように食べやすい大きさ1個ずつに切れて詰まっている。





