ドイツベルリン。昭和11年(1936年8月)オリンピックが開催されました。
このオリンピック。記録を調べますれば「日本人の活躍」が目を引きます。
「民族の祭典」「美の祭典」という記録映画(?ですが。この話題は避けます)を見ますと、やはり印象に残るのが「バトンを落としたドイツリレーチームを見ていたヒットラー」ではないでしょうか。
という訳で、あの棒高跳びの名勝負「西田・大江」の活躍は日本オリンピック史上まれに見る名勝負だったと思えます。
当時、ベルリンには日本人が案外住んでおりました。
「西島さん、今日のお目当ては?」
「この前、三段跳びで優勝したでしょ。今日もね、行けるんじゃないかって」
「今日は棒高飛びでしたっけ」
「そうそう、西田と大江が出るんですよ」
結果。5時間を越える熱戦。優勝はアメリカのメドゥウス。大江と西田は2位・3位の決定戦をせず。メダルを半分にして「友情のメダル」と致します。
西島は「美の祭典」その棒高跳びのシーンで日の丸を持って応援しているのを写されております。
「西島さん独逸へはどうして・・」(三井の駐在員が尋ねます)
「独逸の技術を・・・・見に来たんです」
西島亮二。日本造船界に革命的業績を残した「異端児」です。
遡ること1年前。昭和10年(1935年)9月。横須賀工廠から艦政本部第四部へ転勤を命ぜられました西島です。
横須賀で建造した「大鯨」の建造が評価されてのものでした。西島は九州大学の出身。東大出身者が殆どの艦政部にあっては異例の人事でした。
「独逸造船監督官」彼の肩書きでした。
ですが、「友鶴事件」を上回る事件「第四艦隊事件」が発生します。西島は研究どころではなくなります。この事件の調査を指揮するのも「平賀」でした。
平賀は波により船体が破損した原因は「電気溶接による変形」と見ていたのでした。西島は「大鯨」は船体を電気溶接を駆使して建造しております。また、横須賀の工廠では電気溶接の研究が進んでおり、その主任が「福田烈」でした。
艦政部内。調査委員会席上です。
「船体が破損したのは、電気溶接をむやみに使用したからではないか!!」
平賀吼えています。
「どうだね?西島君!」
「・・・・・・・」
西島は反論できずにおります。ですが、横須賀で経験した溶接技法全てに疑問を持っていたわけではありません。自問自答を繰り返しております。
「最近の造船屋が電気溶接に酔っぱらっているから、こんな事件が起こるんだ」とも溶接に関してはことさら過激な発言を繰り返す平賀です。
「溶接には不測の害がないと断言できないの反し、リベットを用いて充分立派な船が出来るんだから、何も好んで妖しげな電気溶接を使う必要があろうか。そう思わんかね牧野君」と話していたとも言います。
確かに、当時の日本の技術において電気溶接は未熟なところがありました。
「単に重量軽減の利点だけで電気溶接を行っていたというのが実際だったと思います。当時、船体そのものにどう影響するかとまではまだ上手く説明できない。そんな状況でした」とは、大和設計に関わる松本喜太郎です
西島は破損した船体の詳細を見ております。
「電気溶接個所だけではない。リベットで繋げた部分にも同じような破損個所が見受けられる。たしかに溶接は技術的に未熟なところもあるが」
だが、当時の平賀へ意見する者はおらず、(言っても仕方ない?と思われている節も多々ありますが・・)平賀の推し進める「溶接制限措置法」がそのまま受け入れられるのでした。
「松本!(松本喜太郎⇒大和設計船殻担当)これをすぐ実行に移せ」
部屋に入るなり平賀が怒鳴っております。
「何をもたもたしておるのかぁぁ!」
「先生、これは?」
「これは?君は何寝ぼけた事を言っておるのだ!」
松本は平賀直筆のメモを見て驚きました。
尽く、溶接を排除し、既存艦艇の改修を行うべくその方策が書かれているのでした「ここだけの話だけど・・・」艦政部内手洗い。
「どうした?」
「平賀先生、ありゃ、溶接嫌いもいいとこだぜ!絶対に私情だよな。お前思わんか?」
「思うがなぁぁ」
トイレ内での噂話以上に平賀の溶接嫌いの話は日増しにそのトーンを上げていくのでした。
横須賀海軍工廠内、福田烈を尋ねる西島でした。
ちょうど、「第四艦隊事件」の後始末が平賀の一声で本決まりになり、再び「独逸監督官」に任命された直後の事です。
「福田さん。やはり溶接の研究と実験はやめずにおられるのですね」
「そりゃ、そうだ。総トン数を制限されているんだ。少しでも艦体を軽量化するには電気溶接しかないじゃないか」
「福田さんにとって平賀さんとは・・」
「まぁ府立一中からの先輩だしなぁ。でも平賀さんも時期解るようになるさ。世界の趨勢は溶接だし、今から技術を研究しておけば船の完成スピードも格段に上がるのだからね」
「そうは、言っても、今建造している空母ですが・・」
「『飛龍』だな。西島君。溶接の音がしないって言いたいんだろう!」
図星でした。「大鯨」建造のときはあれほど電気溶接の音がしていた工廠内に今はリベットを打ち込む音が響いているのでした。
「福田さん、実は独逸へ行ってきます」
「そうだったね。独逸の他では電気溶接の文献は見当たらない。いい機会ではないか。徹底的に勉強して日本での電気溶接の名誉を復活させてもらいたい・・ものだ」福田は笑ってそう言いました。
西島は、こんな時勢にあっても黙々と電気溶接の実験を繰り返す福田烈の姿勢に頭が下がる思いがしたのです。
「自分自身日本におるが強力させてもらうヨ」最後の言葉でした。
福田烈は西島が独逸へ旅立った後、大掛かりな実験を試みます。
仮想敵国と成りうる米国の新造空母「サラトガ」の格納庫より上の部分の実物大模型を作成しこれに対し艦爆を仕掛けその破損状況を調査するというものでした。
福田はあることを思いつきました。想定空母甲板の半分をリベット、半分を溶接にしその状況を比較するというものです。
鹿島(当時爆撃場がありました)で行われた実験。
結果。
鋲接の部分はリベットが飛び散り、隣接する区画も破損していたが、溶接部分では、爆弾が落とされたその部分のみの被害で済んでおりました。
福田は溶接が単に「軽量化」だけではなく「防御」の面でも大いに効果がると確信したのでした。
西島ベルリン着。
福田との話があってから船中で西島は決心していたのでした。
「内燃機関の研究もしたいのだが。独逸では電気溶接技術の習得。これ一本にしよう」
この技術が無ければ、西島が考えている船を部分的にパーツとして組み立てる「ブロック工法」が出来なくなるのでした。
「A140F5」が出来上がるのと同じ頃西島はベルリンの地に立つのでした。
このオリンピック。記録を調べますれば「日本人の活躍」が目を引きます。
「民族の祭典」「美の祭典」という記録映画(?ですが。この話題は避けます)を見ますと、やはり印象に残るのが「バトンを落としたドイツリレーチームを見ていたヒットラー」ではないでしょうか。
という訳で、あの棒高跳びの名勝負「西田・大江」の活躍は日本オリンピック史上まれに見る名勝負だったと思えます。
当時、ベルリンには日本人が案外住んでおりました。
「西島さん、今日のお目当ては?」
「この前、三段跳びで優勝したでしょ。今日もね、行けるんじゃないかって」
「今日は棒高飛びでしたっけ」
「そうそう、西田と大江が出るんですよ」
結果。5時間を越える熱戦。優勝はアメリカのメドゥウス。大江と西田は2位・3位の決定戦をせず。メダルを半分にして「友情のメダル」と致します。
西島は「美の祭典」その棒高跳びのシーンで日の丸を持って応援しているのを写されております。
「西島さん独逸へはどうして・・」(三井の駐在員が尋ねます)
「独逸の技術を・・・・見に来たんです」
西島亮二。日本造船界に革命的業績を残した「異端児」です。
遡ること1年前。昭和10年(1935年)9月。横須賀工廠から艦政本部第四部へ転勤を命ぜられました西島です。
横須賀で建造した「大鯨」の建造が評価されてのものでした。西島は九州大学の出身。東大出身者が殆どの艦政部にあっては異例の人事でした。
「独逸造船監督官」彼の肩書きでした。
ですが、「友鶴事件」を上回る事件「第四艦隊事件」が発生します。西島は研究どころではなくなります。この事件の調査を指揮するのも「平賀」でした。
平賀は波により船体が破損した原因は「電気溶接による変形」と見ていたのでした。西島は「大鯨」は船体を電気溶接を駆使して建造しております。また、横須賀の工廠では電気溶接の研究が進んでおり、その主任が「福田烈」でした。
艦政部内。調査委員会席上です。
「船体が破損したのは、電気溶接をむやみに使用したからではないか!!」
平賀吼えています。
「どうだね?西島君!」
「・・・・・・・」
西島は反論できずにおります。ですが、横須賀で経験した溶接技法全てに疑問を持っていたわけではありません。自問自答を繰り返しております。
「最近の造船屋が電気溶接に酔っぱらっているから、こんな事件が起こるんだ」とも溶接に関してはことさら過激な発言を繰り返す平賀です。
「溶接には不測の害がないと断言できないの反し、リベットを用いて充分立派な船が出来るんだから、何も好んで妖しげな電気溶接を使う必要があろうか。そう思わんかね牧野君」と話していたとも言います。
確かに、当時の日本の技術において電気溶接は未熟なところがありました。
「単に重量軽減の利点だけで電気溶接を行っていたというのが実際だったと思います。当時、船体そのものにどう影響するかとまではまだ上手く説明できない。そんな状況でした」とは、大和設計に関わる松本喜太郎です
西島は破損した船体の詳細を見ております。
「電気溶接個所だけではない。リベットで繋げた部分にも同じような破損個所が見受けられる。たしかに溶接は技術的に未熟なところもあるが」
だが、当時の平賀へ意見する者はおらず、(言っても仕方ない?と思われている節も多々ありますが・・)平賀の推し進める「溶接制限措置法」がそのまま受け入れられるのでした。
「松本!(松本喜太郎⇒大和設計船殻担当)これをすぐ実行に移せ」
部屋に入るなり平賀が怒鳴っております。
「何をもたもたしておるのかぁぁ!」
「先生、これは?」
「これは?君は何寝ぼけた事を言っておるのだ!」
松本は平賀直筆のメモを見て驚きました。
尽く、溶接を排除し、既存艦艇の改修を行うべくその方策が書かれているのでした「ここだけの話だけど・・・」艦政部内手洗い。
「どうした?」
「平賀先生、ありゃ、溶接嫌いもいいとこだぜ!絶対に私情だよな。お前思わんか?」
「思うがなぁぁ」
トイレ内での噂話以上に平賀の溶接嫌いの話は日増しにそのトーンを上げていくのでした。
横須賀海軍工廠内、福田烈を尋ねる西島でした。
ちょうど、「第四艦隊事件」の後始末が平賀の一声で本決まりになり、再び「独逸監督官」に任命された直後の事です。
「福田さん。やはり溶接の研究と実験はやめずにおられるのですね」
「そりゃ、そうだ。総トン数を制限されているんだ。少しでも艦体を軽量化するには電気溶接しかないじゃないか」
「福田さんにとって平賀さんとは・・」
「まぁ府立一中からの先輩だしなぁ。でも平賀さんも時期解るようになるさ。世界の趨勢は溶接だし、今から技術を研究しておけば船の完成スピードも格段に上がるのだからね」
「そうは、言っても、今建造している空母ですが・・」
「『飛龍』だな。西島君。溶接の音がしないって言いたいんだろう!」
図星でした。「大鯨」建造のときはあれほど電気溶接の音がしていた工廠内に今はリベットを打ち込む音が響いているのでした。
「福田さん、実は独逸へ行ってきます」
「そうだったね。独逸の他では電気溶接の文献は見当たらない。いい機会ではないか。徹底的に勉強して日本での電気溶接の名誉を復活させてもらいたい・・ものだ」福田は笑ってそう言いました。
西島は、こんな時勢にあっても黙々と電気溶接の実験を繰り返す福田烈の姿勢に頭が下がる思いがしたのです。
「自分自身日本におるが強力させてもらうヨ」最後の言葉でした。
福田烈は西島が独逸へ旅立った後、大掛かりな実験を試みます。
仮想敵国と成りうる米国の新造空母「サラトガ」の格納庫より上の部分の実物大模型を作成しこれに対し艦爆を仕掛けその破損状況を調査するというものでした。
福田はあることを思いつきました。想定空母甲板の半分をリベット、半分を溶接にしその状況を比較するというものです。
鹿島(当時爆撃場がありました)で行われた実験。
結果。
鋲接の部分はリベットが飛び散り、隣接する区画も破損していたが、溶接部分では、爆弾が落とされたその部分のみの被害で済んでおりました。
福田は溶接が単に「軽量化」だけではなく「防御」の面でも大いに効果がると確信したのでした。
西島ベルリン着。
福田との話があってから船中で西島は決心していたのでした。
「内燃機関の研究もしたいのだが。独逸では電気溶接技術の習得。これ一本にしよう」
この技術が無ければ、西島が考えている船を部分的にパーツとして組み立てる「ブロック工法」が出来なくなるのでした。
「A140F5」が出来上がるのと同じ頃西島はベルリンの地に立つのでした。















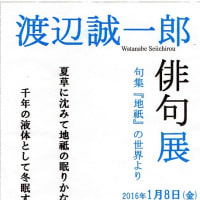

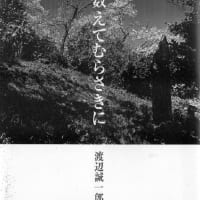








画家の東山魁夷も、当時のベルリンに留学しておったと思います。
ベルリンオリンピックといえば・・・
レニ・リーフェンシュタール、聖火リレー、入場行進のハイル・ヒットラー・・・
でも家主様が「触れない」との仰せ。小生も触れぬことにします。
鋲打ち工法か、溶接工法か・・・
張り合わせる鉄板の他に鋲の分の重さが加わりますね。
しかも満載排水量で7万2千トンの艦(フネ)ですから、鋲の重さも半端でないですね。
水に対する抵抗の問題もあるでしょう。
やはり艦船に「沈頭鋲」は無理だったでしょうか・・・
しかし溶接工法が重量軽減だけでなく、防禦の面でも鋲打ち工法にまさるというのは驚きです。
しかも当時の実験が証明しているのですから。
確かに被弾の振動で「鋲が緩む」ということは考えられますね。
「○×」という立派なものがあるのに、何でまたことさらに新しいものを・・・
技術に限ったことではありませんが、過渡期にはよくある発想ですね。
頭が石器時代の爺さんたちは、えてして若い者の発想を認めたがらないものです。
(小生の業界にも、未だに老害をタレ永し続ける大センセーが・・・)
それで何かが起きると、何でもかんでも「○×」が悪いということになるのですから、若い者はたまりません。
たとえば友鶴事件もそうでしたが、藤本さんの設計した艦船が抱えていた問題は溶接工法のみではありません。
藤本さんはじめかつての部下(後輩)たちのやることを苦々しく思っていたのが、平賀さんだったのでしょう。
自分の理解を超えることに対して、人間はえてしてこういう反応を示します。
それが藤本さんの設計したフネが続けて事故を起したので、
「溶接工法が悪い」ということになったのでしょうね。
導入期にあった溶接工法に問題を生じた時、
「直ちに修理」となれば鋲打ち工法というのも、分らぬではありません。
戦闘艦艇の修理は急を要します。
「問題のない溶接工法」の開発を待ってはおれない事情もあったのではないか・・・
ということを平賀さんのために申し上げます。
しかし造船界のその後の展開を見れば、溶接工法が主流になっています。
藤本さんの導入した技術は、方向性としては間違っていなかったのだと思います。
(ですが、このコミックのおかげで平賀の事が知らされております。これはこれで中々出来のよいコミックです。内容にケチを付けるものではございません)
しかして、大和・武蔵の建造過程を顧みますれば、多くの人がその思いを込めて建造していることがわかります。
今少しばかり続けさせてください。
実績を重視し技術の研究を怠ると、浦島太郎状態に・・・・
なかなか新しいものを受け入れたく無い人も居ますが、いつも近未来を想像し研究する人がいます。
基礎があって、その上に新しい技術が出来ていくのでしょう。
大和の設計=日本の設計でもあるようですね。
21世紀のこの国は「老害」に「老害」が重なり、さらにその上に「老害」が積み重なってしまいました。
山脈を乗り越えようとする「若手」と呼ばれる我々?も、一昔前ならばすでに「お年寄り」です。
本来の、新しい価値を創造すべき世代は、ロストジェネレーションと呼ばれてしまいました。20代・30代の人間はまったく覇気が不足しているように感じます。
「老害大国」は我々の世代も巻き込んで、でーん!と一気に倒れこみそうです。
ですから大和が誕生したのかとも思いました。
大和の建造、特に戦後日本の技術立国を考えますと、共通した部分はあるのでした。
鋲か熔接も・・・。
ですが、結局一号艦はブロックで建造されることとなるのです。