本来ならば、本日の更新は「大和を生みし者達その五」をお話する予定でございました。ですが、史実を訂正する個所が何個か見つかりました。
今回はそれを中心に語ります。
「ヤヌス・シコルスキー」氏はポーランド人です。彼は、ポーランドにおりながら「戦艦大和建造」に関する書を著しております。
「戦艦大和図面集 (株)光人社 1998年2月19 第一刷」がこれですが、この翻訳解説の部分にはこうございます。
「船体の主要防御区画の中心部をなすエンジンルームは200mmの厚い装甲板で覆われることになっている。この装甲板は防御用というだけでなく、船体構造の一部となっているため、いったんエンジンを据え付けたが最後、万一、何か問題が起きても、取り替えることはできない。設計陣は原案にもどり、推進設備として軸馬力15000馬力のタービンエンジンを使わざるをえなかった。1937年3月、日本帝国海軍を代表する軍艦設計の大家、平賀譲(技術中将)博士が最終設計案を指導した」
(同氏著、抜粋)
気づかなかったのでした。ここに記載されております「1937年3月」ですが。この日にポイントがあったわけでした。
ですが、時系列を整理いたしますと「A140F5」いわゆる「最終設計案」が完成するのが1936年7月20日です。そしてこの段階で設計案は「呉海軍工匠」へ渡っております。牧野茂もこの時期には図面作成に取り掛かっておるはずです。
その半年近く経ってからのエンジン主要の変更です。
余りにも、突発的なそして計画性のない出来事のように思えるのでした。
牧野茂の視点から見ますと
1937年(昭和12年)牧野は「福田啓二」等が練り上げた「A140F5」の図面を元に詳細な設計図を検証していることとなります。牧野は図面への打ち合わせ等に忙しく回っていた頃です
ここで訂正しなくてはならないのが「牧野はA140の詳細を知らなかった」とした「その四」のくだまきです。
牧野は詳細をまた、設計案の過程も知っていたのでした。
お詫び申し上げます。
さて、図面が呉へ到着した後の主機関変更です。
牧野茂「艦船ノート」にはこうあります。酔漢流に再現して見ましょう。
昭和12年(1937年)3月。牧野はイギリスジョージ6世戴冠観艦式に参列いたします(「スコッチの話」⇒「ロイヤルサリュート編」でした)
そして、その洋行途中、牧野は海軍艦政部を尋ねます
「どうも、お久しぶりです。牧野です」
と、いつものように艦政第四部のドアを開けた牧野でした。
「あれ?福田主任は?それにどうしたんです?皆して頭抱え込んで・・・」
ある技官が牧野に話かけます。
「後で福田さんから話があると思うけれど・・・単刀直入に聞くゾ!牧野、今から設計図の書き換えが可能か?」
「えぇぇぇぇぇ・・・・・そんなぁぁぁぁ!もう詳細図面の作成に取り掛かっているんですよ。どこをどう直すんですかぁぁ」
牧野絶叫です。
「書き換えるって・・・僕はこれから『足柄』でイギリスへ向うんですよぉぉ」
艦政部のドアが開きました。設計主任、「福田啓二」が入って来ました。
牧野は福田の顔を見て驚きました。白髪が増えていたのです。
「こんなにも、設計に命を削っておったのか」と思ったのでした。
「やぁ、牧野君。お久しぶり。呉はどうだね?」
「どうだねって、主任、設計図の書き直しって・・一体全体・・」
「もう耳に入ったか。君には連絡をしなければと思っておったが・・結論を言おう。『A140』の主要機関はタービン4基でいくことになった」
牧野は返す言葉を失いました。呉では、内示図面から詳細な設計図への落とし込みが始まっているのです。この場での計画変更は、スケジュール全体へ影響するのは必至でした。
主機の変更は機関室ばかりではなく、配管、周辺機関全てに影響し、排水量、燃料タンクも変わってきます。
「半年は・・・狂います」
牧野は率直に意見するのでした。
「まぁ、慌てるな。そうなるやもしれんと考えて、図面は用意してある」
「用意って?」
「平賀さんのディーゼル嫌いは艦政でも有名だからな。タービン4基の想定はしたおいたんだよ」
「でも、呉には僕はいない・・・誰が・・・」
牧野はふと「松本喜太郎」を思い出しました。
「あの石橋を叩いても渡らない松本さんまで、これまで慎重にことを運んでいたのに、この土壇場になって。平賀先生はこの適時を使ったのか・・・」
「牧野君!牧野君!どうしたんだ?」
「いや、そのう・・・平賀先生が仕組んだものかと・・」
福田の顔が曇ったように見えました。
「まず、詳細図面の作成は艦政部で行うが。君はイギリスへ行きたまえ」
福田が冷静に話をしているのを聞き、牧野も少しは頭の血が下がりました。
戦艦武蔵建造録では⇒「この変更はかねてから予期されていたかのように極めて速やかに基本計画の改正が行われた」とあります。
4月3日。牧野を載せた「足柄」はイギリスへと向います。
艦政本部では修正図面の作成に取り掛かりますが、製図工50名ではとても足りません。牧野は出航直前、呉工匠から製図工を艦政部へ数名派遣いたしました。
「西君(西時男⇒腕利きの製図工。呉の技手)留守中頼む」
牧野はこう言い残してイギリスへと旅立つのでした。
「折角、設計建造準備が艦本(艦政本部)内示図面によって着々進んでいたところに、十二年三月末に至り、主機のディーゼルをやめて全てタービン艦とする基本設計の大変更が行なわれた。機関室関連の部分的改正にとどまらず、長さも三メートル増し、排水量も三千トン増えるので、線図の変更もあった。
この大事な時期に私は、重巡足柄の英国訪問の遠洋航海に乗艦を命ぜられ、約四ヶ月弱、呉を留守するハメになり、大変気がかりであった」
(牧野茂⇒艦船ノートより)
「主機がディーゼルとタービン併用からタービンのみに。相当進んでいた線図を塗りつぶして書き直した」
(造船官の記録から「呉工匠船殻主任 梶原正夫の証言)
「ディーゼルかぁ。期待していたのになぁ。がっかりだなぁ。日本のディーゼルは確かに信用性が無くはない。でも、世界の趨勢はディーゼルだよなぁ。」とは、牧野です。
「大和で最も見劣りするのは、その機関ではかろうか」
昭和56年座談会で・・出席者 牧野茂、松本喜太郎、福井静夫、船殻担当呉工匠西島亮二、福井又助技術大佐(当時)⇒メンバーすごい!
その席での牧野の言葉でした。
テレビCMです「ベルリン世界陸上開催さる!」(どうも言い回しが昭和臭く?なってきた、酔漢でございます)という。
ベルリンと言えば「ベルリンオリンピック」
「前畑頑張れ」は有名ですが。このオリンピックが開催されましたのが昭和11年(1936年)8月の事です。
その競技。これはオリンピック史上にも残る名勝負ですが、「棒高飛」「西田と大江」の活躍は記録に残っているところです。5時間を越える勝負。最後はアメリカが金。日本は銀、銅となります。二つのメダルを半分にして「友情のメダル」としたことは有名な話ですが、その競技場の中。
映画「美の祭典」に突如現れる「日の丸おじさん」⇒ドアップです。
「にっぽぉぉーーーん」と叫んでおります。
この人こそ「西島亮二」なのです。
遅れました!次回この奇跡ともいうべき「壱号艦建造」を西島の視点から語ります。「大和」と「武蔵」福田を初め作り上げた設計図は同じです。
ですが、「大和」は武蔵の半分近いコストで出来上がるのでした。
この過程を語りたいと考えております。
驚きましたか?
今回はそれを中心に語ります。
「ヤヌス・シコルスキー」氏はポーランド人です。彼は、ポーランドにおりながら「戦艦大和建造」に関する書を著しております。
「戦艦大和図面集 (株)光人社 1998年2月19 第一刷」がこれですが、この翻訳解説の部分にはこうございます。
「船体の主要防御区画の中心部をなすエンジンルームは200mmの厚い装甲板で覆われることになっている。この装甲板は防御用というだけでなく、船体構造の一部となっているため、いったんエンジンを据え付けたが最後、万一、何か問題が起きても、取り替えることはできない。設計陣は原案にもどり、推進設備として軸馬力15000馬力のタービンエンジンを使わざるをえなかった。1937年3月、日本帝国海軍を代表する軍艦設計の大家、平賀譲(技術中将)博士が最終設計案を指導した」
(同氏著、抜粋)
気づかなかったのでした。ここに記載されております「1937年3月」ですが。この日にポイントがあったわけでした。
ですが、時系列を整理いたしますと「A140F5」いわゆる「最終設計案」が完成するのが1936年7月20日です。そしてこの段階で設計案は「呉海軍工匠」へ渡っております。牧野茂もこの時期には図面作成に取り掛かっておるはずです。
その半年近く経ってからのエンジン主要の変更です。
余りにも、突発的なそして計画性のない出来事のように思えるのでした。
牧野茂の視点から見ますと
1937年(昭和12年)牧野は「福田啓二」等が練り上げた「A140F5」の図面を元に詳細な設計図を検証していることとなります。牧野は図面への打ち合わせ等に忙しく回っていた頃です
ここで訂正しなくてはならないのが「牧野はA140の詳細を知らなかった」とした「その四」のくだまきです。
牧野は詳細をまた、設計案の過程も知っていたのでした。
お詫び申し上げます。
さて、図面が呉へ到着した後の主機関変更です。
牧野茂「艦船ノート」にはこうあります。酔漢流に再現して見ましょう。
昭和12年(1937年)3月。牧野はイギリスジョージ6世戴冠観艦式に参列いたします(「スコッチの話」⇒「ロイヤルサリュート編」でした)
そして、その洋行途中、牧野は海軍艦政部を尋ねます
「どうも、お久しぶりです。牧野です」
と、いつものように艦政第四部のドアを開けた牧野でした。
「あれ?福田主任は?それにどうしたんです?皆して頭抱え込んで・・・」
ある技官が牧野に話かけます。
「後で福田さんから話があると思うけれど・・・単刀直入に聞くゾ!牧野、今から設計図の書き換えが可能か?」
「えぇぇぇぇぇ・・・・・そんなぁぁぁぁ!もう詳細図面の作成に取り掛かっているんですよ。どこをどう直すんですかぁぁ」
牧野絶叫です。
「書き換えるって・・・僕はこれから『足柄』でイギリスへ向うんですよぉぉ」
艦政部のドアが開きました。設計主任、「福田啓二」が入って来ました。
牧野は福田の顔を見て驚きました。白髪が増えていたのです。
「こんなにも、設計に命を削っておったのか」と思ったのでした。
「やぁ、牧野君。お久しぶり。呉はどうだね?」
「どうだねって、主任、設計図の書き直しって・・一体全体・・」
「もう耳に入ったか。君には連絡をしなければと思っておったが・・結論を言おう。『A140』の主要機関はタービン4基でいくことになった」
牧野は返す言葉を失いました。呉では、内示図面から詳細な設計図への落とし込みが始まっているのです。この場での計画変更は、スケジュール全体へ影響するのは必至でした。
主機の変更は機関室ばかりではなく、配管、周辺機関全てに影響し、排水量、燃料タンクも変わってきます。
「半年は・・・狂います」
牧野は率直に意見するのでした。
「まぁ、慌てるな。そうなるやもしれんと考えて、図面は用意してある」
「用意って?」
「平賀さんのディーゼル嫌いは艦政でも有名だからな。タービン4基の想定はしたおいたんだよ」
「でも、呉には僕はいない・・・誰が・・・」
牧野はふと「松本喜太郎」を思い出しました。
「あの石橋を叩いても渡らない松本さんまで、これまで慎重にことを運んでいたのに、この土壇場になって。平賀先生はこの適時を使ったのか・・・」
「牧野君!牧野君!どうしたんだ?」
「いや、そのう・・・平賀先生が仕組んだものかと・・」
福田の顔が曇ったように見えました。
「まず、詳細図面の作成は艦政部で行うが。君はイギリスへ行きたまえ」
福田が冷静に話をしているのを聞き、牧野も少しは頭の血が下がりました。
戦艦武蔵建造録では⇒「この変更はかねてから予期されていたかのように極めて速やかに基本計画の改正が行われた」とあります。
4月3日。牧野を載せた「足柄」はイギリスへと向います。
艦政本部では修正図面の作成に取り掛かりますが、製図工50名ではとても足りません。牧野は出航直前、呉工匠から製図工を艦政部へ数名派遣いたしました。
「西君(西時男⇒腕利きの製図工。呉の技手)留守中頼む」
牧野はこう言い残してイギリスへと旅立つのでした。
「折角、設計建造準備が艦本(艦政本部)内示図面によって着々進んでいたところに、十二年三月末に至り、主機のディーゼルをやめて全てタービン艦とする基本設計の大変更が行なわれた。機関室関連の部分的改正にとどまらず、長さも三メートル増し、排水量も三千トン増えるので、線図の変更もあった。
この大事な時期に私は、重巡足柄の英国訪問の遠洋航海に乗艦を命ぜられ、約四ヶ月弱、呉を留守するハメになり、大変気がかりであった」
(牧野茂⇒艦船ノートより)
「主機がディーゼルとタービン併用からタービンのみに。相当進んでいた線図を塗りつぶして書き直した」
(造船官の記録から「呉工匠船殻主任 梶原正夫の証言)
「ディーゼルかぁ。期待していたのになぁ。がっかりだなぁ。日本のディーゼルは確かに信用性が無くはない。でも、世界の趨勢はディーゼルだよなぁ。」とは、牧野です。
「大和で最も見劣りするのは、その機関ではかろうか」
昭和56年座談会で・・出席者 牧野茂、松本喜太郎、福井静夫、船殻担当呉工匠西島亮二、福井又助技術大佐(当時)⇒メンバーすごい!
その席での牧野の言葉でした。
テレビCMです「ベルリン世界陸上開催さる!」(どうも言い回しが昭和臭く?なってきた、酔漢でございます)という。
ベルリンと言えば「ベルリンオリンピック」
「前畑頑張れ」は有名ですが。このオリンピックが開催されましたのが昭和11年(1936年)8月の事です。
その競技。これはオリンピック史上にも残る名勝負ですが、「棒高飛」「西田と大江」の活躍は記録に残っているところです。5時間を越える勝負。最後はアメリカが金。日本は銀、銅となります。二つのメダルを半分にして「友情のメダル」としたことは有名な話ですが、その競技場の中。
映画「美の祭典」に突如現れる「日の丸おじさん」⇒ドアップです。
「にっぽぉぉーーーん」と叫んでおります。
この人こそ「西島亮二」なのです。
遅れました!次回この奇跡ともいうべき「壱号艦建造」を西島の視点から語ります。「大和」と「武蔵」福田を初め作り上げた設計図は同じです。
ですが、「大和」は武蔵の半分近いコストで出来上がるのでした。
この過程を語りたいと考えております。
驚きましたか?















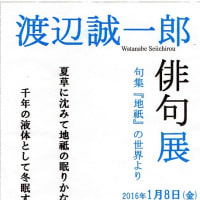

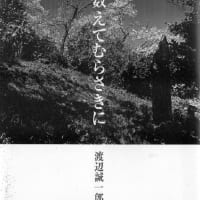








歴史の研究をやっていると(専門じゃないけど)、よくあることです。
たとえば大黒屋光太夫です。
帰国の後、彼は生涯を小石川の薬草園に幽閉されて過したことになっていました(吉川弘文館版『大黒屋光太夫』)。
しかし新資料が発見され、伊勢の国は白子の浜に帰り、親戚たちと会うことが許されたことが明らかになりました(岩波新書版『大黒屋光太夫』)。
歴史に限らず、我が業界でも・・・
論文を書いて発表した後に、「同じことが別の文献に書いてあった」なんてことが分ることがあるのです。
分った時には訂正する。
それでいいのではないでしょうか。
あまり気に病まぬことですよ。
それにしても今回の話にあった座談会、凄いですね。
昭和56年つったら、お互い浪人中だったね。
「大和」に関係した技術者がある程度まとまって健在。
そういう時期が、そろそろ限界になりつつあった頃ですね。
現存するその記録は、技術史の史料としても貴重なものだと思います。
ところで「信濃」です。
信濃沈没の原因として気密試験の未了を挙げました・・・
豊田穣さんの『空母「信濃」の生涯』によれば、
防毒区画と中甲板以上の区画の気密試験の省略、
軍令部から横須賀工廠に下された命令だったのですね。
マリアナ沖海戦における母艦3隻の喪失・・・
よくよく重大な影響だったのだと思います。
食糧不足に起因する関係者の栄養状態、
損傷を受けた艦船の修理が立て込む中での建造、
過重労働による事故の多発・・・
月並な言い方になりますが、
関係者はよくぞ頑張って「信濃」を作ったと思います。
それだけに実践に参加せぬまま沈没したその生涯が残念でなりません。
「気まぐれな」「思いつきの」根本的な方針変更など、「よくあること」。日常茶飯事です。
主要機関が帆走に変更されるぐらいの、無茶振りです。
まあ、皆さんもそれぞれの職場なりの悲哀はさまざまですね。
足柄。
「飢えた狼」との評価は、実は「嫌悪感」の表現だったとか。
でも、挑みかかるような姿は、これぞ軍艦!ですね。
信濃にしろ、急場しのぎの改装空母にしろ、軍令部は制式空母と同列の軍事力としてカウントしてますよね。
まだまだ米機動部隊と五分に闘えるとの見通しで、結局は悲惨な状況がより長く続いてしまっただけでした。
大戦後期は艦載機が大型化し、飛行甲板の狭さと最大戦速のダウンで、離着艦が出来ないような空母ばかりでした。
パイロットの錬度についてはご承知の通りです。
それでも国民は、軍令部を信じ、神風が吹くことを待っていたのですね。
仙台七夕の時期は、原爆の記憶の時期ですね。
どんな種明かしがあるのかチョット楽しみでもあります。
大和ベースの船には、空母もあったかと?
まぁ、比較には出来ませんが。
その3楽しみにしてます。
さて、信濃ですが、横須賀の造船所がその建艦過程において最後の詰めまでめんどう見切れていないということが呉にも伝わります。
西島亮二はそれを感じ、「信濃の最終工程を呉で」と申し入れます。
そこで呉回航が決定ずけられました。
西島は晩年、「自身がその申し入れをしなければ信濃は無事であったのではなかろうか」と証言しております。
運命とは言え、返す返す、後1年早かったらと思わざるをえません。
横須賀生まれの3号艦。
横須賀の風景が違っておったのかと思います。
本当にありますよね。
ですが、その思惑を推察するのにエネルギーを使うわけです。
果たして、現在「図面」を書いている自身です。
職業もクロンシュタット様はご存知でしょうが、おそらく(「改装屋」と自負しております酔漢ですが)これから予算と喧嘩しなくてはなりません。
本題と離れましたが・・・。
足柄は傑作だと思います。
平賀の魂のような艦ですが・・。
多くの事実に出くわし、それが新しい情報だったりもいたします。
本来ならばすでに「祖父のこと」を語っている時期ですが、興味のまま大和誕生まで語ろうかと決心いたしました。
案外知られていない事が多く、知っていらっしゃる方々も「マニア」的見方をしているものですから、そうではない「くだまき」にしたいと考えております。
酔漢さんのブログを拝見するまで「戦艦大和誕生」という本も、前間孝則という人も知りませんでした。
前間孝則という人は戦後生まれのようですが、相当の資料を集めて書かれたのでしょうね。
ぜひ読んでみようと思います。
吉村昭の「戦艦武蔵」にも艦造の興味深い記述があります。
とうぜん、その艦形も写真や映像で何度も見ています。
が!しかし、です…
実際には、同類の巨砲巨艦時代の戦艦というものを見たことがありません。
一般の船舶ならタンカーやフェリー、大型客船も実際に目にし、船内をじっくり見たことがあるので
頭の中に物差しができており、こんな船と言われればおおよそイメージできますが…
こと巨大戦艦のこととなると「200㎜の装甲板」とか、それが「躯体構造の一部」であるとか聞いても
データがイメージに変換できずに消化不良をおこしてしまいます…
こりゃぁ、このあたりの港でときどき見かける海自の巡洋艦なんか見学してもだめかも…
横須賀あたりへでかけて、米軍の原子力空母でも見学しないとスケールの実感ができねんでねーべかねぇ~~~!
それにしても「大和誕生」は当時の艦政部、オールスターキャストです。それぞれの繫がりが一本のストーリーとして構成され、また史料も忠実に再現されております。
ルポそして編集と一流の「歴史科学書」だと思いました。
自身の間違いがかなり訂正されました。
豪華客船、巨大タンカーではなく、やはり兵器としての船。その巨大な、そして異様なまでの形は圧倒する何かを持っております。
三笠記念館で三笠を見ても、小さいながらやはり軍艦のオーラを感じます。
同感です。