「総員(みな)がんばれ」
「みながんばれ」
第一艦橋よりさらに上、露天の防空指揮所より有賀艦長がありったけの声を伝声管へぶつけております。
残存の全火力を発揮して、阻止撃譲、転舵回避に努めるが、各方面から同時に進んでくる魚雷の白い航跡は、クモの巣のごとく、連続する急降下と機銃は雨のごとく、この双方を無事回避しおおせることは到底不可能で、続いてまたまた左舷に二、三本の魚雷と、中部甲板に七、八発の爆弾が命中、注排水装置の右舷タンクは、すでに満水していたので、累加する左舷の魚雷被害は、刻々艦の傾斜を増加した、
左舷の高角砲、機銃は、ほとんど破壊され、大部分の配員は死傷した。防御力がなくなると見るや、なおさら敵機は左舷をねらい撃つ。艦はもっぱら転舵回避で、敵の攻撃をそらそうと努めるが、艦は左舷がやられている。その傾いた左舷を平衡にたて直すには左旋回するしかない。かつ艦速は低下し、傾斜し、ますます運動の自由を欠き、被害は急速に増加するばかりであった。
時に左舷傾斜十五度。速力はいぜん十八ノット。
十三時五十分
(能村次郎 大和副長 証言 手記より抜粋)
「復元を急げ、復元を急げ」
と有賀幸作艦長みずからが、伝声管にむかって叫んでいた。その姿は空しく、また、悲痛なものを感じさせた。
しかし、左舷に大傾斜した大和の船体を復元させることは、だれが考えてものぞみようがなかった。
私の配置は前部測的所である。ここは艦長がいる防空指揮所の上段に位置しており、ごく近い位置にある。そのため、艦長の戦闘指揮のようすが、手にとるようにわかるのだ。(中略)艦は左に二○度ちかく傾斜して戦闘能力を完全に消失した。断末魔の様相である。すでに沈没は、時間の問題と考えてよかった。(中略)もはや、注排水装置を使用しての復元の方法はない。
最後に残された手段は、右舷の主機械室と六個の罐室に注水することである。
(坂本一郎 大和 上曹 証言 手記より抜粋)
大和注排水装置は建造過程においてもしばしば語ってまいりました。ダメージコントロール、所謂「ダメコン」の装置です。並みの戦艦であれば十分すぎるほどのタンクキャパシティーを持ってしても、そのタンクが満水状態。大和は身を削ってもその復元に努めることとなります。設計段階ではこれでも十分なキャパシティーと想定されております。
もっとも、設計段階においては、航空機による攻撃は想定されておりません。あくまでも、対戦艦としてのダメコンだと言えます。
設計主任「牧野茂」氏は、戦後「いかなる空襲に遭遇したとしても、沈没する設計ではなかった」とこう証言されておられますが、(他の設計陣におきましても同様の証言ではございますが)やはり激しい空襲では、限界が来たと考えます。
艦内、防御指揮所内、能村次郎副長です。最早、注排水ポンプでの艦傾斜復元が不可能である事を知っております。各種警報ブザーが鳴りっぱなしの指揮所内。
有賀艦長からの再三再四の催促が聞こえて来ます。
「艦傾斜の復旧!イソゲ!」
副長はあるジャッジを迫られております。
「この傾斜を復旧させるためには、無傷である『右舷外側十一区画内第三罐室』と『十三区画内第十一罐室』および『十六区右舷水圧機室』への注水以外にはない。しかし、傾斜は一時的には収まるかもしれないが、果たしてこの状態で沖縄まで行きつけることができるのか」副長は、艦を真南へ転身下令した有賀艦長の覚悟を思う時、また自身の職務を遂行する為には、「何としても沖縄到達」を考えなくてはならない。そう信じているのでした。
電話が鳴りました。
受話器を取る副長です。
「タンクの注水限度!右舷機械室、罐室への注水許可を!」
右舷下甲板、注排水指揮所内、防禦指揮官「林 紫郎中佐」(戦死後特進大佐 大和内務長)からです。
「罐室への注水は推進力を失うこととなる。他に手段はないのか」
「ありません。これ以上・・・アリマセン!」
電話はこれで途切れます。
「伝令兵!注排水指揮所!」
副長はありったけの声で指示しました。一人の伝令が注排水指揮所へ向かいます。
更に有賀艦長から。
「傾斜復旧・・・早くしろ!」
副長は決断いたしました。
沖縄到達は推進力にかかっている。思い余って咄嗟には、許可の指令を出しかねた。傾斜のままだと砲銃はうまく撃てないのだ。ついに意を決して注排水指揮所へ
「右舷機械室注水!右舷罐室注水!」を発令す。
(能村次郎大和副長 証言手記より抜粋)
全力運転中の機械室、罐室ー機関科員の配置なり これまで灼熱、噪音とたたかい、終始黙々と艦を走らせ来たりし彼ら 戦況を疑う由もなき艦底に屈息し、全身これ汗と油にまみれ、会話連絡すべて手先信号に頼る
海水ポンプ所掌の応急科員さすがに躊躇
「急げ」われ電話一本にて指揮所を督促
機関科員数百名、海水奔入の瞬時、飛沫の一滴となってくだけ散る。
彼らその一瞬、何も見ず何も聞かず ただ一魂となりて溶け、渦流となりて飛散したるべし
沸き立つ水圧の猛威
数百の生命、辛くも艦の傾斜をあがなう
されど方舷航行の哀れさ、速度計の指針は折るるごとく振れ傾く
隻脚、跛行、もって飛燕の重囲とたたかう
(吉田満氏著 戦艦大和 河出書房新社 昭和四十一年十二月二十日 発行。七十一頁~七十二頁より抜粋)
機械室内での戦死者は多数です。これは戦没者名簿を見ても明らかでございます。喫水線下での生還者は極めて少ない。これは事実です。電信室にいたと推察している祖父も例外ではございません。機関科員のご遺族を思う時、この史実はあまりにも歴史を淡々と語るには重すぎる話ではございます。ですが、今一度この命令を発しました能村次郎副長の手記を見てみます。
私は意を決して、注排水指揮所へ「右舷機械室注水」
ついで「右舷罐室注水」を発令す。
各室に非常緊急退避のブザーが、連続的に鳴り響いた。数十人の在室員は傾斜して歩きにくい羽化を走って手近の階段に飛びつく。と同時に、壁の最下部、床に接して配してある注水孔から、海水が怒涛のごとく、機械室、罐室に奔入した。
注水した罐室、機械室は、注水速度から考え四、五分で満水したことと思われる。
一方機械室で、いちばん出口に遠い遠い持ち場の者が、機械の横をすり抜け、下をくぐり抜けて出口にたどりつき、中甲板にでるまでに三分。罐室は比較的退避しやすいが出入り口が一箇所しかないので、やはり最後の兵が退避するまで三分ぐらいはかかったであろう。しかし機械室、罐室勤務員には負傷者もなかったから、いずれにしても各室が満水する前に在室員全員が退避できたはずである。
(能村次郎 大和副長 証言手記より抜粋)
上記、吉田満氏の言とは違っていることに気づきます。吉田氏は数百名の生命が失われたと著し、能村元副長は数十名が全員退避(したはず)としております。
どちらが史実かは今となっては検証することが難しい。
「他に証言がないか」と調べてみますと技術的視点からの証言がございます。ご紹介いたします。
大和設計に携わりました「堀 元美 海軍技術中佐」の手記でございます。
友人Y君との会話からです。彼と酒を酌み交わしている堀氏。酒の席上、上記の話題になりました。
「そんな事になるような設計だったのか?」とY君は質問した。
大和の艤装の詳細記録はのこっていないので、機械室、罐室の注水をどの海水管系統のよって行われたかは、明らかではないが、一般艤装図から略算すると、外側機械室の容積は役1000立方メートル、外側罐室は約600立方メートルで、その容積率を65%と仮定しても、これらの区画を満水させるには機械室約700トン、罐室役390トンの海水を入れなければならない。これらの区画には排水用として、1時間当たり500トン能力のエジェクターを、罐室には1台、機械室には2台そなえてある。
罐室に水を入れるには、このエジェクターを逆に水を通して入れるほかないので、非常に時間がかかるはずである。見当でいえば30分ぐらいではないかと思われる。
機械室の方は、主機復水管の冷却水ポンプを利用して排水する管系があるので、これを逆に水をとおせばずっと早く水が入るはずだが、それには機械室内で、巨大なハンドルをまわして仕切弁をひらき、またこの強力な冷却水のポンプを止めなければならない。
したがって、機械室内の勤務員に無警告で注水は出来ない。エジェクター系統だけで注水すれば、時間のかかることは罐室の場合と同様である。どちらの場合も瞬時に、あるいは退避のひまもない短時間に満水して、全員が溺死するということはありえないのである。
(中略→この間、堀氏は武蔵沈没の教訓から注排水装置強化が技術部内で検討され、大和の注排水設備を有力なものに改造する必要性があると結論付されたと記しておられています)
いずれにせよ、造船設計上、応急措置としての注水は、われわれが望むような短時間では行い得ない、つまりそんな大きな注水孔や注水管は設けることができないことが悩みであった。ともあれ、この注水措置により、多数の機関科員の生命をもって艦の傾斜をあてがったという記述は、形容的表現としてはともかく、客観的には思いすごしというべきである。
(堀 元美 元海軍技術中佐証言より抜粋)
堀氏は、きっぱりと「できない」と結論を述べておられます。
吉田満氏にとりましては、彼の生前の証言
「すべてを真実と捕えられては困る」と申しておられます。
酔漢にとりまして「戦艦大和」と「戦艦大和ノ最期」(いづれも、吉田氏著)はその顛末を語ります上では大変重要な書であることは間違いではございませんし、その価値を否定するものでもございません。が、やはり史実を検証する上におきましては、その記述されております箇所箇所をきちんと確かめる必要性も感じております。
私見でございます。実際には罐室、機械室(正確には右舷外側十一区画第三罐室。十三区画第十一罐室。十六区画右舷水圧機室)の注水の効果があったかと疑問に思うのです。この下令は確かなものだと考えておりますが、果たしてあの状況で、ポンプが正常に作動し、満水状態になったのか疑問です。実際は「注水は行われたが、満水にするまでには至らず、ポンプ機器も正常に作動しなかったのではないか。そして、罐室、機械室への浸水は攻撃によるものであるのではないか。(実際には最後とどめは右舷への魚雷被弾四発)。機関科員の戦死はその攻撃によるものではないか。
上記のように考えるのです。
傾斜は一時的に復旧します。がすぐさま(ほんの数十分ももたない)傾斜が増加します。
注排水指揮所へ伝令を出した能村副長です。
伝令が帰ってきません。
注排水指揮所が破壊され林中佐以下総員が戦死したことを知ります。
そし更に大和は致命傷を負います。
「舵取機室、浸水増。止まりません」
大和の誇る防禦防水区画が悉く破壊され、浸水が止まらなくなっております。
「浸水多く、操舵不能」
この報から操舵室との連絡が途絶えます。
操舵長以下総員戦死。
舵のきかない大和は左旋回を続けるだけとなっております。
祖父のいた通信室の浸水はこれより前の出来事です。
証言が少ない(ほとんどない)中で先にご紹介いたしました吉田満氏著「戦艦大和」にその件が記述されております。
魚雷集中のため、防水の完璧を誇る送受信室もついに浸水に潰ゆ
通信長以下、通信科員の過半をここに失う
艦隊旗艦「大和」に通信機能なし 今やただ発行と旗旒による
巨人のその耳、口を失いえ何をか為すべき
(吉田満氏著「戦艦大和」七十七頁より抜粋)
伊藤整一第二艦隊司令長官。最後の判断を下します。
追加補足
先にご紹介いたしました「能村次郎副長手記」は「慟哭の海」からの抜粋です。が「読売新聞掲載。昭和史の天皇」での証言が違っております。
角川文庫335ページ記載には下記のように記述されております。
『右舷機械室注水!右舷罐室注水!』
を発令す(機械室、罐室は十二区画に分かれていた)。在室員に退去警報を出した後の処置であることはもちろんである(しかし全員が退去し得たかどうか不明だ)。
以前、「暗号解読」「暗号翻訳」でも語りましたが、後に編集され直した「昭和史の天皇」記述は先の「慟哭の海」(どちらも読売新聞社編)の不具合を訂正出版されておるように考えます。前回は単に「記述の問題」とも言えなくもないのですが、今回は明らかに「意図をもった編集ではないか」と推察できるような記述です。
はたして、「副長はあの時点でどのように考えておられたのか」
事実を検証するには難しい事となっております。
ここに補足、私見を述べさせていただきました。
「みながんばれ」
第一艦橋よりさらに上、露天の防空指揮所より有賀艦長がありったけの声を伝声管へぶつけております。
残存の全火力を発揮して、阻止撃譲、転舵回避に努めるが、各方面から同時に進んでくる魚雷の白い航跡は、クモの巣のごとく、連続する急降下と機銃は雨のごとく、この双方を無事回避しおおせることは到底不可能で、続いてまたまた左舷に二、三本の魚雷と、中部甲板に七、八発の爆弾が命中、注排水装置の右舷タンクは、すでに満水していたので、累加する左舷の魚雷被害は、刻々艦の傾斜を増加した、
左舷の高角砲、機銃は、ほとんど破壊され、大部分の配員は死傷した。防御力がなくなると見るや、なおさら敵機は左舷をねらい撃つ。艦はもっぱら転舵回避で、敵の攻撃をそらそうと努めるが、艦は左舷がやられている。その傾いた左舷を平衡にたて直すには左旋回するしかない。かつ艦速は低下し、傾斜し、ますます運動の自由を欠き、被害は急速に増加するばかりであった。
時に左舷傾斜十五度。速力はいぜん十八ノット。
十三時五十分
(能村次郎 大和副長 証言 手記より抜粋)
「復元を急げ、復元を急げ」
と有賀幸作艦長みずからが、伝声管にむかって叫んでいた。その姿は空しく、また、悲痛なものを感じさせた。
しかし、左舷に大傾斜した大和の船体を復元させることは、だれが考えてものぞみようがなかった。
私の配置は前部測的所である。ここは艦長がいる防空指揮所の上段に位置しており、ごく近い位置にある。そのため、艦長の戦闘指揮のようすが、手にとるようにわかるのだ。(中略)艦は左に二○度ちかく傾斜して戦闘能力を完全に消失した。断末魔の様相である。すでに沈没は、時間の問題と考えてよかった。(中略)もはや、注排水装置を使用しての復元の方法はない。
最後に残された手段は、右舷の主機械室と六個の罐室に注水することである。
(坂本一郎 大和 上曹 証言 手記より抜粋)
大和注排水装置は建造過程においてもしばしば語ってまいりました。ダメージコントロール、所謂「ダメコン」の装置です。並みの戦艦であれば十分すぎるほどのタンクキャパシティーを持ってしても、そのタンクが満水状態。大和は身を削ってもその復元に努めることとなります。設計段階ではこれでも十分なキャパシティーと想定されております。
もっとも、設計段階においては、航空機による攻撃は想定されておりません。あくまでも、対戦艦としてのダメコンだと言えます。
設計主任「牧野茂」氏は、戦後「いかなる空襲に遭遇したとしても、沈没する設計ではなかった」とこう証言されておられますが、(他の設計陣におきましても同様の証言ではございますが)やはり激しい空襲では、限界が来たと考えます。
艦内、防御指揮所内、能村次郎副長です。最早、注排水ポンプでの艦傾斜復元が不可能である事を知っております。各種警報ブザーが鳴りっぱなしの指揮所内。
有賀艦長からの再三再四の催促が聞こえて来ます。
「艦傾斜の復旧!イソゲ!」
副長はあるジャッジを迫られております。
「この傾斜を復旧させるためには、無傷である『右舷外側十一区画内第三罐室』と『十三区画内第十一罐室』および『十六区右舷水圧機室』への注水以外にはない。しかし、傾斜は一時的には収まるかもしれないが、果たしてこの状態で沖縄まで行きつけることができるのか」副長は、艦を真南へ転身下令した有賀艦長の覚悟を思う時、また自身の職務を遂行する為には、「何としても沖縄到達」を考えなくてはならない。そう信じているのでした。
電話が鳴りました。
受話器を取る副長です。
「タンクの注水限度!右舷機械室、罐室への注水許可を!」
右舷下甲板、注排水指揮所内、防禦指揮官「林 紫郎中佐」(戦死後特進大佐 大和内務長)からです。
「罐室への注水は推進力を失うこととなる。他に手段はないのか」
「ありません。これ以上・・・アリマセン!」
電話はこれで途切れます。
「伝令兵!注排水指揮所!」
副長はありったけの声で指示しました。一人の伝令が注排水指揮所へ向かいます。
更に有賀艦長から。
「傾斜復旧・・・早くしろ!」
副長は決断いたしました。
沖縄到達は推進力にかかっている。思い余って咄嗟には、許可の指令を出しかねた。傾斜のままだと砲銃はうまく撃てないのだ。ついに意を決して注排水指揮所へ
「右舷機械室注水!右舷罐室注水!」を発令す。
(能村次郎大和副長 証言手記より抜粋)
全力運転中の機械室、罐室ー機関科員の配置なり これまで灼熱、噪音とたたかい、終始黙々と艦を走らせ来たりし彼ら 戦況を疑う由もなき艦底に屈息し、全身これ汗と油にまみれ、会話連絡すべて手先信号に頼る
海水ポンプ所掌の応急科員さすがに躊躇
「急げ」われ電話一本にて指揮所を督促
機関科員数百名、海水奔入の瞬時、飛沫の一滴となってくだけ散る。
彼らその一瞬、何も見ず何も聞かず ただ一魂となりて溶け、渦流となりて飛散したるべし
沸き立つ水圧の猛威
数百の生命、辛くも艦の傾斜をあがなう
されど方舷航行の哀れさ、速度計の指針は折るるごとく振れ傾く
隻脚、跛行、もって飛燕の重囲とたたかう
(吉田満氏著 戦艦大和 河出書房新社 昭和四十一年十二月二十日 発行。七十一頁~七十二頁より抜粋)
機械室内での戦死者は多数です。これは戦没者名簿を見ても明らかでございます。喫水線下での生還者は極めて少ない。これは事実です。電信室にいたと推察している祖父も例外ではございません。機関科員のご遺族を思う時、この史実はあまりにも歴史を淡々と語るには重すぎる話ではございます。ですが、今一度この命令を発しました能村次郎副長の手記を見てみます。
私は意を決して、注排水指揮所へ「右舷機械室注水」
ついで「右舷罐室注水」を発令す。
各室に非常緊急退避のブザーが、連続的に鳴り響いた。数十人の在室員は傾斜して歩きにくい羽化を走って手近の階段に飛びつく。と同時に、壁の最下部、床に接して配してある注水孔から、海水が怒涛のごとく、機械室、罐室に奔入した。
注水した罐室、機械室は、注水速度から考え四、五分で満水したことと思われる。
一方機械室で、いちばん出口に遠い遠い持ち場の者が、機械の横をすり抜け、下をくぐり抜けて出口にたどりつき、中甲板にでるまでに三分。罐室は比較的退避しやすいが出入り口が一箇所しかないので、やはり最後の兵が退避するまで三分ぐらいはかかったであろう。しかし機械室、罐室勤務員には負傷者もなかったから、いずれにしても各室が満水する前に在室員全員が退避できたはずである。
(能村次郎 大和副長 証言手記より抜粋)
上記、吉田満氏の言とは違っていることに気づきます。吉田氏は数百名の生命が失われたと著し、能村元副長は数十名が全員退避(したはず)としております。
どちらが史実かは今となっては検証することが難しい。
「他に証言がないか」と調べてみますと技術的視点からの証言がございます。ご紹介いたします。
大和設計に携わりました「堀 元美 海軍技術中佐」の手記でございます。
友人Y君との会話からです。彼と酒を酌み交わしている堀氏。酒の席上、上記の話題になりました。
「そんな事になるような設計だったのか?」とY君は質問した。
大和の艤装の詳細記録はのこっていないので、機械室、罐室の注水をどの海水管系統のよって行われたかは、明らかではないが、一般艤装図から略算すると、外側機械室の容積は役1000立方メートル、外側罐室は約600立方メートルで、その容積率を65%と仮定しても、これらの区画を満水させるには機械室約700トン、罐室役390トンの海水を入れなければならない。これらの区画には排水用として、1時間当たり500トン能力のエジェクターを、罐室には1台、機械室には2台そなえてある。
罐室に水を入れるには、このエジェクターを逆に水を通して入れるほかないので、非常に時間がかかるはずである。見当でいえば30分ぐらいではないかと思われる。
機械室の方は、主機復水管の冷却水ポンプを利用して排水する管系があるので、これを逆に水をとおせばずっと早く水が入るはずだが、それには機械室内で、巨大なハンドルをまわして仕切弁をひらき、またこの強力な冷却水のポンプを止めなければならない。
したがって、機械室内の勤務員に無警告で注水は出来ない。エジェクター系統だけで注水すれば、時間のかかることは罐室の場合と同様である。どちらの場合も瞬時に、あるいは退避のひまもない短時間に満水して、全員が溺死するということはありえないのである。
(中略→この間、堀氏は武蔵沈没の教訓から注排水装置強化が技術部内で検討され、大和の注排水設備を有力なものに改造する必要性があると結論付されたと記しておられています)
いずれにせよ、造船設計上、応急措置としての注水は、われわれが望むような短時間では行い得ない、つまりそんな大きな注水孔や注水管は設けることができないことが悩みであった。ともあれ、この注水措置により、多数の機関科員の生命をもって艦の傾斜をあてがったという記述は、形容的表現としてはともかく、客観的には思いすごしというべきである。
(堀 元美 元海軍技術中佐証言より抜粋)
堀氏は、きっぱりと「できない」と結論を述べておられます。
吉田満氏にとりましては、彼の生前の証言
「すべてを真実と捕えられては困る」と申しておられます。
酔漢にとりまして「戦艦大和」と「戦艦大和ノ最期」(いづれも、吉田氏著)はその顛末を語ります上では大変重要な書であることは間違いではございませんし、その価値を否定するものでもございません。が、やはり史実を検証する上におきましては、その記述されております箇所箇所をきちんと確かめる必要性も感じております。
私見でございます。実際には罐室、機械室(正確には右舷外側十一区画第三罐室。十三区画第十一罐室。十六区画右舷水圧機室)の注水の効果があったかと疑問に思うのです。この下令は確かなものだと考えておりますが、果たしてあの状況で、ポンプが正常に作動し、満水状態になったのか疑問です。実際は「注水は行われたが、満水にするまでには至らず、ポンプ機器も正常に作動しなかったのではないか。そして、罐室、機械室への浸水は攻撃によるものであるのではないか。(実際には最後とどめは右舷への魚雷被弾四発)。機関科員の戦死はその攻撃によるものではないか。
上記のように考えるのです。
傾斜は一時的に復旧します。がすぐさま(ほんの数十分ももたない)傾斜が増加します。
注排水指揮所へ伝令を出した能村副長です。
伝令が帰ってきません。
注排水指揮所が破壊され林中佐以下総員が戦死したことを知ります。
そし更に大和は致命傷を負います。
「舵取機室、浸水増。止まりません」
大和の誇る防禦防水区画が悉く破壊され、浸水が止まらなくなっております。
「浸水多く、操舵不能」
この報から操舵室との連絡が途絶えます。
操舵長以下総員戦死。
舵のきかない大和は左旋回を続けるだけとなっております。
祖父のいた通信室の浸水はこれより前の出来事です。
証言が少ない(ほとんどない)中で先にご紹介いたしました吉田満氏著「戦艦大和」にその件が記述されております。
魚雷集中のため、防水の完璧を誇る送受信室もついに浸水に潰ゆ
通信長以下、通信科員の過半をここに失う
艦隊旗艦「大和」に通信機能なし 今やただ発行と旗旒による
巨人のその耳、口を失いえ何をか為すべき
(吉田満氏著「戦艦大和」七十七頁より抜粋)
伊藤整一第二艦隊司令長官。最後の判断を下します。
追加補足
先にご紹介いたしました「能村次郎副長手記」は「慟哭の海」からの抜粋です。が「読売新聞掲載。昭和史の天皇」での証言が違っております。
角川文庫335ページ記載には下記のように記述されております。
『右舷機械室注水!右舷罐室注水!』
を発令す(機械室、罐室は十二区画に分かれていた)。在室員に退去警報を出した後の処置であることはもちろんである(しかし全員が退去し得たかどうか不明だ)。
以前、「暗号解読」「暗号翻訳」でも語りましたが、後に編集され直した「昭和史の天皇」記述は先の「慟哭の海」(どちらも読売新聞社編)の不具合を訂正出版されておるように考えます。前回は単に「記述の問題」とも言えなくもないのですが、今回は明らかに「意図をもった編集ではないか」と推察できるような記述です。
はたして、「副長はあの時点でどのように考えておられたのか」
事実を検証するには難しい事となっております。
ここに補足、私見を述べさせていただきました。















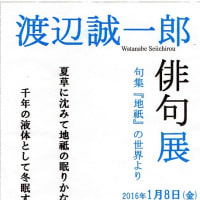










難しく、そして思い話題ですね。
こと大和の最期については、吉田満さんの『戦艦大和の最期』から多くの情報を得ていました。
吉田さんの本の書き方は劇的ですね。
『最期』によれば、数百人が一瞬にして水に呑まれたことになっています。
また能村次郎さんの『慟哭の海』によれば、数十名が退避できたはずだということです。
堀元美さんによれば、機械室と罐室の注水弁は機関科の所掌だったそうですね。
しかもスイッチ一つで一瞬にしてあの巨大な空間が満水状態になることはあり得ないとか。
もう一つ気になるのは、吉田さんの本によると
「われ、電話一本にて指揮所を督促」。
すなわち吉田さん自身が注水の命令を注排水指揮所につたえたような書き方になっていることです。
吉田さんは大和では電測士でした。
確かに戦闘中は艦橋当直でしたが、艦長附でも副長附でもありません。
酔漢さんも書いておられますが、
注水の指令は防禦指揮官である副長の所掌です。
だとすれば注排水指揮所への命令は、
艦長⇒副長⇒内務長⇒注排水指揮所
注排水区画が満杯で罐室と機械室に直接注水を命令するならば、
艦長⇒副長⇒機関長⇒罐部指揮官/機械室指揮官
であるはずです。
吉田さんの本を読んだ後で色々な関連文献を読むと、記述内容にあれこれ食い違いが見つかりました。
確かに「何ていい加減な」と思ったこともあります。
しかし吉田さん自身が
「自分の書いたことをすべて事実だと思ってもらっては困る」という意味のことを言っています。
察するに吉田さんは、
すべての資料を整えた上で記述内容も可能な限り正確を期した記録を残そうとしたのではないと思います。
これも吉田さん自身が言っていることですが、
『戦艦大和の最期』はほぼ一晩で一気に書き上げられたそうです。
だとすれば「書かずにはいられない」何かに突き動かされて、
気持ちの整理をつけるために書いたのではないかと、
最近は思うのです。
ドイツにいた時に御世話になった人に、
阿川弘之さんと海軍予備学生で同期だった方がいます。
その方に「海軍文人の会」に呼んで頂いたことがあります。
五月二十七日の海軍記念日に市ヶ谷ので行なわれる
海軍出身で文筆に携る皆さんの会合です。
その会で吉田満さんの奥さんに会いました。
非常に上品で物静かな方でした。
『戦艦大和の最期』の疑問点について確認するには絶好の機会だったのですが・・・
何となくためらわれて、尋ねずじまいだったです。
阿川弘之さんの『軍艦長門の生涯』に以下の記述があります。
ご参考まで。
近代化された長門の特色の一つに、注排水装置というものがある。防禦区画のコントロール・ルームに、工作長の機関少佐が指揮官として坐っていて、戦闘時、各部からの被害報告を聞きながら、傾斜復原の応急中排水指令を出す。魚雷一本なら、どんな急所に命中しても、五分以内に傾斜を四度以下に戻せということになっていた。
ブザーを鳴らし、退避を命じ、いきなり罐室のような大区画に海水が注入される。逃げ出す方は必死で、場合によっては五体健全のまま水地獄で命を捨てることになるが、うまく行かないと、艦は傾斜が増大して沈む。
(新潮文庫版中巻)
※昭和十年前後の事が書いてある箇所です。「五体健全のまま水地獄で命を捨てる」とは書いてありますが、「一瞬にして」とは書いてありません。
エンジンの責任者が的場機関長、戦う長門の代表が砲術長の越野公威中佐とすれば、守る長門の親方は、的場中佐と同郷の内務長稲田進中佐である。内務長という職は、新しく設定されたもので、従来の運用長の仕事に、工作科、電気科の仕事が加わり、フネの応急万般を担当する。(同下巻)
※昭和十九年、マリアナ沖海戦の少し前のくだりです。内務長の職は、指揮権の継承(軍令承行)問題の改正に際して作られました。応急関係の部署を一つの科にまとめたものですが、兵科だけでなく機関科出身者でもその職に就ける点にも特色があります。
吉田さんが艦長ないしは副長の命令を受けて
伝声管またはマイクに向って「急げ」と言うことは考えにくいことだと思います。
この「われ」ですが、自分がいる艦橋全体、
ないしは艦橋配置の者全員をひっくるめて
「われ」と言ったのではないでしょうか。
注水の話。ご生還された方も「後の話として聞いていた」とされていらした方がほとんどだったらしいのでした。
一人歩きした史実かもしれません。
いよいよ、大和の記述に突入ですね。
戦争の第一線で、攻撃を受けている中での記憶ですから,忠実に記憶することも艦内の細部でのことも掌握することは不可能だったでしょう。 当然、予想での記述も含まれて当たり前なのかもしれません 。
しかし、生存者などとの交流や 多方面からの情報で訂正されて いくことは悪いことではありませんね。
注水…もしそれで閉じ込められていれば胸が苦しくなりますね。
「あった」「なかった」そして「退避できた」「出来なかった」ですが、その史実よりも、最後まで大和のスクリューが回っていたとする証言が多数ございます。
機関科員は最後の最期まで奮戦していたのです。この任務に対する多大な責任感を思う時、この事実が重くのしかかるのでした。