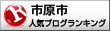良く晴れて汗ばむ陽気となった今日、地元八幡運動公園と八幡公民館にて「第36回八幡臨海まつり」が行われました。
キャッチフレーズは「手をつなごう八幡はひとつ」。
地元町会、商店会をはじめとする諸団体、臨海部などの企業群が協同で行うお祭りです。
野外ステージでは、和太鼓の演奏や踊り、バンド演奏などが繰り広げられ、

模擬店もたくさん立ち並んで大賑わい!

上総いちはら国府祭りのマスコット・オッサくんは、ここでも子供たちに大人気(^^)

もちろん、佐久間市長もお見えになりました。TV取材を受けてます。

毎年恒例の八幡臨海まつりですが、
大震災を経験した36回目の今回ほど、
皆が「企業も市原の住民のひとり」との意識を共有して、互いの連携の大切さを考えた年はなかったのではないでしょうか。
さて、午後は東海大付属望洋高校で行われた里山シンポジウムへ。
県内では、120あまりの団体が里山を守る活動をしています。そのうち、市原市は14団体です。
シンポジウムの午後の部では、県や市の担当課職員の方からの現状と課題などの説明のあと、
アートディレクターの北川フラムさんによる基調講演がありました。

北川フラムさんは、以前ブログでもご紹介しました。
来年度の市制50周年に向け、南市原の里山をアートによって活性化するというプロジェクトの仕掛け人でもあります。
講演では、北川さんがこれまで日本各地で手掛けてきたプロジェクトの一つとして、越後妻有の「大地の芸術祭」の例が紹介されました。
ご覧になった市原市民の皆さんは、どうお感じになりましたか?
来年の市原市の取り組みのイメージが、なんとなく見えてきたでしょうか。
講演の後は、佐久間市長、農民文学者の遠山あきさん、上古敷谷里山の会会長の林秀一さんのお三方によるパネルディスカッション。

95歳になられる遠山さんの言葉は、さすがにどれも重みがありました。
「今は過去の積み重ね。未来は今の積み重ね」
「文明が発達すると、人間は不器用になる」
「21世紀の間に必ず水危機が来る。水を育んでいる里山を本気で大切にしなければならない」
会場には、里山を守る活動をしている方が市外各地からも大勢訪れていました。
里山の魅力と、里山を愛する人々に触れることができた、貴重な時間でした。
キャッチフレーズは「手をつなごう八幡はひとつ」。
地元町会、商店会をはじめとする諸団体、臨海部などの企業群が協同で行うお祭りです。
野外ステージでは、和太鼓の演奏や踊り、バンド演奏などが繰り広げられ、

模擬店もたくさん立ち並んで大賑わい!

上総いちはら国府祭りのマスコット・オッサくんは、ここでも子供たちに大人気(^^)

もちろん、佐久間市長もお見えになりました。TV取材を受けてます。

毎年恒例の八幡臨海まつりですが、
大震災を経験した36回目の今回ほど、
皆が「企業も市原の住民のひとり」との意識を共有して、互いの連携の大切さを考えた年はなかったのではないでしょうか。
さて、午後は東海大付属望洋高校で行われた里山シンポジウムへ。
県内では、120あまりの団体が里山を守る活動をしています。そのうち、市原市は14団体です。
シンポジウムの午後の部では、県や市の担当課職員の方からの現状と課題などの説明のあと、
アートディレクターの北川フラムさんによる基調講演がありました。

北川フラムさんは、以前ブログでもご紹介しました。
来年度の市制50周年に向け、南市原の里山をアートによって活性化するというプロジェクトの仕掛け人でもあります。
講演では、北川さんがこれまで日本各地で手掛けてきたプロジェクトの一つとして、越後妻有の「大地の芸術祭」の例が紹介されました。
ご覧になった市原市民の皆さんは、どうお感じになりましたか?
来年の市原市の取り組みのイメージが、なんとなく見えてきたでしょうか。
講演の後は、佐久間市長、農民文学者の遠山あきさん、上古敷谷里山の会会長の林秀一さんのお三方によるパネルディスカッション。

95歳になられる遠山さんの言葉は、さすがにどれも重みがありました。
「今は過去の積み重ね。未来は今の積み重ね」
「文明が発達すると、人間は不器用になる」
「21世紀の間に必ず水危機が来る。水を育んでいる里山を本気で大切にしなければならない」
会場には、里山を守る活動をしている方が市外各地からも大勢訪れていました。
里山の魅力と、里山を愛する人々に触れることができた、貴重な時間でした。