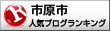今、政府が福祉政策で最も力を入れて目指そうとしているのが「地域共生社会」。
これまで高齢者・障害者・生活困窮などカテゴリーごとに縦割りだった支援体制を見直して、個人や世帯が抱える問題を丸ごと支援する体制へ転換するというものです。
これはとても大きな変革と言えると思います。
人口が減っても福祉サービスを充実させるための合理的な手法という打算的な見方もできますが、複雑な問題を抱えていたり、制度の隙間からこぼれ落ちていたり、支援を求めたくても求める力すらない人々も救えるようになれば、まさに日本は成熟した福祉国家になったと言えるでしょうね。
問題は、この理念をどうやって地域で具現化するか。
ここで行政の本気度と住民の底力が試されるのです。
先日消防局講堂で開かれたのは、地域共生社会の実現に向けた研修会。地域の福祉関係者や行政職員が100名近く参加しました。

講師は(一社)コミュニティネットハピネス代表理事の土屋幸己さんです。富士宮市で相談支援窓口のワンストップ化に全国に先駆けて取り組んだ実績があります。
私も12月の本会議で「ひきこもり」の問題を切り口に共生社会について取り上げたので、とても興味深く聞かせてもらいました。
加えて後日、森山さんと一緒に研修会を主催した社会福祉協議会を訪ね、地域共生社会について現在までの取り組み状況や今後の計画などを確認。

関連して、今月末には辰巳台地区の皆さんと江戸川区へ視察、来月始めにもまた研修会の予定があります。
この機会に更に学びを深めたいと思っています。
これまで高齢者・障害者・生活困窮などカテゴリーごとに縦割りだった支援体制を見直して、個人や世帯が抱える問題を丸ごと支援する体制へ転換するというものです。
これはとても大きな変革と言えると思います。
人口が減っても福祉サービスを充実させるための合理的な手法という打算的な見方もできますが、複雑な問題を抱えていたり、制度の隙間からこぼれ落ちていたり、支援を求めたくても求める力すらない人々も救えるようになれば、まさに日本は成熟した福祉国家になったと言えるでしょうね。
問題は、この理念をどうやって地域で具現化するか。
ここで行政の本気度と住民の底力が試されるのです。
先日消防局講堂で開かれたのは、地域共生社会の実現に向けた研修会。地域の福祉関係者や行政職員が100名近く参加しました。

講師は(一社)コミュニティネットハピネス代表理事の土屋幸己さんです。富士宮市で相談支援窓口のワンストップ化に全国に先駆けて取り組んだ実績があります。
私も12月の本会議で「ひきこもり」の問題を切り口に共生社会について取り上げたので、とても興味深く聞かせてもらいました。
加えて後日、森山さんと一緒に研修会を主催した社会福祉協議会を訪ね、地域共生社会について現在までの取り組み状況や今後の計画などを確認。

関連して、今月末には辰巳台地区の皆さんと江戸川区へ視察、来月始めにもまた研修会の予定があります。
この機会に更に学びを深めたいと思っています。