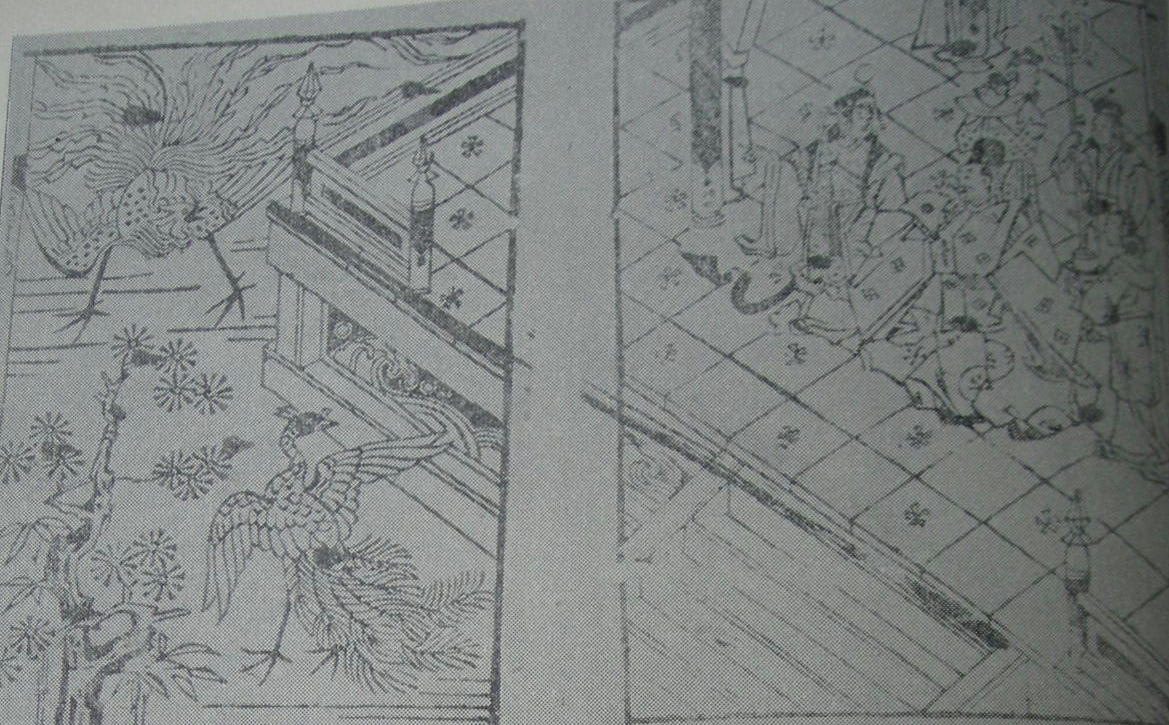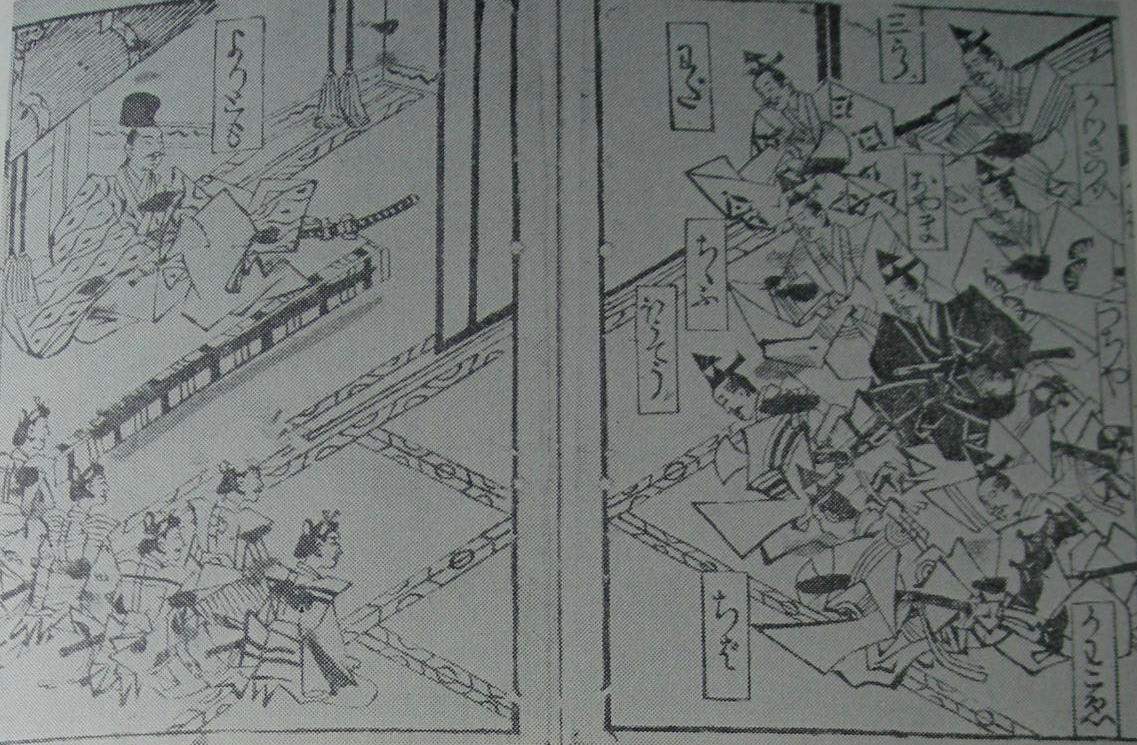このページで忘れ去られた物語シリーズが破損していて読めないことをお詫びいたします。
いとう様のリクエストにお応えして、「中将姫」を再掲載いたします。
また、ファイルの破損等で読めない記事がありましたら、お手数ですがお知らせください。
渡部八太夫
中将姫 ①
さて、大和の国の当麻(たいま)曼荼羅の由来を詳しく尋ねてみることにいたしましょう。
神武天皇より四十七代の廃帝天皇(淳仁天皇758年~764年)の頃のことです。大職冠
鎌足の四代後の孫で、横佩(よこはぎ)の右大臣、藤原豊成(とよなり)とい方は、又の名
を、難波の大臣と申します。藤原の豊成には、子供が一人おりました。名前は、中将姫と
言いました。十三歳になった中将姫の姿はの美しさは、秋の月と言いましょうか。お顔は、
露が降りた春の花。翡翠の黒髪は、背丈ほど。眦(まなじり)は愛嬌があり、丹花の唇は
鮮やかです。微笑む歯茎は健康で、細い眉は、優しげです。辺りも輝くそのお姿の話を聞い
ただけでも、恋に落ちない男は居ませんでした。
しかし、可哀想な事に、中将姫は既に母を亡くしていたのでした。父豊成は、これを不憫と思
って、後添えを貰ったのでした。中将姫は、素直に継母を受け入れて、良く従って、親孝行
をしましたので、心の奥底は分かりませんが、継母も表面的には、中将姫を可愛がったので
した。こうして、表面的には、平穏な日々が流れ、豊成も喜んだのでした。
ところで、中将姫のことを、内々に聞いた御門は、難波の大臣豊成を、内裏に呼ぶと、
中将姫を皇后に迎える由の宣旨を下したのでした。
「年の暮れか、来年の春には、秋の宮に迎えよう。」
これを聞いた豊成は、畏まって退出し、喜び勇んで館へと戻るのでした。天皇家への輿入れ
に、一人を除いて、皆大喜びです。昔から、継子と継母が仲良しだった例しはありません。
この事を聞いた継母は、自分の子供の出世の機会が奪われると感じて、その心は、忽ちに曇りました。
そして、何とかして、姫を殺してしまおうと、恐ろしい計画を立てるのでした。
御台所は、親近の若者を選ぶと、こう命じたのでした。
「お前は、冠、肩衣の正装で、朝夕、中将姫の所へ出入りしなさい。」
命じられた若者は、言われるままに、毎日、中将姫の所に出掛けて行くのでした。それから、
当御台は、豊成に近付いて、こう言うのでした。
「どうか、お聞き下さい。窺いますところでは、この頃、姫の所に、怪しい者が通っている
ということです。まったく女の身程、浅ましいものはありません。」
継母は、泣き真似までして、訴えるのでした。豊成は、これを聞くと、
「姫は、まだ子供であるぞ。そんなことがあるはずがない。それは、誰かの偽り事であろう。」
と相手にしませんでしたが、御台が更にしつこく、
「私も、そうであろうとは思いますが、事の次第をはっきりさせるため、物陰から、ちょっ
と覗いて見ることにしましょう。」
と迫るので、豊成は仕方無く、御台と連れ立って、中将姫の様子見に行きました。このこと
が、姫君の運命を変えてしまったのです。
さて、中将姫の部屋の近くを見てみますと、年の頃十七八歳の衣冠正しい若者が、忍び
顔で部屋から出て来るのでした。これを見た豊成は、刀に手を掛け、飛び掛かり、その場で
切り捨てようとしましたが、
『待て暫し、我が心。ここで奴を誅すれば、返って我が身の恥をさらすことになる。』
と思い留まると、怒りに顔を真っ赤にして、自室に戻りました。
余りの事に、豊成は、竹岡の八郎経春(つねはる)を呼びつけると、
「やれ、経春。中将姫を引っ立てて、雲雀山(ひばりさん:奈良県宇陀市;日張山)に連れ
て行き、殺せ。」
と、言い放ちました。経春は、驚いて、
「これは、どんな咎があって、そうのようなことを仰るのですか。恐れながら、お姫様は、
先ず、私にお預け下さい。」
と、取りなしますが、豊成は、
「思う子細があるのだ。早や、急げ。」
と、頑な(かたくな)です。経春は重ねて、
「何と仰られても、このようなご命令を、簡単に引き受けることはできません。一先ず、
姫君をお預かり申します。」
と、食い下がりましたが、豊成は、気色を変えて、
「親の私が、子供の命を絶てと言っているのだから、そのような重い咎があったと思え。
お前が引き受けないというのなら、中将姫と諸共に、勘当じゃ。」
と、怒鳴り散らすと、奥へと入って行ってしまうのでした。
困り果てた経春は、せまじきものは宮仕えと、口説き立てますが、なんともしようがあり
ません。いくら嘆いても仕方が無いので、経春は、継母の御台所に何とかしてもらおうと考
えました。経春は、御台所の所に駆けつけると、
「姫君の事を、まだご存じ無いのですか。殿の御機嫌が悪く、直ぐに殺して来いと仰って
おられるのです。どうか、何とかして、殿を宥めて、姫の命をお助け下さい。」
と涙ながらに訴えるのでした。女房達が、御台所に取り次ぐと、御台所は、
「経春が、わざわざ言いに来なくても、私も、そうとは思います。しかし、原因は、世の常
のことではないとも聞きましたよ。唯々、豊成殿のお心に任せます。」
と無愛想な返事です。経春が、更に、
「それはご尤もですが、只一度の御勘気で、その上まだ、ほんのご幼少。どれほどの罪を
犯したというのでしょうか。御台様が申し入れなされれば、殿の気も変わるかもしれません。
叶わないまでも、どうか、今一度、殿を宥めていただけないでしょうか。お願いします。」
と食い下がると、御台所は気色を変えて、出居まで飛んで降り、
「経春。聞きなさい。お前は、まだ、知らないのか。毎日、姫君の本へ通う者は幾人とも限
りも無い。それをどうして、私が宥められるものですか。」
と言い張るのでした。御台所は、
「あら、難しや。」
と、言い捨てると、簾中の中へと逃げ込むのでした。
経春は、面目も無く、ただ、呆れ果てていましたが、
『これは、継母の御台の謀り事に違い無い。例え、そうしたことが事実であったとしても、
実母であるなら、必ず助けに入るだろう。なんと、なさぬ仲の浅ましき事か。』
と、気が付くのでした。経春は、悔し涙の暇より、
『とにかく、姫君を我が館に匿い。何度でも嘆願いたそう。それでもだめならば、腹切って
死ぬ外あるまい。』
と決心したのでした。八郎経春の心の内の頼もしさは、何とも言い様がありません。
つづく
中将姫②
八郎経春は、何とかして姫君を助けようと思いましたが、検使の役が付いてしまったので、
思う様に姫を匿うこともできませんでした。とうとう観念した経春は、
『もう、逃げようが無い。この上は、姫君のお首をいただいて、豊成に見せたなら、遁世し
て、姫の菩提を問う外はあるまい。』
と思い定めると、姫君を伴って、雲雀山へと向かうのでした。
雲雀山の山中の、とある谷川の辺りに輿を止めました。何も知らない姫君は、御輿から
降りると、経春に聞きました。
「経春よ。どうして、こんな寂しい山中に連れて来たのですか。不思議ですね。」
これを聞いた経春は、言葉も無く泣くばかりです。姫君が、
「どうしたというのですか。おかしいですね。何故、何も言わないのです。何があったのですか。」
と、重ねて問い正すと、経春は、ようやく涙をぬぐって、
「ここまで来ては、隠すこともできません。父上様のご命令で、姫君のお命を頂戴いたします。
そのために、ここまでおいで願ったのです。」
と言うのでした。聞いた姫君は、夢現かと驚いて、
「それは、本当ですか。」
と、絶句して泣くばかりです。涙ながらに姫君は、
「母様が亡くなられてからというもの、ひとときも母様のことを忘れた事は無く、心が慰め
られることもなかったので、私を、慰めるために、ここまで連れてきてくれたのかと思って
いましたのに。それどころか、私を殺すというのですか。ああ、これは継母の仕業ですね。
なんという情け無い事でしょうか。」
と口説いて、身を悶えて嘆くばかりです。姫君は、更に続けて、
「やあ、経春よ。前世からの宿業で、お前の手に掛かって死ぬ命を、惜しい等とは露にも
思いません。親の不興を受けた者には、日の光も、月の光をも射さないとききますが、
私は、一体どういうわけで、父から捨てられたのでしょうか。いやいや、それを聞いたとし
ても、もうどうしようもありませんね。
私は、七歳の時から、母上様の為に、毎日、お経を六巻づつ読誦して参りましたが、今日
はまだ読誦しておりません。これが、最期というのなら、今一度、母のために読経いたしま
すから、暫くの時間を与えて下さい。」
と、言うのでした。聞いて、経春は、
「ああ、なんと勿体ないことでしょうか。姫君様。御最期でありますので、何時もよりも、
お心静に読誦をして下さい。」
と涙ぐむのでした。中将姫も涙ながらに、敷き葉の上に座り直して、右の袂より浄土経を
取り出しました。中将姫は、さらさらと押し開くと、迦陵頻伽(かりょうびんが)のお声で、
読誦なされるのでした。殊勝なこと限り有りませんが、流石に姫君は、父の大臣への名残が
惜しいのでしょう。雨の様な涙が只々、落ちるばかりです。労しいことに姫君は、余りに
お心がやるせないので、ようやく三巻を読み終えて、
「一巻は、母の為、又一巻は父の為、現世来世の二世の為。さて、もう一巻は、自分自身の
正念です。どうか、九品の浄土にお迎え下さい。」
と、泣く泣く回向をされるのでした。中将姫は、思い切って、経春に向かうと、
「如何に、経春。私が死んだ後、絶対に後の恥を曝してはなりませんよ。私の首を、父上に
見せる時には、顔についた血飛沫を、よくよく洗い流してからにしてくださいね。そして、
命を惜しむようなことは無かった、素晴らしい最期であったと、伝えて下さいよ。さあ、
これから念仏を唱えます。十念が終わったならば、首を刎ねなさい。」
と言うと、背丈ほどもある黒髪を、きりきりと唐輪(からわ)に結い上げて、西に向かって
手を合わせました。
「南無西方の弥陀如来。例え、後生が三重に罪深くて、十方浄土に選ばれぬ女なりとも、
只今のお経、念仏の功力により、母上様諸共に、西方極楽浄土に、迎えて下さい。」
と、声高く、十念を唱えるのでした。南無阿弥陀仏を十度唱えて、姫君は、
「どうした経春。早、首を取れ。」
と迫ります。経春は、太刀を抜き放ち、お首を打ち落とそうとしました。しかし、姫のお姿
が目に入れば、余りにもお労しく、とうとう、太刀を投げ捨てて、地に倒れ伏して泣く外は
ありません。姫君は、経春をご覧になり、
「愚かであるぞ、経春。そのような不覚の者が、父の命を受け、私を殺すために、ここまで
連れて来たのですか。心弱くてはなりませんよ。善に強いのなら、悪にも退いてはなりませ
ん。さあさあ、如何に如何に。」
と、泣き崩れるのでした。経春は、漸く涙を押し留めて、
「しかし、姫君は、まだご幼少の事ですから、それほどの罪があるとは思われません。それ
なのに、やみやみと殺さなければならないとは、どうしても納得できません。」
と、言うのでした。姫君は、涙と共に、こう口説きました。
「親が憎む子は、その一門の者まで憎むと聞きますが、どうして経春は、そんなに優しくし
てくれるのですか。今のあなたのお志しは、草葉の陰に行っても決して忘れませんよ。草葉
の陰で私が見ていると思って、後世を問うて下さいな。さあさあ、そんなに思い悩まずに、
父の命に従って下さい。」
しかし、経春は、これを聞いて、
「ああ、なんと愛おしいことでしょうか。乳房の母がご健在であるならば、こんなことには
ならなかったのに。為さぬ仲の継母が浅ましい。」
と更に悶々と思い悩むのでした。しかし、やがて思い切り、
『ええ、姫君を殺して恩賞に預かったとしても、千年万年と生きられる訳では無いわ。我が
身の事はさて置き、一門眷属までも引き出され、ずたずたにされたとしても、姫君を助けな
いでどうするか。しかし、検使をどうするか。否というなら、奴らの首を掻くまでだ。』
と決心するのでした。経春が、検使に姫を助けると告げると、なんと検使の者も、
「私もそのように思います。いざ、お助けいたしましょう。」
と言うのでした。
それから姫のために、雲雀山に庵を建てると、経春は、都から女房や郎等を呼び寄せました。
経春は、
「私は、これから都へ戻り、姫君様の事を、どのようにでも、申し開きをして参る。皆の者
は、ここに留まって、姫君を守り助けるのだぞ。」
と言い残して、都へと帰って行ったのでした。かの経春の志は、頼もしいともなんとも、
なかなか言い表す言葉もみつかりません。
つづく
中将姫 ③
さて、父の大臣豊成は、家来の侍を集めて、こう言いました。
「姫の処分を、経春に命じたが、その後、何の報告も無い。急いで、経春の所へ行き子細を
尋ねて参れ。」
侍達が、経春の所へ行き、事の子細を問うと、経春は、
「これはこれは、直ぐにでも、ご報告に上がろうとは思っていましたが、何しろ、姫君の
死骸が、火車によって運び去られてしまったので、報告もできないでいたのです。哀れと思
って、お許し下さるのなら、これより伺候して、姫君の最期のご様子をお話いたしましょう。」
と言うのでした。使いの侍が、館に戻って、経春の返答を伝えると、豊成は怒って、
「居ながらの返事とは、なんと生意気な。命令をし遂げなかったな。つべこべいわせずに、
経春を連れて来い。」
と命じたのでした。二十余人の強者達が、経春の館へと駆けつけました。侍達は、
「如何に経春殿。お殿様の申すには、中将姫の首を見せぬのは何故だ。検使の役の者共はど
こへ行ったのだ。詳しく尋ねることがあるから、急いで来る様に、とのことです。」
と言うのですが、経春は、
「おお、ご尤も。しかしなあ、なんだか今日は、気が進まぬ。又日を改めて、参ることに
いたしましょう。」
と、相手にしません。侍達もむっとして、
「憎っくき、今の物言い。このまま帰るならば、こちらが詰め腹切らされる。さあ、引っ立
てろ。」
と、左右に分かれて飛び掛かりました。本より大力の経春は、飛び掛かる侍どもを、取って
は投げ、取っては投げて応戦します。残りの奴原を、四方へ蹴散らかすと、経春は、郎等ど
もを集めて、言いました。
「きっと、これから追っ手が攻めてくるであろう。とても敵うものではないから、お前達
は、どこへでも落ち延びて、後世を問うてくれ。さあ、早く。」
と言うのでした。しかし、郎等共は、
「なんと、残念な仰せでしょうか。主君の先途を見届けずに、落ち延びることなどできるは
ずもありません。是非、お供させて下さい。」
と、譲りませんでした。経春が、
「おお、それは頼もしい。では、用意いたせ。」
と言うと、皆々勇んで、最期の出立ちを整えました。やがて、豊成方の軍勢が押し寄せて
鬨の声を上げました。経春は、大勢の中に飛んで入り、ここを先途と戦いました。しかし、
多勢に無勢。郎等達も皆悉く討ち殺されていまいました。経春は、もうこれまでと思い、
敵を、四方におっ散らすと、門内につっと入りました。鎧の上帯を切って捨てると、腹を
十文字に掻き切って、自らの首を掻き落としたのでした。この経春の振る舞いは、上下万民
押し並べて、感激しない者はありませんでした。
つづく
中将姫 ④
危うく命拾いをした中将姫は、物憂い山住まいの毎日を過ごしていました。その上、頼み
の綱の経春が討ち死にしたとの知らせもあり、心の内のやるかたない風情も哀れです。そん
な中でも、中井の三郎と経春の女房は、姫君をお守りして、落ち穂を拾い、物乞いをして
支えたのでした。
しかし、ある時、中井の三郎は重い病に伏してしまいます。中将姫も、女房も、枕元で、
励ましますが、山中のこととて、癒やし様もありません。縋り付いて泣くばかりです。もう
これが最期という時に、中井の三郎は女房に介錯されて起き上がると、
「姫君様。娑婆でのご縁も終わりです。これより冥途の旅に出掛けます。私が生きている限
り、必ず父大臣に申し開き、再び御世に戻して差し上げようと、明け暮れ、このことだけ
を思い続けていたというのに、とても残念です。どうか、必ず姫君様は、お命を全うして
くだされませ。神は正しい者の頭に宿ります。きっと必ず、父上様に再び、お会いになるこ
とは鏡に掛けて明らかです。死する命は惜しくはありませんが、姫君のお心の内を推し量り
ますと、只それだけが、名残惜しく思われます。」
と、最期の言葉を残して、明日の露と消えたのでした。姫も女房もこれはこれはと、泣くよ
り外はありません。姫君は涙の暇より、口説き立て、
「ああ、何という浅ましいことでしょう。父上に捨てられて、経春は討ち死にし、この
寂しい山中で、お前だけを頼りにして暮らして来たのに、今度は、お前まで失って、これか
らどうやって暮らしていけばよいのですか。私も一緒に連れていって下さい。」
と、空しい死骸を押し動かし、押し動かして、慟哭するのでした。女房は、
「お嘆きはご尤もです。しかしながら、最早帰らぬ事です。さあ、どうにかして、この死骸
を葬りましょう。」
と、健気にも励まします。山中には外に頼める僧も無く、女房と姫君二人で、土を掘り死骸
を埋め、塚を築いて、印の松を植えたのでした。それから、姫君自ら、お経を唱え、回向
をするのでした。
さて、その後も山中の寂しい日々が続いていましたが、姫君は、称賛浄土経を書き写して
暮らしておりました。ある日、姫君は女房に、こう話しました。
「このお経は、釈迦仏の弥陀の浄土を褒め称えたお経です。毎日唱えて、夫の経春の供養を
して下さい。」
女房は、これは有り難いと、お経を給わったのです。それから女房は、髪を剃り落とし尼と
なって暮らしたのでした。
さて一方、難波の大臣豊成は、ある年の春にこんなことを思い立ちました。
「そろそろ、山の雪も消え、谷の氷も解けたことであろう。雲雀山に登って狩りでもして、
心の憂さを晴らそう。」
豊成は、沢山の勢子を伴って、雲雀山にやって来ました。峰々、谷々を狩り巡りますが、
鹿の子一匹、捕まりません。豊成は腹立ち紛れに、峨々たる峰に駆け上がりました。得物は
居ないかと、谷を見下ろすと、とある尾根に庵が有り、仄かな煙が上がっているのが目に入
りました。豊成は、
「昔より、この山に、人の住んだ例しは無い。なにやら怪しい。」
と思い、馬から飛んで降りると、庵に近付き様子を窺いました。庵の中を覗いて見ると、年
の頃、十四五の覆面をした女が、写経をしており、傍に五十ばかりの尼が付き添っています。
豊成は、これを見て、
「これは、私を騙すために、野干化けているのだな。ひとつ、懲らしめてやろう。」
と思い、蟇目(ひきめ)の矢を番えると、ひょうとばかりに、射放ちました。しかし、姫君
は、そもそも仏の化身でありますから、お体には別状無く、矢は経机に、突き立ったのでした。
驚いた姫君が、
「これは、何者の仕業ですか。」
と、走り出ようとするところを、尼公(にこう)は姫君の矢面に立って、引き留めました。
姫君は尼公の袂に縋り付きました。
「矢に当たってはなりませんよ。お前が死んでしまったら、私はどうして良いか分かりません。」
この様子を見た豊成は、これは人間に違い無いと思い、
「これ、そこの女。このような人里遠い深山に住んでいるとは、何者か。名を名乗れ。」
と言いました。姫君は立ち出でて、
「ご不審はご尤もです。私は十三歳の時に、継母の計略に掛かって、この山で殺されそうに
なりましたが、ある郎等の働きにより、命を助けられ、これまで長らえております。私は殺
されても構いませんが、この尼御前だけは助けてあげて下さい。」
と頼むのでした。これを聞いた豊成は、はっとして、
「お前の父の名は何と言うのか。」
と尋ねました。姫君が、
「難波の大臣と申します。」
と答えると、言い終わらぬ内から豊成は、
「やあ、我が子であるか。我こそ父、豊成であるぞ。」
と、飛びつきました。互いにひっしと抱き合って、涙々の対面です。暫くして、姫君は、涙
の顔を上げて、
「父上様。私は、経春の情けによって、命を長らえましたが、親に不孝をする者は、三世の
諸佛からも憎まれると聞きます。私は、父上の不興を受けた身の上ですから、もう生きる
甲斐も無いのです。」
と口説くのでした。豊成が、
「もう、恨みなど無い。継母の嘘と気付かずに、お前を殺せと命じたが、お前の年頃の娘
を見る度に、お前がこの世に生きていたなら、こんふうに育ったに違い無いと思い忍び、
念仏をして経を読み、回向をしてきたのじゃ。その甲斐あって、今ここで、再び巡り逢った。
なんという喜びであろうか。さあ、一緒に都へ帰るぞ。」
と言うと、姫君は、
「有り難う御座います。都へお供したくは思いますが、継母がいらっしゃいます。後の親を
親とせよとの例え通りですが、私に一度は辛く当たった母上様が穏便であるならば、都に
かえりましょうが、そうでなければ、この山で朽ち果てるつもりです。」
と、嘆くのでした。豊成は、尤もと思い、
「おお、お前は、大変心が正しいのう。よく分かった。何事もお前の思うに任せよう。」
と答えました。姫君は喜んで、
「そうであるならば、都にお供いたします。さあ、女房。中井の三郎殿に暇乞いをいたしましょう。」
と言うと、三郎の塚に立ち寄って、
「やあ、三郎殿。お前が、言った通りに、父上に会うことができましたよ。私は、これから、
都に戻ります。草葉の陰で、きっと喜んでくれていることでしょう。こんな物憂い山中も
お前に名残が惜しまれて、後ろ髪が引かれます。三郎信綱よ。名残惜しや。」
と言い残すと、御輿に乗り込み、都を目指して帰って行ったのでした。
ところで、この事態を聞いた都の継母は、
「今更、中将姫と会うことなどできない。」
と思い、夜半に紛れて、館を去って行ったのでした。知人を尋ねて、頼もうと思いましたが、
この者は、内々に事情を知っていたので、継母を家に入れようとはしませんでした。そこで、
親戚筋なら大丈夫だろうと、親しくしてきた親戚を訪ねましたが、
「お前の様に、非情の者は、一門の者では無い。」
と言われ、荒々しく追い出されてしまいました。もうこうなっては、何処にも行く当てもありません。
継母は、
「浮き世に命長らえて、他人から後ろ指を指されて生きるぐらいなら、どこかの川に身を沈
めてしまえ。」
と思い切り、ある淵に走り行き、そのまま身を投げて死んでしまったのでした。この継母の
最期の有様を、憎まない者はおりません。
つづく
中将姫 ⑤
さて、中将姫が雲雀山から都にお帰りになられて、暫くした頃のことです。姫君は十六歳
になられました。そして、后の位に就く話が再び持ち上がったのでした。しかし、姫君は、
「例え私が十全万葉の位に就いたとしても、無間八難の底に沈むことから、救われる訳では
無い。出家をして、母も継母も回向しよう。」
と、菩提の心がむくむくと湧いて来たのでした。
「私が、無断で忍び出ることは、親不孝なことかもしれませんが、私が先に浄土へ行き、
父を迎えることこそ、真実の報恩であると信じます。」
と、姫君は誓うと、その夜の内に、奈良の都を出て、七里の道を急いで、当麻の寺へと向か
ったのでした。姫君は、寺に着くと、とある僧坊に立ち寄って、出家の望みを伝えましたが、
上人は、
「まだ、幼いあなた様が、どうして出家などなされるのですか。思い留まりなさい。」
と、諭しました。しかし、姫君は重ねて、
「私は、無縁の者で、頼りにする所もありません。殊に、親のご恩に報いる為に思い立った
出家ですから、どうか平にお願い申し上げます。」
と涙ながらに頼むのでした。さすがに、上人も哀れと思われて、
「それでは、結縁申しましょう。」
と、背丈ほどある黒髪を下ろし、戒を授け、その名を、善尼比丘尼(※実際は法如)と付け
たのでした。
ある時、善尼比丘尼は、本堂に七日間、籠もられて、
「私は、生身(しょうじん)の弥陀如来を拝むまでは、ここから一歩も出ません。」
と大願を立てられて、一食調菜(いちじきちょうさい)にて、一年間の不断念仏行に入られ
たのでした。
仏も哀れに思し召したのでしょうか。第六日目の天平宝字七年六月十六日(763年)の
酉の刻頃(午後6時頃)に、五十歳ぐらいの尼が現れ、中将姫の傍にやって来たのでした。
すると、その尼は、
「汝、生身の弥陀を拝みたいのであるならば、蓮の茎を百駄分(馬一頭分の荷駄:135Kg)
を調えなさい。そうすれば、極楽の変相を織り表してお目にかけましょう。」
と言うと、掻き消すように消えたのでした。善尼比丘尼は、
「あら、有り難や」
と、西に向かって手を合わせると、
「願いが叶った。」
と御堂を飛んで出るのでした。そして、父の所へ真っ先に行き、事の次第を話すのでした。
不思議に思った父大臣は、この奇跡について、さっそく御門に奏聞しました。すると、御門
は只ならぬお告げであると感じて、蓮の茎を集めよとの宣旨を下されたのでした。近国の者
達は、この勅命に応じて、我も我もと、蓮の茎を当麻寺へ運んだので、あっと言う間に百駄
の蓮の茎が集まったのでした。山の様に集まった蓮の茎を見て、禅尼比丘尼が喜んでいると、
いつかの尼御前がいつの間にかやって来て、蓮の茎から糸を引き出すのでした。有り難い
限りです。それから、お寺の北側から突然、池が湧き上がりました。その水は五色の色を
していて、その水で糸を染め上げるのでした。この池は、今に至るまで、染殿の池と呼ばれ
ています。(染殿の井:石光寺:奈良県葛城市)
それから、尼御前が、虚空を招くと、十七八の天人が天より降りて来て、乾の隅(北側)
に機織機を立てました。三世の諸佛までもが御来迎して、やがて、曼荼羅を織り始めたのでした。
やがて、浄土三部経の中巻、無量寿経の一部始終が、曼荼羅として織り上がりました。天女
達は、中将姫の前に曼荼羅を広げると、再び虚空に消えて行ったのです。
それから、尼御前は、その曼荼羅をお寺の正面に掛けると、中将姫を招いて、曼荼羅の
表す所を説き始めたのでした。大変有り難いことです。
「これは、弥陀の三尊。あれは三十七尊。これは、青(しょう)黄(おう)赤(せき)白(びゃく)
黒(こく)の華が咲き乱れている所です。あそこで拝まれていらっしゃるのは、宝珠の本体
である弥陀の三尊です。説法をされているので、多くの聖衆(しょうじゅ)が集まって来て、
弥陀を供養している所です。」
と、尼御前は、それぞれの菩薩達をひとつひとつ説明するのでした。中将姫は、喜びの余り
尼御前に縋り付いて、
「これほどに、尼御前の大恩を受けながら、ご恩を返さなければ、木石にも劣ります。お名
前は何と仰るのですか。又、どちらにお住まいなのですか。」
と、叫びました。尼公は、中将姫の額を三度撫でて、
「私こそ、西方極楽浄土の主、阿弥陀如来である。汝の心を汲み取って、ここに現じて来たのだ。
又、曼荼羅を織ったのは、私の左の脇立、観世音菩薩である。」
と言うなり、雲に乗ると、空高くに飛び上がって行ったのでした。禅尼比丘尼は、有り難し
有り難しと、三度礼拝なされるのでした。ですから今でも、当麻寺の北に観音堂(中之坊十一面観音)
が建っているのです。
こうして中将姫は、当麻寺に十四年間お勤めし、弥陀如来の誓いを顕して、遍く衆生を導
いたのでした。禅尼比丘尼の御法力の尊さには、貴賤上下を問わず、感心しない者はありま
せんでした。
つづく
中将姫⑥終
宝亀六年四月十三日(775年)のことでした。善尼比丘尼の法談があるということで、
近国の人々が、我も我もと当麻寺に集まって来ました。貴賤の群集夥しい中で、善尼比丘尼は、
「さあ、聴衆の皆様。私は、生年二十九歳。明日十四日には、大往生を遂げるのです。今宵、
ここに集まった皆々様は、ここで通夜をなされ、私の最期の説法を聞きなさい。
私は女ではありますが、どなたも、疑う事無く、ようく聞いて悟りなさい。忝くも、御釈
迦様の御本心は、この世界の一切の人々を、西方極楽浄土へと救うことなのです。阿弥陀如
来が、まだ法蔵比丘でいらっしゃった時にも、必ず安養世界へ救い取ろうと、固く誓約され
ました。このような有り難い二尊の御慈悲を知らないで、浮き世の栄華を望み、あちらこち
らと迷うことを、妄執と言うのです。また因果とも言い、そのまま、三途の大河に飲み込ま
れて、紅蓮地獄の氷に閉じ込められてしまうのです。そして、餓鬼、畜生、修羅、人天、天
道を流転して、ここで生まれ、あそこで死に、生々世々(しょうじょうぜぜ)のその間に、
浮かばれる事も無いのです。まったく浅ましいことではありませんか。
しかしながら、弥陀の本願の有り難さは、例え、そのような大罪人であっても、只、一心
不乱に、『南無阿弥陀仏、助け給え』と唱えれば、必ず弥陀は来迎なされて、極楽浄土の上
品上生にお導き下さるのです。何の疑いが有りましょうか。よくよく、ここを聞き分けて、
念仏を唱えなさい。」
と、声高らかに、御説法されるのでした。
その時のことです。継母の母は、二十丈(約60m)あまりの大蛇となって、中将姫の説
法を妨げてやろうと、現れたのでした。大蛇は、声荒らげて、
「やあ、中将姫、我を誰と思うか。恥ずかしながら、お前の継母であるぞ。浮き世で思い詰
めた怨念は、消えることは無いぞよ。」
と言うと、鱗を奮わせ、角を振り上げ、舌をべろべろと伸ばして、迫って来ます。まったく
恐ろしい有様です。中将姫は、
「なんと、浅ましいお姿でしょうか。その様なお心だからこそ、蛇道に落ちてしまうのです。
しかし、だからといって、あなたを無下にすることはありませんよ。幼くして母を失い、
あなたを、本当の母と思ってお慕い申し上げたのに、為さぬ仲と思いになって、私をお疎み
になられたことは、浅ましい限りです。これからは、その悪念を捨て去って、仏果を受け取
りなさい。」
と、御手を合わせて祈られるのでした。
「諸々の仏の中に、菩薩の御慈悲は、大乗のお慈悲。罪深き、女人悪人であろうとも、有情
無常の草木に至るまで、漏らさず救わんとの御誓願。私の継母もお救い下さい。」
そうして、中将姫は大蛇に向かい、
「さあ、母上。今より、悪心を振り捨てて、念仏を唱えなさい。そもそもこの名号には、
釈迦一代でお説きになった諸経の功徳の全てが、収まっているのですから、名号を唱えれば、
極楽往生は間違い無いのです。だからこそ、八万諸聖経皆是阿弥陀仏(浄土教古徳之偈)と
言うのです。この心をよくよく聞き分けて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えなさい。」
と迫るのでした。すると、大蛇は、忽ちに苦しみを逃れ、黄色の涙を流すのでした。
「あら、有り難や。このようなこととは知らないで、悪念を抱いた事は浅ましいかぎりです。
今より後は、あなたを偏に頼みます。どうかお導き下さい。」
大蛇はそう言うと、仏果を得て、虚空に舞い上がって行ったのでした。当麻寺、四月十四日
の練り供養の時、染殿の池から蛇の形をした物が飛び出てくるのが、この蛇であることは
隠れも無い事実です。
さて、そうしてその日が暮れました。お寺に詰め掛けた人々は、明日は善尼比丘尼の御入
滅と聞き、その夜の明けるのをじっとまちました。五更の天が明けると、善尼比丘尼は、高
座より、四方をきっと見渡して、
「さあ、皆さん。後世を願うのには、弥陀の御名を唱えるのが一番です。名僧知識の念仏も
皆さんの様な愚痴無知の人々、悪人でも女人でも、唱えた念仏に区別も差別も御座りません。
さて、悟りを目前にして、己心の弥陀(こしんのみだ)を拝むことがあります。己心の弥陀
を信じて、西方の弥陀を願わなくては、悟りの目を開くことにはなりません。浄土宗で見る
己心の弥陀というのは、弥陀の悟りそのものなのです。その悟りがあるからこそ、光明赫奕
とお姿を顕して、念仏を唱える者を、浄土へと導くことができるのです。
このように、浄土宗の心は、弥陀浄土正覚の内証を、忽然と実現して、迷う者も悟る者
も、一人残らず救うから、超世の願(ちょうせのがん)と言うのです。そして、また、無量
寿経の文言には、『光明返照 十方世界 念仏衆生 摂取不捨』とある。つまり、光明とは、
仏の身体より発する光が、遍く世界を照らすということである。また、十方とは、東西四維
(しゆい)上下を合わせて十方と言うのです。世界とはその十方の国土です。十方の国土に
あらゆる念仏の行者を、その身光で照らしているのです。摂取とは、収める心、不捨とは、
念仏行者を守り、御心を失わないので、不捨なのです。さあ、皆さん。ひとつひとつ、我が
心をよっく聞き分けて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、唱えなさい。」
と、声高らかに、お話になるのでした。そして、
「さて、四月十四日になりました。大往生を遂げましょう。」
と言うと、突然、弱弱となされ、最期に
「南無阿弥陀仏。」
と唱えると、二十九歳で、大往生をなされたのでした。
大勢の人々に見守られ、沢山の僧が供養して、野辺送りが行われましたが、その時、突然
紫雲が棚引き、虚空に妙音がこだまして、異香が薫じて、花が降ってきました。すると、
弥陀の三尊がご来迎なされて、菩薩達が、中将姫を救い取って行ったのでした。なんとも
有り難い限りです。
おわり
いとう様のリクエストにお応えして、「中将姫」を再掲載いたします。
また、ファイルの破損等で読めない記事がありましたら、お手数ですがお知らせください。
渡部八太夫
中将姫 ①
さて、大和の国の当麻(たいま)曼荼羅の由来を詳しく尋ねてみることにいたしましょう。
神武天皇より四十七代の廃帝天皇(淳仁天皇758年~764年)の頃のことです。大職冠
鎌足の四代後の孫で、横佩(よこはぎ)の右大臣、藤原豊成(とよなり)とい方は、又の名
を、難波の大臣と申します。藤原の豊成には、子供が一人おりました。名前は、中将姫と
言いました。十三歳になった中将姫の姿はの美しさは、秋の月と言いましょうか。お顔は、
露が降りた春の花。翡翠の黒髪は、背丈ほど。眦(まなじり)は愛嬌があり、丹花の唇は
鮮やかです。微笑む歯茎は健康で、細い眉は、優しげです。辺りも輝くそのお姿の話を聞い
ただけでも、恋に落ちない男は居ませんでした。
しかし、可哀想な事に、中将姫は既に母を亡くしていたのでした。父豊成は、これを不憫と思
って、後添えを貰ったのでした。中将姫は、素直に継母を受け入れて、良く従って、親孝行
をしましたので、心の奥底は分かりませんが、継母も表面的には、中将姫を可愛がったので
した。こうして、表面的には、平穏な日々が流れ、豊成も喜んだのでした。
ところで、中将姫のことを、内々に聞いた御門は、難波の大臣豊成を、内裏に呼ぶと、
中将姫を皇后に迎える由の宣旨を下したのでした。
「年の暮れか、来年の春には、秋の宮に迎えよう。」
これを聞いた豊成は、畏まって退出し、喜び勇んで館へと戻るのでした。天皇家への輿入れ
に、一人を除いて、皆大喜びです。昔から、継子と継母が仲良しだった例しはありません。
この事を聞いた継母は、自分の子供の出世の機会が奪われると感じて、その心は、忽ちに曇りました。
そして、何とかして、姫を殺してしまおうと、恐ろしい計画を立てるのでした。
御台所は、親近の若者を選ぶと、こう命じたのでした。
「お前は、冠、肩衣の正装で、朝夕、中将姫の所へ出入りしなさい。」
命じられた若者は、言われるままに、毎日、中将姫の所に出掛けて行くのでした。それから、
当御台は、豊成に近付いて、こう言うのでした。
「どうか、お聞き下さい。窺いますところでは、この頃、姫の所に、怪しい者が通っている
ということです。まったく女の身程、浅ましいものはありません。」
継母は、泣き真似までして、訴えるのでした。豊成は、これを聞くと、
「姫は、まだ子供であるぞ。そんなことがあるはずがない。それは、誰かの偽り事であろう。」
と相手にしませんでしたが、御台が更にしつこく、
「私も、そうであろうとは思いますが、事の次第をはっきりさせるため、物陰から、ちょっ
と覗いて見ることにしましょう。」
と迫るので、豊成は仕方無く、御台と連れ立って、中将姫の様子見に行きました。このこと
が、姫君の運命を変えてしまったのです。
さて、中将姫の部屋の近くを見てみますと、年の頃十七八歳の衣冠正しい若者が、忍び
顔で部屋から出て来るのでした。これを見た豊成は、刀に手を掛け、飛び掛かり、その場で
切り捨てようとしましたが、
『待て暫し、我が心。ここで奴を誅すれば、返って我が身の恥をさらすことになる。』
と思い留まると、怒りに顔を真っ赤にして、自室に戻りました。
余りの事に、豊成は、竹岡の八郎経春(つねはる)を呼びつけると、
「やれ、経春。中将姫を引っ立てて、雲雀山(ひばりさん:奈良県宇陀市;日張山)に連れ
て行き、殺せ。」
と、言い放ちました。経春は、驚いて、
「これは、どんな咎があって、そうのようなことを仰るのですか。恐れながら、お姫様は、
先ず、私にお預け下さい。」
と、取りなしますが、豊成は、
「思う子細があるのだ。早や、急げ。」
と、頑な(かたくな)です。経春は重ねて、
「何と仰られても、このようなご命令を、簡単に引き受けることはできません。一先ず、
姫君をお預かり申します。」
と、食い下がりましたが、豊成は、気色を変えて、
「親の私が、子供の命を絶てと言っているのだから、そのような重い咎があったと思え。
お前が引き受けないというのなら、中将姫と諸共に、勘当じゃ。」
と、怒鳴り散らすと、奥へと入って行ってしまうのでした。
困り果てた経春は、せまじきものは宮仕えと、口説き立てますが、なんともしようがあり
ません。いくら嘆いても仕方が無いので、経春は、継母の御台所に何とかしてもらおうと考
えました。経春は、御台所の所に駆けつけると、
「姫君の事を、まだご存じ無いのですか。殿の御機嫌が悪く、直ぐに殺して来いと仰って
おられるのです。どうか、何とかして、殿を宥めて、姫の命をお助け下さい。」
と涙ながらに訴えるのでした。女房達が、御台所に取り次ぐと、御台所は、
「経春が、わざわざ言いに来なくても、私も、そうとは思います。しかし、原因は、世の常
のことではないとも聞きましたよ。唯々、豊成殿のお心に任せます。」
と無愛想な返事です。経春が、更に、
「それはご尤もですが、只一度の御勘気で、その上まだ、ほんのご幼少。どれほどの罪を
犯したというのでしょうか。御台様が申し入れなされれば、殿の気も変わるかもしれません。
叶わないまでも、どうか、今一度、殿を宥めていただけないでしょうか。お願いします。」
と食い下がると、御台所は気色を変えて、出居まで飛んで降り、
「経春。聞きなさい。お前は、まだ、知らないのか。毎日、姫君の本へ通う者は幾人とも限
りも無い。それをどうして、私が宥められるものですか。」
と言い張るのでした。御台所は、
「あら、難しや。」
と、言い捨てると、簾中の中へと逃げ込むのでした。
経春は、面目も無く、ただ、呆れ果てていましたが、
『これは、継母の御台の謀り事に違い無い。例え、そうしたことが事実であったとしても、
実母であるなら、必ず助けに入るだろう。なんと、なさぬ仲の浅ましき事か。』
と、気が付くのでした。経春は、悔し涙の暇より、
『とにかく、姫君を我が館に匿い。何度でも嘆願いたそう。それでもだめならば、腹切って
死ぬ外あるまい。』
と決心したのでした。八郎経春の心の内の頼もしさは、何とも言い様がありません。
つづく
中将姫②
八郎経春は、何とかして姫君を助けようと思いましたが、検使の役が付いてしまったので、
思う様に姫を匿うこともできませんでした。とうとう観念した経春は、
『もう、逃げようが無い。この上は、姫君のお首をいただいて、豊成に見せたなら、遁世し
て、姫の菩提を問う外はあるまい。』
と思い定めると、姫君を伴って、雲雀山へと向かうのでした。
雲雀山の山中の、とある谷川の辺りに輿を止めました。何も知らない姫君は、御輿から
降りると、経春に聞きました。
「経春よ。どうして、こんな寂しい山中に連れて来たのですか。不思議ですね。」
これを聞いた経春は、言葉も無く泣くばかりです。姫君が、
「どうしたというのですか。おかしいですね。何故、何も言わないのです。何があったのですか。」
と、重ねて問い正すと、経春は、ようやく涙をぬぐって、
「ここまで来ては、隠すこともできません。父上様のご命令で、姫君のお命を頂戴いたします。
そのために、ここまでおいで願ったのです。」
と言うのでした。聞いた姫君は、夢現かと驚いて、
「それは、本当ですか。」
と、絶句して泣くばかりです。涙ながらに姫君は、
「母様が亡くなられてからというもの、ひとときも母様のことを忘れた事は無く、心が慰め
られることもなかったので、私を、慰めるために、ここまで連れてきてくれたのかと思って
いましたのに。それどころか、私を殺すというのですか。ああ、これは継母の仕業ですね。
なんという情け無い事でしょうか。」
と口説いて、身を悶えて嘆くばかりです。姫君は、更に続けて、
「やあ、経春よ。前世からの宿業で、お前の手に掛かって死ぬ命を、惜しい等とは露にも
思いません。親の不興を受けた者には、日の光も、月の光をも射さないとききますが、
私は、一体どういうわけで、父から捨てられたのでしょうか。いやいや、それを聞いたとし
ても、もうどうしようもありませんね。
私は、七歳の時から、母上様の為に、毎日、お経を六巻づつ読誦して参りましたが、今日
はまだ読誦しておりません。これが、最期というのなら、今一度、母のために読経いたしま
すから、暫くの時間を与えて下さい。」
と、言うのでした。聞いて、経春は、
「ああ、なんと勿体ないことでしょうか。姫君様。御最期でありますので、何時もよりも、
お心静に読誦をして下さい。」
と涙ぐむのでした。中将姫も涙ながらに、敷き葉の上に座り直して、右の袂より浄土経を
取り出しました。中将姫は、さらさらと押し開くと、迦陵頻伽(かりょうびんが)のお声で、
読誦なされるのでした。殊勝なこと限り有りませんが、流石に姫君は、父の大臣への名残が
惜しいのでしょう。雨の様な涙が只々、落ちるばかりです。労しいことに姫君は、余りに
お心がやるせないので、ようやく三巻を読み終えて、
「一巻は、母の為、又一巻は父の為、現世来世の二世の為。さて、もう一巻は、自分自身の
正念です。どうか、九品の浄土にお迎え下さい。」
と、泣く泣く回向をされるのでした。中将姫は、思い切って、経春に向かうと、
「如何に、経春。私が死んだ後、絶対に後の恥を曝してはなりませんよ。私の首を、父上に
見せる時には、顔についた血飛沫を、よくよく洗い流してからにしてくださいね。そして、
命を惜しむようなことは無かった、素晴らしい最期であったと、伝えて下さいよ。さあ、
これから念仏を唱えます。十念が終わったならば、首を刎ねなさい。」
と言うと、背丈ほどもある黒髪を、きりきりと唐輪(からわ)に結い上げて、西に向かって
手を合わせました。
「南無西方の弥陀如来。例え、後生が三重に罪深くて、十方浄土に選ばれぬ女なりとも、
只今のお経、念仏の功力により、母上様諸共に、西方極楽浄土に、迎えて下さい。」
と、声高く、十念を唱えるのでした。南無阿弥陀仏を十度唱えて、姫君は、
「どうした経春。早、首を取れ。」
と迫ります。経春は、太刀を抜き放ち、お首を打ち落とそうとしました。しかし、姫のお姿
が目に入れば、余りにもお労しく、とうとう、太刀を投げ捨てて、地に倒れ伏して泣く外は
ありません。姫君は、経春をご覧になり、
「愚かであるぞ、経春。そのような不覚の者が、父の命を受け、私を殺すために、ここまで
連れて来たのですか。心弱くてはなりませんよ。善に強いのなら、悪にも退いてはなりませ
ん。さあさあ、如何に如何に。」
と、泣き崩れるのでした。経春は、漸く涙を押し留めて、
「しかし、姫君は、まだご幼少の事ですから、それほどの罪があるとは思われません。それ
なのに、やみやみと殺さなければならないとは、どうしても納得できません。」
と、言うのでした。姫君は、涙と共に、こう口説きました。
「親が憎む子は、その一門の者まで憎むと聞きますが、どうして経春は、そんなに優しくし
てくれるのですか。今のあなたのお志しは、草葉の陰に行っても決して忘れませんよ。草葉
の陰で私が見ていると思って、後世を問うて下さいな。さあさあ、そんなに思い悩まずに、
父の命に従って下さい。」
しかし、経春は、これを聞いて、
「ああ、なんと愛おしいことでしょうか。乳房の母がご健在であるならば、こんなことには
ならなかったのに。為さぬ仲の継母が浅ましい。」
と更に悶々と思い悩むのでした。しかし、やがて思い切り、
『ええ、姫君を殺して恩賞に預かったとしても、千年万年と生きられる訳では無いわ。我が
身の事はさて置き、一門眷属までも引き出され、ずたずたにされたとしても、姫君を助けな
いでどうするか。しかし、検使をどうするか。否というなら、奴らの首を掻くまでだ。』
と決心するのでした。経春が、検使に姫を助けると告げると、なんと検使の者も、
「私もそのように思います。いざ、お助けいたしましょう。」
と言うのでした。
それから姫のために、雲雀山に庵を建てると、経春は、都から女房や郎等を呼び寄せました。
経春は、
「私は、これから都へ戻り、姫君様の事を、どのようにでも、申し開きをして参る。皆の者
は、ここに留まって、姫君を守り助けるのだぞ。」
と言い残して、都へと帰って行ったのでした。かの経春の志は、頼もしいともなんとも、
なかなか言い表す言葉もみつかりません。
つづく
中将姫 ③
さて、父の大臣豊成は、家来の侍を集めて、こう言いました。
「姫の処分を、経春に命じたが、その後、何の報告も無い。急いで、経春の所へ行き子細を
尋ねて参れ。」
侍達が、経春の所へ行き、事の子細を問うと、経春は、
「これはこれは、直ぐにでも、ご報告に上がろうとは思っていましたが、何しろ、姫君の
死骸が、火車によって運び去られてしまったので、報告もできないでいたのです。哀れと思
って、お許し下さるのなら、これより伺候して、姫君の最期のご様子をお話いたしましょう。」
と言うのでした。使いの侍が、館に戻って、経春の返答を伝えると、豊成は怒って、
「居ながらの返事とは、なんと生意気な。命令をし遂げなかったな。つべこべいわせずに、
経春を連れて来い。」
と命じたのでした。二十余人の強者達が、経春の館へと駆けつけました。侍達は、
「如何に経春殿。お殿様の申すには、中将姫の首を見せぬのは何故だ。検使の役の者共はど
こへ行ったのだ。詳しく尋ねることがあるから、急いで来る様に、とのことです。」
と言うのですが、経春は、
「おお、ご尤も。しかしなあ、なんだか今日は、気が進まぬ。又日を改めて、参ることに
いたしましょう。」
と、相手にしません。侍達もむっとして、
「憎っくき、今の物言い。このまま帰るならば、こちらが詰め腹切らされる。さあ、引っ立
てろ。」
と、左右に分かれて飛び掛かりました。本より大力の経春は、飛び掛かる侍どもを、取って
は投げ、取っては投げて応戦します。残りの奴原を、四方へ蹴散らかすと、経春は、郎等ど
もを集めて、言いました。
「きっと、これから追っ手が攻めてくるであろう。とても敵うものではないから、お前達
は、どこへでも落ち延びて、後世を問うてくれ。さあ、早く。」
と言うのでした。しかし、郎等共は、
「なんと、残念な仰せでしょうか。主君の先途を見届けずに、落ち延びることなどできるは
ずもありません。是非、お供させて下さい。」
と、譲りませんでした。経春が、
「おお、それは頼もしい。では、用意いたせ。」
と言うと、皆々勇んで、最期の出立ちを整えました。やがて、豊成方の軍勢が押し寄せて
鬨の声を上げました。経春は、大勢の中に飛んで入り、ここを先途と戦いました。しかし、
多勢に無勢。郎等達も皆悉く討ち殺されていまいました。経春は、もうこれまでと思い、
敵を、四方におっ散らすと、門内につっと入りました。鎧の上帯を切って捨てると、腹を
十文字に掻き切って、自らの首を掻き落としたのでした。この経春の振る舞いは、上下万民
押し並べて、感激しない者はありませんでした。
つづく
中将姫 ④
危うく命拾いをした中将姫は、物憂い山住まいの毎日を過ごしていました。その上、頼み
の綱の経春が討ち死にしたとの知らせもあり、心の内のやるかたない風情も哀れです。そん
な中でも、中井の三郎と経春の女房は、姫君をお守りして、落ち穂を拾い、物乞いをして
支えたのでした。
しかし、ある時、中井の三郎は重い病に伏してしまいます。中将姫も、女房も、枕元で、
励ましますが、山中のこととて、癒やし様もありません。縋り付いて泣くばかりです。もう
これが最期という時に、中井の三郎は女房に介錯されて起き上がると、
「姫君様。娑婆でのご縁も終わりです。これより冥途の旅に出掛けます。私が生きている限
り、必ず父大臣に申し開き、再び御世に戻して差し上げようと、明け暮れ、このことだけ
を思い続けていたというのに、とても残念です。どうか、必ず姫君様は、お命を全うして
くだされませ。神は正しい者の頭に宿ります。きっと必ず、父上様に再び、お会いになるこ
とは鏡に掛けて明らかです。死する命は惜しくはありませんが、姫君のお心の内を推し量り
ますと、只それだけが、名残惜しく思われます。」
と、最期の言葉を残して、明日の露と消えたのでした。姫も女房もこれはこれはと、泣くよ
り外はありません。姫君は涙の暇より、口説き立て、
「ああ、何という浅ましいことでしょう。父上に捨てられて、経春は討ち死にし、この
寂しい山中で、お前だけを頼りにして暮らして来たのに、今度は、お前まで失って、これか
らどうやって暮らしていけばよいのですか。私も一緒に連れていって下さい。」
と、空しい死骸を押し動かし、押し動かして、慟哭するのでした。女房は、
「お嘆きはご尤もです。しかしながら、最早帰らぬ事です。さあ、どうにかして、この死骸
を葬りましょう。」
と、健気にも励まします。山中には外に頼める僧も無く、女房と姫君二人で、土を掘り死骸
を埋め、塚を築いて、印の松を植えたのでした。それから、姫君自ら、お経を唱え、回向
をするのでした。
さて、その後も山中の寂しい日々が続いていましたが、姫君は、称賛浄土経を書き写して
暮らしておりました。ある日、姫君は女房に、こう話しました。
「このお経は、釈迦仏の弥陀の浄土を褒め称えたお経です。毎日唱えて、夫の経春の供養を
して下さい。」
女房は、これは有り難いと、お経を給わったのです。それから女房は、髪を剃り落とし尼と
なって暮らしたのでした。
さて一方、難波の大臣豊成は、ある年の春にこんなことを思い立ちました。
「そろそろ、山の雪も消え、谷の氷も解けたことであろう。雲雀山に登って狩りでもして、
心の憂さを晴らそう。」
豊成は、沢山の勢子を伴って、雲雀山にやって来ました。峰々、谷々を狩り巡りますが、
鹿の子一匹、捕まりません。豊成は腹立ち紛れに、峨々たる峰に駆け上がりました。得物は
居ないかと、谷を見下ろすと、とある尾根に庵が有り、仄かな煙が上がっているのが目に入
りました。豊成は、
「昔より、この山に、人の住んだ例しは無い。なにやら怪しい。」
と思い、馬から飛んで降りると、庵に近付き様子を窺いました。庵の中を覗いて見ると、年
の頃、十四五の覆面をした女が、写経をしており、傍に五十ばかりの尼が付き添っています。
豊成は、これを見て、
「これは、私を騙すために、野干化けているのだな。ひとつ、懲らしめてやろう。」
と思い、蟇目(ひきめ)の矢を番えると、ひょうとばかりに、射放ちました。しかし、姫君
は、そもそも仏の化身でありますから、お体には別状無く、矢は経机に、突き立ったのでした。
驚いた姫君が、
「これは、何者の仕業ですか。」
と、走り出ようとするところを、尼公(にこう)は姫君の矢面に立って、引き留めました。
姫君は尼公の袂に縋り付きました。
「矢に当たってはなりませんよ。お前が死んでしまったら、私はどうして良いか分かりません。」
この様子を見た豊成は、これは人間に違い無いと思い、
「これ、そこの女。このような人里遠い深山に住んでいるとは、何者か。名を名乗れ。」
と言いました。姫君は立ち出でて、
「ご不審はご尤もです。私は十三歳の時に、継母の計略に掛かって、この山で殺されそうに
なりましたが、ある郎等の働きにより、命を助けられ、これまで長らえております。私は殺
されても構いませんが、この尼御前だけは助けてあげて下さい。」
と頼むのでした。これを聞いた豊成は、はっとして、
「お前の父の名は何と言うのか。」
と尋ねました。姫君が、
「難波の大臣と申します。」
と答えると、言い終わらぬ内から豊成は、
「やあ、我が子であるか。我こそ父、豊成であるぞ。」
と、飛びつきました。互いにひっしと抱き合って、涙々の対面です。暫くして、姫君は、涙
の顔を上げて、
「父上様。私は、経春の情けによって、命を長らえましたが、親に不孝をする者は、三世の
諸佛からも憎まれると聞きます。私は、父上の不興を受けた身の上ですから、もう生きる
甲斐も無いのです。」
と口説くのでした。豊成が、
「もう、恨みなど無い。継母の嘘と気付かずに、お前を殺せと命じたが、お前の年頃の娘
を見る度に、お前がこの世に生きていたなら、こんふうに育ったに違い無いと思い忍び、
念仏をして経を読み、回向をしてきたのじゃ。その甲斐あって、今ここで、再び巡り逢った。
なんという喜びであろうか。さあ、一緒に都へ帰るぞ。」
と言うと、姫君は、
「有り難う御座います。都へお供したくは思いますが、継母がいらっしゃいます。後の親を
親とせよとの例え通りですが、私に一度は辛く当たった母上様が穏便であるならば、都に
かえりましょうが、そうでなければ、この山で朽ち果てるつもりです。」
と、嘆くのでした。豊成は、尤もと思い、
「おお、お前は、大変心が正しいのう。よく分かった。何事もお前の思うに任せよう。」
と答えました。姫君は喜んで、
「そうであるならば、都にお供いたします。さあ、女房。中井の三郎殿に暇乞いをいたしましょう。」
と言うと、三郎の塚に立ち寄って、
「やあ、三郎殿。お前が、言った通りに、父上に会うことができましたよ。私は、これから、
都に戻ります。草葉の陰で、きっと喜んでくれていることでしょう。こんな物憂い山中も
お前に名残が惜しまれて、後ろ髪が引かれます。三郎信綱よ。名残惜しや。」
と言い残すと、御輿に乗り込み、都を目指して帰って行ったのでした。
ところで、この事態を聞いた都の継母は、
「今更、中将姫と会うことなどできない。」
と思い、夜半に紛れて、館を去って行ったのでした。知人を尋ねて、頼もうと思いましたが、
この者は、内々に事情を知っていたので、継母を家に入れようとはしませんでした。そこで、
親戚筋なら大丈夫だろうと、親しくしてきた親戚を訪ねましたが、
「お前の様に、非情の者は、一門の者では無い。」
と言われ、荒々しく追い出されてしまいました。もうこうなっては、何処にも行く当てもありません。
継母は、
「浮き世に命長らえて、他人から後ろ指を指されて生きるぐらいなら、どこかの川に身を沈
めてしまえ。」
と思い切り、ある淵に走り行き、そのまま身を投げて死んでしまったのでした。この継母の
最期の有様を、憎まない者はおりません。
つづく
中将姫 ⑤
さて、中将姫が雲雀山から都にお帰りになられて、暫くした頃のことです。姫君は十六歳
になられました。そして、后の位に就く話が再び持ち上がったのでした。しかし、姫君は、
「例え私が十全万葉の位に就いたとしても、無間八難の底に沈むことから、救われる訳では
無い。出家をして、母も継母も回向しよう。」
と、菩提の心がむくむくと湧いて来たのでした。
「私が、無断で忍び出ることは、親不孝なことかもしれませんが、私が先に浄土へ行き、
父を迎えることこそ、真実の報恩であると信じます。」
と、姫君は誓うと、その夜の内に、奈良の都を出て、七里の道を急いで、当麻の寺へと向か
ったのでした。姫君は、寺に着くと、とある僧坊に立ち寄って、出家の望みを伝えましたが、
上人は、
「まだ、幼いあなた様が、どうして出家などなされるのですか。思い留まりなさい。」
と、諭しました。しかし、姫君は重ねて、
「私は、無縁の者で、頼りにする所もありません。殊に、親のご恩に報いる為に思い立った
出家ですから、どうか平にお願い申し上げます。」
と涙ながらに頼むのでした。さすがに、上人も哀れと思われて、
「それでは、結縁申しましょう。」
と、背丈ほどある黒髪を下ろし、戒を授け、その名を、善尼比丘尼(※実際は法如)と付け
たのでした。
ある時、善尼比丘尼は、本堂に七日間、籠もられて、
「私は、生身(しょうじん)の弥陀如来を拝むまでは、ここから一歩も出ません。」
と大願を立てられて、一食調菜(いちじきちょうさい)にて、一年間の不断念仏行に入られ
たのでした。
仏も哀れに思し召したのでしょうか。第六日目の天平宝字七年六月十六日(763年)の
酉の刻頃(午後6時頃)に、五十歳ぐらいの尼が現れ、中将姫の傍にやって来たのでした。
すると、その尼は、
「汝、生身の弥陀を拝みたいのであるならば、蓮の茎を百駄分(馬一頭分の荷駄:135Kg)
を調えなさい。そうすれば、極楽の変相を織り表してお目にかけましょう。」
と言うと、掻き消すように消えたのでした。善尼比丘尼は、
「あら、有り難や」
と、西に向かって手を合わせると、
「願いが叶った。」
と御堂を飛んで出るのでした。そして、父の所へ真っ先に行き、事の次第を話すのでした。
不思議に思った父大臣は、この奇跡について、さっそく御門に奏聞しました。すると、御門
は只ならぬお告げであると感じて、蓮の茎を集めよとの宣旨を下されたのでした。近国の者
達は、この勅命に応じて、我も我もと、蓮の茎を当麻寺へ運んだので、あっと言う間に百駄
の蓮の茎が集まったのでした。山の様に集まった蓮の茎を見て、禅尼比丘尼が喜んでいると、
いつかの尼御前がいつの間にかやって来て、蓮の茎から糸を引き出すのでした。有り難い
限りです。それから、お寺の北側から突然、池が湧き上がりました。その水は五色の色を
していて、その水で糸を染め上げるのでした。この池は、今に至るまで、染殿の池と呼ばれ
ています。(染殿の井:石光寺:奈良県葛城市)
それから、尼御前が、虚空を招くと、十七八の天人が天より降りて来て、乾の隅(北側)
に機織機を立てました。三世の諸佛までもが御来迎して、やがて、曼荼羅を織り始めたのでした。
やがて、浄土三部経の中巻、無量寿経の一部始終が、曼荼羅として織り上がりました。天女
達は、中将姫の前に曼荼羅を広げると、再び虚空に消えて行ったのです。
それから、尼御前は、その曼荼羅をお寺の正面に掛けると、中将姫を招いて、曼荼羅の
表す所を説き始めたのでした。大変有り難いことです。
「これは、弥陀の三尊。あれは三十七尊。これは、青(しょう)黄(おう)赤(せき)白(びゃく)
黒(こく)の華が咲き乱れている所です。あそこで拝まれていらっしゃるのは、宝珠の本体
である弥陀の三尊です。説法をされているので、多くの聖衆(しょうじゅ)が集まって来て、
弥陀を供養している所です。」
と、尼御前は、それぞれの菩薩達をひとつひとつ説明するのでした。中将姫は、喜びの余り
尼御前に縋り付いて、
「これほどに、尼御前の大恩を受けながら、ご恩を返さなければ、木石にも劣ります。お名
前は何と仰るのですか。又、どちらにお住まいなのですか。」
と、叫びました。尼公は、中将姫の額を三度撫でて、
「私こそ、西方極楽浄土の主、阿弥陀如来である。汝の心を汲み取って、ここに現じて来たのだ。
又、曼荼羅を織ったのは、私の左の脇立、観世音菩薩である。」
と言うなり、雲に乗ると、空高くに飛び上がって行ったのでした。禅尼比丘尼は、有り難し
有り難しと、三度礼拝なされるのでした。ですから今でも、当麻寺の北に観音堂(中之坊十一面観音)
が建っているのです。
こうして中将姫は、当麻寺に十四年間お勤めし、弥陀如来の誓いを顕して、遍く衆生を導
いたのでした。禅尼比丘尼の御法力の尊さには、貴賤上下を問わず、感心しない者はありま
せんでした。
つづく
中将姫⑥終
宝亀六年四月十三日(775年)のことでした。善尼比丘尼の法談があるということで、
近国の人々が、我も我もと当麻寺に集まって来ました。貴賤の群集夥しい中で、善尼比丘尼は、
「さあ、聴衆の皆様。私は、生年二十九歳。明日十四日には、大往生を遂げるのです。今宵、
ここに集まった皆々様は、ここで通夜をなされ、私の最期の説法を聞きなさい。
私は女ではありますが、どなたも、疑う事無く、ようく聞いて悟りなさい。忝くも、御釈
迦様の御本心は、この世界の一切の人々を、西方極楽浄土へと救うことなのです。阿弥陀如
来が、まだ法蔵比丘でいらっしゃった時にも、必ず安養世界へ救い取ろうと、固く誓約され
ました。このような有り難い二尊の御慈悲を知らないで、浮き世の栄華を望み、あちらこち
らと迷うことを、妄執と言うのです。また因果とも言い、そのまま、三途の大河に飲み込ま
れて、紅蓮地獄の氷に閉じ込められてしまうのです。そして、餓鬼、畜生、修羅、人天、天
道を流転して、ここで生まれ、あそこで死に、生々世々(しょうじょうぜぜ)のその間に、
浮かばれる事も無いのです。まったく浅ましいことではありませんか。
しかしながら、弥陀の本願の有り難さは、例え、そのような大罪人であっても、只、一心
不乱に、『南無阿弥陀仏、助け給え』と唱えれば、必ず弥陀は来迎なされて、極楽浄土の上
品上生にお導き下さるのです。何の疑いが有りましょうか。よくよく、ここを聞き分けて、
念仏を唱えなさい。」
と、声高らかに、御説法されるのでした。
その時のことです。継母の母は、二十丈(約60m)あまりの大蛇となって、中将姫の説
法を妨げてやろうと、現れたのでした。大蛇は、声荒らげて、
「やあ、中将姫、我を誰と思うか。恥ずかしながら、お前の継母であるぞ。浮き世で思い詰
めた怨念は、消えることは無いぞよ。」
と言うと、鱗を奮わせ、角を振り上げ、舌をべろべろと伸ばして、迫って来ます。まったく
恐ろしい有様です。中将姫は、
「なんと、浅ましいお姿でしょうか。その様なお心だからこそ、蛇道に落ちてしまうのです。
しかし、だからといって、あなたを無下にすることはありませんよ。幼くして母を失い、
あなたを、本当の母と思ってお慕い申し上げたのに、為さぬ仲と思いになって、私をお疎み
になられたことは、浅ましい限りです。これからは、その悪念を捨て去って、仏果を受け取
りなさい。」
と、御手を合わせて祈られるのでした。
「諸々の仏の中に、菩薩の御慈悲は、大乗のお慈悲。罪深き、女人悪人であろうとも、有情
無常の草木に至るまで、漏らさず救わんとの御誓願。私の継母もお救い下さい。」
そうして、中将姫は大蛇に向かい、
「さあ、母上。今より、悪心を振り捨てて、念仏を唱えなさい。そもそもこの名号には、
釈迦一代でお説きになった諸経の功徳の全てが、収まっているのですから、名号を唱えれば、
極楽往生は間違い無いのです。だからこそ、八万諸聖経皆是阿弥陀仏(浄土教古徳之偈)と
言うのです。この心をよくよく聞き分けて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えなさい。」
と迫るのでした。すると、大蛇は、忽ちに苦しみを逃れ、黄色の涙を流すのでした。
「あら、有り難や。このようなこととは知らないで、悪念を抱いた事は浅ましいかぎりです。
今より後は、あなたを偏に頼みます。どうかお導き下さい。」
大蛇はそう言うと、仏果を得て、虚空に舞い上がって行ったのでした。当麻寺、四月十四日
の練り供養の時、染殿の池から蛇の形をした物が飛び出てくるのが、この蛇であることは
隠れも無い事実です。
さて、そうしてその日が暮れました。お寺に詰め掛けた人々は、明日は善尼比丘尼の御入
滅と聞き、その夜の明けるのをじっとまちました。五更の天が明けると、善尼比丘尼は、高
座より、四方をきっと見渡して、
「さあ、皆さん。後世を願うのには、弥陀の御名を唱えるのが一番です。名僧知識の念仏も
皆さんの様な愚痴無知の人々、悪人でも女人でも、唱えた念仏に区別も差別も御座りません。
さて、悟りを目前にして、己心の弥陀(こしんのみだ)を拝むことがあります。己心の弥陀
を信じて、西方の弥陀を願わなくては、悟りの目を開くことにはなりません。浄土宗で見る
己心の弥陀というのは、弥陀の悟りそのものなのです。その悟りがあるからこそ、光明赫奕
とお姿を顕して、念仏を唱える者を、浄土へと導くことができるのです。
このように、浄土宗の心は、弥陀浄土正覚の内証を、忽然と実現して、迷う者も悟る者
も、一人残らず救うから、超世の願(ちょうせのがん)と言うのです。そして、また、無量
寿経の文言には、『光明返照 十方世界 念仏衆生 摂取不捨』とある。つまり、光明とは、
仏の身体より発する光が、遍く世界を照らすということである。また、十方とは、東西四維
(しゆい)上下を合わせて十方と言うのです。世界とはその十方の国土です。十方の国土に
あらゆる念仏の行者を、その身光で照らしているのです。摂取とは、収める心、不捨とは、
念仏行者を守り、御心を失わないので、不捨なのです。さあ、皆さん。ひとつひとつ、我が
心をよっく聞き分けて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、唱えなさい。」
と、声高らかに、お話になるのでした。そして、
「さて、四月十四日になりました。大往生を遂げましょう。」
と言うと、突然、弱弱となされ、最期に
「南無阿弥陀仏。」
と唱えると、二十九歳で、大往生をなされたのでした。
大勢の人々に見守られ、沢山の僧が供養して、野辺送りが行われましたが、その時、突然
紫雲が棚引き、虚空に妙音がこだまして、異香が薫じて、花が降ってきました。すると、
弥陀の三尊がご来迎なされて、菩薩達が、中将姫を救い取って行ったのでした。なんとも
有り難い限りです。
おわり