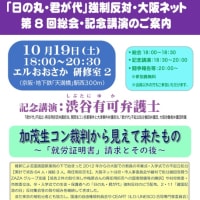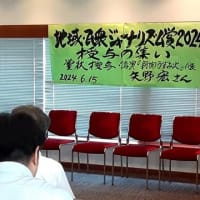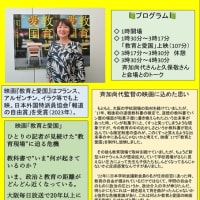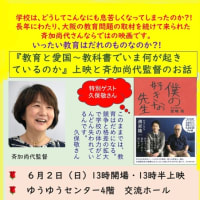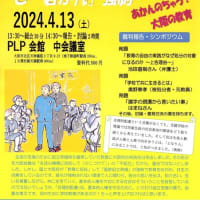※時折、橋下徹大阪市長にツイッターを見るのですが、また「吠えて」います。今度のお相手は毎日新聞です。
どうも彼が「吠える」時は、批判が図星の時のように思います。
つまり、それをやみくもにごまかす為に、大阪弁でいうところの「かます」を用いるように思います。
「かます」と言うのは、強い大きな声で驚かしたり、脅したりすることを意味します。
まず橋下さんのツイッターから引用します。
橋下徹@t_ishin
毎日新聞が僕が知事になってからの5年間で何の成果もないと丁寧な記事を出してくれた。色んな数字を出して知事就任前と就任後に変化がないと。非情に有難いことだけど、毎日新聞てこんなに頭の悪い新聞だとは思わなかった。僕の権限かどうかの分析もなく、大阪のあらゆることは僕が変えられるとの前提
毎日新聞(2月6日付大阪朝刊)
http://mainichi.jp/area/news/20130206ddn001010009000c.html
橋下改革5年:大阪再生、2/3足踏み 生活24指標分析
橋下徹・大阪市長が08年に大阪府知事に就任し、6日で5年を迎える。毎日新聞が府民生活に関する24項目のデータについて5年間の変化を調べたところ、経済など3分の2は足踏み状態だった。教育分野を中心に3分の1では改善したが、元の数値が極端に悪かった項目も複数含まれる。暮らしの改善や街の活性化といった大阪の再生に関し、現時点で橋下改革が目立った成果を上げていないことが浮き彫りになった。(3面にクローズアップ、26面に「大阪は変わったか」)
調べたのは、教育・子育て▽くらし・雇用▽にぎわい・経済▽医療・福祉▽安心・安全−−の5分野。
経済や暮らし面は、低迷傾向のまま変化が乏しい。企業の転出入をみると、毎年100社前後の転出超過が続く。08年からの4年間の転出数は計1040社で、転入の計642社を大きく上回った。企業への課税の基準になる「法人所得」は、07年の約5兆9000億円から10年の約3兆8000億円へと大幅に落ち込んだ。高校中退率や朝食を毎日食べる中学3年生の割合は、数値こそ改善したが、ともに都道府県最下位が続いている。
一方、橋下氏が注力した一部項目は上昇している。子どもの学力は教科によって上昇。小学生の算数(基礎)の学力は07年に全都道府県で41位だったが、12年は14位。給食を実施する公立中は極端に低かったが、同時期に10・4%から26・3%に増えた。ただ、全国平均は80%を超え、なお低位だ。【平野光芳】
クローズアップ2013:橋下氏、知事就任から5年 制度改変に偏重 生活・経済、乏しい成果
毎日新聞 2013年02月06日 大阪朝刊3面
「皆さんにリンゴを与えることはできません。リンゴのなる木の土を耕し直します」。共同代表を務める日本維新の会の綱領でうたうように、最近の橋下徹大阪市長は大阪都構想などに代表される制度改変に力点を置く。大阪府知事として政界進出して6日で5年。毎日新聞のデータ分析によると、橋下市長と後継の松井一郎知事らによる改革に、府民生活などの改善といった成果は現時点で乏しかった。制度万能論に懐疑的な声も出るが、リンゴのなる日は来るのか。【堀文彦、平野光芳、熊谷豪】
「経済を良くするなんて、自治体では無理だ」。経済などの指標が向上していない現状を問われた橋下氏は5日、記者団に持論を展開した。大阪都構想の目的を「大阪に人、物、金を呼び込むため」と主張してきたが、この日は「経済を良くするには、金融政策、財政出動、構造改革の3本柱が必要だ。三つとも自治体ではできない」と説明。「根っこの部分を変えることに集中してきたつもりだ」と、制度改変の重要性を改めて強調した。
だが、企業の本社流出など、地盤沈下に歯止めがかからないのも大阪の現実だ。帝国データバンクによると、02年からの10年間で大阪府は1154社の転出超過だった。東京都の2891社こそ下回るが、愛知県の152社を大きく上回る。売上高でみると10年間に転出した企業の合計は約14兆円だが、転入企業の合計は約3兆5000億円。兵庫、奈良両県では10年連続で転入が上回り、関西圏でも衰退は際立つ。
大阪大大学院の北村亘准教授(行政学)は「橋下氏は仕組みを変えれば課題解決の道筋ができると考え、都構想などに注力してきた。だが制度改革が、府民生活の向上や当初の公約の実現にどうつながるのかはっきりしない」と疑問を呈する。
一方、橋下氏が注力した一部の項目は好転した。府が市町村への補助制度を設けた公立中の給食実施率は、07年5月に約10%だったが、12年末で約26%になった。
ただ、実施率は学校数ベースで、生徒の利用状況にはばらつきがある。大阪、摂津など7市は、各校の調理室で賄う「自校調理方式」でなく、調理・配送を委託した民間業者の弁当を希望者が食べる「デリバリー方式」を導入または予定する。直前の注文変更が難しかったり使い勝手が悪く、実施した吹田市では生徒の利用率は17%と低調だ。欠食がちの生徒への支援にどこまで寄与できるか未知数だ。
住民の転入・転出も外的要因が大きい。10年まで15年連続の転出超過が11、12年と転入超過に転じたが、りそな総合研究所の荒木秀之主席研究員は、11年は東日本大震災で企業が東京一極集中を見直し、12年は関西出身の学生の地元就職志向が強まったためとみる。
悪化項目はないことから北村准教授は「底割れを防いだ」と評価しながら、「府民が改善を実感できる状況とは言い難い。改善しても全国では依然低位の項目が多い」と全体としては厳しくみる。そのうえで「首長は日々の行政サービスや地元での成果に責任を負う。どれくらいの期間でどのような成果を上げるのか、残りの任期中に示す必要がある」と、制度万能論に警鐘を鳴らす。
◇施策実現、見えぬ道筋
橋下氏らが重視する制度改変や規制緩和も、現実には思うようには進んでいない。
看板である都構想とともに特に注力してきたのが、医療や新エネルギー分野の企業誘致を図る「関西イノベーション国際戦略総合特区」だ。その特区での規制緩和策24項目を、大阪府などが11年9月に提案した。
しかし、各省庁の回答はつれない。「引き続き検討していく」「継続して協議してまいりたい」。実現で合意できたのはわずか4項目。15項目が「協議継続」、5項目が「協議終了」と結論付けられた。松井知事は「特区の指定を受けた意味がない」と不満を漏らし、府幹部は自嘲する。「これでは“なんちゃって特区”だ」
特区についても橋下氏は、「大枠を決めるのは国で、細部は地方に委ねるっていう大胆な発想で国のシステムを変えないといけない」と、“制度改革なくして成長なし”との認識を強調した。
政界進出時から橋下氏が制度論に傾注していたわけではない。08年知事選の公約には、乳幼児医療費・不妊治療費助成の拡充▽若い夫婦への家賃補助制度創設−−などの給付型施策が並ぶ。橋下氏に仕えた府幹部は「就任後に府庁改革だけでは限界があると感じていた」と振り返る。「次の一手を考えないといけないですね」。度々そう問いかけられたという。
「収入の範囲で予算を組む」として府の財政再建を当初の旗印にしていた橋下氏はその後、大阪府市を統合してトップを1人にすべきだと訴え始める。11年4月の統一地方選や同年11月の府知事・大阪市長のダブル選で大阪府市を制すると、「地方の自立には法改正するしかない」として、舞台を「日本の統治機構」に広げている。
首相公選制、道州制、地方交付税の廃止と消費税の地方税化……。日本維新は「国のかたち」を変える施策を掲げて衆院選に打って出たが、自民に過半数を奪われ、政界で主導権を発揮できる状況にはない。これらの施策が大阪の再生とどうつながるかも、はっきり示されていない。持論の実現時期も実現後の自治体施策への展開も、不透明感に包まれているのが現状だ。
◇改善状況の基準
改善状況は原則として、府内と全国平均それぞれについて、就任前と最新のデータの変化を比較して判断した。5年間で府が全国平均より0・3ポイント以上改善した場合はA▽0・3未満〜0・1ポイント以上の改善はB▽0・1ポイント未満の改善〜0・1ポイント未満の悪化がC▽0・1以上〜0・3ポイント未満の悪化がD▽0・3ポイント以上の悪化はE−−との基準を設けた。その結果、A4項目▽B3項目▽C17項目▽D、Eはともにゼロ−−だった。
==============
◆橋下氏の大阪府知事、大阪市長の5年間の歩み
−08年−
1月27日 知事選で初当選
2月 6日 知事に就任。「財政非常事態」を宣言
4月11日 「財政再建プログラム試案」を発表
7月31日 大阪(伊丹)空港の廃港検討を表明
8月 5日 WTC(現・府咲洲庁舎)への府庁移転を表明
9月 1日 全国学力テストの市町村別結果公表を府教委に要請
7日 学テ結果公表に絡み「くそ教育委員会」と発言
−09年−
3月24日 府議会がWTCへの府庁移転条例案を否決
26日 国直轄事業負担金を「ぼったくりバー」と批判
9月15日 大阪臨海部へのカジノ誘致構想を表明
10月27日 府議会でWTC購入予算案が成立。府庁移転条例案は2回目の否決
−10年−
1月13日 大阪都構想を打ち出す。実現のため11年の統一地方選に向け、地域政党を設立する考えを表明
4月 1日 府内の私立高校授業料の無償化制度を開始
19日 地域政党「大阪維新の会」を設立。代表に就任
5月23日 大阪維新の初陣となる大阪市議補選で新人当選
−11年−
2月15日 槙尾川ダム(和泉市)の建設中止を決定
4月10日 統一地方選で大阪維新が府議会過半数を獲得。大阪・堺両市議選では第1党に
6月 3日 大阪維新の提案で、教職員に君が代の起立斉唱を義務付ける全国初の条例が府議会で成立
4日 府議会定数を109から88に大幅削減する条例案を維新が強行採決
8月18日 WTCの耐震性を理由に府庁全面移転を断念
10月22日 知事の辞職願を提出し、大阪市長選に出馬表明
11月27日 大阪市長選で平松邦夫氏を破り初当選。知事選では、大阪維新の松井一郎幹事長が初当選
12月19日 大阪市長に就任
−12年−
1月29日 政権公約「維新八策」を策定すると表明
3月24日 衆院選の候補者を選抜する「維新政治塾」開講
5月31日 大飯原発再稼働を「事実上容認」
6月28日 消費税の地方税化を争点に国政進出への決意を表明
7月27日 大阪市の職員政治規制条例が成立
9月12日 国政政党「日本維新の会」結党を宣言
11月17日 石原慎太郎氏率いる太陽の党が維新に合流
11月29日 維新が政権公約発表。自主憲法制定を盛り込む
12月16日 衆院選で維新が54議席を獲得、第3党に
−13年−
1月11日 安倍晋三首相と会談。補正予算に協力姿勢示す
生活がちっとも良くなっていないことは、大阪人なら、ほとんどの人が皮膚感覚で感じています。
とにかく毎日毎日の暮らしがよくなっていないわけです。
学力テスト小学算数・基礎の全国順位があがったといいうのも手放しで喜ぶことはできません。
大阪府教育委員「100マス計算」で著名な陰山英男さんの威信にかけても、これだけは数値をあげなければならなかったのでしょうが、
今の学校なら、一点主義で教師が馬車馬にように遮二無二になって力を注ぐのはある意味非常に想像しやすいことです。
校長から「特命」を受け、それだけに力を入れ「いい」評価をゲットする教員は残念ながら増えているのですから。
そして、高校中退率低下は低下しているように見えるのは、実はここにもからくりがあるのです。
大阪ではなく全国に、教育産業の一環として、留年した生徒を受け入れる「受け皿」としての学校があることをご存じでしょうか。
単位制私立高校のことです。大阪にも数校があります。
つまり「退学」者は減っているが、それは「転学」と言う形態で、入学校を去る高校生が増えているだけで、橋下教育改革の成果など
ではないのです。
しかし、毎日新聞はよく検証していると思います。それはなにより、橋下さんが「吠えて」いることからも明らかなわけです。