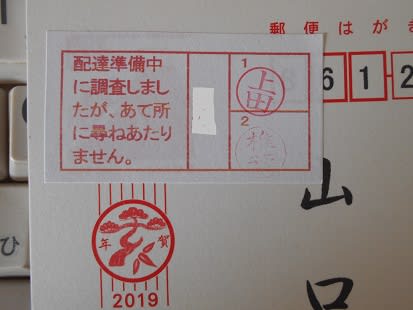わが家の正月のイベントでちょっとした変わり種は、0時を回った途端に屠蘇とお吸い物を頂くというものがある。
何故か知らないが、しきたりの如く祖父母がキッチリ守って続けているのを見て育ったので、私の代でも継承している。
当初は首をかしげていた相方も、やむを得ずイベントを継承したので子供達もわが家の正月はそこから始まると思っている。
あと一つは、相方の作る「のっぺい汁」が殊の外好評で、調子に乗って毎年作るのが恒例になってしまった。
そこからが問題で、今年はその作成担当者だった相方が骨折し、誰あろう私にその仕込み作業から料理までのお鉢が回ってきた。
もちろん年越しソバの、つゆの仕込みも合わせて作業する。
作業の合間にストレッチを入れないと、足腰が固まってしまいそうになる。
今はその作業も一段落し、火を通している最中なので相方が見張りを担当している。
つまり、正月のちょっとしたイベントのために、大晦日は結構忙しいということで、相方の毎年の苦労を体験する貴重な一時を与えて貰ったということだ。

この一年でも反省してみようかと、思いを巡らせてみるがさっぱり反省点を思い出せない。
つまり、なにやら判らぬままに日々を送り、一日が早いのなんのと言いつつも、何らそれらしい事もやってはいないのだ。
確か年の初めに、今年こそはと心に誓ったこともあったのだが、きれいに忘れた振りをしてノータッチだった。
平均寿命からしても、脳や体の活動余命からしても、沢山の時間は残されていない。
除夜の鐘と共に、流してしまってはならない煩悩を一つや二つ残して置くことが生きる励みとなる筈だ。
「菜を洗い肉を刻んで年の瀬の煮炊き指示受く妻は骨折」
この一年、由とするか。

にほんブログ村
何故か知らないが、しきたりの如く祖父母がキッチリ守って続けているのを見て育ったので、私の代でも継承している。
当初は首をかしげていた相方も、やむを得ずイベントを継承したので子供達もわが家の正月はそこから始まると思っている。
あと一つは、相方の作る「のっぺい汁」が殊の外好評で、調子に乗って毎年作るのが恒例になってしまった。
そこからが問題で、今年はその作成担当者だった相方が骨折し、誰あろう私にその仕込み作業から料理までのお鉢が回ってきた。
もちろん年越しソバの、つゆの仕込みも合わせて作業する。
作業の合間にストレッチを入れないと、足腰が固まってしまいそうになる。
今はその作業も一段落し、火を通している最中なので相方が見張りを担当している。
つまり、正月のちょっとしたイベントのために、大晦日は結構忙しいということで、相方の毎年の苦労を体験する貴重な一時を与えて貰ったということだ。

この一年でも反省してみようかと、思いを巡らせてみるがさっぱり反省点を思い出せない。
つまり、なにやら判らぬままに日々を送り、一日が早いのなんのと言いつつも、何らそれらしい事もやってはいないのだ。
確か年の初めに、今年こそはと心に誓ったこともあったのだが、きれいに忘れた振りをしてノータッチだった。
平均寿命からしても、脳や体の活動余命からしても、沢山の時間は残されていない。
除夜の鐘と共に、流してしまってはならない煩悩を一つや二つ残して置くことが生きる励みとなる筈だ。
「菜を洗い肉を刻んで年の瀬の煮炊き指示受く妻は骨折」
この一年、由とするか。
にほんブログ村