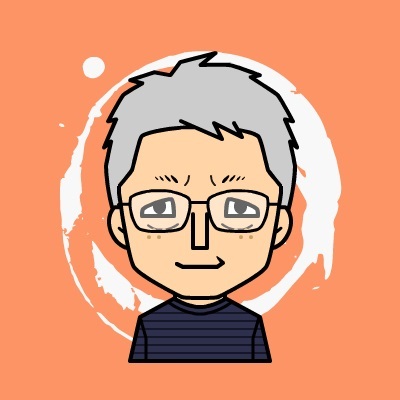昨年の1/15に自宅近辺の熊野街道を、1/24に大阪市内の熊野街道を載せました。
部分だけですが、本日は、和泉市の熊野街道です。
こんなマップがありました。

泉井上神社です。

総社本殿です。
豊臣秀頼が慶長10年(1605年)に建立したもので、重要文化財に指定されているそうです。

説明書きです。
天平宝字元年(757年)河内国から、かつて和泉監のおかれていた大鳥、和泉、日根の三郡が分離して和泉国ができ、その国衙が当地におかれたそうです。
この時その東傍に総社を建立し、大鳥、穴師、聖、積川、日根野の神を祀ったとなるので、古い神社です。
神功皇后が半島より帰還した際に一夜にしてわき出したので、これを瑞兆として霊泉とよび宮を設け、そのほとりに社殿を造営したと伝わると言います。

街道筋の景観です。





井ノ口王子跡です。
熊野詣の道中、熊野の御子神を祀り難行苦行の信仰の道をつなぐために設けられた神社が「熊野九十九王子」で、その1つの跡です。

熊野街道は、ボチボチとつないで歩きたいと思います。
部分だけですが、本日は、和泉市の熊野街道です。
こんなマップがありました。

泉井上神社です。

総社本殿です。
豊臣秀頼が慶長10年(1605年)に建立したもので、重要文化財に指定されているそうです。

説明書きです。
天平宝字元年(757年)河内国から、かつて和泉監のおかれていた大鳥、和泉、日根の三郡が分離して和泉国ができ、その国衙が当地におかれたそうです。
この時その東傍に総社を建立し、大鳥、穴師、聖、積川、日根野の神を祀ったとなるので、古い神社です。
神功皇后が半島より帰還した際に一夜にしてわき出したので、これを瑞兆として霊泉とよび宮を設け、そのほとりに社殿を造営したと伝わると言います。

街道筋の景観です。





井ノ口王子跡です。
熊野詣の道中、熊野の御子神を祀り難行苦行の信仰の道をつなぐために設けられた神社が「熊野九十九王子」で、その1つの跡です。

熊野街道は、ボチボチとつないで歩きたいと思います。