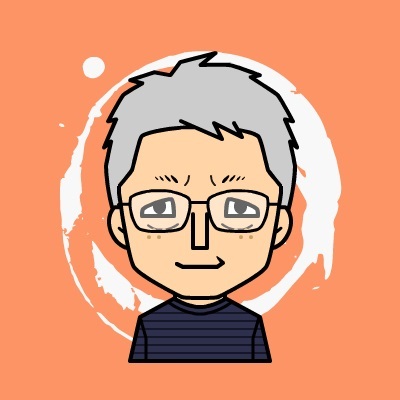NACS-J自然観察指導員講習会が、吹田市自然体験交流センターで行われました。
スタッフとして参加して来ました。
千里北公園です。
蓮間池です。

公園内の紅葉・黄葉です。




研修室です。
ここで講義とかが行われました。

野外実習「森を通して自然のしくみを見にいこう」です。
森の遠景をスケッチしました。

森の中に入って行きます。

森の優先種に気付く観察です。

森の遷移や構造について観察しました。

森を支える土について観察しました。
落ち葉の葉っぱは、めくる度に段々と細かくなります。

土の中には菌糸がはびこり、分解が進みます。

土の中で見つかった生き物も色々いました。

観察した森を、もう一度、振り返りました。

2日目の早朝のオプション観察会です。
ケヤキの種の広がりは、葉っぱによって飛んで行く事です。

針葉樹(ラクウショウ)の落ち葉です。

ラクウショウとメタセコイヤの違いを確認しました。

ススキとセイタカアワダチソウの競争の境界です。

シンジュ(ニワウルシ)です。

ヤマナラシです。

コウヨウザンです。

受講生のミニ観察会のための素材探しです。
今いる場所の水(雨水)の流れを土地の状況から考えてみたり。
色見本と自然の色を合わせてみたり。
ルーペで拡大した世界を見てみたり。
キジバトが猛禽に襲われた場所で、色々と推理したり。
アオツヅラフジの実の中の種を見たり。
植物が、この場所で生息している理由や今後について考えたり。

同じ種類の葉っぱを拾って、柄の長さの順番に並べて、この違いを考えてみたり。

そして、実際の葉っぱの付き方を確認したり。

セイタカアワダチソウの葉っぱの感触から毛の生え方を考えたり。
エノコログサの穂をニギニギして移動させてみたり。
そして、仕上げはミニ観察会の実習を体験させて貰いました。
受講生のミニ観察会の一例です。

自然観察の原点を振り返る事ができて、良かったです。
スタッフとして参加して来ました。
千里北公園です。
蓮間池です。

公園内の紅葉・黄葉です。




研修室です。
ここで講義とかが行われました。

野外実習「森を通して自然のしくみを見にいこう」です。
森の遠景をスケッチしました。

森の中に入って行きます。

森の優先種に気付く観察です。

森の遷移や構造について観察しました。

森を支える土について観察しました。
落ち葉の葉っぱは、めくる度に段々と細かくなります。

土の中には菌糸がはびこり、分解が進みます。

土の中で見つかった生き物も色々いました。

観察した森を、もう一度、振り返りました。

2日目の早朝のオプション観察会です。
ケヤキの種の広がりは、葉っぱによって飛んで行く事です。

針葉樹(ラクウショウ)の落ち葉です。

ラクウショウとメタセコイヤの違いを確認しました。

ススキとセイタカアワダチソウの競争の境界です。

シンジュ(ニワウルシ)です。

ヤマナラシです。

コウヨウザンです。

受講生のミニ観察会のための素材探しです。
今いる場所の水(雨水)の流れを土地の状況から考えてみたり。
色見本と自然の色を合わせてみたり。
ルーペで拡大した世界を見てみたり。
キジバトが猛禽に襲われた場所で、色々と推理したり。
アオツヅラフジの実の中の種を見たり。
植物が、この場所で生息している理由や今後について考えたり。

同じ種類の葉っぱを拾って、柄の長さの順番に並べて、この違いを考えてみたり。

そして、実際の葉っぱの付き方を確認したり。

セイタカアワダチソウの葉っぱの感触から毛の生え方を考えたり。
エノコログサの穂をニギニギして移動させてみたり。
そして、仕上げはミニ観察会の実習を体験させて貰いました。
受講生のミニ観察会の一例です。

自然観察の原点を振り返る事ができて、良かったです。