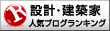建築は祭事とイロイロ・・・深く関係するものがありますが、
地鎮祭以後の一つの節目となる時期に、行うもの・・・・・・・上棟式。
明日・・・・12月6日は(仮称)借景を楽しむ和モダンの玄関共有二世帯住宅新築工事の祝上棟日。
上棟式(棟上げ)は、平安時代初期から行なわれ、
中世に盛んとなり、居礎(いしずえ)、事始め、
手斧始め(ちょうなはじめ)、立柱、上棟、軒づけ、棟つつみ等、完成まで の建築儀式が数多くありましたが、
江戸時代になってこれらの建築儀式を代表する形で、「上棟」式だけが行なわれるようになりました。
歴史のあるもの・・・・・・。
このように昔は建築儀式がたくさんありましたが、
時代の変化とともに儀式(上棟式)も変わりつつあります。
一般的に上棟式は、
新築の家の土台が出来上がり、柱、梁、桁、力板などの「骨組み」が完成したあと
棟木というものを 取り付けて補強する際に行ないます。
このように上棟式は建築工事の途中で行う儀式で、
工事の方法にもよりますが、
木造の一般的に行われている木造軸組工法という工事の仕方では、
棟木を棟に上げる時に・・・・・・・鉄骨造では鉄骨工事が完了したとき、
鉄筋コンクリート造では躯体コンクリートの打ち込みが終了したころに行います。
また上棟式(棟上げ)では、
魔よけのための御幣(ごへい)を鬼門に向けて立てて、
四隅の柱に酒や塩、米などをまき、天地四方の神を拝みます。
上記の内容を略式で行う事が多いです・・・・・・・・地域によっては、
餅やお金(硬貨)をまくところもあり・・・・本当にイロイロ。
同時に棟札に上棟年月日、建築主などを書き、
後日・・・・・工事を行う棟梁が一番高い棟木に取り付けなどを行います。
この取り付け方も風土や工務店によっても様々・・・・・。
本来、上棟式(「棟上げ)とは、
無事棟が上がったことを喜び、感謝、祈願する儀式ですが、
現在の上棟式は「儀式」というよりも施主・住まい手さん・クライアントと呼ばれる人達が、
職人さんや関係者をもてなす「お祝い」の意味が
強くなっていて、「地鎮祭」や「上棟式」を略式でされる方が多くなっています。
上棟式は地鎮祭と違って神主さんに来て頂くことが少ないため
(地域によっても異なりますよ。)現場監督や棟梁等が式を進めることがほとんどです。
明日はそういうお祝いと感謝のとき・・・・・。
今回も、地元吉野・・・・美吉野醸造株式会社の清酒・花巴を用意。
美吉野醸造株式会社 ホームページ
美吉野醸造株式会社の杜氏であるH本さんに、
清酒・・・花巴を吉野のアトリエへ届けていただきました・・・・・。
ご縁があって・・・・イロイロお願いしています。
午前中は別件で出張ですが、
明日は午後から(仮称)借景を楽しむ和モダンの玄関共有二世帯住宅新築工事の現場で、
素敵な時間を「住まい手さん」・「造り手の皆さん」と共に過ごさせていただきますよ・・・・。
団らんをしたり寛いだり・・・・・暮らしのスペースはイロイロ。
部屋名もイロイロありますよね。
実際計画する際は「大きさ等」は別にして・・・・・「部屋」を考えたりします・・・・・。
一つの枠組みとして。
でも・・・・・住まいづくりのスペースの考え方はイロイロです。
こういう部屋だからこういう部屋名だからこうだという住まい方ではなくて、
自由な発想でイイと思うんです。
例えばですが、洗面所は歯磨きや洗顔、
化粧などパウダールームとして・・・・・・。
浴室の隣にあれば、裸になって濡れた身体を拭く脱衣室として、
洗濯機が置いてあれば家事室としての役割があります。
洗面所は浴室やキッチンに比べて、1坪分のスペースで当たり前、
水まわりだから南側や東側・・・便利な部分以外に・・・・・と言う具合に、
簡単に・・・そして後回しにされることも多いのですが、
実際の事を考えると、
家族全員が毎日必ず多目的に使う場所ですから、
小さな工夫が家族全員の暮らしに大きく関係してくる場所でもあったりします。
暮らしに寄り添うように、使う上で不自由にならないようにするポイントは、
化粧品や歯ブラシ、ヘアスプレーなどの小物の収納にあります。
細かいアイテムを片付けしやすいように引き出しを活用したり、
奥行きの薄い収納スペースを確保したり、スペースそのものの見直しや動線の工夫など。
壁の厚みを利用した壁埋め込み収納も便利ですし、少し前に計画し
実際にリノベーションを施した住まい・・・・・玄関共有二世帯住宅で実施させていただいた内容だと、
暮らしに合わせて「洗面スペース」と「脱衣スペース」・「洗濯スペース」を分断・・・・切り離し、
本質を考えて「レイアウト」をした例などもありますよ・・・・二世帯住宅としての
二階全体のリノベーションですから。
単世帯住宅を玄関共有の一階親世帯・二階子世帯の為の分離型二世帯へのリフォーム
脱衣のスペースとして考えると、
寒い冬でも暖かくいられるような暖房設備を使えるような工夫・・・・。
水に強い床材や壁材を選んでおくことも大切です。
ガスコンセントをつけておけば、
給油の手間がなく素早く温風が出てくるガスファンヒーターを使うこともできます。
スペースや収納との関係を見直して計画することは必要ですけどね・・・・・・。
洗濯機置き場にしてある場合は、
ストックする場合の洗剤などを入れておく収納を確保し、
洗濯ものの干し場との連携も確認することが大事ですよね。
物事の本質をキチンと考える事で見えてくる住まいの「プラン」がありますよね。
枠にとらわれすぎない計画で「暮らしを豊かに」することができますよ。
風が冷たい日ですが、段々そんな時期であるので「気忙しさ」が目立ってきますね。
冷たい風の中、今日は朝から工務店さんとそのチームの皆さんが住まいの棟上げの準備で、
ガンバってくださっています・・・・・朝からお礼だけさせていただいて、スグに現場を後に。
その様子は夜のブログで紹介させていただこうかと思います。
現場に立ち寄った後には奈良K市役所の関係窓口へ・・・・。
別案件での計画での下調べ・・・・準備のための「調査」です。
住まい手さんからご依頼をいただき、
イロイロ「本当に計画が可能な土地なのか」を先ず・・・・調べに・・・・。
よくある話しですが、ご自身の土地・・または親・・・身内の土地だし、「家」だから、
自由に建てることが出来ると考えている方もいらっしゃいますが、
実はそうではなくて・・・・法治国家で当たり前のことですが、
「法津」が関係してきますので、その「中身」の確認・・・・・・。
耳にした事があるかもしれませんが、「建築基準法」や「都市計画法」などといった
法律の枠の中で・・・制約の枠の中で、「建築」をつくりだしているんですよ・・・・。
だから「そのカタチ」や「規模」・・・「建物の位置」・・・・大きな部分から、
「窓」や「部屋の大きさ」・・・「屋根の形」といった部分に仕上げなど・・・地域や
敷地の形も道路も連動してその制約の枠の中に組み込まれて・・・・制限されているんですよ。
その大体の枠組を「リサーチ」・・・・・。
建物の高さや屋根の位置・・・ボリュームを検討する際にも敷地に対して何パーセントまで
建てることができるのか・・・・・。
調査の内容はそういう「現地」では見えない法律の問題と勿論「インフラ」も含めて・・・・・。
まずは「情報整理」。
計画の出発地点ですから、ここで提出すべき「書類」の種類や量も変わってくるのです。
書類の流れや種類・・・・・・量などでも「着工可能となる時期」は変わるので、
「キチンと調べる事」は「キチンと工事のための工程を組むこと」にもつながりますよ・・・・・。
K市特有の文化財包蔵の「大藤原京遺跡」の地域にも含まれていたので、
発掘届け出も4部必要ですし・・・・。
市街地でもそういうのは・・・ありますからね。
物理的に可能なスケジュールを計算しながら頭に入れて考える仕事も同時進行ですよ・・・・・。
どちらを優先すべきかも・・・キチンと考えて。