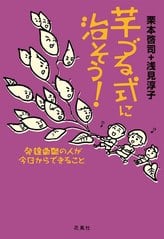先日、届いた宅急便の荷物の中に、
季節外れではありますが、小さめの島バナナが荷物の中に入っていました。
小さいので、ちゃんと熟すかなぁ、と思いながらも、
我が家のいちばん陽の当たる、あたたかい窓辺に置いていました。
今日は、だいぶ色も付き、黄色くなっていたので、
ひとつ食べてみましたが、もうちょっと、渋さと芯のかたさがありました。
大きさも小さいので、芯はどうしようもないのか?
もうちょっと置いたら、おいしくなるか?
もうしばらく、バナナの観察です。
このところ、来週末の講演会に向けて、
こよりさんの本を精読熟読、読み直しています。

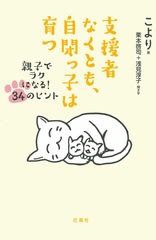
何度、読み返しても再発見があり、
読んだその時その時の色とりどりの線でカラフルな中身になっています。
そして、読みながら思うのは、
子どもが困らないようにすることは、親のエゴではなくて愛だなぁ、ということです。
ある場所で、一見、仲良く遊んでいる子どもたちがいます。
私は、その場所では一参加者でしかないので、何か言うことはないのですが、
凸凹っ子に理不尽な目に合い、助けを求めてくる子に、
「嫌なら、ちゃんと嫌だ!って強く言えることも大事よ。」と言っています。
一方、凸凹っ子のほうは、保護者さんはいるのか、いないか、わかりませんが放置状態。
何事か感じるのか、その凸凹っ子は、決して、私の近くに来ません。
ああ、この凸凹っ子の保護者さんに、こよりさんの本を講演会をお勧めしたいなぁ、と、
その子が走り回る姿を見るたびに、思います。
でも、こよりさんの本を読んだ方で、
「私には、こんなことはできない」と早々に白旗をあげた方もいらっしゃいます。
こよりさんがお子さんにしていたことは、
専門知識がいることでもなく、特別な道具がいることでもなく、
ましてや、誰かに教えてもらって資格をとらなくてはしてはやってはいけないことでもありません。
また、こよりさんが子どもさんにしてきたことは、
お子さんの個性を殺すようなことを強制してさせていたのではなく、
お子さんが社会の中で生きるために必要なこと、
親なき後にも、自分で生きていくために必要なことだと思います。
こよりさんのお子さんも
どこのお子さんでも経験するかもしれない試練もあり、大変な時期もあったのだろうなぁ、と
本を読むと感じましたし、何事もなく、すくすく育ったというわけではないと思います。
ただ、こよりさんのことだから、どんなときも悲観も楽観もせず淡々と、
すべきことをし、できることをし、日々を暮らしておられたのだろうなぁ、と
ブログや本を読んで私は感じています。
そして、どんなときにもこよりさんの本から感じるのは、
この子がちゃんと社会の中で生きていけるように!という、
お子さんへの慈しみです。
世の中には、子どもに凸凹があっても、それは個性だし、
私にだって凸凹はあるし、それも含めて子どもも私も愛おしいという人もいます。
でも、そこで立ち止まって、
自分や子どもをいい子、いい子とすることが、
果たして、子への愛なのか、なんなのか、私には全く理解できないなぁ、と思います。
今度の講演会では、
親自身が、子どもの未来を消化試合のようにしてしまわないように、
そんなことも考えて欲しいなぁ、本を読みながら思うことでした。
季節外れではありますが、小さめの島バナナが荷物の中に入っていました。
小さいので、ちゃんと熟すかなぁ、と思いながらも、
我が家のいちばん陽の当たる、あたたかい窓辺に置いていました。
今日は、だいぶ色も付き、黄色くなっていたので、
ひとつ食べてみましたが、もうちょっと、渋さと芯のかたさがありました。
大きさも小さいので、芯はどうしようもないのか?
もうちょっと置いたら、おいしくなるか?
もうしばらく、バナナの観察です。
このところ、来週末の講演会に向けて、
こよりさんの本を精読熟読、読み直しています。

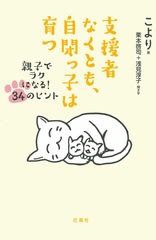
何度、読み返しても再発見があり、
読んだその時その時の色とりどりの線でカラフルな中身になっています。
そして、読みながら思うのは、
子どもが困らないようにすることは、親のエゴではなくて愛だなぁ、ということです。
ある場所で、一見、仲良く遊んでいる子どもたちがいます。
私は、その場所では一参加者でしかないので、何か言うことはないのですが、
凸凹っ子に理不尽な目に合い、助けを求めてくる子に、
「嫌なら、ちゃんと嫌だ!って強く言えることも大事よ。」と言っています。
一方、凸凹っ子のほうは、保護者さんはいるのか、いないか、わかりませんが放置状態。
何事か感じるのか、その凸凹っ子は、決して、私の近くに来ません。
ああ、この凸凹っ子の保護者さんに、こよりさんの本を講演会をお勧めしたいなぁ、と、
その子が走り回る姿を見るたびに、思います。
でも、こよりさんの本を読んだ方で、
「私には、こんなことはできない」と早々に白旗をあげた方もいらっしゃいます。
こよりさんがお子さんにしていたことは、
専門知識がいることでもなく、特別な道具がいることでもなく、
ましてや、誰かに教えてもらって資格をとらなくてはしてはやってはいけないことでもありません。
また、こよりさんが子どもさんにしてきたことは、
お子さんの個性を殺すようなことを強制してさせていたのではなく、
お子さんが社会の中で生きるために必要なこと、
親なき後にも、自分で生きていくために必要なことだと思います。
こよりさんのお子さんも
どこのお子さんでも経験するかもしれない試練もあり、大変な時期もあったのだろうなぁ、と
本を読むと感じましたし、何事もなく、すくすく育ったというわけではないと思います。
ただ、こよりさんのことだから、どんなときも悲観も楽観もせず淡々と、
すべきことをし、できることをし、日々を暮らしておられたのだろうなぁ、と
ブログや本を読んで私は感じています。
そして、どんなときにもこよりさんの本から感じるのは、
この子がちゃんと社会の中で生きていけるように!という、
お子さんへの慈しみです。
世の中には、子どもに凸凹があっても、それは個性だし、
私にだって凸凹はあるし、それも含めて子どもも私も愛おしいという人もいます。
でも、そこで立ち止まって、
自分や子どもをいい子、いい子とすることが、
果たして、子への愛なのか、なんなのか、私には全く理解できないなぁ、と思います。
今度の講演会では、
親自身が、子どもの未来を消化試合のようにしてしまわないように、
そんなことも考えて欲しいなぁ、本を読みながら思うことでした。