
蕪村は京都に来てから、転々と居を変えていたが、晩年になって仏光寺烏丸西入ルに落ち着く。仏光寺通りから南に入った路地の奥で、そこには地蔵が祭られていたという。蕪村は仏光寺通りの長屋住まいで、いろいろ苦労したようである。
以下2句はいずれも蕪村の生活感が出ている。
我を厭う隣家寒夜に鍋を鳴す(自筆句帳984)安永4年
これには鳴鍋弁というタイトルがついた長い後書きが添えてある。
比句の意は漢ノ高祖は沛と云所の人にて甚貧しくおはしけるに、嫂の方へふと行かれけるに、折しも何やらあつものを煮て居たりけるが、劉邦に喰う事を惜しみて、杓子で鍋の底を鳴らし、最早何もないと云うことをしらせて劉邦に喰せざりける故事也。
しかし考えてみると、長屋の隣の亭主やカミさんが、劉邦の貧窮時代の苦労話を知っていて夜中に鍋を鳴らすわけがない。蕪村家族への単なる嫌がらせで騒音を立てているのだ。現代でも、神経の少しいおかしいこのような迷惑住民がたまにアパートにいて問題になる。ともかく「我を嫌う」仲の悪い隣人の日常的ないやがらせなのである。蕪村の後書きは、それを踏まえた上での一種の諧謔である。
かはもりやむかいの女房こちを見る(自筆句帳298)
蕪村のすむ長屋の天井裏にはアブラコウモリがたくさん住み着いていた。これはアブラムシと呼ばれ、天井を汚す気味の悪い飛翔動物として人々は嫌っていた。蒸し暑い夏の夕方、このアブラムシが蕪村の屋根の隙間からバタバタ飛び出していく様を鬱陶しくみつめる向いのカミサンと目があった。なんとも気まずい雰囲気がただよう。尾形功の校注(『蕪村全集:発句』)は、目があったのを艶情としてとらえているが、これはおかしな誤った解釈である。
高井几董(1741-89)への蕪村の手紙に、京都人への悪口が露骨に書かれている。
何かに付け京師之心、日本第一之悪性にて候。日頃は左も不存候所、俳諧をはじめ候て後、つくづくと思い合候事共多御座候。凡日本過半は行暦いたし、人心之善悪も掌をさすごとくあきらめ居申候
(「何かにつけて京都の人間の心は日本一の性悪である。日頃はそうも思わないが、ここで俳諧をはじめて、つくづくとそれに思いあたることが多い。私は日本全国を歩き回り、人の心の善悪が掌をさすように分かっている」)
門人の中で若い几董ばかりを、蕪村が依怙贔屓するという陰口を伝え聞いて頭に来て書いた手紙である。蕪村は苦労人で、あまり人の悪口を云わない自制的な人だったが、たまに怒ると迫力がある。他国から京都に来て長年すんでいると、蕪村の気持ちがよくわかる気がする。京都人の裏表の違いがはっきりしているのには驚かされることが多い。
追記 (2020/08/13)
井上泰至 『<悪口>の文学、文学者の<悪口>』には蕪村以外にも、芭蕉や一茶の「悪口」も載せられている。ただ芭蕉のは、すこしハメをはずした路通にたいする師匠の揶揄だし、一茶のは相続問題で揉めている弟の批判である。

















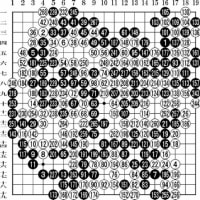








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます