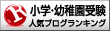今日は、まさに、さわやかな「五月晴れ」
娘の大好きなエクスカーションの日です
ニッコニコ で出かけていきました。
で出かけていきました。
行き先の公園では、今ハマっている「ドロケイ」をやるんだとか…
何のことはない…
「泥棒と警察」のことらしい
早い話が「おにごっこ」です
娘はほぼ毎朝、登校して着替えるや否や「ドロケイ」をやっているそうです。
しかも、ほとんどが「男子」
今日も「ドロケイ」にイノチをかける娘
By the way…
昨日、年長の受験生のママからちょっとした質問があったので、今日は国語について少し書いてみたいと思います。
開智学園総合部のペーパー入試内容に「言語の運用」というのがあります。
その中で、ここ2年ほど出題されているのが、言葉の「音数」です。
例えば… 上に「すいか」の絵が描いてありますね。
上に「すいか」の絵が描いてありますね。
すいかは3つの文字の言葉です。
今からこの「す・い・か」と同じように名前が3つの文字のものを下の絵から選んで、○をつけてください。
○はいくつつけても構いません。
(20年度ペーパーA)
小学受験においては、基本的に文字が「読めない」「書けない」が大前提なので、もちろん「すいか」と書かせたりはしません
では、このような問題についてどう指導するかと言うと…
まずは、子どもたちに「す・い・か」と発音させながら、同時に「パン・パン・パン」と手を叩かせるようにします
そして3つの音からできている言葉である、ということを理解させます
もちろん、入試の時は手は叩けませんから、手を叩いているつもりになって心の中で言葉を言いながら指を折らせるようにします
さて、その時に問題になるのが「拗音」「促音」「撥音」「長音」です。
「拗音」(ようおん)
=「きゃ」「きゅ」「きょ」などのように、小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」を含む音。
「促音」(そくおん)
=「きって」などの小さい「っ」。「つまる音」とも言う。
「撥音」(はつおん)
=「さんま」などの「ん」。「はねる音」とも言う。
「長音」(ちょうおん)
=「スキー」などの「ー」。「のばす音」とも言う。
ちなみに…
「清音」(せいおん)
=「は」「ひ」「ふ」「へ」「ほ」のように、濁らない音。
「濁音」(だくおん)
=「ば」「び」「ぶ」「べ」「ぼ」のように、「゛=濁点」がつく音。濁る音。
「半濁音」(はんだくおん)
=「ぱ」「ぴ」「ぷ」「ぺ」「ぽ」のように「゜=半濁音符」がつく音。
です。
いわゆる「五十音図」は、「音」(おん)というよりは「かな文字」の「図」と言うべきでしょう。
「音」(おん)の図だったら、「拗音」や「濁音」「半濁音」も含むべきだと思います。
最近はそういう教科書や参考書もありますね。
それから、意外に知られていないのが、「ひらがな」に「長音」はない、ということ
例えば、「スキー」をひらがなで書くと「すきい」であって「すきー」ではありません。
「カタカナ」未習段階では外来語もひらがな表記をし、「わたしはすきいに行きました。」と書くのです。
この場合、「ー」の部分は、直前の文字に影響されるため、「スケート」は「すけえと」、「カーネーション」は「かあねえしょん」、「トースター」は「とおすたあ」となります。
もちろんカタカナを習ったあとでは、外来語はカタカナ表記が基本ですが…
話が逸れましたので、本題に戻しましょう。
先ほどの「拗音」「促音」「撥音」「長音」ですが… 「拗音」は、小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」も含めた全体で「1音」と数えます
「拗音」は、小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」も含めた全体で「1音」と数えます
例えば、「きゅうり」は文字数だけ見ると「4文字」ですが、「きゅ・う・り」の3音の言葉です。
手を「パン・パン・パン」 と叩きながら「きゅ・う・り」と言ってみましょう。
と叩きながら「きゅ・う・り」と言ってみましょう。
「いちょう」も3音、「ひょうたん」は4音ですね。
ちなみに、光村図書1年生の教科書では「おもちやとおもちゃ」という単元で、「拗音」は1音と数えない、ということを学習します。
「でんしゃ」=3音
「じゃんけん」=4音
「あくしゅ」=3音
「しょっき」=3音
「としょしつ」=4音
「きょうしつ」=4音
一方、 「促音」「撥音」「長音」は、全て「1音」と数えます
「促音」「撥音」「長音」は、全て「1音」と数えます
例えば…
「促音」を含む言葉=「きって」は3音です。
もし2音だったら「きて」となってしまいます
ところが、子どもは「きって」と言いながら「パン・パン」と2回しか叩かない子が多いので 繰り返し練習させます。
繰り返し練習させます。
光村では前述の「しょっき」=3音として出てきます。
「撥音」を含む言葉=「さんま」が3音というのは、比較的わかりやすいですね
光村では「でんしゃ」=3音、「じゃんけん」=4音。
また、「長音」を含む言葉=「スキー」の「ー」は、先ほど説明したようにひらがな表記してみるとちゃんとした1音となるわけですから、やはり「スキー」は3音となるのです。
私が子どもの頃は、そこに階段があれば必ず「グ・リ・コ」の遊びをやったものです
最近の子どもたちは階段で遊ぶと怒られるのか、あまり見かけませんけどね
ジャンケンをして「グー」で勝ったら「グ・リ・コ」で3段、パーで勝ったら「パ・イ・ナ・ツ(小さい「ッ」ではありません)プ・ル」で6段、チョキで勝ったら「チ・ヨ(これも小さい「ょ」ではない)コ・レ・イ・ト」で6段ずつ階段を上がれます
そして、誰が一番先にゴール するか、という単純なゲーム
するか、という単純なゲーム
上まで行ったらまた下に引き返してきて、1番最初の地点に早く到達した者が、勝ち
今考えると、「グリコ」と「パイナツプル」の音数はあっているけど、「チヨコレイト」は本当は5音だったのよね~
1段でも多く跳びたかったんでしょうね~
しかも、「ちよこれいと」ではなくてひらがな表記上では「ちよこれえと」が正しいし
さて、開智の入試問題に戻りますが…
以上のことを踏まえてみると、開智の問題はちょっとばかり誤解を招きやすい問題ですね。
厳密には「文字」と言わないで、「おと(おん)のかず」と言って欲しいと思います。 すいかは3つのおとでできている言葉です。
すいかは3つのおとでできている言葉です。
今からこの「す・い・か」と同じように名前が3つのおとでできているのものを下の絵から選んで、○をつけてください。
…というように。
まぁ、実際はあまり難しい言葉は今まで出ていませんが…
「ひらがな」を中途半端にかじってしまっている子どもたちほど「音(おん)数」と「文字数」を混同しがちなので、私も注意して指導しています
さて、開智の「ペーパーA」
入試変革の今年は、何が出題されるのでしょう