安住の地建設
「日本人が、いずれかの日に、祖国を脱出しなければならなくなる日が来るかもしれない。その時に、どこに安住の地を求めるのか。そういうシミュレーションを、ずっと私はしてきました。それは、災害かもしれないし、何らかの国難かもしれません。第一次世界大戦と第二次世界大戦を現地で経験し、何が起こってもおかしくない世界の中で、幸運に支えられて今まで生き延びてきた自分が、経験の中から考え続けてきたことです。」
真剣な面持ちで晃が語りだした。
「第二次世界大戦が終わってから、アメリカ、モロッコ、エチオピア、ケニア、タンザニア、ブラジル、パラグアイ、アルゼンチンなどを見て周り、最終的に選び出したのがニューギニアでした。もし、政治的に話がつけばですが、この地以外にないという結論にいたったのです。」
それは、どこまでが本当で、どこからが夢物語か分からないような話だった。
「いくつか理由があるのですが、日本から比較的近距離にあること、熱帯・温帯・寒帯を有する唯一の未開地であること、などがあげられますが、最大の理由は、第一次世界大戦当時、私はこの地にいて、オランダの植民地政策を見てきたからです。オランダは、瓜哇(ジャワ)、スマトラ、ボルネオ、セレベス、ニューギニアの資源開発を行っていました。当時、私は三井物産から派遣されていて、茶、コーヒー、砂糖をはじめ、熱帯植物の栽培に関するオランダ語の書物の翻訳をし、日本人に可能な農業の研究をしていました。」
この夢物語を実践するために、晃は実際に可能性の検討を行っている。おそらく膨大な資金を必要とするので、日本からの投資だけではだめだろうと思い、オランダ人、ユダヤ人、華僑、台湾人などに会って、投資の可能性を打診している。また、香港、ニュージーランド、オーストラリア、パプアニューギニア、フィリピンなどの視察も行った。
「もし、99年くらいの期間で借地が可能なら、ちょうど南米のコスタリカのような国を作ることが可能かもしれません。この国は、1949年に常備軍の廃止を憲法で決めています。兵隊と勲章を持たないで、島内の秩序を維持していくこと。すべての住民に対して平等であること、外資に門戸を開放すること、宗教的な軋轢を避けること、そんな理想郷を作りたいと思います。」
こう語る晃の眼は輝いていた。結局、彼の夢は実現されなかったが、極東という世界の東の果てに位置する日本の未来を考えるとき、このような理想郷の追求はありえる選択かもしれない。というのは、人類の繁栄は、さまざまな形の地球資源の食いつぶしにかかっているからである。資源のない国の未来は、先細ることを晃はよく見抜いていた。
つづく











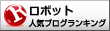

 Michio Kumagai @KumasanHakken
Michio Kumagai @KumasanHakken





