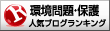森村誠一の著作に「ミッドウェイ」がある。
1942年6月5日から7日にかけての日米海戦が主題だ。
この戦いで、日本は「赤城」・「加賀」・「蒼龍」・「飛龍」の航空母艦4と、重巡洋艦1、重巡洋艦1大破、駆逐艦1中破、戦死者3,057名を失った。
敗戦の理由は、運の悪さと、レーダーや暗号解析の相違も指摘されている。
ただ、私は、日本人は戦争に向いていないのだと思う。
森村はこう書いている。
***
戦場では人間性も非人間性もむき出しにされる。
敵を殺さなければ自分が殺されるという絶対的な戦いの構図の枠の中で、自分一人が生き残るためには戦友をも見捨てなければならないという場面も展開する。
友を見捨てるにしのびず共に死んで行った者もいれば、生き残る意志の下に友を見捨てた者もあるだろう。
生者死者いずれにしても同じ地獄を覗いた。
死んだ者は永久に語らず生き残った者は口を閉ざした。
***
日本民族というのはもともと、弾圧や戦争から逃れてきた人々によって構成されている。
だから決して「果断に」なることはできない。
それを慢心とか軟弱とかと批判することは適切ではない気がする。
奇妙な展開だが、「ミッドウェイ」の中で、森村は立原道造の詩を取り上げている。
なぜに立原を?
24歳という若さで夭逝した稀有な詩人だ。
東京帝国大学工学部建築学科卒業というから、異色でもある。
***
悲劇のやうに思ってはいけない。
これは何でもないことなのだから。
ラムダは山の頂にくらしはじめた。
それはラムダが、人がうつくしい水に身投げするやうに、天に身投げしたかったからだ。
人は死ぬるとき明るい青い海で日が底までまっすぐにさす海を欲しがるものだ。
だがラムダは天を欲しがった。
彼が白や黄の雲の間に浮んで、それから手や足が溶けてゆくのはどんなにしづかであらう。
人は海に沈むとき、きれいに光る白いあぶくをたてて行く。
海では魚は溶けない。
天でラムダは死にたかった。
***
こんな詩を紡ぎだす人々に、戦争なんかできっこない。
ないものねだりをしないで、戦争は放棄しておく方がよい。
それより、どうやったら戦争をしないで生き延びれるかを真剣に考えた方がよい。