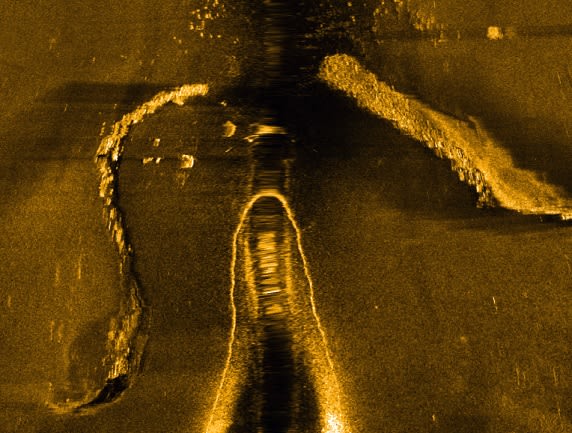京都大学経済学部の川北英隆教授は、1970年京大入学の同期だ。
昔、同じ山の同好会に所属していた。
登山のためにニッセイ基礎研究所を退職したつわものである。
彼に関する面白い記事を見つけたので紹介する。
全文は、日経電子版を見てほしい。
******
消費税率が上がっても経済が冷え込まないためには、企業の収益改善が賃金上げにつながる必要がある。
賃金上昇を測るために注目しているのは、国内製造業の付加価値率と労働分配率だ。
付加価値率とは、営業利益、人件費、減価償却の合計が売上高に占める割合だ。
付加価値率は、95年ごろから低下傾向にある。
円高の時期だけでなく06~07年ごろの円安の時期でも下がっている。
付加価値率の低下が示すのは、日本の製造業の国際的な競争力の低下だ。
付加価値を削り価格を下げないと、海外はもちろん、国内でも製品が売れなくなった。
デフレの根本的要因も、この競争力と製品価格の低下にある。
企業は、90年代後半から米国と同様に人件費を削減して付加価値の分配を変えた。
労働分配率も低下傾向にある。
人件費の削減は短期的には企業業績を上向かせるが、それを長期間繰り返すことで消費が収縮して、高いものが売れない、値上げが通らないといった状況を生んだ。
この悪循環がデフレを深刻にした。
人件費の削減圧力が今後も続くと非常に良くない。
そこに、消費税の引き上げが加わってしまうと、消費がいっそう収縮して、株価の足を引っ張ることになりかねない。
**************
素人ながらそうだと思う。
わかりやすい論理だ。
最近アメリカ型大店舗が増えたことによって、製品価格は低下している。
従来の小売りは軒並み倒産した。
特に、地方がひどい。
規制緩和を行うことが裏目に出ているのかもしれない。
為替や株価で得た資金は、当然、逆の場合も想定しなければならない。
賃金が上がったとしても、恒常的になるとは思われない。
そこが大きなジレンマだろう。
生産を上げ、売り上げを伸ばさない限り、見通しは暗い。
では何を作り、何を売るのか。
日本にしかないもの、日本人にしかできないものに夢を託したい気がする。
画期的な発明の多くは、既存の技術から生まれてきていることを役人は学習すべきだ。












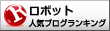


 Michio Kumagai @KumasanHakken
Michio Kumagai @KumasanHakken