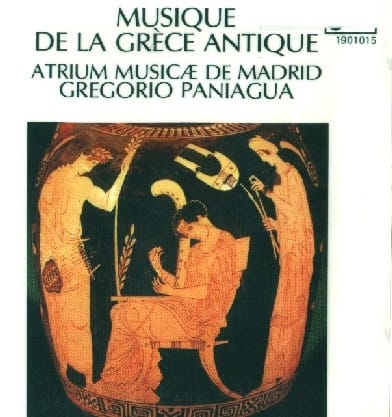1975年3月の、カール・ベーム&ウイーンフィル来日公演のDVDを頂いたので、さっそく観てみました。反日のNHK版なので君が代演奏はカットされていましたが、ベームがアンコールの終りに聴衆に向けた「イツマデモ…」のシーンは入っていました。僕が録音したFMでも、ヨハン・シュトラウスの常動曲の終りに聞こえていた言葉です。
カール・ベームは、拍手が鳴り止まない日本の聴衆に感激して、次回の来日を約束した熱い魂の人です。彼が若かった時代の、音楽で討論を戦わした熱情を日本に見たようです。今の日本の、戦うことを避ける、飼い慣らされた犬のような集団にはガッカリするかもしれませんね。
1975年3月と言えば、僕が芸大2年の時で、芸大寮が建て替えられている最中かもしれません。僕は、夏のアルバイトでFMチューナーを買い、アンプやスピーカー等をローンで揃えていました。それで、この公演のライブ放送や再放送などを、必死にカセットに録音したものです。そのテープの最後に再アンコールの常動曲が入っており、ベームの言葉がちゃんと録音されていたのです。このテープは失ってしまいましたが。
ベームは、常動曲という何時までも続く曲を選び、自分のメッセージを日本に残したのです。いつまでもこのようでありたいと願うベームは、実に多くのものを遺してくれました。照明や指揮台に注文をつけるリハーサルや、あるいは神社で手を洗ったり、あるいは日本のファンから花束を受け取るシーン一つでも、本当に観る価値があります。今から思えば、本当に奇跡的な出来事でした。
当時の日本は、モナリザが上野で公開されたり、ベームが来日したり、僕にとっては貴重な時間の連続でした。カセットテープがステレオ化され、オーディオに使える音質を獲得したのもこの時代です。しかし、DVD(音はFMのものを映像に重ね)ではテープヒスノイズをカットしているために、肝心のトライアングルの音までもカットされています。NHKには「死ね」と言いたいですね。
ワーグナーのニュルンベルクのマイスタージンガーは、このトライアングルの連打が花なのですが、見事にカットされているので、せっかくのヤマハのトゥイーターが泣いています。トライアングルを美しく再生できるのがヤマハJA0506なのです。送ってくれた読者はLPも届けてくれるそうなので、そちらに期待してみます。
カール・ベームは法律の学校を出た異色の経歴ですが、音符やパートを吟味して、一つ一つに丹念な意味付け(必然性)を与えています。流して美しく聴かすという手法は取らないので、聴けば聴くほど深みが理解できてきます。ブラームスの交響曲第1番は、楽譜とにらめっこしながら毎日のように聴いていますが、それでも飽きることはありません。
少し前に、N響を振った、ネヴィル・マリナーのブラームス交響曲第1番を放送していましたが、途中で録画をやめました。聴くに耐えなかったからですが、ベームがレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画なら、マリナーはモノクロ写真のような感じです。神秘も深みもない、ナルシシストの自己満足でしたね。
黄金の時代のベームやカラヤンを理解するには、当時に頂点を究めた日本のFETアンプの相性が良いと思います。僕のミカエル型のバックロードホーンは、そういう意味でも、僕が35年も追い続けた音かもしれませんね。ということで、板取(910×1820 12ミリ厚合板)と音道の見取り図をアップしました。板取図には書いてありませんが、僕は側板に13ミリ厚の桐の集成材(910ミリ×350ミリ)を使いました。どこでも手に入るわけではないので、高さと奥行きが一緒なら15~21ミリ厚の合板で構いません。
底板の階段は余った板を有効利用したので、図とは違います。短い板でも、見えないところに空間を作るように組み合わせれば、階段は何とか作れます。ホーンの広がり方が自然になるように工夫してみてください。フロントバッフルは接着しなければ交換式に出来ます。なお、音道を15ミリ厚で構成すればベターなので、その時は奥行きが長くなり、音道を構成する板も変更する必要があります。その辺は、試行錯誤で独自色を出してください。本当は、奥行きがもう少しあれば設計も楽だったのですから。
エフライム工房 平御幸
カール・ベームは、拍手が鳴り止まない日本の聴衆に感激して、次回の来日を約束した熱い魂の人です。彼が若かった時代の、音楽で討論を戦わした熱情を日本に見たようです。今の日本の、戦うことを避ける、飼い慣らされた犬のような集団にはガッカリするかもしれませんね。
1975年3月と言えば、僕が芸大2年の時で、芸大寮が建て替えられている最中かもしれません。僕は、夏のアルバイトでFMチューナーを買い、アンプやスピーカー等をローンで揃えていました。それで、この公演のライブ放送や再放送などを、必死にカセットに録音したものです。そのテープの最後に再アンコールの常動曲が入っており、ベームの言葉がちゃんと録音されていたのです。このテープは失ってしまいましたが。
ベームは、常動曲という何時までも続く曲を選び、自分のメッセージを日本に残したのです。いつまでもこのようでありたいと願うベームは、実に多くのものを遺してくれました。照明や指揮台に注文をつけるリハーサルや、あるいは神社で手を洗ったり、あるいは日本のファンから花束を受け取るシーン一つでも、本当に観る価値があります。今から思えば、本当に奇跡的な出来事でした。
当時の日本は、モナリザが上野で公開されたり、ベームが来日したり、僕にとっては貴重な時間の連続でした。カセットテープがステレオ化され、オーディオに使える音質を獲得したのもこの時代です。しかし、DVD(音はFMのものを映像に重ね)ではテープヒスノイズをカットしているために、肝心のトライアングルの音までもカットされています。NHKには「死ね」と言いたいですね。
ワーグナーのニュルンベルクのマイスタージンガーは、このトライアングルの連打が花なのですが、見事にカットされているので、せっかくのヤマハのトゥイーターが泣いています。トライアングルを美しく再生できるのがヤマハJA0506なのです。送ってくれた読者はLPも届けてくれるそうなので、そちらに期待してみます。
カール・ベームは法律の学校を出た異色の経歴ですが、音符やパートを吟味して、一つ一つに丹念な意味付け(必然性)を与えています。流して美しく聴かすという手法は取らないので、聴けば聴くほど深みが理解できてきます。ブラームスの交響曲第1番は、楽譜とにらめっこしながら毎日のように聴いていますが、それでも飽きることはありません。
少し前に、N響を振った、ネヴィル・マリナーのブラームス交響曲第1番を放送していましたが、途中で録画をやめました。聴くに耐えなかったからですが、ベームがレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画なら、マリナーはモノクロ写真のような感じです。神秘も深みもない、ナルシシストの自己満足でしたね。
黄金の時代のベームやカラヤンを理解するには、当時に頂点を究めた日本のFETアンプの相性が良いと思います。僕のミカエル型のバックロードホーンは、そういう意味でも、僕が35年も追い続けた音かもしれませんね。ということで、板取(910×1820 12ミリ厚合板)と音道の見取り図をアップしました。板取図には書いてありませんが、僕は側板に13ミリ厚の桐の集成材(910ミリ×350ミリ)を使いました。どこでも手に入るわけではないので、高さと奥行きが一緒なら15~21ミリ厚の合板で構いません。
底板の階段は余った板を有効利用したので、図とは違います。短い板でも、見えないところに空間を作るように組み合わせれば、階段は何とか作れます。ホーンの広がり方が自然になるように工夫してみてください。フロントバッフルは接着しなければ交換式に出来ます。なお、音道を15ミリ厚で構成すればベターなので、その時は奥行きが長くなり、音道を構成する板も変更する必要があります。その辺は、試行錯誤で独自色を出してください。本当は、奥行きがもう少しあれば設計も楽だったのですから。
エフライム工房 平御幸