第16話 東京大学工学系大学院の航空宇宙専攻での授業内容
概要;
研究成果の現実社会への反映を重視する政策がすすめられているが、エンジニア生活40年を経験した筆者には、まだ不徹底の思いが強い。そんな中で、東大工学系大学院の航空宇宙専攻の研究室から授業の依頼を受けた。準備期間は短かったが、「実際の経験談を中心に」とのことだったので、敢えてお受けした。テーマは、「FMEA,FTA,ワイブル分布の設計開発における応用」であった。
航空機用エンジンの新規開発では、この3つは重要な役割を担っている。質疑応答と直後のアンケートから感じたことは、やはり大学教育と開発設計エンジニアの距離感であった。
授業の内容;


航空機用エンジンの設計は、他の工業製品よりはメタエンジニアリングに係わる知識が格段に多く必要である。耐環境性は勿論、世界中のどんな国で運用されても、安全性を確保しなければならない整備性など。
また、原発と並んで、ニュートン物理学に逆らった科学の成果を信頼性を保って利用してゆかなければならない。その為に、Design on Liberal Arts Engineeringの出番が多い。

Airbus A320用エンジンの開発設計で、Rolls RoyceとPratt&Whitneyの設計思想を経験した後で。GEとの共同開発が並行して始まった。
新機種の開発は、3社3様の思想が現れて面白い。戦略的な考えでは、明らかに負けるのだが、問題が特定された後の解決策の完成には、負ける気がしない。日本の技術陣には、それだけの人材が揃っていた。

「全ての科学には、賞味期限がある」とは、米国のメタエンジニアリング研究者の言葉である。科学と技術がともに多様化し、かつ専門分野化が進む中では、科学とその結果を利用する産業におけるエンジニアリングの間には、メタエンジニアリングという思考過程が必要な世の中になりつつある。

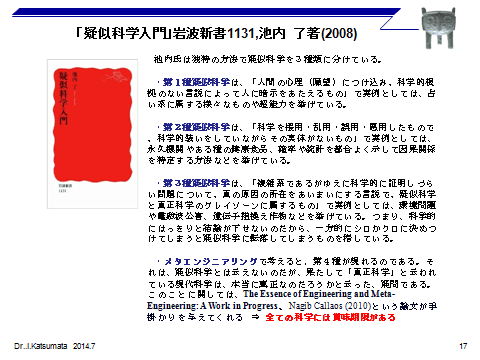
最近は、顧客に喜ばれる設計が主流となりつつあるが、その傾向が本当に人類の将来の為になるのかどうか、将来 負の価値を残すことにならないかを綿密に考えなければならないほどに、エンジニアリングの影響は大きくなってしまった。

日本では、教養学科の教育と、専門領域の教育が並行して行われることはほとんど無い。しかし、そのことを見直す時期に来ている。



FMEAだけでは、形骸化する恐れがある。
Criticality Analysisを加えた、FMECAを行わなければ、価値が半減される。
最近、日本国内で頻発する事故や不具合は、当初の設計時に、FMECAを行っていたら、防ぐことができたと思わざる得ないことが、多い。




この図に示されるように、日本では、欧米に比べてFTA(Fault Tree Analysis)が重要視される傾向にある。事故が起こってからの対応に眼が向いているためではないだろうか。
一方、欧米ではFTAよりは、FMEA(FMECA)をより多く活用している。

ワイブル分布を実際の研究開発や開発設計に用いるケースは限られているが、もっと活用するべきだと思う。原因が複雑で特定することが危険なケースが増えつつある中では、従来多用されている統計法よりは、有効な側面がある。
また、世の中のデジタル化が進み、先ずはグラフ用紙にプロットをして、傾向を把握する態度が見られなくなってしまった。逐次グラフにプロットをしていると、自然に将来の傾向が見えてくる ものなのだが、その価値が失われている。



結論は、このように纏めました。
「想定外」とか「規定外」といった言い訳は、設計技術者の口からは決して発してほしくない言葉です。

概要;
研究成果の現実社会への反映を重視する政策がすすめられているが、エンジニア生活40年を経験した筆者には、まだ不徹底の思いが強い。そんな中で、東大工学系大学院の航空宇宙専攻の研究室から授業の依頼を受けた。準備期間は短かったが、「実際の経験談を中心に」とのことだったので、敢えてお受けした。テーマは、「FMEA,FTA,ワイブル分布の設計開発における応用」であった。
航空機用エンジンの新規開発では、この3つは重要な役割を担っている。質疑応答と直後のアンケートから感じたことは、やはり大学教育と開発設計エンジニアの距離感であった。
授業の内容;


航空機用エンジンの設計は、他の工業製品よりはメタエンジニアリングに係わる知識が格段に多く必要である。耐環境性は勿論、世界中のどんな国で運用されても、安全性を確保しなければならない整備性など。
また、原発と並んで、ニュートン物理学に逆らった科学の成果を信頼性を保って利用してゆかなければならない。その為に、Design on Liberal Arts Engineeringの出番が多い。

Airbus A320用エンジンの開発設計で、Rolls RoyceとPratt&Whitneyの設計思想を経験した後で。GEとの共同開発が並行して始まった。
新機種の開発は、3社3様の思想が現れて面白い。戦略的な考えでは、明らかに負けるのだが、問題が特定された後の解決策の完成には、負ける気がしない。日本の技術陣には、それだけの人材が揃っていた。

「全ての科学には、賞味期限がある」とは、米国のメタエンジニアリング研究者の言葉である。科学と技術がともに多様化し、かつ専門分野化が進む中では、科学とその結果を利用する産業におけるエンジニアリングの間には、メタエンジニアリングという思考過程が必要な世の中になりつつある。

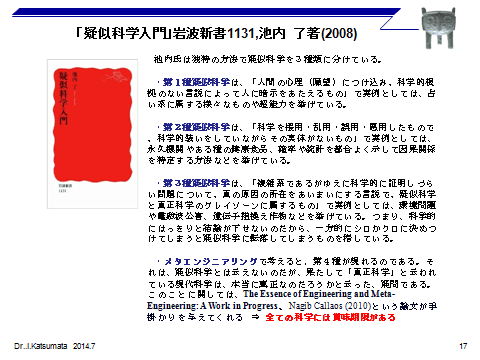
最近は、顧客に喜ばれる設計が主流となりつつあるが、その傾向が本当に人類の将来の為になるのかどうか、将来 負の価値を残すことにならないかを綿密に考えなければならないほどに、エンジニアリングの影響は大きくなってしまった。

日本では、教養学科の教育と、専門領域の教育が並行して行われることはほとんど無い。しかし、そのことを見直す時期に来ている。



FMEAだけでは、形骸化する恐れがある。
Criticality Analysisを加えた、FMECAを行わなければ、価値が半減される。
最近、日本国内で頻発する事故や不具合は、当初の設計時に、FMECAを行っていたら、防ぐことができたと思わざる得ないことが、多い。




この図に示されるように、日本では、欧米に比べてFTA(Fault Tree Analysis)が重要視される傾向にある。事故が起こってからの対応に眼が向いているためではないだろうか。
一方、欧米ではFTAよりは、FMEA(FMECA)をより多く活用している。

ワイブル分布を実際の研究開発や開発設計に用いるケースは限られているが、もっと活用するべきだと思う。原因が複雑で特定することが危険なケースが増えつつある中では、従来多用されている統計法よりは、有効な側面がある。
また、世の中のデジタル化が進み、先ずはグラフ用紙にプロットをして、傾向を把握する態度が見られなくなってしまった。逐次グラフにプロットをしていると、自然に将来の傾向が見えてくる ものなのだが、その価値が失われている。



結論は、このように纏めました。
「想定外」とか「規定外」といった言い訳は、設計技術者の口からは決して発してほしくない言葉です。










