メタエンジニアの眼シリーズ 03
このシリーズはメタエンジニアリングで文化の文明化のプロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
新石器時代から土器時代へ
・ジャレット・ダイヤモンド「文明の崩壊」下巻,草思社[2012] KMB3089
メタエンジニアリング的に考え始めると、日本の縄文時代は単なる文化ではなく、人類史上唯一の1万年以上(註1)も続いた文明ということ浮かび上がってくる。近年の縄文土器をはじめとする縄文時代の遺物を先端科学で研究した欧米歴史学者の結論は、古代エジプトやメソポタミヤを越える独特の文明が存在したと主張している。例えば、「文明の崩壊」[2005]の中で、著者のジャレット・ダイヤモンド、カリフォルニア大学教授は、18世紀から19世紀の実例として江戸時代の日本の森林資源の管理を挙げている。

『しかし日本は、ドイツとは関係なく同時期にトップダウン方式の森林管理を発展させていたことがわかっている。この事実にも、驚かされる。日本は、ドイツと同様、工業化された人口過密な都市社会だからだ。先進大国の中でもっとも人口密度が高く、・・・(中略)』(pp.40)
このストーリーは戦国時代を経て江戸時代が始まった歴史を詳細に述べたうえで、『平和と安定によって逆説的にもたらされた環境及び人口の危機に対応する目的で生まれた』としている。木造建築の大都市の発展と、度び重なる大火で日本の森林資源は危機を迎えた。そこで打たれた徳川幕府の政策は、世界史上まれにみる細かさと厳しさで、数十年の間に森林資源の循環系を確立してしまった。
しかし、この森林資源の循環系を確立したのは、三内丸山の縄文人であった。
縄文人は文字と農耕文化を持たなかったので、文明人と思われていなかった。しかし、近年の三内丸山遺跡とその周辺の総合的研究から、長期間にわたって分散していたが、徐々に集合されて都市になり三内丸山を中心に、数千年間栄えたことが証明されている。世界の4大文明発祥地は、いずれも農耕文化に頼ったために、長期間の定住で人口が増えすぎて、土地が極端に痩せたために、多くは砂漠化して衰亡したといわれている。農耕文化は自然の森を破壊して畑をつくることから始まる。そのことは、古代文明の崩壊の一つの共通した原因とされている。縄文時代は、森と海に食糧を依存して、農耕文化に頼ることをしなかった、独特の文明と云えるのではないか。
三内丸山遺跡の巨大遺構から、樹齢250年を超える栗の巨木が多数使われていたことが判明した。栗の木は通常はまっすぐには育たないのだが、巨大な建造物の柱材としては最適であると判断した。そこで、縄文人は栗の実を重要な食料として確保すると同時に、何世代にわたって優れた林業の技術を継
承してきた。この技術は、現代の林業でも実現できていない。この時代は、世界史的には新石器時代に相当するのだが、この縄文文明は土器なしでは存続しない。世界で初めて土器を生産し、生活の最重要品として芸術とも言われている技術を造り上げたのであるから、石器時代と古代の間に、一万年に及ぶ「縄文時代」という時代設定をするべきと考える。
(註1)縄文時代は、紀元前131世紀頃から紀元前4世紀頃に日本列島で発展した。世界史では、新石器時代に含まれている。
・山田康弘「つくられた縄文時代」新潮社、新潮選書[2015] KMB3142
縄文人は外洋航海術を持っていた。栗林を計画的に植林し、管理した。栗林を食料と同時に建築用材として育てた。栗の木は、自然に生やすと曲がってしまうが、縄文人はまっすぐな大木を育てた、樹齢250年以上のまっすぐな大木が何本も使われていたのが、その証拠である。
この著書では、教科書における生業形態の記述変化に注目をしている。
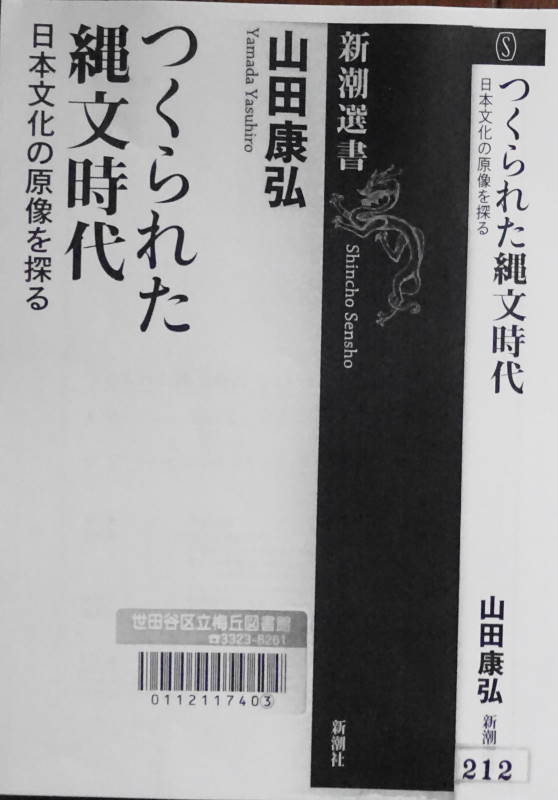
『1984年版では「縄文時代は、狩猟・漁労・採集の段階にとどまり、生産力は低かった。動物や植物資源の獲得は、自然条件に左右されることが多く、人々は不安定できびしい生活をおくっていたと考えられる。」と記述されていたが、2013年版では「食料の獲得法が多様化したことによって、人びとの生活は安定し、定住的な生活が始まった。」となっている。』
つまり、生活が不安定から安定に、たった20年間の間に評価が正反対になっている。
『歴史を叙述するにあたって「縄文時代」、「縄文文化」と言った場合、それは当初から「日本」における「一国史」としての枠組みが前提とされる。当然ながら「日本」以外には「縄文時代」という概念は存在せず、世界的には、本格的な農耕を行っていない新石器時代というユニークな位置付けが与えられることになる。』
私は、新石器時代の後に、「土器時代」・「土器文明」という言葉があってよいのではないかと考える。つまり、土器により人類は初めて文明を手にした。そして、土器文明の発祥の地は「日本列島」であり、農耕に頼らない土器による調理と保存技術の発展で、自然共存の文明が誕生した、と言えるのではないだろうか。土器製造技術を調理と保存器として汎用化できなかった民族は、例えば中国における青銅器のように、土器時代を経ずに金属器を用いる古代に突入した。
『16000年前から3000年ほど前の食料獲得経済を旨とする時期を一括的に叙述するタームとしては、「縄文時代」・「縄文文化」は非常に使い勝手がよい。』
・ジャレット・ダイヤモンド「第三のチンパンジー」草思社[2015]KMB3163
著者のジャレット・ダイヤモンドは、カリフォルニア大学ロスアンゼルス校の社会学部教授で、「銃・病原菌・鉄」や「文明崩壊」などの著書で有名な生物・生理学者。チンパンジーとの1.6%の遺伝子の違いで、なぜ人間だけが『ありふれた大型哺乳動物』でなくなったのかを追求している。例えば、芸術は遺伝子によるのか、人間社会による後天的なものなのかなど。

メタエンジニアリング的に注目をしたのは、農業の正の価値と負の価値を追求した内容である。
一般的には、人類は、狩猟・採集文化から農業文化に移行することによって、文明を手に入れたといわれてきたが、現代の評価は異なる。このことは、日本の縄文文化を文明とする考え方に一致する。
そのことは、紀元前8000年の中東、紀元前6000年のギリシャ、紀元前2500年のイギリスにおける、その前後の遺骨から推定されている。つまり、それ以前の狩猟・採集文化と以後の農業文化の比較である。
農業文化の正の価値;多くの人口を養うことが可能、都市の発達、道具の発達
農業文化の負の価値;疫病、階級的不平等、支配者による専制、環境破壊、飢饉
このように羅列すると、負の価値の大きさが目立つが、更に決定的な事実が存在する。
① 現代のブッシュマンの生活は、世界の一般の社会よりも余暇時間が多く、睡眠時間も長い。同じ環境の周辺の農民よりは楽な生活を続けている。
② 狩猟・採集文化のほうが、たんぱく質の摂取量と栄養バランスが良い。ギリシャ・トルコの遺骨からは、紀元前6000年以降、身長が急激に低くなり、現代でもまだ追いついていない。アメリカ先住民の虫歯の数は、トウモロコシの栽培開始以降7倍になった。
③ 日本の縄文時代には大量の死者が同時に出た痕跡はないが、西欧では飢饉や疫病による大量の餓死の例が多く記録されている。
つまり、農業文明は長期間にわたって一方的な発展を続けた結果、人類に栄養素の偏重、社会の不平等、環境破壊などの基本的な負の価値の増大を招いたといえる。このことを、現代の科学・技術文明に置き換えると、ほぼ同じことが言えるのではないだろうか。つまり、ヒトの動物としての能力、社会制度、地球環境の3つの基本要素に対して、正と負のバランスが逆転する時期を既に通り越しているという認識が成り立つのではないだろうか。
この正負の基本的な関係は、現代の科学と技術のさらなる力で再逆転が可能なのだろうか、それともさらに悪い方向に進んでしまうのだろうか。21世紀の文明論者は、後者を支持する傾向が強まってきているように見受けられる。
このシリーズはメタエンジニアリングで文化の文明化のプロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
新石器時代から土器時代へ
・ジャレット・ダイヤモンド「文明の崩壊」下巻,草思社[2012] KMB3089
メタエンジニアリング的に考え始めると、日本の縄文時代は単なる文化ではなく、人類史上唯一の1万年以上(註1)も続いた文明ということ浮かび上がってくる。近年の縄文土器をはじめとする縄文時代の遺物を先端科学で研究した欧米歴史学者の結論は、古代エジプトやメソポタミヤを越える独特の文明が存在したと主張している。例えば、「文明の崩壊」[2005]の中で、著者のジャレット・ダイヤモンド、カリフォルニア大学教授は、18世紀から19世紀の実例として江戸時代の日本の森林資源の管理を挙げている。

『しかし日本は、ドイツとは関係なく同時期にトップダウン方式の森林管理を発展させていたことがわかっている。この事実にも、驚かされる。日本は、ドイツと同様、工業化された人口過密な都市社会だからだ。先進大国の中でもっとも人口密度が高く、・・・(中略)』(pp.40)
このストーリーは戦国時代を経て江戸時代が始まった歴史を詳細に述べたうえで、『平和と安定によって逆説的にもたらされた環境及び人口の危機に対応する目的で生まれた』としている。木造建築の大都市の発展と、度び重なる大火で日本の森林資源は危機を迎えた。そこで打たれた徳川幕府の政策は、世界史上まれにみる細かさと厳しさで、数十年の間に森林資源の循環系を確立してしまった。
しかし、この森林資源の循環系を確立したのは、三内丸山の縄文人であった。
縄文人は文字と農耕文化を持たなかったので、文明人と思われていなかった。しかし、近年の三内丸山遺跡とその周辺の総合的研究から、長期間にわたって分散していたが、徐々に集合されて都市になり三内丸山を中心に、数千年間栄えたことが証明されている。世界の4大文明発祥地は、いずれも農耕文化に頼ったために、長期間の定住で人口が増えすぎて、土地が極端に痩せたために、多くは砂漠化して衰亡したといわれている。農耕文化は自然の森を破壊して畑をつくることから始まる。そのことは、古代文明の崩壊の一つの共通した原因とされている。縄文時代は、森と海に食糧を依存して、農耕文化に頼ることをしなかった、独特の文明と云えるのではないか。
三内丸山遺跡の巨大遺構から、樹齢250年を超える栗の巨木が多数使われていたことが判明した。栗の木は通常はまっすぐには育たないのだが、巨大な建造物の柱材としては最適であると判断した。そこで、縄文人は栗の実を重要な食料として確保すると同時に、何世代にわたって優れた林業の技術を継
承してきた。この技術は、現代の林業でも実現できていない。この時代は、世界史的には新石器時代に相当するのだが、この縄文文明は土器なしでは存続しない。世界で初めて土器を生産し、生活の最重要品として芸術とも言われている技術を造り上げたのであるから、石器時代と古代の間に、一万年に及ぶ「縄文時代」という時代設定をするべきと考える。
(註1)縄文時代は、紀元前131世紀頃から紀元前4世紀頃に日本列島で発展した。世界史では、新石器時代に含まれている。
・山田康弘「つくられた縄文時代」新潮社、新潮選書[2015] KMB3142
縄文人は外洋航海術を持っていた。栗林を計画的に植林し、管理した。栗林を食料と同時に建築用材として育てた。栗の木は、自然に生やすと曲がってしまうが、縄文人はまっすぐな大木を育てた、樹齢250年以上のまっすぐな大木が何本も使われていたのが、その証拠である。
この著書では、教科書における生業形態の記述変化に注目をしている。
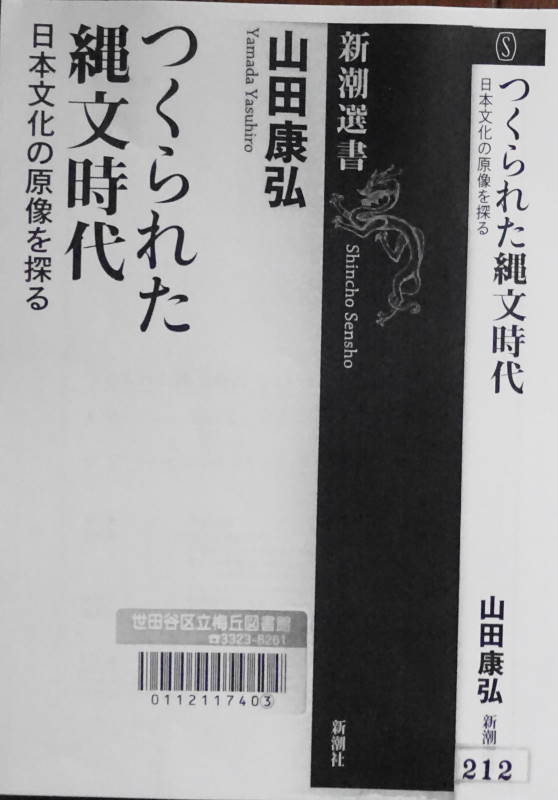
『1984年版では「縄文時代は、狩猟・漁労・採集の段階にとどまり、生産力は低かった。動物や植物資源の獲得は、自然条件に左右されることが多く、人々は不安定できびしい生活をおくっていたと考えられる。」と記述されていたが、2013年版では「食料の獲得法が多様化したことによって、人びとの生活は安定し、定住的な生活が始まった。」となっている。』
つまり、生活が不安定から安定に、たった20年間の間に評価が正反対になっている。
『歴史を叙述するにあたって「縄文時代」、「縄文文化」と言った場合、それは当初から「日本」における「一国史」としての枠組みが前提とされる。当然ながら「日本」以外には「縄文時代」という概念は存在せず、世界的には、本格的な農耕を行っていない新石器時代というユニークな位置付けが与えられることになる。』
私は、新石器時代の後に、「土器時代」・「土器文明」という言葉があってよいのではないかと考える。つまり、土器により人類は初めて文明を手にした。そして、土器文明の発祥の地は「日本列島」であり、農耕に頼らない土器による調理と保存技術の発展で、自然共存の文明が誕生した、と言えるのではないだろうか。土器製造技術を調理と保存器として汎用化できなかった民族は、例えば中国における青銅器のように、土器時代を経ずに金属器を用いる古代に突入した。
『16000年前から3000年ほど前の食料獲得経済を旨とする時期を一括的に叙述するタームとしては、「縄文時代」・「縄文文化」は非常に使い勝手がよい。』
・ジャレット・ダイヤモンド「第三のチンパンジー」草思社[2015]KMB3163
著者のジャレット・ダイヤモンドは、カリフォルニア大学ロスアンゼルス校の社会学部教授で、「銃・病原菌・鉄」や「文明崩壊」などの著書で有名な生物・生理学者。チンパンジーとの1.6%の遺伝子の違いで、なぜ人間だけが『ありふれた大型哺乳動物』でなくなったのかを追求している。例えば、芸術は遺伝子によるのか、人間社会による後天的なものなのかなど。

メタエンジニアリング的に注目をしたのは、農業の正の価値と負の価値を追求した内容である。
一般的には、人類は、狩猟・採集文化から農業文化に移行することによって、文明を手に入れたといわれてきたが、現代の評価は異なる。このことは、日本の縄文文化を文明とする考え方に一致する。
そのことは、紀元前8000年の中東、紀元前6000年のギリシャ、紀元前2500年のイギリスにおける、その前後の遺骨から推定されている。つまり、それ以前の狩猟・採集文化と以後の農業文化の比較である。
農業文化の正の価値;多くの人口を養うことが可能、都市の発達、道具の発達
農業文化の負の価値;疫病、階級的不平等、支配者による専制、環境破壊、飢饉
このように羅列すると、負の価値の大きさが目立つが、更に決定的な事実が存在する。
① 現代のブッシュマンの生活は、世界の一般の社会よりも余暇時間が多く、睡眠時間も長い。同じ環境の周辺の農民よりは楽な生活を続けている。
② 狩猟・採集文化のほうが、たんぱく質の摂取量と栄養バランスが良い。ギリシャ・トルコの遺骨からは、紀元前6000年以降、身長が急激に低くなり、現代でもまだ追いついていない。アメリカ先住民の虫歯の数は、トウモロコシの栽培開始以降7倍になった。
③ 日本の縄文時代には大量の死者が同時に出た痕跡はないが、西欧では飢饉や疫病による大量の餓死の例が多く記録されている。
つまり、農業文明は長期間にわたって一方的な発展を続けた結果、人類に栄養素の偏重、社会の不平等、環境破壊などの基本的な負の価値の増大を招いたといえる。このことを、現代の科学・技術文明に置き換えると、ほぼ同じことが言えるのではないだろうか。つまり、ヒトの動物としての能力、社会制度、地球環境の3つの基本要素に対して、正と負のバランスが逆転する時期を既に通り越しているという認識が成り立つのではないだろうか。
この正負の基本的な関係は、現代の科学と技術のさらなる力で再逆転が可能なのだろうか、それともさらに悪い方向に進んでしまうのだろうか。21世紀の文明論者は、後者を支持する傾向が強まってきているように見受けられる。












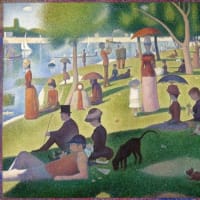
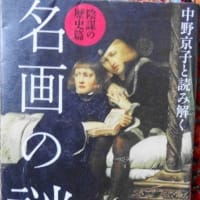


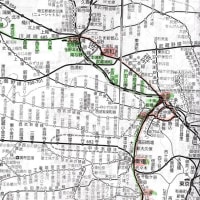


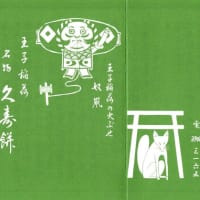
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます