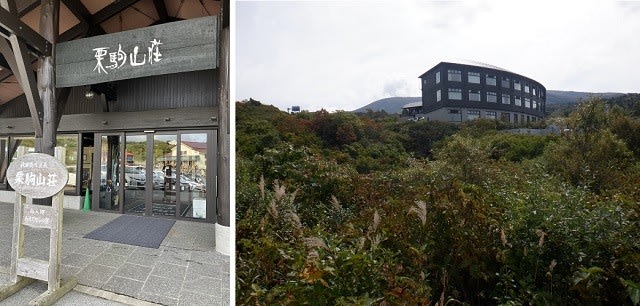盛りを過ぎたと言うけれどまだまだきれいな蝋梅
令和7年3月2日(日)
自転車仲間の面々と早春の宝登山ハイキングに行きました。この時期は蝋梅・福寿草・梅で有名ですが花を愛でるというより下山後の慰労会がメインかも。
西武線で西武秩父から秩父線のお花畑駅へ。そこから長瀞駅へ行きます。駅から宝登山神社に向かって歩き始めます。
ハイキングというのに登るのは嫌だということでロープウェイ「ばんび号」にに乗車。
山頂駅から歩き始めます。蝋梅がきれいです。
福寿草も可憐な姿でお出迎え。
秩父市内の向こうには武甲山が見えます。
山頂まで木々の花を楽しみながら登ります。
宝登山神社奥宮で参拝。
すぐに宝登山山頂に到着。休日でハイカーが大勢いました。
武甲山のアップ。
慰労会に向け、山頂を後にします。
もちろん帰りもロープウェイ「もんきー号」乗車。下車後、参道を駅に向かって下り長瀞屋さんで慰労会を開催。飲んで飲んで・・・おっきりこみで締めました。
仲間との楽しい1日を過ごすことが出来ました。