
▲日本の江戸期の検地測量の様子
◆一般主婦様
街を歩いていると測量機を使う
人達、郊外の散歩を延長して田
園地帯に至ると畑にヒモを引っ
張り畝を作る人、住宅地建築前
の地面に縄紐も張られている事
を散歩の過程で見て長谷川先生
のブログ記事を連想しました。
アスフアルトの道路に真新しい
路上表示を見掛けてチヨークの
下書き腺が残っている事世の万
物に設計腺やレイアウト腺が必
然的に存在する事を今更ながら
気付きました。日常の中に遺跡
や土木建築の謎を解くカギがあ
る事に気付始めた最近の私です。
◆対談者様
一見むずかしい城郭ビイスタ
論が私の予想を超えた反響が
あって失敗動画が3900人もの
人が見ている現実に驚きます。
◆古代東北城柵趣味の人
いやあ~!
秋田城、払田柵、多賀城など
古代大和朝廷が設けた城柵や
政庁のビイスタ解説をブログ
で拝見して本当新鮮に感じた
遺跡見る観点視点が変わった。
▼払田柵 ビイスタ工法
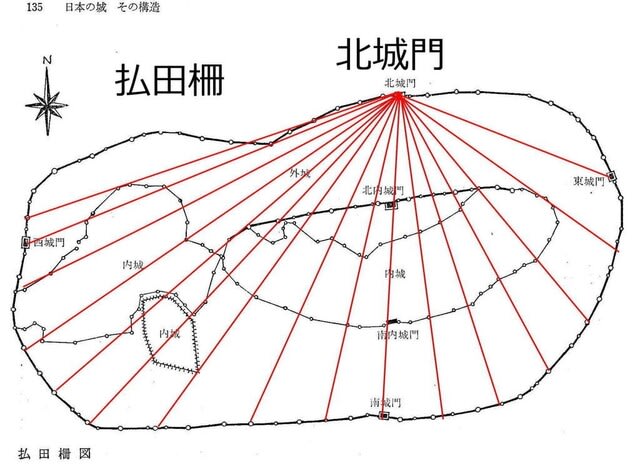
▼秋田城 ビイスタ工法
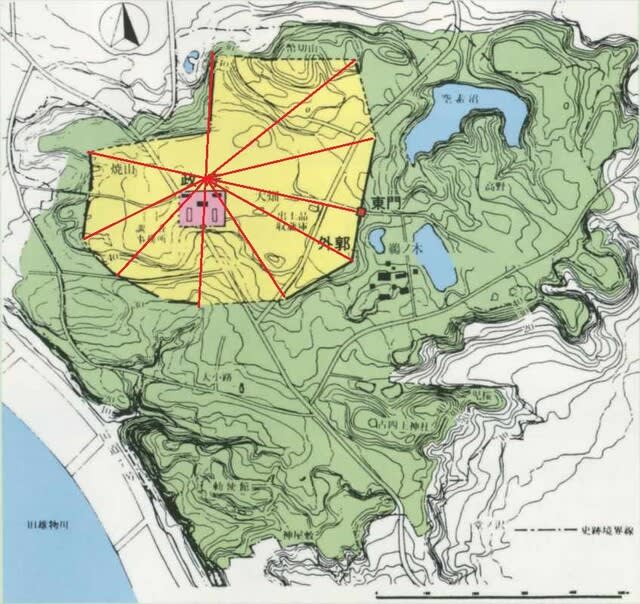
▼多賀城 ビイスタ工法

◆古代東北城柵趣味の人
長谷川先生には是非東山官衙
遺跡の基礎構造グランドプラ
ンを是非御教示願いたいです。
併せて宮城の壇の越遺跡をも
解説いただけるなら東北城柵
の縄張や設計構想の一端も判
明するのではないか思います。
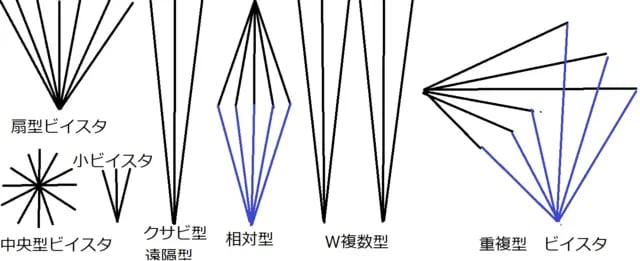
▼東山官衙遺跡

▼長谷川
浅学の私が遺跡構図を解説する
事は恐れ多く憚れる事案ですが
研究視点という意味から考察を
したいと思います。端的に言う
なら重複型ビイスタ工法ですね。
遺跡の基本構造とは「犬走」や
「腰郭」「要害地形」からなる
順然たる要塞や城郭の要素があ
ります。この丘上に官衙が設営
され土塀も併せて築造されたと
私は考察を致します。日本の城
の画期をなすとされる山科本願
城なども加賀の城つくりの伝統
による伝承された高い測量技術
築城術にあると私は思います。

◆学識質問者
壇の越遺跡の山麓、東山官衙
遺跡山麓から発掘された南郭
材木塀配列とは如何?
◆長谷川
南郭材木塀配列とは碁盤目の土
地区画「坊条制」とは異なる角
度を持っています。おそらくビ
イスタ工法としては東山官衙遺
跡や壇の越遺跡を統合した城塞
としてのビイスタ工法かと思いま
す。今後の発掘結果の進展を待ち
ます今回は暫定的に水底に赤線を
入れました。

◆学識質問者
東山官衙遺跡の外郭に相当する
壇の越遺跡には城壁に付随する
櫓の柱穴も発見されていますが
これ等を如何に長谷川先生とは
解釈されますか?
◆長谷川
外郭櫓列と進シンクロ「連携」
したビイスタは東山官衙遺跡
の北から遠隔測量したビイスタ
だと私は考えております。

◆対談者様
やはり長谷川先生の解説には「深み」
「妙味」含蓄のある考察をされます。
























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます