年に一度の"出合い"の日。お盆前の、地域あげてのクリーン・アップ・デーのことで、お互い年齢をひとつ重ねた近所の衆と顔を合わせる日である。みなさん昼間は仕事に出てるからこういう機会でないとゆっくり話せない。久闊(きゅうかつ)を叙(じょ)するという表現がぴったりだ。お隣さんそれぞれ高齢化していることもあって、貴重な時間となる。ローカルルールを学び、ことの起源や由来などを伝承する場でもある。
午前7時というのにもう充分暑かった。隣家との境に珍しくのっぽの槙の木があるのだが、そこで両隣のおじさんたちが話をしている。
「今年もキツツキが来とったなぁ…。」
「うん、あんまし大きくないヤツな。」
その言葉に促されてふと幹を見やると、まん丸い穴がいくつも穿(うが)たれている。驚いたのなんの。キツツキの存在どころか、当事者のぼくが知らずにご近所さんがしっかり把握されておられることに。ぼくの目は節穴のようだ。
確かに鶯のみごとな鳴き音に目を覚ます朝がある。仏法僧らしき鳥の音に驚くこともあり、部屋から屋外を眺める度にいろんな鳥の姿が目に入ることが多い。我が家の庭で珍しい鳥がツガイで戯れるのを目撃することすらある。それどころか車のウィンドウガラスに鳥糞がこびりつき嘆くのもしばしばだ。イタチらしき小動物を発見して錯覚かと疑ったが、鳥を狙って出没したものと考えれば合点が行く。留守にするのがもったいないほど、我が家には自然が残されている。
これも隣のアニさんから聞いたことだが、横山の北東麓に位置する田園地帯に「ホトケドジョウ」と呼ばれる泥鰌の生息が確認されたらしい。これはビッグ・ニュースに値する。志摩辺りで発見されることは珍しく、なんでも主に関東地方に生息するのだと。しかも絶滅危惧種に指定されおり、保存が叫ばれている。
志摩にはまだまだ自然がいっぱいだ。なぜなら、
- 生息に適した水温
- 綺麗な水質
の証明なのだから。
しかし、お米を作る立場のアニさんとしては辛いこともあると言う。
- 肥料や農薬での汚染を防ぐ
- 埋め立てや水田の整備を控える
など、工夫や制約が求められる。実に繊細な農作業となるのだから、そのご苦労を思うと、頭が下がる。
ジブリの「おもひでぽろぽろ」の1シーンが頭を過った。
お百姓が自然を作った…
すっかり夏の気配。ガソリンを入れようと出掛けると車の渋滞に遭遇した。県外ナンバーにあふれ、サーファーも、観光客も多い。この夏、志摩を訪れる人の多いことを願って止まない。今日のBGMは、オフコースの「夏の日」で決まり。











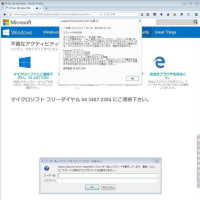





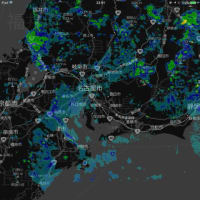



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます