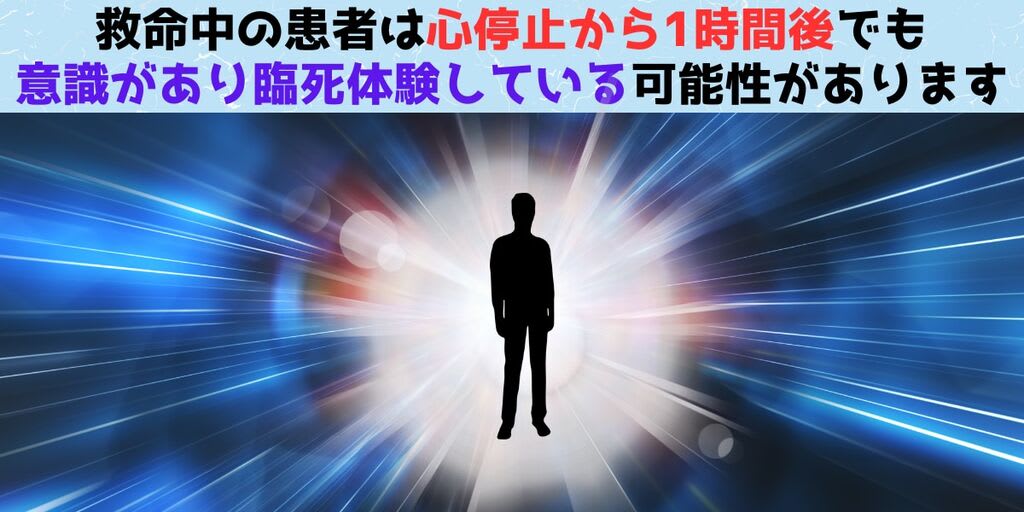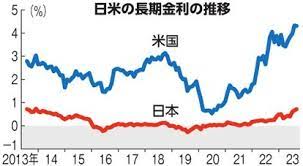太平洋戦争中、日本の軍艦が次々と沈没していった「残念な理由
8/15/2022

----------
太平洋戦争では、じつは日本海軍の軍艦は致命的な欠陥を抱えていた。そのため魚雷攻撃に非常に弱く、いとも簡単に沈没していたのだ。これにより艦隊の編制に支障をきたし、戦艦大和の行動も制限されて、海軍が描いた勝利の方程式は崩壊したのである。 いったい日本の軍艦にはどのような欠陥があったのか? 歴史の謎を科学で解き明かして大好評を博した『日本史サイエンス』の第2弾を著した播田安弘氏が、終戦から77年を機に専門である船舶設計の知見をもとに喝破する。
----------
【写真】敵艦に突入する零戦を捉えた超貴重な1枚…!
「常套句」に隠されたもの
太平洋戦争における日本の敗因は、そもそも米国と戦ったことだとは、よくいわれるところです。たしかに開戦直前の国力の差は、GNPで比べると日本は米国の約9%にすぎませんでした。これでよくも開戦したものと驚くばかりです。
しかも、日本が乏しい国力を傾けて建造した戦艦大和は、ほとんど出撃しないまま終戦直前に沈没し、戦後になってピラミッド、万里の長城と並ぶ「無用の長物」と揶揄されました。そんなものをつくった海軍は時代遅れの「大艦巨砲主義」に陥っていたと非難され、ただでさえ不利なのにこれでは勝てるはずがなかった、などと総括されています。
しかし私は、そうした常套句だけでこの戦争を語るのは、何か大事なものを見過ごすことになるように思われてならないのです。もとより歴史や軍事の専門家ではありませんので、戦略や戦術についてのくわしいことはわかりません。それでも船のエンジニアとしての立場から、指摘しておきたいことがあるのです。
世界を驚かせた「造船の神様」
世界初の本格的な空母「鳳翔」(ウィキメディア・コモンズ)
太平洋戦争前の国内工業は、たしかにあらゆる点で欧米先進国より遅れていて、工作機械もすべて輸入品でした。しかし、進取の気性に富む海軍は、航空機時代の到来を世界に先駆けて予見し、1922(大正11)年には航空母艦「鳳翔」を完成させました。これは世界で初めて設計段階から空母をつくる目的で建造された、本格的空母でした。
さらに山本五十六連合艦隊司令官は海軍航空隊まで設立し、ほとんどの国がまだ航空機の効能を軽視していたなかで、確信をもって飛行訓練を重ねていました。そもそもは、日本の海軍は「大艦巨砲主義」ではなかったのです。むしろ、当時は米国や英国のほうが多くの大型戦艦を建造していました。世界が航空機の重要性に気づいたのは皮肉にも、日本がのちに真珠湾攻撃と、続くマレー沖海戦で大勝利をおさめてからでした。
1922年、第一次世界大戦の戦勝国である米英仏伊日の戦艦建造競争が過熱してきたため、ワシントン海軍軍縮条約によって戦艦保有規模が制限され、日本は米英の6割に抑えられました。そこで日本海軍はやむなく、巡洋艦や駆逐艦などの補助艦に活路を見いだす方針を打ち出します。巡洋艦とは、戦艦よりは小さくて速度がある中型の軍艦で、駆逐艦は、さらに小型で俊敏な艦です。
翌1923年に完成した「夕張」は、排水量3100tと小型ながら、14 cm砲6門、61cm連装魚雷発射管2基を搭載し、なんと速力は34ノットと、5500t型巡洋艦と同等の戦闘能力を装備した画期的な巡洋艦でした。
公開された夕張を見た各国の海軍関係者は、巡洋艦設計の概念を根本から覆す構想と、その工法に大きな衝撃を受けました。これにより、「夕張」を設計した造船中将・平賀譲の名は一躍、世界に知れわたったのです。平賀はまた、「古鷹」でも、世界で初めて戦艦並みの20cm砲を巡洋艦に搭載してみせました。
しかしワシントン条約以降は巡洋艦の建造競争が過熱したため、1930(昭和5)年のロンドン海軍軍縮条約によって、巡洋艦も排水量や砲の口径を基準に保有数を制限することになり、制限の対象となるものは重巡洋艦、それ以下のものは軽巡洋艦と呼ばれました。
それでも平賀は、条約による制限のもとで精魂込めて、小型の巡洋艦でも1クラス上の巡洋艦と同じ性能や砲力をもたせようと、特異な設計をして世界を驚愕させつづけました。平賀は「造船の神様」とも呼ばれ、まさに伝説の設計者となったのです。
なお、『アルキメデスの大戦』には、平賀をモデルにした平山忠道造船中将が登場し、戦艦大和をみずから設計して主人公の櫂直と対立しますが、実際の平賀は大和の設計には指導や助言をするのみだったようです。
のちに東京帝国大学の総長もつとめた平賀を、私は船舶設計者としても、人間としても非常に尊敬しています。しかし、これから述べようとしているのは、そのような「神様」にも過ちがあったという話です。
以下はリンクで