
★註:司法審査基準の重層性-アメリカの二重螺旋構造的司法審査基準
アメリカの現在の司法審査においては、(一応、精神活動の自由と経済活動の自由では憲法が要求する保障の度合いが異なるとする所謂「二重の基準論」を前提にした上で)その憲法適合性が問題になっている制約が(α)精神的自由の制限か(β)経済的自由の制限か。経済的自由の制限とすれば、(β3)それは(食品や住居の耐震基準等の国民の安心安全を図るための)社会的規制か(β1or2)それとも狭義の経済政策的の規制か。
更に、後者とすれば、(β1)それは(所有権や経済活動の自由を制限する)消極的な経済規制なのか、それとも、(β2)ケインズ政策の断行、社会経済の円滑な運営や福祉国家の実現のための積極的経済規制なのか。これらの権利カテゴリーの差違に従い、権利が司法により保障される度合には差があるものと考えられています。
また、その規制と制約の様態の差も加味して、理念的に言えば、規制を行なう国家にとって違憲判決を喰らい易い順/合憲判決を獲得することの難度の順、すなわち、権利制限のための敷居が高い順(高→低)に並べれば次の通り、
↓(α1)表現内容に着目した精神的自由の制限(合憲判断はほぼ不可能)
↓(α2)表現内容には無関係な精神的自由の制限(合憲判断を獲得するのは一仕事)
↓(β1)消極的経済規制(杜撰な規制法規や規制措置には合憲判断が出ない、鴨)
↓(β2)積極的経済規制(合憲判断が出なけりゃ嘘でしょう)
↓(β3)社会的規制(合憲判断を覆すのはほぼ無理)
而して、憲法が「権利制限を制限する度合」は、具体的には、(イ)憲法訴訟の司法審査基準:どの程度の厳格さで人権侵害の有無や是非を審査するか(および、この裏面としての「権利を制約する法規の目的の妥当性と規制手段の相当性に合憲性が推定されるかどうか」あるいは「違憲を立証する責任は誰に帰属するか」)、そして、(ロ)憲法訴訟の合憲性判断基準:具体的な案件に際して何が満たされれば違憲とされるか(例えば、「その表現行為が社会に対して明白かつ現在する/明白かつ切迫した危機を惹起しているのかどうか」「より制限的でない他の選びうる手段が存在するのかいなか」等々の検討)の二つの軸の交点に求められる。
蓋し、それはアメリカ司法が自生的に紡ぎ出し編み上げた結果や伝統の「事後的かつ鳥瞰的の理解」であると同時に、(ⅰ)なんで自分の行動を他人や国家権力に指図されなあかんのやという素朴な疑問と、他方、(ⅱ)一応、全国民の委託を受けた政治代表が議会で決めたルールに職能集団でしかない司法府がなんでいちゃもんつけられるちゅーねんという(「立憲主義と民主主義」の一種宿命的な緊張関係の一斑たる)本質的な疑問の両者の均衡の中で自生的に編み上げられ紡ぎ出されたアメリカ司法の叡智の結果であろう。と、そう私は考えます。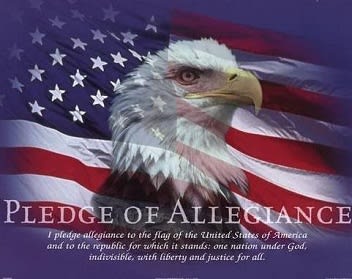
畢竟、(ロ)の審査基準は文字通り権利のカテゴリーに応じて、かつ、訴訟の内容を構成する重要な事実関係毎に異なってくるのですが、(ロ)に比べてより抽象的でかつ論理的にも(ロ)に先行する(イ)の「憲法訴訟の司法審査基準」の大枠をまとめれば、一般的にはそれは次の3種「厳格な審査基準」「厳格な合理性の審査基準」「合理性の審査基準」に分類されています。
・厳格な審査基準
審査対象となっている規制には違憲性が推定され、それなしには社会が立ちゆかない非常に強力な社会的利益(compelling interest)を確保する目的のためのものであり、利益を確保する手段として必要最小限の規制措置であり、かつ、それらの目的と手段との間に必要不可欠の関係が確認されない限り、その規制法規は違憲となる
・厳格な合理性の審査基準
審査対象となっている規制には合憲性が推定されるものの、社会的に重要な利益(important interest)を確保する目的のためのものであり、利益を確保する手段として他により制限的でない手段が見当たらず、かつ、それらの目的と手段との間に実質的関係性が確認されない限り、その規制法規は違憲となる
・合理性の審査基準
審査対象となっている規制には合憲性が推定され、社会的に正当な利益(legitimate interest)を確保する目的のためのものであり、それは利益を確保する手段として著しく不合理であることが明白ではなく、かつ、それらの目的と手段との間に合理的関係性が確認されない限り、その規制法規は違憲となる
けれども、例えば、アメリカ合衆国憲法修正5条および14条を根拠とする、所謂「実体的デュープロセス:substantive due process」の理論が、19世紀末葉から1937年-1938年のニューディール政策の中期に至るまでは、ニューディールの立法を次々に違憲判決で葬った、今で言えば「新自由主義的」な経済活動や契約の自由のたよりになる守護神であったのが、今ではプライバシーの権利や同性愛者の権利なるものを擁護するための<小道具>としてしばしば用いられている経緯。前者の代表的判例であるLochner v. New York(1905)やAdkins v.Children's Hospital(1923)、もしくは、 これら新自由主義的憲法価値の守護神としての「実体的デュープロセス:substantive due process」の理論に終止符を打ったUnited States v. Carolene Products Co.(1938)およびFerguson v. Skrupa(1963)、そして、後者のサンプルとしてのRoe v. Wade(1973)を紐解けば誰しも容易に観察理解できる経緯を紐解けば誰しも容易に観察理解できること、鴨。
更に、例えば、精神的自由、就中、政治を巡る表現の自由を制限する規制の合憲性判断基準としての所謂「明白かつ現在の危機:clear and present danger」の理論は、それが登場したSchenk v. United States States(1919年)を紐解けば自明のように、当初は精神的自由の制約を正当化する機能を果たすものであったのに対して(実際、Schenk判決で明白かつ現在の危機の理論は、徴兵制度反対の言論を第一次世界大戦中に行ったアメリカ社会党のKYでDNQな幹部に有罪判決のお灸をすえるためのロジックとして用いられました。)、それからちょうど半世紀を経て連邦最高裁が出したBrandenburg v. Ohio(1969年)では「明白かつ現在の危機:clear and present danger」の理論は規制法規に対するかなり厳格な(要は、その規制の憲法適合性判断に関して合憲判決が出るのはかなり難しくなる)審査基準として「新装開店」されたこと。
これらの「実体的デュープロセス:substantive due process」の理論や「明白かつ現在の危機:clear and present danger」の理論に象徴されるように、(イ)「司法審査基準」も(ロ)「合憲性判断基準」も、実は、その(少なくとも、具体的な訴訟に際して実際に適用される場面では、その)内容は時代と共に変遷してきたと言える、鴨です。
実際、自分が所有する国旗を燃やすことは日本でも所有者の勝手であり自由です(Texas v. Johnsonでは被上告人によって燃やされた星条旗は第三者が盗んで被上告人に手渡したものであり、この場合、動産の即時取得とは言いませんが、「自分が所有する/平穏に占有する権利を持っている」とは言えるケースだったのですけれども)。
よって、ある「日の丸」の布地の持ち主がそれを燃やすことは、(彼や彼女のその行為は世間からの生暖かい顰蹙を間違いなく浴びるにせよ、その行為に対して)刑事処罰が課されるわけでも民事的・行政的な制裁を受けるわけでもなく、また、その所有者の非常識な行為に対して誰も差し止め請求などもできないという意味では彼や彼女の自由であり、そのような状況にあることを「権利」と呼ぶのであれば、(どの調査を見ても、国旗侮辱行為を禁止する条項を加える連邦憲法の改正を国民の60%前後が一貫して支持している、あるいは、そのような憲法改正条項に上下両院の全議員の70%から60%が一貫して賛成票を投じているアメリカに比べて)日本こそ「国旗を燃やす権利が確立している社会」と言えるでしょう。
また、West Virginia State Board of Education v. Barnetteでは被上告人は、本稿で紹介するAP配信記事の話題の中心である「忠誠の誓い:the Pledge of Allegiance」を巡り、公立学校内で国旗への敬礼を自身の信仰に基づき拒否したことにより退学処分を受けたケースであり、おそらく、被上告人が受けた社会的制裁の大きさと「忠誠の誓い」を公立学校で生徒達に斉唱させることがもたらす社会的利益を比較衡量すれば、日本の保守派の少なからずもまた支持はしないまでも同連邦最高裁判決を是認する事例ではないかと思います。
だって、非常識かもしれないけれど間違いなく健気なBarnetteちゃん、彼女には級友が「忠誠の誓い」を斉唱している間は別室で『あしながおじさん』や『続・あしながおじさん』、または、『おちゃめなパティ』(★)でも黙読させておけばアメリカ憲法の勉強とアメリカに根付く保守主義の涵養にも役立つ上に、そうしても本人にも級友にも社会にも特に害はなかったのではないか。そうではありますまいか、ありますまいか。
★註:『あしながおじさん』に刻まれているアメリカ憲法の神髄と変遷
19世紀末から20世紀初葉のアメリカ社会を舞台にしている、ウェブスターの『おちゃめなパティ大学に行く:When Patty Went to College』(1903), 『おちゃめなパティ:Just Patty』(1911), 『あしながおじさん:Daddy-Long-Legs』(1912), 『続・あしながおじさん:Dear Enemy』(1915)等の作品は、その全作品に(その後、1920年に発効した合衆国憲法修正19条が保障する)女性参政権付与に対する賛意、あるいは、犯罪者に遺伝的や資質的な犯罪を起こす傾向を認める当時流行の近代学派の刑罰理論への賛意が記してあります。
加之、(裁判所に提出されたその被上告人側の準備書面が、後に「Brandeis Brief」として有名になるのですが、「連邦や州は、正当な立法目的と妥当な立法事実があれば、社会的規制や経済的規制を行い個人の財産権や契約の自由を制限できるのかどうか」という、当時のアメリカで最大級の憲法問題の各論と位置づけられる)女性労働者の健康維持を立法目的とする、洗濯業者に雇用された婦人の労働時間を1日10時間に制限するオレゴン州の州法が連邦憲法のデュープロセス条項(修正5条および14条)が保障する「個人間の契約の自由」の不当な制限であるかどうかが争われた「Muller v. Oregon, 208 U.S. 412 (1908)」を俎上に載せている(cf. Just Patty, chapter 3)等々、『あしながおじさん』を含むウェブスター女史の作品は、当時のアメリカでは政治小説とまでは言わないけれど間違いなく作者の政治的主張を露わにした<憲法>をも射程に入れた社会派の小説だったのだと思います。
<続く>



















