
しばしば、「民主主義」という言葉はmagic wordと呼ばれます。つまり、北朝鮮の国名が「朝鮮民主主義人民共和国」であるというブラックジョークに端的なように、この言葉は、大凡、ありとあらゆる政治的な事象を正当化することが可能な、よって、内容空虚な言葉である、と。而して、「民主主義」を巡るこの経緯は、最近の日本では「立憲主義」や「法の支配」についても言えること、逆に、プラスイメージではなくマイナスイメージの貼り付けという点で180度異なるものの「ナショナリズム」や「右翼」についても言えること、鴨。
このような、「民主主義」「立憲主義」「法の支配」という言葉に憑依するイメージの拡散--言語の指示対象の膨張、すなわち、概念の外延の拡大--、逆に言えば、意味内容および概念の内包の希薄化について考えていたとき、正に、その傾向の好例を目にしました。些か、旧聞に属するものですが今年2014年1月3日の朝日新聞の社説。これです。
▽「1強政治」と憲法 「法の支配」を揺るがすな
安倍首相が最近よく使う言葉に、「法の支配」がある。中国の海洋進出を念頭に「力による現状変更ではなく、法の支配によって自由で繁栄していく海を守る」という具合だ。「法の支配」とは何か。米国の政治学者フランシス・フクヤマ氏は、近著「政治の起源」でこう説明している。
「政治権力者が、自分は法の拘束を受けていると感じるときにのみ、法の支配があるといえる」
この「法」は、立法府がつくった制定法とは違う。近代以前は、神のような権威によって定められたルールと考えられていた。法と制定法の違いは、現代でいえば憲法と普通の法律の違いにあたるという。
今年、安倍首相は「憲法9条改正」に挑もうとしている。ただし、憲法96条の改正手続きによってではない。解釈の変更によるのだという。最高法規の根幹を、政府内の手続きにすぎない解釈によって変える。これは「法の支配」に反するのではないか。・・・
(以上、引用終了)
この朝日新聞社説の「法の支配」理解のどこがおかしいのか。
それは以下の3点。すなわち、
(Ⅰ)有権解釈者がその権限の範囲内で「最高法規の根幹を、政府内の手続きにすぎない解釈によって変える」ことは毫も「法の支配」にも反するするものではない
(Ⅱ)フクヤマ氏が述べている通り、「政治権力者が、自分は法の拘束を受けていると感じるときにのみ、法の支配がある」、そして、「この「法」は、立法府がつくった制定法とは違う。近代以前は、神のような権威によって定められたルールと考えられていた。法と制定法の違いは、現代でいえば憲法と普通の法律の違いにあたる」ということは満更間違いではないとしても、しかし、ここで言われている「憲法」は必ずしも「憲法典」に限られるわけではなく、憲法慣習や憲法の事物の本性を包摂するより広汎な規範であること
(Ⅲ)安倍総理は、支那の強面の対外進出傾向や韓国の国際法を無視した対日批判を牽制すべく、国際政治における「法の支配」を掲げているのであって、ならば専ら国内法を念頭に置いた「法の支配」の理解からその用語使用の整合性を論じるのは適当ではない
いずれにせよ、朝日新聞のこの社説は、「法の支配」をmagic word的に用いた安倍総理批判のためにする議論であり、それは<騙し絵>的の詐術を弄した揚げ足取りにすぎない。と、そう私は考えます。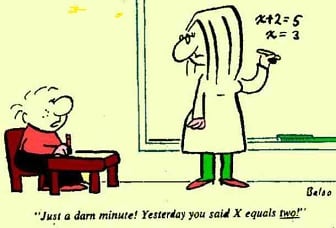
ある言葉をどのような意味に用いるかはかなりの程度論者の自由に属すること。けれども、議論をより生産的かつ建設的にしようとするのならば、論者は、その使用する言葉を一般的に用いられている語義--その議論がある専門領域に属するのならば、その専門領域の専門家コミュニティーで普通に受け取られる語義--で用いるか、そうでない場合にはその都度自前の定義を施した上で用いる心配りが肝要ではないかと思います。
而して、「法の支配」とはどのような意味が憑依する言葉なのか。人口に膾炙しているように、中世以来の伝統を持つこの法理念に彫琢を施しある程度明確な輪郭を与えたのはDicey『イギリス憲法序説:Introduction to the study of the law of the constitution』(1885)であり、Diceyは次の3個の特徴的性質を抽出して「法の支配」、より正確に言えば<法の支配>が貫徹している英国法を称揚しました。すなわち、「正当な法」(regular law)をコモンロー裁判所およびエクイティー裁判所といった通常裁判が発見し適用してきた法規範の蓄積のこととすれば、
(1)人治すなわち専断的ではない正当な法の絶対的な優位性
(2)正当な法の前の平等、よって、行政裁判所の否定
(3)憲法もまた通常裁判所の判例の蓄積の結果形成されること
注意すべきは、Diceyは、英国以外の実定法秩序に「法の支配」が見いだされるなどとは露程も述べてはいないこと。よって、「正当な法」の意味内容に「通常裁判が発見し適用してきた法規範」という以上の内容を、例えば、「天賦人権」なりを、かつ、英米法の伝統を超えて読み取るのは「法の支配」の理念に対する過大なクレーム(要求)であり、贔屓の引き倒しの類の暴論であろうと思います。
ならば、少なくとも、(Ⅰ)有権解釈者がその権限の範囲内でする、例えば、占領憲法9条の「自衛権」の意味内容の変更の禁制などを「法の支配」から導くなどは--国会主権の原則(sovereignty of Parliament)が認められる英国ならずとも--不可能と言うべきでしょう。尚、「法の支配」の意味については下記拙稿もご参照いただければ嬉しいです。
・憲法における「法の支配」の意味と意義
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/5a21de3042809cad3e647884fc415ebe
私は、Diceyが抽出した「法の支配」の意味などは、それを英米法の伝統と制度から切り離すとき、カントが『永久平和のために:Zum Ewigen Frieden』(1795)の「国家間の永久平和のための確定条項」の第1確定条項で記した内容、すなわち、永久平和の実現のためには「各国家における市民的体制は、共和的でなければならない」、而して、その<共和的な憲法体制-国家体制>とは次のようなものであるとした内容と親しいのではないか。(一)と(1)、(二)と(2)、(三)と(3)は通底してるのではないか、と。そう考えないではありません。
一、社会の成員が自由であること
二、社会のすべての成員が、唯一にして共同的な立法に(臣民として)従属する
三、社会のすべての成員が(国民として)平等
「臣民が国民ではないような体制、つまり、共和的ではない体制においては、戦争はまったく慎重さを必要としない世間事であるが、それは元首が国家の成員ではなくて、国家の所有者であるからである」「共和的とは立法権と執行権の分離を国家原理とする体制であり、他方、専制的とは国家がみずから与えた法を専断的に執行することを国家原理とする、よって、公共的意志といっても、それは統治者の私的な意志にすぎない体制である」ならば「民衆制は必然的に専制的にならざるを得ない。なぜならば、そこでは全員ではない全員が決議できるから。つまり、代表制ではないすべての統治形態は、元来奇形である。それは立法者が同一の人格において同時にかれの意志の執行者であることができるからである」、と。
而して、「法の支配」の意味を英米法の伝統から切り離すとき、現在ではその意味内容は「立憲主義」の意味内容--事前に制定された憲法に沿った国家権力機構の形成編成と国家権力の行使、および、国家権力によっても侵害されるべきではない一群の権利内容の存在の前提の主張--とかなりの程度重なっていると言える、鴨。そして、通常裁判所の機能を重視する元来の<法の支配>からも、また、現実的には、権利は憲法の具体的な権利条項の解釈の蓄積を通して具現されるべきだとするならば、「法の支配」という言葉には最早国内法的には特に大きな存在意義はないの、鴨。
畢竟、「立憲主義」によって国家権力からも社会の多数派の嫌悪からも守護されるべき権利の存在根拠として--天賦人権論そのもからではなく--、「比較不可能な価値」を担保する権利については誰も誰からも侵害されるべきではないこと、なぜならば、近代国家はそのような「私的領域に本籍を置く価値」を巡る紛争には容喙する権限は与えられていないからだとする長谷部恭男さんが、夙に、
「法の支配」とは「理性的な人々の行動を規制するために法が備えるべき性質」の一つであり、「国家機関の行動を一般的・抽象的で事前に公示される明確な法によって拘束することにより、国民の自由を保障しようという理念」である(『比較不能な価値の迷路』(東京大学出版会)p.149;『憲法』(新世社)p.21)と述べていること。
具体的には、法に関して、①一般性・抽象性、②公示、③明確性、④安定性、⑤相互に無矛盾であること、⑥遡及の禁止、⑦国家機関が法に基づいて行動するように、独立の裁判所のコントロールが確立していることが「法の支配」の内容となり(長谷部ibid)、一言で言えば、「法の支配=適正手続(due process)」であると理解されているのは正しい指摘、鴨。
なるほど、この意味の「法の支配」はそれがなければ憲法が憲法として、法が法として機能しないという意味でそれは憲法および法の「事物の本性」から論理的に演繹される憲法原理と言えると思うから。ならば、朝日新聞の社説は、「法の支配」の理念を--端的には、フクヤマ氏が憲法典に限定していない「権力制約の限界と根拠」を--故意か過失か、意図的に占領憲法典に限定しており、他方、逆に、権利規定ではない統治行為規定にまで拡大する憲法論的誤謬を犯している。
すなわち、(Ⅱ)「法の支配」に言う「法」は必ずしも「憲法典」に限られるわけではないこと--国家の安全保障の確保をも要請する「法」であること--が理解できていない、他方、「法の支配」も「立憲主義」も国家権力の制約根拠のみならず正当化根拠でもある一面を看過したものではないか。と、この社説を私はそう評価します。
最後に、(Ⅲ)支那の海洋進出を念頭にした「力による現状変更ではなく、法の支配によって自由で繁栄していく海を守る」という安倍総理の発言は--例えば、実際、世界の20数カ国がそうしいているように、それが他国の領空を覆うものであるにせよ、単なる「防空識別圏」の設定は各国の自由でしょうが、その識別圏を飛行する他国の民間航空機に飛行計画書を提出させるなどの「領空」の一方的変更に等しい所行を平気で行うような--、支那や韓国の国際法を無視した対日策動を牽制すべく、国際政治にける「法の支配」を述べたもの。
ならば、専ら国内法を念頭に置いた「法の支配」の理解から、安倍総理のこの言葉の用法について整合性を論じるのは適当ではない。実際、安倍総理はこう述べておられるのですからね。
ASEANと日本を包摂するこの地域の平和と安定を維持する上で、総体としてのASEANにとって、自由、民主主義および人権、ならびに、法の支配といった死活的に重要かつ基本的な諸価値を確保し深化することが極めて重要であることは言うまでもありますまい。
(安倍首相、アジアについて語る「ASEANと日本の将来像」,
The Japan News, Dec., 13, 2013)
ならば、国際法と確立された国際政治の慣習を遵守することを指して「法の支配」と呼んでいる安倍総理の地球儀俯瞰的外交戦略を曲解した上で、集団的自衛権の解釈変更と支那や韓国を批判することを「法の支配」に関する矛盾と捉える朝日新聞の理解は姑息かつ杜撰な批判ではなかろうか。と、そう私は考えます。
福岡県JR大牟田駅前の2014年1月3日早朝の風景



















