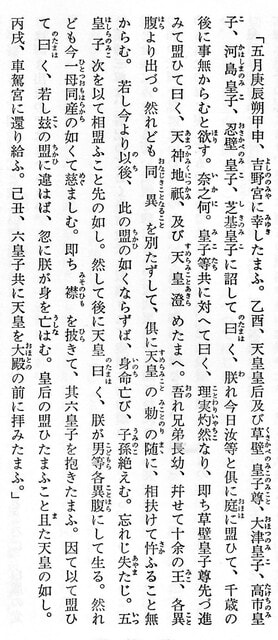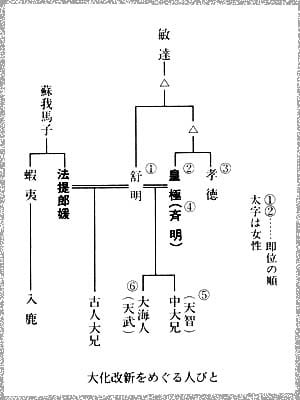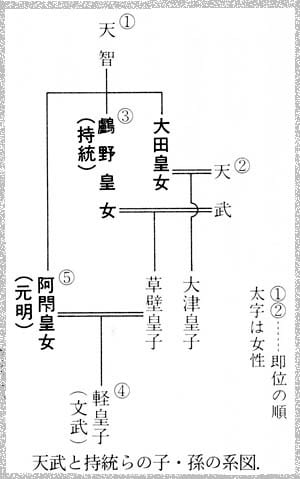NHKラジオ『古典講読』、「歌と歴史でたどる『万葉集』28」より
万葉集には、地方の伝説を詠んだ長歌がある。その一つが、
高橋虫麻呂の長歌、菟原処女(うないおとめ)伝説。
摂津国菟原(うない:現在の芦屋から神戸市東灘区辺り)にいた菟原処女(うないおとめ)は、たいそう美人だった。
たくさんの男が集まってきたが、中でも、菟原壮子(うないおとこ)と血沼壮子(ちぬおとこ)は、競り合って求婚した。
菟原処女は、「自分のために2人が戦っていることを嘆く」と母親に告げ、あの世へ去っていった。
夢でそのことを知った血沼壮子は後を追い、
それに遅れた菟原壮子も負けじと後を追った。
3人が死んでしまったことに親族は悲しんで、処女墓(おとめはか)を真ん中に、
その東と西に壮子墓(おとこはか)を造った。
今の私たちには理解できないこと2つ。
「あの世へ行く」と告げる娘を、母親が送り出したこと。
「夢は異界との間をつなぐもの」らしく、あの世で娘に会えること。
伝説なので、そーですか、じゃないと、話は続かない。
ところで、この墓は現存する。
大阪と神戸の間の海岸近く、阪神電車沿線に、2キロ弱の間隔で3基ある古墳で、
真ん中にあるのが、「処女塚(おとめづか)古墳」、3世紀後半の築造、
全長70mの前方後円墳。
その東にあるのが、「東求女塚(ひがしもとめづか)古墳」、4世紀後半か。
全長80mくらいの前方後円墳だったが、今は形を成してない。
西にあるのが「西求女塚(にしもとめづか)古墳」、3世紀後半の築造。
墳丘98㎡の方墳であったが、今は前方後円墳に整備された。
これらは地元の豪族がよく目立つように作ったが、200~300年も経てば、分からなくなったことだろう。
そして、3基の古墳の由来を語るものとして、「死んで愛を成就する物語」が、創作された。
「語り継ぎ、言い継ぎゆかん」の奈良時代の精神により、長歌に残したのだろう。
ここからは、私見。
古墳は、豪族が自分の権勢を誇示するため造った。
巨大な石で石室を作り、土を盛り、石で固め、埴輪で飾った。
しかし時が経つと、誰の墓かは分からなくなる。
(文字はなかった)
石は別の用途にされ、埴輪は砕け。積み上げた土は流れてしまった。
飛鳥の石舞台古墳がその姿になっている。
ウチの近くにも、古墳がある。
草木に覆われて、中に入る気はしないけど。

万葉集には、地方の伝説を詠んだ長歌がある。その一つが、
高橋虫麻呂の長歌、菟原処女(うないおとめ)伝説。
摂津国菟原(うない:現在の芦屋から神戸市東灘区辺り)にいた菟原処女(うないおとめ)は、たいそう美人だった。
たくさんの男が集まってきたが、中でも、菟原壮子(うないおとこ)と血沼壮子(ちぬおとこ)は、競り合って求婚した。
菟原処女は、「自分のために2人が戦っていることを嘆く」と母親に告げ、あの世へ去っていった。
夢でそのことを知った血沼壮子は後を追い、
それに遅れた菟原壮子も負けじと後を追った。
3人が死んでしまったことに親族は悲しんで、処女墓(おとめはか)を真ん中に、
その東と西に壮子墓(おとこはか)を造った。
今の私たちには理解できないこと2つ。
「あの世へ行く」と告げる娘を、母親が送り出したこと。
「夢は異界との間をつなぐもの」らしく、あの世で娘に会えること。
伝説なので、そーですか、じゃないと、話は続かない。
ところで、この墓は現存する。
大阪と神戸の間の海岸近く、阪神電車沿線に、2キロ弱の間隔で3基ある古墳で、
真ん中にあるのが、「処女塚(おとめづか)古墳」、3世紀後半の築造、
全長70mの前方後円墳。
その東にあるのが、「東求女塚(ひがしもとめづか)古墳」、4世紀後半か。
全長80mくらいの前方後円墳だったが、今は形を成してない。
西にあるのが「西求女塚(にしもとめづか)古墳」、3世紀後半の築造。
墳丘98㎡の方墳であったが、今は前方後円墳に整備された。
これらは地元の豪族がよく目立つように作ったが、200~300年も経てば、分からなくなったことだろう。
そして、3基の古墳の由来を語るものとして、「死んで愛を成就する物語」が、創作された。
「語り継ぎ、言い継ぎゆかん」の奈良時代の精神により、長歌に残したのだろう。
ここからは、私見。
古墳は、豪族が自分の権勢を誇示するため造った。
巨大な石で石室を作り、土を盛り、石で固め、埴輪で飾った。
しかし時が経つと、誰の墓かは分からなくなる。
(文字はなかった)
石は別の用途にされ、埴輪は砕け。積み上げた土は流れてしまった。
飛鳥の石舞台古墳がその姿になっている。
ウチの近くにも、古墳がある。
草木に覆われて、中に入る気はしないけど。