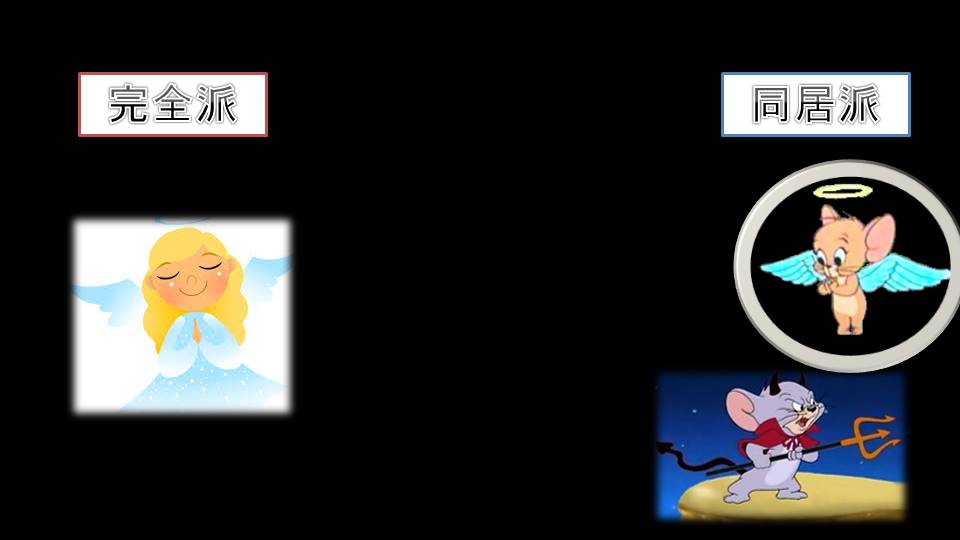2016/12/11 ハイデルベルグ信仰問答44「最も激しい試みの時にも」詩篇一三九1-12
イエスのお誕生を祝う、嬉しく明るいクリスマスには、暗く悲しい十字架の死をお話しすることは不釣り合いなのでしょうか。いいえ、少し前、夕拝で先にイエスの誕生についてお話ししたように、神である主イエスが人としてお生まれになった事自体、限りない謙りでした。イエスがこの世に降られたのは、十字架の死という恥辱にまで降るためでした。そして「使徒信条」では「死にて葬られ、陰府に降り」と言うのです。
問44 なぜ「陰府にくだり」と続くのですか。
答 それは、わたしが最も激しい試みの時にもこのように確信するためです。すなわち、わたしの主キリストは、十字架上とそこに至るまで御自身の魂に受けてこられた言い難い不安と苦痛と恐れとによって、地獄のような不安と痛みからわたしを救い出してくださったのだ、と。
この「陰府」とは英語では「hell」という言葉ですが、「ヘル」だと「地獄」という意味もありますね。地獄とは、聖書の原語では
「ゲヘナ」
と言います。それは、神様が世界の歴史の最後にすべてを裁かれた時、神に逆らう人々を追いやる「永遠の滅び」の場所です。いつまでも燃える火で表現されるような、完全に神様から捨てられた、永遠の状態です。けれども、hellにはもう一つの意味があります。それが「よみ」です。こちらは「ゲヘナ」ではなく、ギリシャ語で
「ハデス」
ヘブル語で
「シェオル」
と言います。それは、死んだ後、すぐに人の魂が行って、復活の日までを過ごす、一時的な状態です。それは、永遠の苦しみの地獄(ゲヘナ)とは違います。「死者の国」とも違います。そこは、いわば終わりの日までの待合所です。永遠でもなければ、火や苦しみとも結びつけられていません。まずこの言葉を整理しておきましょう。
主は
「陰府に降り」
ました。「地獄に行かれた」のではありません。イエスが地獄に行かれたと考えてしまうと大違いになります。死者の国に行ったと考えても、可笑しくなってしまいます。今日のハイデルベルグ信仰問答は、そういう誤解がないように、本当に死に至るまでの苦しみを味わわれたのだ、ということに集中するような解説をしてくれていますね。「陰府に降られたとはどういうことだろう?」とあれこれ想像を逞しくするよりも、本当に死んでくださって、死の後の人間の魂が陰府に行くように、キリストも徹底して人間として死んでくださったのです、ということに絞っています。
…それは、わたしが最も激しい試みの時にもこのように確信するためです。すなわち、わたしの主キリストは、十字架上とそこに至るまで御自身の魂に受けてこられた言い難い不安と苦痛と恐れとによって、地獄のような不安と痛みからわたしを救い出してくださったのだ、と。
陰府とはどこか、どんな場所か、という詮索をしなくて良いのです。むしろ、イエスの御生涯で
「言い難い不安と苦痛と恐れと」
を受けて下さったのです。それは
「地獄のような不安と痛みから私を救い出してくださった」
御生涯でした。だから、私たちが
「最も激しい試みの時にも」
確信をもって、慰めを戴いて、歩むことが出来るのです。そして、死においても、イエスが先立って死んでくださったのだからと、私たちは魂をイエスにお委ねすることが出来るのです。そう考えると「陰府にくだり」という言葉がとても親しく、すばらしく、私の心に響いてくるようになります。
今日の詩篇一三八篇にはこんな言葉がありましたね。
8たとい、私が天に上っても、そこにあなたはおられ、私がよみに床を設けても、そこにあなたはおられます。…
11たとい私が「おお、やみよ。私をおおえ。私の回りの光よ。夜となれ」と言っても、
12あなたにとっては、やみも暗くなく夜は昼のように明るいのです。暗やみも光も同じことです。
私が天に昇っても陰府に降っても、どちらにも神は私とともにおられる、というのです。私たちは、もうすっかり生きていくのが嫌になったりやけくそになったりして「闇よ、私を覆え」と叫ぶ時があるかもしれません。でも、そこでも神は私とともにいてくださいます。
イエスの御生涯で有名な言葉の一つは、十字架上で
「我が神、我が神。どうしてわたしをお見捨てになったのですか」
と叫ばれた言葉です。あの意味もまた深いのですけれども、今日一つだけ言いたいのは、イエスは神に見捨てられてくださいました。それは、すでに陰府や地獄にも等しい、恐ろしい体験でした。神に見捨てられることがどれほど暗く、所在なく、ゾッとすることか、私たちの想像を遙かに超えています。イエスは私たちのために神に見捨てられました。それゆえ、私たちは自分が神に見捨てられたように思う時にも、その自分の孤独や絶望を、イエスが私たちに先立って味わって下さったことを知らされています。イエスは、神から見捨てられたような時にも私たちとともにいてくださいます。つまり、イエスが私のために神に見捨てられる体験をしてくださったので、私たちは神に見捨てられることは決してないのです。
…私たちは最も激しい試みの時にもこのように確信する…私の主キリストは、十字架上とそこに至るまで御自身の魂に受けてこられた言い難い不安と苦痛と恐れとによって、地獄のような不安と痛みからわたしを救い出してくださったのだ、と。
「不安と痛みから…救い出してくださった」
とは言っても、不安や痛みを全く体験しないで済む、という事ではありません。また、不安や痛みが直ぐになくなる、ということでもありません。
「最も激しい試み」
が私たちを襲う時はあるのです。しかし、そのような時に地獄のような不安と痛みを味わいつつも、その中で、イエスが私のために陰府にまで降るほどの低い思いを既に味わってくださったのだから、私は決して独りではない。神に見捨てられたのではない。神は、私とともにおられ、不安と痛みをともにしていてくださる。だから必ず希望はあるという確信を持つことが出来るのです。
クリスマスのイエスのお誕生は、既にその事の証しでした。私とともにいるためにイエスは貧しく低く生まれてくださいました。そして、人生の全ての不安や恐れや痛みも、死後の魂の状態までも全て私たちのために、味わい知っておられるのです。イエスは私たちとともにおられます。たとえ、神に見捨てられたり、地獄のような苦しみや、死んだほうがましのような虚しさに襲われたとしても、そこにも主イエスはともにおられます。それゆえ、私たちはもう陰府や地獄の恐れから救い出されているのです。