
[1] 「善行」ディカイオシュネー。5:6、10、20、6:33と続く、山上の説教の主要テーマ。
[2] 6章33節。
[3] 6章1節の冒頭には、接続詞δὲがあり、前節との連続性が明示されています。それは、もはや自分を義としようとしない、見られることを求めず、神に向かう生き方そのものの「義」です。人に見せるために善行を行うことは、実質的に、信仰による神の義を受けようとするのではなく(それだけでは足りないとして?)自分の行為によって自己義を立てようとする不信仰です。パリサイ人や律法学者にまさる義とは、神の前に生きる義であり、人の前に、人との比較の基準ではなく、見えない神の前に-完全な義を生きて、私たちの隠れたところを見ている神の前に-生きる義なのです。
[4] 「ラッパを吹き鳴らす」 ユダヤの「ラッパの祭り」や「安息年」「ヨベルの年」レビ記23章23-42節、25章、民数記29章1節、出エジプト記21章1-6節など。負債の解放のラッパが、金持ちたちには善行の計算になったろう。
[5] 5章16節。
[6] 「ほめてもらおうと」 ドクサゾー。5:16、父をあがめる、と言われていたのに、自分をドクサゾーすることが目的に。9:8、15:31「神をあがめた」
[7] 「報い」 5:12、16、6:1、2、5、16、10:41、42、20:8。「報いを望まで人に与えよ」という歌(賛美歌536番)もありますが、イエスは「報い」をハッキリと仰います。あの賛美歌も「水の上に落ちて流れし種も何処の岸にか生い立つものを」と、自分のしたことの報いが将来にあることで励ましているのです。
[8] とはいえ、人に見せるためにしない、というのはとても難しいことです。見られることを意識して、どう見られるかを考えます。考えていないと言っていても、人からほめられれば嬉しいし、ケチを付けるような事を言われたら腹が立つものです。それを意識するな、と言われれば、ますます難しくなります。
[9] 単純に文字通りとしては、「隠れた」思いは次の手を使うでしょう。右手のしていることを隠している事自体を自慢することがあります。それを人にではなく、自分に誇ることもあるでしょう。また、自分のしてきたことを自分の善行として、他者からの評価・報いを求めていることがあります。それは、地上で報いを求めることであって、神の報いは得られないのですが…。教会の中で、「お返し」を求める生き方をしない。「お返し」を礼儀とする文化を教会に持たない、ということも大事だと思っています。
[10] 「右の手」には、単なる左右ではない、「義の業」のニュアンスがあります。ここから、マルチン・ルターは「右の手の罪」(義を装った自己中心)という言い方をしています。カンタベリーの大司教の言葉「恩寵とは自分を忘れること、自分を笑うことの出来る人間になることである」が思い出されます。
[11] ローマ2章16節「私の福音によれば、神のさばきは、神がキリスト・イエスによって、人々の隠された事柄をさばかれるその日に行われるのです。」
[12] この「報い」は、なした行為への正当な「刈り取り」という事でしょう。2節の「偽善者」は自分が誉められることを求めているので、それが「自分の報い」なのですが、神からの報いは、行為によって人格を評価するものではありません。神は私たちを既に神の子どもとしてこの上なく愛してくださっています。行為が人格への評価を決める、という発想そのものが、神ではなく、偽善的なものです。神が下さる報いは、その行いそのものへの正当な結果でしょう。
[13] ティモシー・ケラー『「放蕩」する神』の中に、「もし神の恵みが十分感じられないとしたら、最もしてはならないのは、奉仕や活動によって、その不完全さを満たそうとすることです」というような一文があったと記憶しています。が、確認できませんでした。
[14] 25章21節、23節。
[i] style="'margin-top:0mm;margin-right:0mm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:9.0pt;text-indent:-9.0pt;font-size:12px;"Century","serif";color:black;background:white;'>[ii] 「「天、共に在り」本書を貫くこの縦糸は、我々を根底から支える不動の事実である。やがて、自然から遊離するバベルの塔は倒れる。人も自然の一部である。それは人間内部にもあって生命の営みを律する厳然たる摂理であり、恵みである。科学や経済、医学や農業、あらゆる人の営みが、自然と人、人と人の和解を探る以外、我々が生き延びる道はないであろう。それがまっとうな文明だと信じている。その声は今小さくとも、やがて現在が裁かれ、大きな潮流とならざるを得ないだろう。これが、三十年間の現地活動を通して得た平凡な結論とメッセージである。」前掲書、246頁、本文結びの言葉。
[iii] style="'margin-top:0mm;margin-right:0mm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:9.0pt;text-indent:-9.0pt;font-size:12px;"Century","serif";color:black;background:white;'>[iv] 澤地 久枝、中村哲共著『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る――アフガンとの約束』岩波書店、2010年。
[v] 中村『天、共に在り』、5頁。
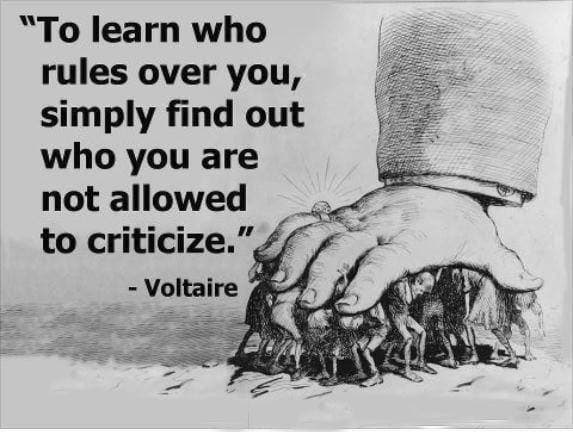


[1] ルカ2章29~32節
[2] style="'margin-top:0mm;margin-right:0mm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:7.0pt;text-indent:-7.0pt;font-size:12px;"Century","serif";color:black;'>[3] その他、6章7~11節「律法学者たちやパリサイ人たちは、イエスが安息日に癒やしを行うかどうか、じっと見つめていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。8イエスは彼らの考えを知っておられた。それで、手の萎えた人に言われた。「立って、真ん中に出なさい。」その人は起き上がり、そこに立った。9イエスは彼らに言われた。「あなたがたに尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは、善を行うことですか、それとも悪を行うことですか。いのちを救うことですか、それとも滅ぼすことですか。」10そして彼ら全員を見回してから、その人に「手を伸ばしなさい」と言われた。そのとおりにすると、手は元どおりになった。11彼らは怒りに満ち、イエスをどうするか、話し合いを始めた。」、9章46~48節「さて、弟子たちの間で、だれが一番偉いかという議論が持ち上がった。47しかし、イエスは彼らの心にある考えを知り、一人の子どもの手を取って、自分のそばに立たせ、48彼らに言われた。「だれでも、このような子どもを、わたしの名のゆえに受け入れる人は、わたしを受け入れるのです。また、だれでもわたしを受け入れる人は、わたしを遣わされた方を受け入れるのです。あなたがた皆の中で一番小さい者が、一番偉いのです。」
[4] 榊原康夫『ルカ福音書講解1』、395頁。
















