
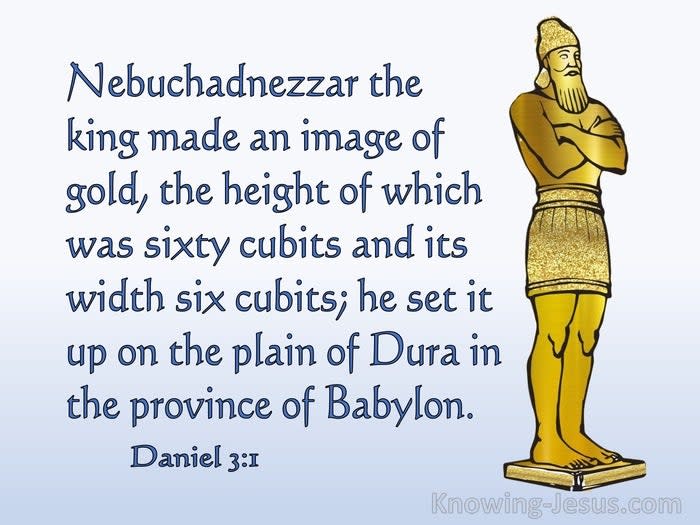







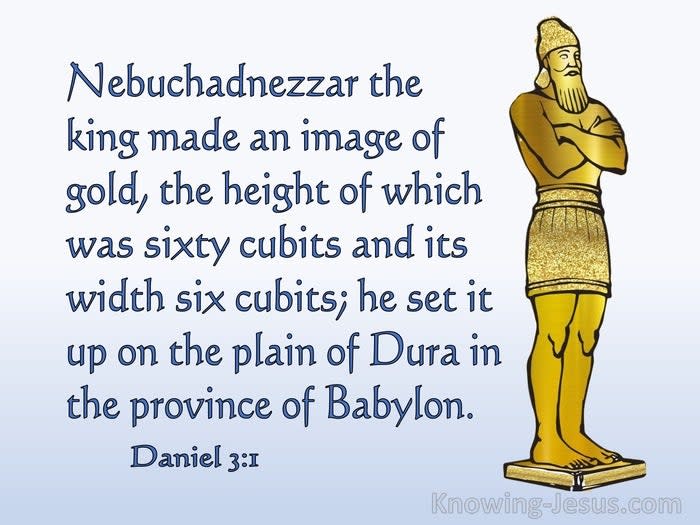






[1] 出エジプト記10章21節「主はモーセに言われた。「あなたの手を天に向けて伸ばし、闇がエジプトの地の上に降りて来て、闇にさわれるほどにせよ。」22モーセが天に向けて手を伸ばすと、エジプト全土は三日間、真っ暗闇となった。」、アモス書8章9節「その日には、──神である主のことば──わたしは真昼に太陽を沈ませ、白昼に地を暗くする。10あなたがたの祭りを喪に変え、あなたがたの歌をすべて哀歌に変える。すべての腰に粗布をまとわせ、頭を剃らせる。その時をひとり子を失ったときの喪のように、その終わりを苦渋の日のようにする。」
[2] ルカやヨハネを見ると、十字架の上でイエスは七回の言葉を残していますが、マタイとマルコが記すのはこの「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」だけです。
[3] 詩篇22篇1節「わが神 わが神 どうして私をお見捨てになったのですか。 私を救わず 遠く離れておられるのですか。 私のうめきのことばにもかかわらず。」
[4] マタイの福音書5章17節。
[5] 12章6節、8節。
[6] 「聖なる人々」ハギオス マタイで10回使われますが、他の九回は「聖霊、聖なる都」です。本節以外、聖徒と訳される場所はなく、どう訳したらいいのかさえ、定かではありません。
[7] この「聖なる人々」とは誰なのか、旧約の預言者たちであればなぜ名前がないのか、彼らはイエスの復活まで何をしていたのか、その後、どうなったのか、などなど好奇心は尽きません。
[8] 1章21節「マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。」
[9] 「マグダラのマリア」は有名ですが、マタイではここで初。61節、28章1節と合わせて3回のみ。ガリラヤからついてきて、今まで無名だったが、イエスの十字架と、埋葬と、復活の証人となった、ということだけ。







[1] 29、37、42。他の多くの語が、ここだけなのに対して「王バシリュース」は、マタイに22回も繰り返されるキーワードです。(マルコ12,ルカ11、ヨハネ16)
[2] 35節で、兵士は「くじを引いてその衣を分けた」とあります。ヨハネの福音書でははっきりと「さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに織った、縫い目のないものであった。」と伝えます(19章23節)。つまり、十字架の主は裸でした。これは当時の十字架刑の通例で、肉体の激痛もさることながら、裸、さらしもの、放っておかれる精神的苦痛こそ、十字架刑の特徴とも言われます。イエスを描く十字架の多くの絵は気が引けて、イエスの腰はどうにか覆っていますが、実際は真っ裸だったのです。文字通り「裸の王さま」、あのお話し以上に本当に「裸の王さま」だったのです。
[3] マントは薄汚れたものでしょうし、太くて長い棘のある茨をわざわざ編んだ冠も、葦の棒も、虐めでしかありません。
[4] 「使徒の働き」13章1節に「ニゲルと呼ばれているシメオン」が、アンテオケ教会の主要メンバーの一人として登場します。この「シメオン」と、クレネ人シモンが同一人物ではないか、という読み方も可能です(断言は誰にも出来ません)。それはともかく、「ニゲル(ニグロ≒黒人)」と呼ばれるとある通り、肌の色が違うことは、当時からも大きな差別だったのでしょう。ここでも、黒人であったシモンを、兵士たちがイエスの十字架を担う役割に無理やりあてがったのは、人種への偏見・蔑視であったことは筋が通ります。
[5] キリストの救いは完全だ。しかし同時に、クレネ人シモンにも助けられた十字架でもある。私たちの助けを必要とはされないが、私たちの働きもそこに関わり、私たちも巻き込まれて、キリストのわざは完成されるのだ。コロサイ書1章24節「今、私は、あなたがたのために受ける苦しみを喜びとしています。私は、キリストのからだ、すなわち教会のために、自分の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。」という大胆ないい方さえ、パウロはしています。人の労苦は、キリストの苦しみにあずかり、確かな役を果たすことです。クレネ人シモンはそのような人の苦難の一面を思わせてくれます。そして、巻き込まれることによって、彼は恐らく、後にキリスト者となりました。だからこそ、名前が伝えられているのでしょう。
[6] Ⅰコリント1章23~24節。同様の表現は、ガラテヤ書3章1節「ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストが、目の前に描き出されたというのに、だれがあなたがたを惑わしたのですか。」にあります。文語訳では「十字架につけられ給いしままなるイエス・キリスト」と明確です。
[7] 昨年召天された、日本長老教会の教師、故村瀬俊夫氏が、この言葉を最初に教えてくれた恩師です。立川福音自由教会のHPで、同氏と「十字架につけられたままのキリスト」のことが触れられていたので、以下、引用します。「村瀬俊夫先生は、ガラテヤ3章1節の文語訳の「愚かなるかな哉、ガラテヤ人よ、十字架につけられ給いしままなるイエス・キリスト、汝らの眼前に顕されたるに、誰が汝らをたぶらかししぞ」という表現を見て、キリスト理解が変わったと言っておられました。それは、既に復活されたキリストが、同時に今も、「十字架につけられたままである」という途方もない逆説です。私たちはあまりにも働きの成果のようなもの(栄誉)に目が向かって、弱さや苦しみ(十字架)の中にある恵みを忘れてしまいがちです。しかし、キリストの苦しみは今も続いており、それによって世界が平和の完成へと導かれているのです。ですから私たちも、キリストとともに十字架につけられたままでいるべきなのです。それは、この世的には恥と敗北ですが、そこに真の神の力が働きます。パウロはキリストについて、「確かに、弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力ゆえに生きておられます。私たちもキリストにあって弱い者ですが、あなたがたに対する神の力のゆえに、キリストとともに生きているのです」(Ⅱ13:4)という不思議なことを言っています。十字架につけられたままのキリストの「弱さ」こそが、弱肉強食の世界秩序を変える鍵なのです。私たちも自分の能力や力を誇るのではなく、私の中に生きておられるその方によって生きるのです。「全能の神を信じているのに、どうして、こんな目に会ってしまうの・・・」というのは人情としてはわかりますが、聖書の物語からしたら「愚問」です。私たちはキリストとも共に苦しむために召されたのだからです。」ゼパニア2章4節〜3章20節「主は喜びをもってあなたのことを楽しみ……」
[8] 黙示録でもキリストは「ほふられたと見える小羊」として登場します。5章6節(また私は、御座と四つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中に、屠られた姿で子羊が立っているのを見た。それは七つの角と七つの目を持っていた。その目は、全地に遣わされた神の七つの御霊であった。)、12(彼らは大声で言った。「屠られた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。」)
[9] ここだけではありません。このマタイの記事には、旧約聖書の言葉が鏤められています。彼らがぶどう酒を飲ませたこと、衣をくじ引きしたこと、罪人と並べたこと、頭を振りながら嘲ったこと、「神のお気に入りだろう」とあざ笑ったこと…。これらは詩篇22篇(7 私を見る者はみな 私を嘲ります。 口をとがらせ 頭を振ります。8 「主に身を任せよ。助け出してもらえばよい。 主に救い出してもらえ。 彼のお気に入りなのだから。」、18 彼らは私の衣服を分け合い 私の衣をくじ引きにします。など)や69篇(21 彼らは私の食べ物の代わりに 毒を与え 私が渇いたときには酢を飲ませました。)、イザヤ書53章(3 彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で、病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。4 まことに、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに、私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。)など、旧約の昔から神が語っていた、冷たく残酷な人間社会の一面です。そうした人間の冷たく、壊れた現実を掬い取り、なめ尽くされるイエスこそ、王、キリストなのです。
[10] 40~43節の人々の言葉、「もし神の子なら、自分を救え」は、最初の四章でサタンが荒野の誘惑でイエスに再三呼びかけた誘惑と通じます。あの時もここでも、神の子ならその力を見せてみろ、もっと楽な道、自分を救う道を選ばないなんて愚かだ、と言う声が付きまといました。
[11] また、今ここでも、「イエスが十字架から降りようと思えば降りられたのだ。しかし、私たちのために十字架に留まってくださったのだ」と言ったところで、その「申し訳なさ」から私たちのうちに生じる思いも、イエスが私たちのうちに造ろうとする信仰とは全く別物です。イエスは、力・栄光によって威圧する神ではなく、無力・無防備さ・裸によって私たちに近づかれることで、初めて生まれる関係、すなわち、愛を求められるお方です。恩着せがましい神ではなく、本当に惜しみない神です。
[12] 英語で苦しみをpassionパッションと言いますが、その派生語が「ともにcon苦しむpassion」から来たコンパッション(思いやり、あわれみ)です。特にキリストの受難はthe Passionと言いますが、それはthe Compassionとも呼べる、私たちとともに苦しむ、あわれみの受難でした。正確には、ラテン語でcompatioの過去分詞から、英語になったもの、だそうです。
[13] その変化がここにも見られます。36節はなぜわざわざ書かれたのでしょう。一つは、これも詩篇22篇7節とダブらせるためでしょう。もう一つは、54節への伏線です。イエスを見張っていたこの兵士たちが、十字架にかけらたイエスとその後の出来事を見て「この方は本当に神の子であった」と言います。復活を見て、ではなく、十字架につけられたキリストを見て、「この方は神の子だった」という告白をしたのです。もう一人は、クレネ人シモンです。わざわざ名前が挙げられるのは、後に彼がキリスト者となり、あの十字架を担ったのは私ですと知られたからでしょう。彼は決してイエスの十字架の贖いを助けたわけではありません。しかし、シモンが十字架を運んだことは、その時は無理矢理な災難としか思えなくても、確かにそれはイエスとの出会いとなり、苦しみがイエスとともに苦しむ新しい意味を持つ始まりとなりました。
[14] このテーマに関して、今週いただいたのが、上沼昌雄氏の記事「ウイークリー瞑想「福音派はニーチェと無関係ではないのか?」2022年2月7日(月)」でした。お許しをいただいていないので、全文の転記は出来ませんが、「私たちが如何にだめなものであるのかを強調して、神の恵みを説くやり方です。私たちの罪意識を駆り立てて、キリストの十字架による救いを説くやり方です。その背後にはニーチェが指摘するように、どこかでどうにもならない自分の方がよいのだという思いが動いていると言えます。それゆえに神が負い目を取り除いてくれるといういやらしい思いです。それに対してニーチェは嫌悪感を持っています。しかし2千年の教会にとって当たり前のことになっています。 さらに信仰を持って一生懸命にやっているのに実際には惨めな思いに苛まれていて、どこかで神に対しての怒りを積み重ねていることがあります。表面的にはクリスチャンらしく寛容に振る舞っているのですが、思い通りに行かないで後悔と反感を内側に深く抱えているのです。ルサンチマンの感情です。そのようなクリスチャンの働き人の姿を結構身近に感じます。どこかで自分のことのように思わされます。ニーチェの批判するキリスト教が自分のうちに宿っているのです。」という指摘は、熟考する必要があります。