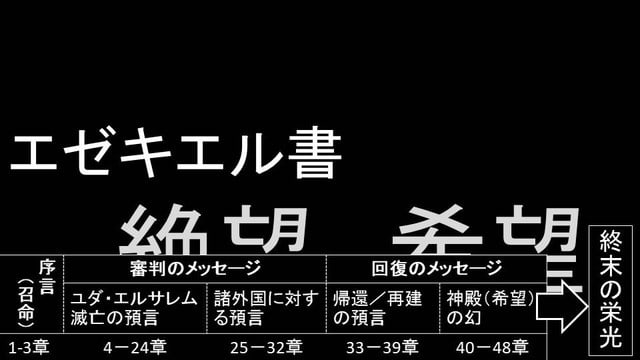2017/8/27 ハ信仰問答85「刈り取りの法則」マタイ18章15-20節
先週「鍵の務め」という事をお話ししました。今読んだマタイ18章18節にも
「つなぐ・解く」
という言葉が出て来ましたが、神は教会に天国の鍵を繋いだり解いたりする働きを与えられました。これを「鍵の務め」と言います。しかし前回お話ししたように、それは教会に特別な権威があるかのように誤解されやすいことです。ハイデルベルグ信仰問答ではそうは教えません。教会が、聖書からイエス・キリストの福音を伝える事、それが言わば鍵の務めなのだ、というのです。そしてもう一つ「キリスト教的戒規」というものが神の国の鍵の役目を果たす、ということが、今日の問85です。
問85 キリスト教的戒規によって天国はどのように開かれまた閉ざされるのですか。
答 次のようにです。すなわち、キリストの御命令によって、キリスト者と言われながら、非キリスト教的教えまたは行いをなし、幾度かの兄弟としての忠告の後にもその過ちまたは不道徳を離れない者は、教会または教会役員に通告されます。もしその訓戒にも従わない場合、教会役員によっては聖礼典の停止をもってキリスト者の会衆から、神御自身によってはキリストの御国から、彼らは閉め出されます。しかし、彼らが真実な悔い改めを約束しまたそれを示す時には、再びキリストとその教会の一員として受け入れられるのです。
「戒規」とは耳慣れない語です。戒める規則と書きます。ここに書かれているように、
「非キリスト教的教えまたは行いをなし」
という人を戒める規則です。キリスト者と言われながら、イエス・キリストの教えや聖書の大切な教理を否定する。あるいは、その生活での行いで犯罪に手を染めるとか不道徳な生き方をする。そういうハッキリした罪をする人を戒めるための手続きが「戒規」です。そこには三段階あることも分かります。分かりやすくしてみましょう。

まず、兄弟として、つまり二人だけで話をします。それでダメなら、もう一人と一緒に注意します。その前に噂話を広めたり、見て見ぬふりをしたりはしません。ちゃんと忠告しましょう、と言う事です。しかし、それでもその人が
「その過ちまたは不道徳を離れない」
なら教会に(役員・小会に)通告します。自分では解決できなかったのですから、教会にお任せして手離すのです。そして、小会が何とかしてその人と話して説得しても従わないかもしれません。その場合は
「聖礼典の停止」
をもってキリストの会衆から閉め出されます。それでもまだ悔い改めようとしないなら、最後には
「除籍」
という措置を取ります。そういう手続きがあるのです。
けれども、戒規というより私たちの日本長老教会は「矯正的訓練」という言い方をするようにしています。確かに、教理や生活での間違いは戒める必要があります。けれども大事なのは戒めて、最後には除籍する、ということではないのです。間違いを正しつつ、それを通して人が回復することですね。元々の言葉は「訓練discipline」なのです。弟子にすることであって、排除ではないのです。今日読んだマタイの18章も、15節から20節の「矯正的訓練」の手続きの前後に、回復や大切な言葉が沢山ちりばめられています。この後にも赦しについての例え話が語られています。一つだけ紹介しましょう。
14このように、この小さい者たちのひとりが滅びることは、天にいますあなたがたの父のみこころではありません。
どんな小さな人も滅びないことが天の父の御心です。過ちや不道徳の中で滅びてはならないから真剣に注意をするのです。そして、その注意の仕方でも頭ごなしに責めたり脅したり対決の姿勢は取らないのです。その人を、滅んではならない大切な人と思うからこそ注意するのであって、もしも帰ってくるなら受け入れられるのですね。
…しかし、彼らが真実な悔い改めを約束しまたそれを示す時には、再びキリストとその教会の一員として受け入れられるのです。
どの段階でも「真実な悔い改め」を約束し、示すなら、再びキリストに結ばれ、教会の一員として受け入れられる。その赦しと回復があるのです。勿論、それは口先だけの反省かもしれません。深い問題がある場合、本当の回復のためにはケアや時間が必要でしょう。何でもすぐに赦して、なかったようなふりをする、ということではありません。その人が本当に間違いを間違いとして理解して、変わっていくようサポートするのです。でもその根っこには、赦しの恵みがあります。その事を現す事として、再び聖晩餐に受け入れて、一緒にパンと杯を頂く食卓を囲むのです。

同じパンを食べ、杯を一緒に飲む事で、交わりの回復を示すのです。この食卓を囲む私たちは、だれも間違いなく生きる事が出来る人などいません。ひょっとすると、堂々と間違った教えを持ち込んだり、責められなければならないような生活を始めたりするかもしれない、弱い者です。だからこそ、友人同士、信徒同士で注意したりされたりすることも必要です。教会の役員によって譴責を受ける事も必要です。それでものらりくらりと逃げ、頑なに心を閉ざすかもしれません。その時に、主の聖晩餐に与れない、という罰でやっと目が覚めてほしい。そうしてやっと恥じ入って、非を認める時、交わりに受け入れられるのです。
「本当に赦されたのだろうか、責められるんじゃないだろうか。」
そう思う私たちが、一緒に主の聖晩餐を頂く時、深い実感と感動をもって、私たちは赦しと交わりの回復を信じさせていただけるのです。この回復にこそ、「戒規」「矯正的訓練」の目的があります。
私たち日本長老教会は「訓練規定」を持っています。教会の訓練について具体的に教えています。この中で、悔い改めた場合の陪餐停止は想定していません。しかし、教会の中には、悔い改めても何ヶ月か陪餐停止にする所もあります。他にもこの鍵の務めを誤解したり乱用したりしてきた事実は教会の歴史を見ると沢山見受けられます。だからこそ、正しい鍵の理解をしたいと思います。
私たちは、間違いやすいものですから、教会の交わりを通して、教え合う事を必要としています。教会の交わりを必要としています。そして、その交わりを壊すような間違いも犯すものです。実際、教会に集まっている一人一人がそうした弱さを抱えているものです。でも、キリストの十字架の恵みによって、その私たちにも天国の鍵が開かれたのです。その恵みを受け止めて、私たちが受け入れ合う時、教会の交わりそのものが、キリストの赦しを味わわせ、見える形で天の鍵が開かれたことを示すような役割を果たすのです。責めて、追い出すための鍵ではありません。ますます主の恵みと赦しを味わい、分かち合うための戒規なのです。