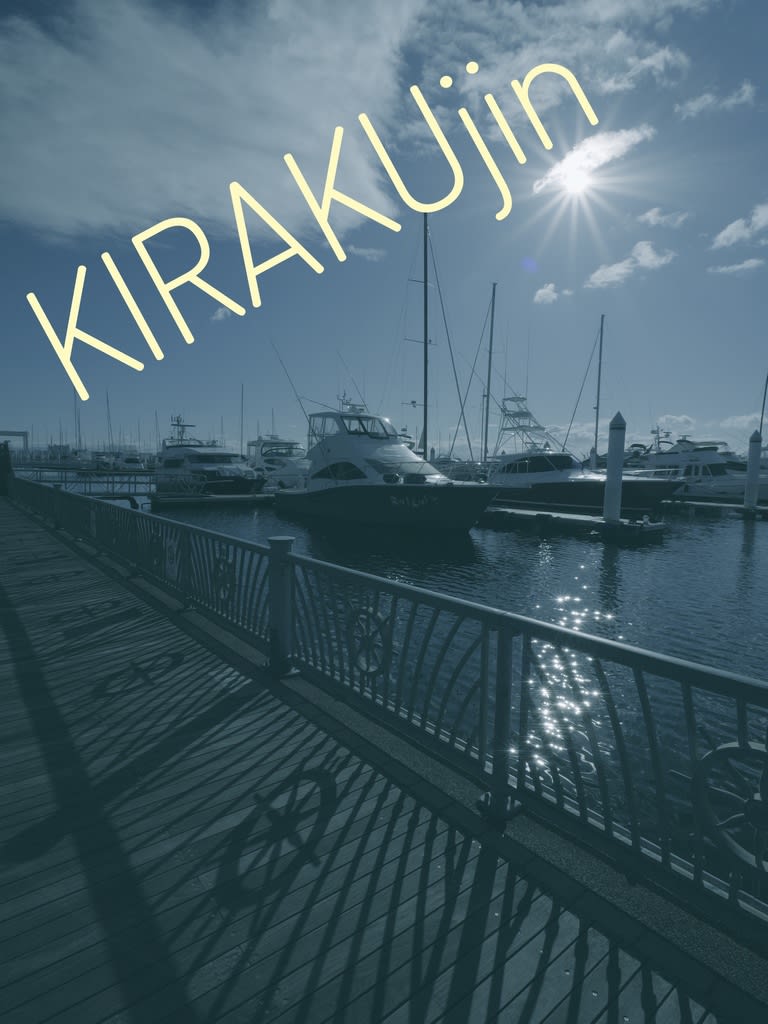いや、きっとそうに違いない。
カメラといえばフィルムが当たり前で、デジタルなど微塵も感じさせなかった頃。
モノクロで撮影し、暗室で現像することが、楽しくて仕方なかったものだ。
今もデジタル世代で生まれた方たちが、古い機械式カメラを提げていらっしゃるのを見る。
レコードやカセットテープで曲を聴くように、アナログの面白さを認識して頂けるのは、嬉しいことだ。
モノクロフィルムで、特に好みだったのは、コダックのTRI-Xだった。
トーンの出方や、適度な粒状感が心地良かった。
デジタルの時代になってもう、久しい。
フィルムが主流ではなくなり、写真の主体はデジタルになり、さらに普段の撮影の主役はスマートフォンになった。
一般的なデジカメですら、かなりシェアを下げている。
しかしそんな時代でも、往年の写真家たちの作品に触れていると、モノクロームの魅力は何ら変わらない。
いやむしろ、モノクロフィルム時代の方が、魅力的に見えることも少なくないのだ。
もし彼らや彼女らがいま、デジタルでモノクロームを撮るとしたら、どのように撮るのだろうか。
おそらくACROSが、大きな選択肢のひとつになることは、間違いない。
毎日気にしていたと問われたら それも嘘になるが
気になって綴ってみても ここ数年はまた 年単位の時が流れていた
写真を撮らなかった訳ではない むしろその逆である
しかし何かに追われれば追われるほど 他のツールへ流れていった
昨日から使ってみたタブレットが ノートパソコンより使い勝手が良いのもあるだろう
しかし今になって再度 ブログの緩さを 懐かしく感じたのかも知れない
最初の投稿に 海が見えない場所で育った私は 海に憧れている
そんな風に綴った と記憶している
自分で紐とけば良いのだか それも億劫だと言える緩さが また良いのかも
時節柄 巨大なアウトレットモールは ゴーストタウンと化し
発着の多かった海上の巨大な国際空港の光もどこか 寂しげだ
写真は光と影 それに少しの心象がエッセンスとして加わるのだとすれば
またこの場所にいずれ立ち 違った心象で撮りたいと願う
本日もお読みいただき ありがとうございました
また近いうちに お会いしましょう
by KIRAKUjin
10年以上前にブログを始めた頃は、毎日ノートパソコンを開け、フィルムからデジタルへの変遷を綴った。
楽しくて夢中になったものだが、ネット環境はブログ以外にも、さまざまな写真関連のサイトが増えていった。
各種SNSは、現在まさに、時代の寵児と言えようか。
最近のネットへの投稿は最新情報が多く、趣味や世の中の事など非常に多岐にわたり、私も恩恵を十二分に受けている。
ただ少し、慌し過ぎるのではないだろうか。
世の中のスピードは早く、また予想だにしなかった事態に、世界中が巻き込まれることもある事を知った。
久しぶりの投稿になる。
この場所だけはそんな、世の趨勢から乖離して、のんびりとしたものにしたい。
かつてのようなノートパソコンではなく、今回からタブレットにしてみた。
ますます、気楽なものにできるだろうか。
(写真について)
例によって、カメラ一台に単焦点レンズ一本である。
写真を撮るための外出ではなく、仕事の延長線のようなもの。
よく知る河口の堤防の夕暮れに、何とか間に合った光である。
"すでに何度か述べたかも知れません いまは最初に一眼レフを購入するとき 標準レンズとしては それは単焦点レンズではなく いわゆる標準ズームなのだと思います
よほど理由がない限り 最初から単焦点レンズを選ぶことは まずないのでしょう しかしまだズームレンズが一般的はなかった遥か昔 とくに1970年代の後半は 一眼レフのカタログには 50mm f1.4 が装置されていたものでした
35mmフィルムカメラ全盛期 スナップカメラの頂点はライカであり それを選ぶカメラマンのタイプによって 選ぶ標準レンズには好みがあり 50mmか35mmが 二つの大きな選択肢だったようです
ゆえにM型ライカの元祖は 究極のレンジファインダーを持つM3であり 50mm枠がメインてあり その後35mm枠も採用したM2が追加されたのです
例えば決定的瞬間という撮影用語の代表格(諸説異論はありますが)である アンリ・カルティエ・ブレッソンは ズミクロン 50mmが代名詞のように語られています
ところで ズミクロンと言えば通常 f2を意味します 現在通常 似たスペックのレンズとしては f1.8になるのでしょうか
もし私が最初に一眼レフを選んだ頃に戻って カメラとレンズを選ぶとしたら シルバーのオリンパスOM-1かブラックのニコンFM そしてレンズは 50mm f1.8かもしれません
当時最も普及していた 50mm f1.4よりも若干暗いとはいえ ズミクロンより明るいわけですし f1.4よりf1.8は 廉価で薄型で 傾向性に優れていました
今回私が使用したレンズはニコンの Ai Af Nikkor 50mm f1.8Dです
1980年に発売されたニコンEMは 当時ブロ仕様とされていたニコンが初めて発売した リトルニコンの代名詞を持つ超小型の一眼レフ
それに合わせて設計された 50mm f1.8 シリーズEはいわゆるパンケーキタイプでしたが 当時NIKKORの銘すら与えられない廉価版でした
このレンズは時代を経て何世代もの変遷を遂げました そしてその基本設計はそのままに 今回の Ai Af Nikkor 50mm f1.8Dに受け継がれており 平成最後も2019年でも 新品で入手することができます しかもニコンで最も廉価なレンズとして
現在の最新設計の優秀な50mmレンズたちとは ちょっと写りは昔風ですし 私のZ7に純正アダプターを介して装着できますが AFは使用できません 最も AFは私にとって必須ではないので この小型軽量のレンズはとても頼りになる相棒です
f1.8開放での神戸旧居留地の撮影ですが 空気感のある しっとりとしたモノクロームを表現できていると思えるのですが いかがなものでしょうか"

かつては貨物基地でした
扇状に広がる線路と 倉庫のような建物と
大阪駅の北側は 先に開発された南側と違い
美しさとは 縁遠い場所でした
大阪駅そのものの再開発に伴い
北側も貨物基地がすべて撤去され
グランフロントを中心とした
賑やかな街に変貌しました
平成は31年目で終わりを迎えます
昭和の頃の佇まいの記憶も 人びとから
徐々に薄れていくことでしょう
街もまるで生きているかのごとく
日々の積み重ねで 変化していきます
街頭スナップは そんな記憶の
積み重ねなのですね

最近のネットニュースの写真関連記事で目立つものは
・フルサイズミラーレス
・スマートフォンの高性能カメラ機能
そして意外によく出くわすのが
・単焦点レンズのすすめ
である
フルサイズミラーレスは渇望されていたもので当然の流れといえる
(私はフルサイズ至上主義ではないが競争原理が機能していない分野であったのは問題である)
スマートフォンは現実的に最も普及しているカメラであり別の機会に語ろう
(これは複眼の画像情報を処理することで画像を構築するという昆虫のような新しい写真のあり方だ)
スマホは薄いゆえに複眼化が解決策の革命的アイデアかも知れない
フルサイズミラーレスはむしろその真逆の進歩といえる
センサーが大きくなれば当然 ボケは出しやすくなる
2本目のレンズとして 単焦点を選ぶのは良い方向だ
いずれ10個くらいレンズがついたスマホと
フルサイズの単センサーの単眼レンズのカメラと
いや いずれではなくいますでに その競争は始まっているのだろう
コンデジがスマホに駆逐されるのに そう時間はかからなかった
しかし一眼レフやミラーレス一眼は 完全にスマホに置くかえることは 現時点では無理だろう
ソニーのマビカ試作機が1981年 ニコンの普及型デジタル一眼レフのD100が2002年
1981年当時 マビカ試作機は新聞紙面を賑わせた
行きつけのカメラ店の店主と話をしたが フィルムに取って代わるには かなりの時間を要するだろうとの見解だった
当時はまだカメラ少年だった私は そんな電子的に画像を創り出して保存するカメラは嫌だと感じた
しかもソニーなんて まるで静止画ビデオカメラじゃないかと思っていた
カメラ店主の予言どおり この電子カメラがデジタルカメラとして主流になるのに 約30年かかったことになる
ただし次は30年ではなく 10年いや5年でも 大きな変革が見られるだろう
携帯はスマ ホになることで ボタンはどんどん減り 究極はボタンも端子も存在しない ツルツルになるのかも知れない
一方カメラは進歩すればするほど 操作部位としてのダイヤルは復活し とくにフジフィルムやオリンパスのOM-Dシリーズは フィルム時代を彷彿とさせる
ライカなどもっと極端で 巻き上げレバー以外は フィルムのM型にそのデザインは酷似している
単焦点レンズの話をするつもりだったのだが 脱線したまま突き進んでしまったので また別の機会に
写真は
Nikon Z7 + Af-S Nikkor 85mm f.1.8G
最近の私の お気に入りである
最近の複眼スマホは美しいボケを表現できてとても素晴らしいが
まだまだ フルサイズミラーレスと単焦点レンズの敵ではないのが嬉しいし そう単純には置き換えは難しい
フィルムがデジタル化されたのとは 理論的にも根本的に異なるのである