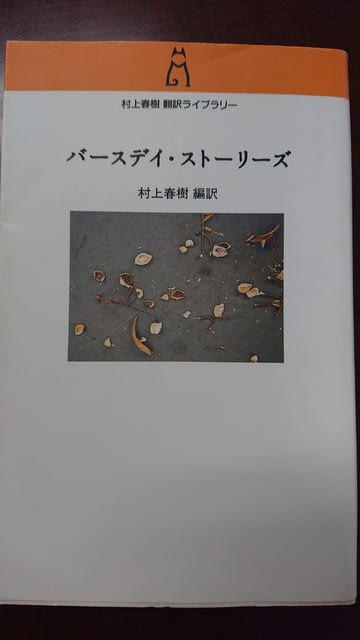美食家宣言
2020-05-12 | 食
僕はいわゆる美食家ではない。だからと言って何を食べてもいいという気持ちではないけれど、いわゆる美食家に対して憧れも無いし、そのような生き方を今後もしないのではないかという予感がある。もちろん、大枚はたいてそのようにできる素養が無いというのは確かだろうが(大金が入るとそうする可能性がゼロとは言えない)、それなりに思うところがあるからだ。
ハンバーガーがまずいわけではないが、自分の選択としてはまずありそうではない。いわゆるジャンクフードっぽい感じが嫌なだけかもしれない。かみさんが作ってくれるハンバーガーなら喜んで食べるが、チェーン店のものなら、まず食べには行かないだろう。
牛丼も同じくそういう感じか。仕方なくなら入ることも無いではないが、進んで食べたいものではない。まずくはないかもしれないが、貧しさはあるせいだろうか。何か作法がありそうな感じが嫌なだけかもしれない。「つゆだくで」という言い方をしたくないのだろうとは思われるが、そういうのを説明するのがめんどくさい。常連でもないのに常連っぽい雰囲気を作らなくてはならない感じがしゃらくさい。単に考えすぎであるけど。
そうだった、思うところある理由だった。
寿司なんかを食っていて、特にこれを思うのである。そんなに回らない寿司を食うわけではないが、たまに食うことはある。確かに旨いし、これは回転寿司とは別物であるというくらいは分かる。さらにこの寿司屋というのは、ものすごいところがあったりする。これもめったに行かないからありがたく楽しいが、支払いは楽しいわけではない。さらにそれくらい凄いところは若気の至り以来行ってないからもう忘れそうだけど、確かに美味しかったなあ、という感動とともになんとなく襲ってくる感慨のようなものがあって、しかしこれが同じ寿司として数十倍も美味しいかといえば、果たしてそうかな、ということかもしれない。ネタによっては百倍くらい値段の違いのものも、あるかもしれない。しかし百倍旨いかという問題には、ならないのである。
もちろん、エンタティメントとしての加算はあろう。場の雰囲気や技能に対するリスペクトや、そういうものが加味した値段でもあるし、もしもそういうものが安いのであれば、かえって口に入りにくくなり(予約が取れなかったり並んだりする時間を要したりの手間)合理性を欠けるというのも分かる。高いものは燦然と高額である方がいいと、市場経済を鑑みて正当に思う者でもある。
しかし、もう一つの合理性を求める自分自身に、この何倍かの差をうめるべく正当な合理性を認めていないところがあるのかもしれない。そういうものが食べ物の世界であって、美食の世界への不信でもあるのだ。
ということで、僕は食べ物に倍率を求めていない。そういう何倍もの上の旨さのあるかもしれない(または何倍も不味いかもしれない)素材があるからといって、現在食べようとしているそのものを、味わうことに集中したい。記憶をたどってどうだというのは言えるのかもしれないが、今味わっている味のことの方が、何倍よりもリアルに、今の自分の体験として重要だ。ただ今僕が旨い。そういう素直さにおいて、僕だってすでに美食家なのである。