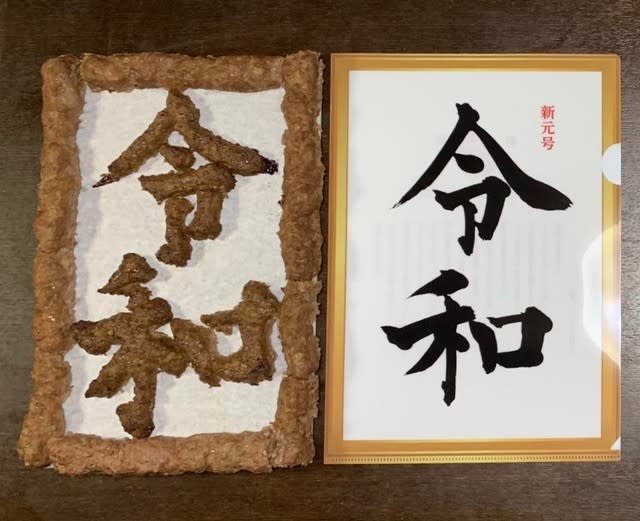悪意/ホーカン・ネッセル著(東京創元社)
5編組んであるので短編集であるが、最後の一編以外はそれなりに重厚な物語構成になっており、日本のいわゆる短編集とは違う感じだ。二段組でもあるし、読みごたえがある。先が気になって仕方なくなるので、この長さでないと我慢できないかもしれないが。
殺人事件が主で、いわゆるミステリ作品なのだが、文学作品としてたいへんに優れているのではないか。今はノーベル文学賞は休止しているようだが、このような作品が受賞するべきではないだろうか。大げさに聞こえるかもしれないが、それくらいものすごく上手い文章だし、構成が見事なのである。人間心理が描けていて、適度のユーモアがある。独特の皮肉も効いていて、思わず唸らされる。それでいて面白くて読むのがやめられない。こんな作品にはめったに出会えるものではない。なぜ日本ではこれを含めて二冊しか翻訳が無いのだろうか。
厳密にいうと人を殺してはならないわけだが、人を殺すにもそれなりに理由がある。それを正当化するという意味ではなくて、ある程度納得ができなければ、その殺人自体が宙に浮いてしまうことがあるのではないか。いわゆるミステリ作品の中には、そのトリックを成立させるためだけの殺人というのがあって、謎解きのゲームとしてはそれで面白さがあるというのは分かるのだが、どうにもその殺人自体が納得できなくて、残念に思うことがある。人を殺したいと思うようなことを考えたことが無い人間であっても、作中人物に思いを寄せることはできる。それが読書体験の醍醐味であって、自分とは全く性格も境遇も違う人物が殺人に至る精神性を、読みながら体験できるというのは貴重なのではないか。または殺した本人でなくとも、その周辺の人の気持ちになれるのだ。それは必ずしも幸福なこととは違うのだが、激しく心を惑わされることにはなる。それが文学体験でなくて何であろう。そういうものを文学性の高さだと考えるのは、まっとうなことなのではないか。
娯楽作品だから格が低いというのは、単なる歴史的な偏見である。人間が何かを学ぶ知性があるとしたら、この作品の文学性を理解できることにもつながることだろう。