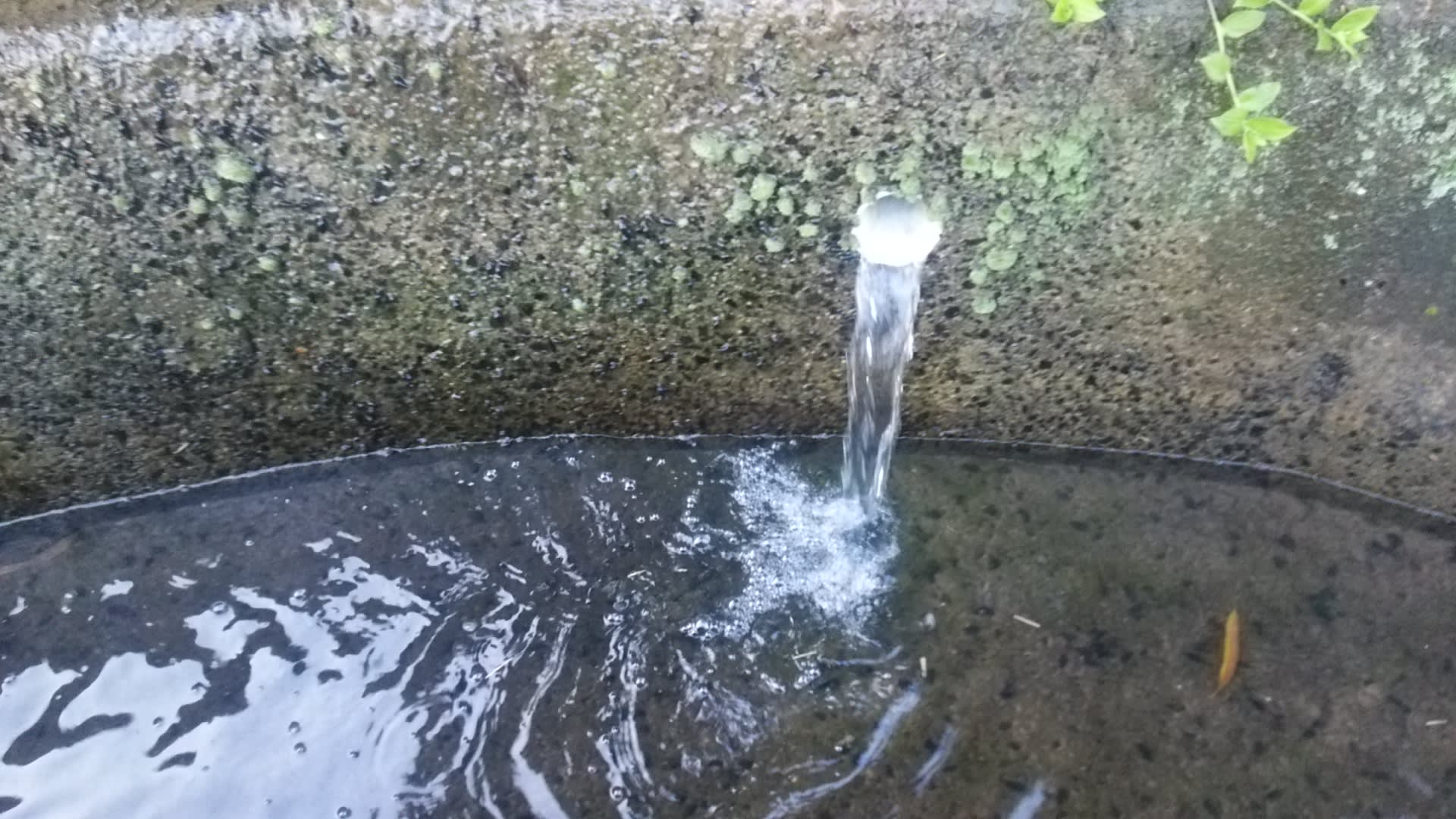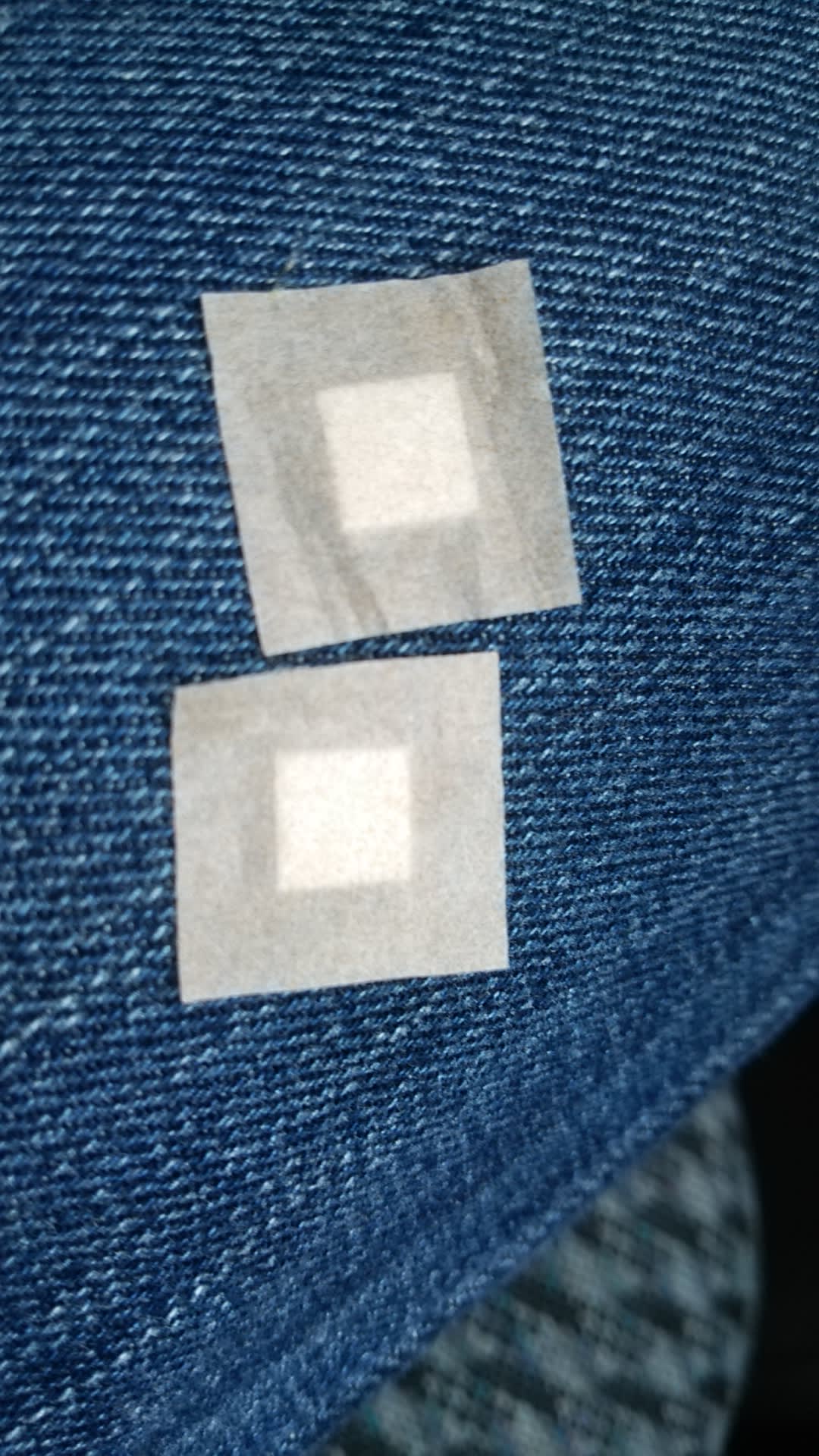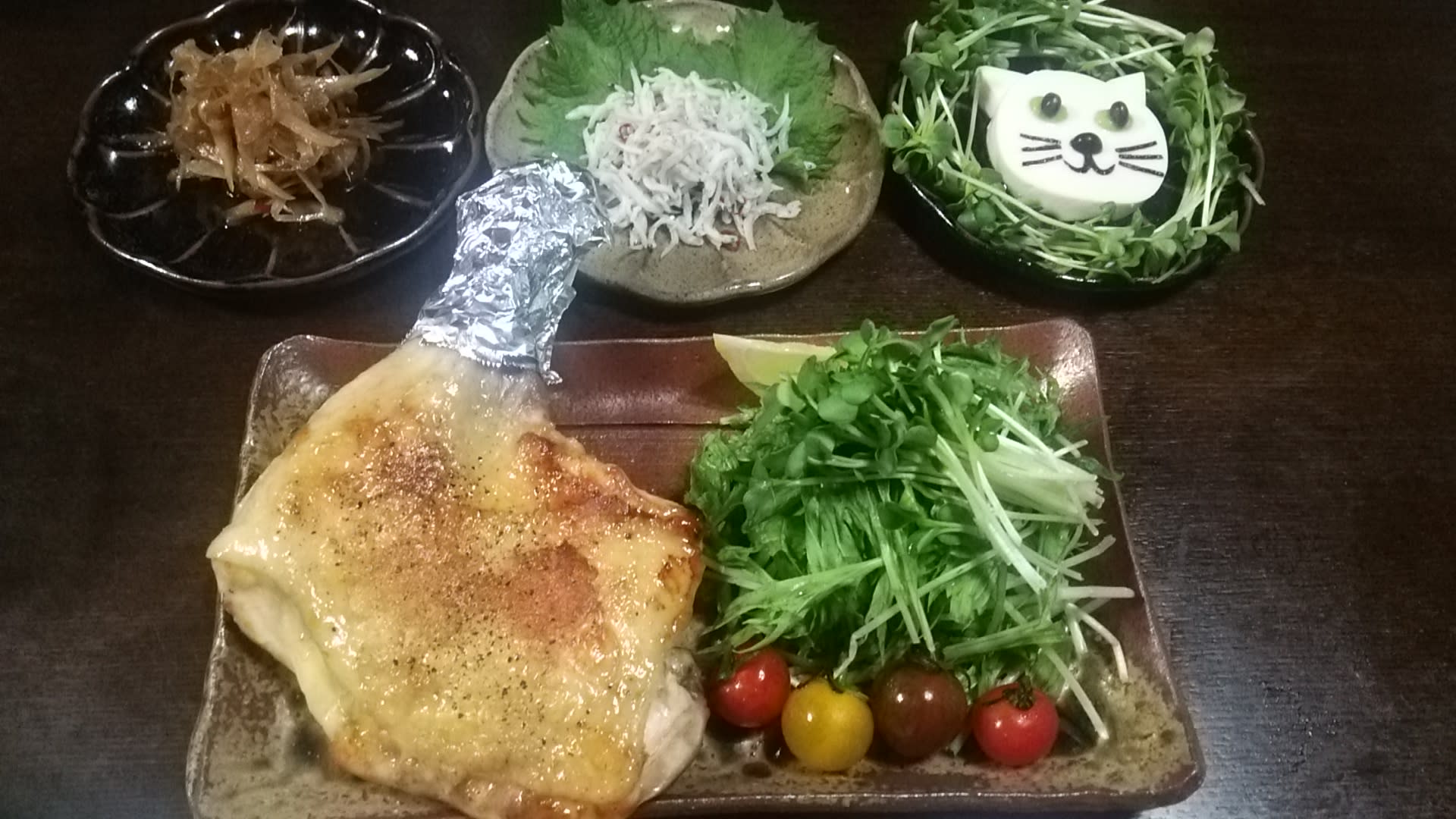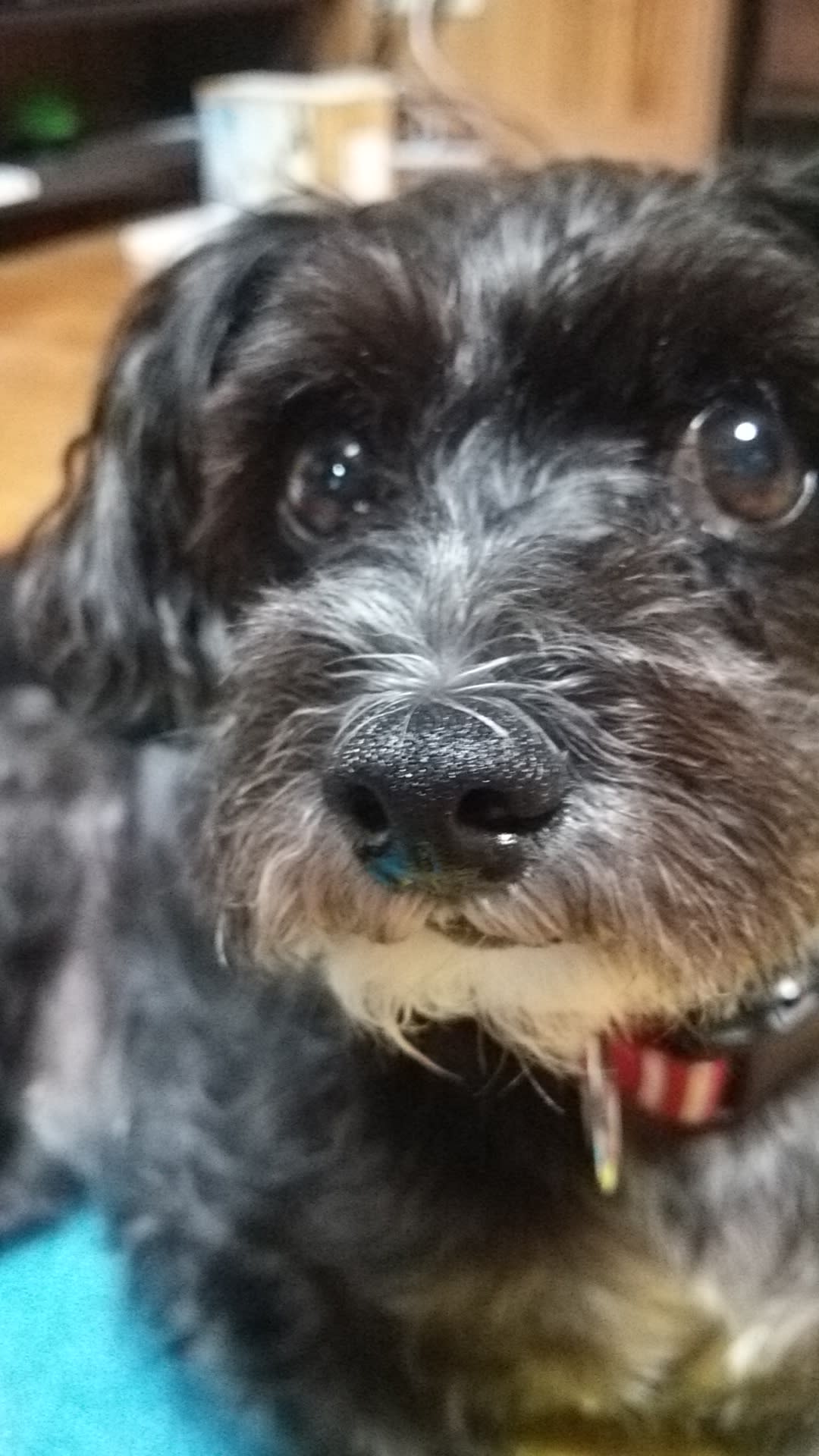サンタクロースになった少年/ヨハ・ウリオキ監督
サンタクロースは北欧の伝説であるという話は聞いたことがあるようだ。後に米国の商業主義とマッチして全世界へ伝播し、現在に至ったとされる。しかしながら僕のような戦後育ちの人間には、家でも普通の行事で既に定着していた感がある。アメリカが悪いというのはそれは違いないことだが、要するに現代的な感覚としては、きわめてなじみやすい風習なのであろう。
ともあれこれはフィンランド映画で、サンタクロースの誕生秘話ということになるのかもしれない。
妹の病気のために医者に連れて行く途中、妹と両親ともども氷が割れたために死んでしまう。留守番をしていたため、天涯孤独、みなしごになった少年は、どこか特定の家が引き取るということではなく、この村で一年ごとに家を変えて面倒を見てもらうことになった。そのようにして世話になった家に、少年は何かお礼をしたいと考えて、手先の器用さを生かして、木彫りの人形を玄関に置いていくことにする。何か人付き合いの下手なところのある子供のようで、そのようにしか感謝の表現ができなかったのかもしれない。
そういう風にして、毎年世話になる家が増えていき、プレゼントを配る家も増えていく。ところがある年は記録的な不漁になり、どの家も少年を引き取れないという。その時に町に行商に来る恐ろしげな家具商人が、少年の手先の器用さに目をつけて、自分が引き取るという。形の上では体よく解決したようなことだが、少年は家具小商人の家で、ますます腕を上げて一人前になっていく。
そうしてすっかり家具商人の家になじむのだが、家具商人も年をとっていき、息子たちが引き取ることになった。また元少年は孤独になってしまうのだが、家具商人はこっそり資産をベッドに下にため込んでおり、これを元少年に託すのである。
このお金をもとに、元少年は村の子供たち全員に対して、プレゼントを配るようになるのである。そうしてすっかりこういう習慣になっていたのだけれど、今度は元少年が年を取ってしまう。それでプレゼントを配るのも最後にしようと決めて配り終えると行方不明になってしまう。次の年からは誰もプレゼントを配るものが居なくなったにもかかわらず、引き続き、今度は親たちがそれぞれの子供たちにプレゼントを配るようになったということなのである。
基本的にいい話で、映像もそんなに洗練されている訳ではなく、ハリウッド的な派手さとも無縁で、淡々と物語は進んでいく。なんとなく神話的な物語でありながら、実に説明的に地味である。
まあ、由来の通りの物語であろうから、その通りなんだろうが、善人の多そうな民主的な村なのに、結果的に意地の悪そうな家具職人に哀れな子供を託してしまう。死ぬか生きるかの事情があるとのことだが、なんとなく不甲斐ない。さらに急に家具職人は実にいい人で、一緒にプレゼントを配ってくれたりもする。そうして今まで気配さえなかった息子達が年を取ると引き取りに来るのだ。考えてみるとおかしなところだらけという気もするんだが、まあ、昔の話なんだから仕方がない。
実は僕はプレゼントを選ぶのが非常に億劫である。子供が欲しがるのならそれを与えればいいのかもしれないが、何が欲しいのかを考えて与えるというのが、ものすごく難しいことのように思える。帰りにアイスクリームを買って帰るのとはわけが違う。クリスマスのようなイベントが良いとか悪いとかは思わないが、子供がある程度大きくなって、このような風習と関係が無くなったことは、大変にありがたいな、としあわせを感じるのであった。