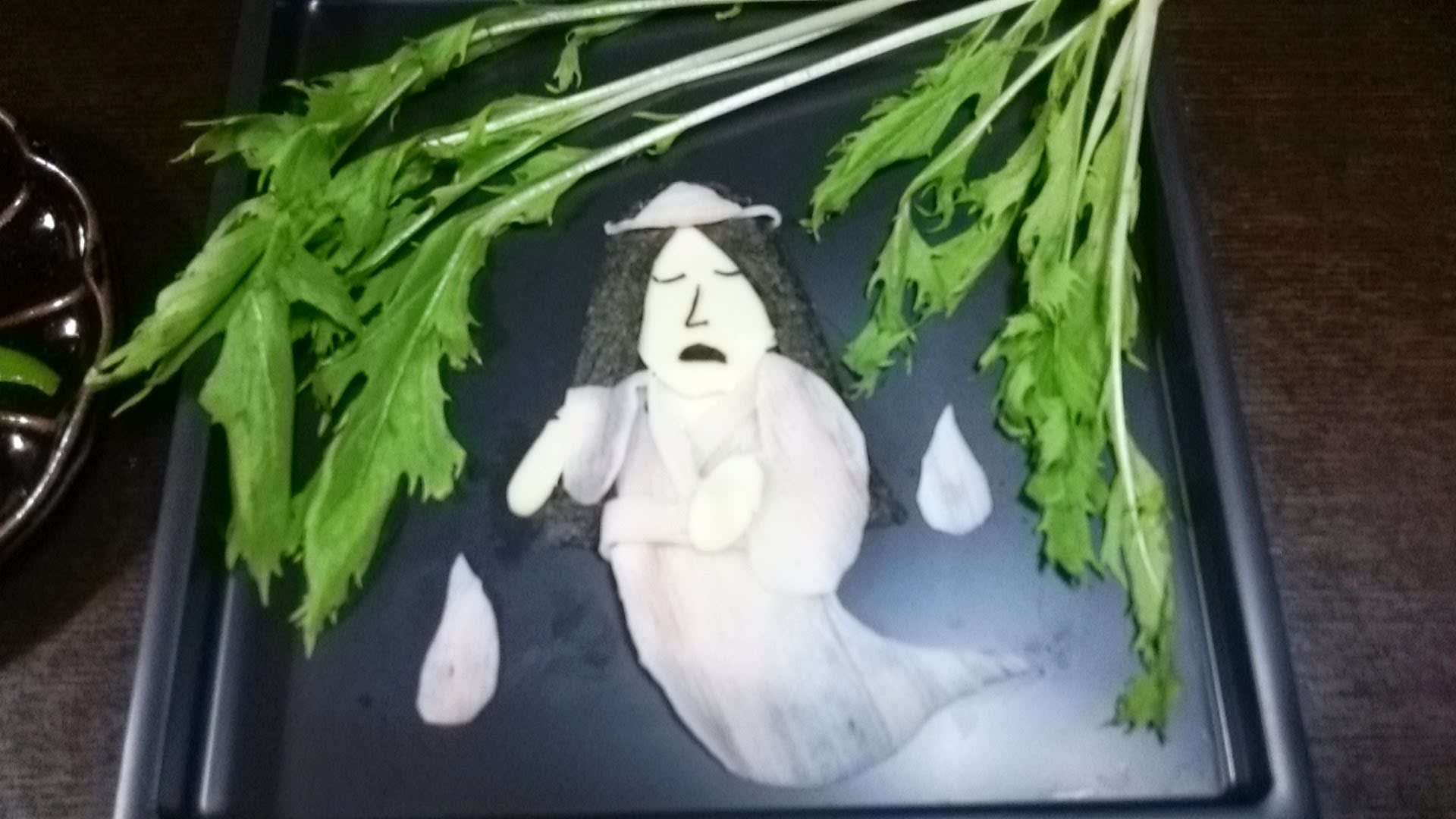ビフォア・サンライズ/リチャード・リンクレーター監督
「恋人までの距離(ディスタンス)」という邦題時代に、一度観ている。夜明けまで男女が会話するだけの映画でありながら、これほど劇的な感じのする作品は他に知らない。もちろんそういうことで多くの人に支持され、続編が作られ、そうして第3作目も近年高評価であると聞く。またそのような道筋を辿るためにも、また見かえてしておくべきだと考えたわけだ。
見返してみてまた驚いたのだが、その新鮮度は落ちていなかったことだ。本当に最初から最後まで、なんと言うか、ドキドキしてしまうのだ。恋というもののみずみずしさが、まさにはち切れんばかりだ。会話は確かにたわいも無い。どちらかといえば女性の方が知性的で、男性の方は直感的だ。というか男性は自分本位に自説をぶち(なんともアメリカ人的だ)、女性側はある一定の根拠を持った上で感性を語る。しかし共通するのはお互いがお互いに持っている好意と、そして相手を知りたいという好奇心だ。偶然に出会ったばかりの二人だから、当然のことながらお互いが相手のことを何にも知らないわけだ。たわいの無いおしゃべりをしながら、本当に徐々に相手のことが分かっていく。なぜ偶然出会ってしまったのか、そうしてお互いにいつから恋に落ちたのか。
そういう謎解きもスリリングだし、でもその偶然性と国や文化の違いなどから、やはり夜が明けるまでしか二人には時間が残されていない。結果的に一夜の情愛は確かめられたようだけれど、それだけが目的だったわけでもない。今のみずみずしい感情は宝石のように貴重だが、しかし本当にこのまま離れてしまっていいものだろうか。時間の経過とともに、なんとも切ない気分がせき止められず溢れようとしている。
恐らく、この時点で続編は意識しては居なかったのではなかろうか。この映画だけでも非常に完成度が高いからだ。この映画を観て、このような出会いを夢見る人は相当数に登っただろうことも予想される。しかし、このような奇跡的な輝きが、本当に一夜の出来事として起こりえたかは分からない。それはまさに「ローマの休日」へのオマージュだろうし、このような展開だからこそ、いつまでも甘い感情が色あせないのだろうとも思われる。
しかし、人間の情愛というものは、思い出だけにあるわけではない。人間はいつでも今を生きているわけだ。そうして、今を生きるなかに、離れたくないパートナーも居るということだ。結婚は制度上のものだけれど、恐らくその基本的なところでは、そのような感情を形に変えたものでもあるだろう。もちろんこれに家が絡むと少し別の文化論になってしまうが、結婚という制度を利用しなくても、離れたくない感情こそが、二人を支えていることは間違いなかろう。たとえ一時顔も見たくないような状態になろうとも、それが一時のものだということを知っているからこそ、その次の時間を共有することが可能になる。そのスタートというか根拠というか、そういうものが詰まっているのが、他ならぬこの作品なのである。だから恋にはこれだけで十分ということが(もしくは不十分)分かるわけだ。
しかしながらお互いがお互いそのように思ってくれるというは、やはり奇跡的なことのようにも思える。実はお互いの許容の問題もあるんだろうけれど、それをいえばシラけるので止めておこう。二人だけの奇跡があるからこそ、そのことを信じられるからこそ二人には未来がある。たとえそれが勘違いであろうとも、二人にとっては真実なのだ。