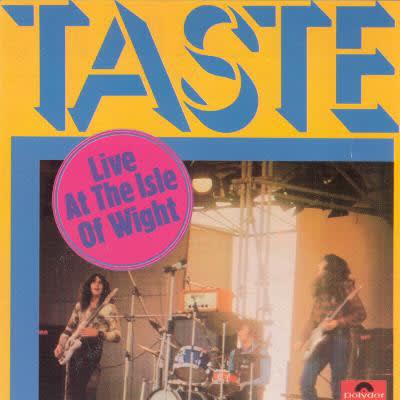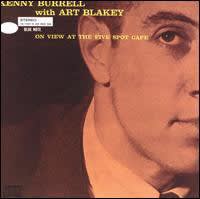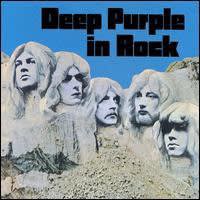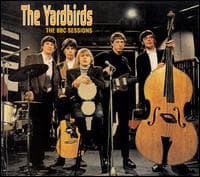2003年2月2日(日)
V.A.「BLUES MASTERS, VOLUME 4: HARMONICA CLASSICS」(RHINO R2 71124)
(1)JUKE (Little Walter & His Night Cats) (2)ENDS AND ODDS (Jimmy Reed) (3)ROCKET88 (James Cotton Blues Quartet) (4)HELP ME (Sonny Boy Williamson II) (5)MESSIN' WITH THE KID (Junior Wells Chicago Blues Band) (6)BLUES WITH A FEELING (Paul Butterfield Blues Band) (7)SUGAR COATED LOVE (Lazy Lester) (8)STEADY (Jerry McCain) (9)I'LL BE AROUND (Howlin' Wolf) (10)I WAS FOOLED (Billy Boy Arnold) (11)TAKE A LITTLE WALK WITH ME (Big John Wrencher) (12)EASY (Jimmy & Walter) (13)BOOGIE TWIST (Snooky Pryor) (14)WOLF CALL BOOGIE (Hot Shot Love) (15)LAST NIGHT (George Smith And The Chicago Blues Band) (16)I GOT LOVE IF YOU WANT IT (Slim Harpo) (17)CHERRY PINK AND APPLE BLOSSOM WHITE (Fabulous Thunderbirds) (18)CHRISTO REDEMPTOR (Charlie Musselwhite)
最近、筆者もブルースマンのはしくれとして、マウスハープ、つまりハーモニカをアマチュア・ミュージシャンのサークルに加わって、練習している。
ブルースハープというものは楽器自体も安価でとっつきやすいが、実際やってみるとまことに奥が深いもので、なかなか上達せずに苦しんでいる(笑)。先人たちの出した"音"が、全然うまく出ないのである。
まあここは、彼らの模範演奏をじっくり聴いて、その奥義を盗むしかあるまい。
ということで、本日の一枚はこれ。おなじみRHINOの「BLUES MASTERS」シリーズ中の一枚、ブルースハープの名演集である。
トップの(1)は、ハーピストなら誰でも一度はコピーに挑戦するという、あまりにも有名な一曲。52年リリース。
ハーピスト達にとって「神」にも等しい、リトル・ウォルター=ウォルター・ジェイコブスの十八番。
このわずか3分たらずのインスト・ナンバーの中に、ハーピストがマスターすべき基本の全てがギュッと凝縮されているといえよう。
ちなみにバックには、ジミー・ロジャーズにマディ・ウォーターズといった大物が参加しているんだとか。
続く(2)は、シンガーとしても名高いジミー・リード。堅実なリズム・カッティングで定評のあるエディ・テイラーのギターを従え、ギターを弾きつつハープを演奏する。58年リリース。
リトル・ウォルターのような華やかさはないが、彼のキャラそのままの、枯れた味わいのハープがまことにいい。
(3)は以前「A SUN BLUES COLLECTION/BLUE FLAMES」なる一枚を紹介したが、その中に収録されたジャッキー・ブレンストン&デルタ・キャッツのヴァージョンがオリジナル。
「一番最初のロック・ロール・レコード」とよばれるこの曲をカヴァー、66年にリリースしたのが、ジェイムズ・コットンとそのバンドだ。
オーティス・スパンの達者なピアノをバックに、軽妙なヴォーカル、そしてエモーショナルなハープを聴かせてくれる。
まさにそのアーティストのキャラクターを反映した音が出るところが、このハープという楽器の面白いところだ。
(4)はサニーボーイ二世の、以前紹介した「MORE REAL FOLK BLUES」なるアルバムに収められていた一曲。
曲はMG'S風ビートのモダンなブルース。だが、ヴォーカルやハープを聴けば、まぎれもないサニーボーイ調。
あくまでも泥臭い。でも、そこがまたイカしているんだよなあ。
(5)はジュニア・ウェルズの代表曲。多くのフォロワーによるカヴァーを持つことでも有名だ。
65年録音のヴァージョンはやはり、さすがの迫力。怒鳴るようなヴォーカル、そしてむせび泣くようなハープ。相方バディ・ガイのとんがったギター・プレイも、もちろん聴き逃がせない。
(6)では白人・黒人混成のポール・バターフィールド・ブルース・バンドが、リトル・ウォルターの作品をカヴァー。65年リリース。
ヴォーカル、そしてハープはもちろん、バターフィールド。マイク・ブルームフィールドとエルヴィン・ビショップのツートップ・ギターを従えて、堂々のプレイを聴かせてくれる。
白人として初めて黒人街で暮し、ブルースハープを極めた男、バターフィールドの勇姿がここにある。
(7)は、日本ではあまりおなじみでないシンガー/ハーピスト、レイジー・レスター、58年のレコーディング。
ルイジアナ出身で、おもにエクセロ・レコードでレコーディングしているとのことだが、よくは知りまへん。詳しいかた、教えてちょ。
残念ながら歌の方は、お名前通りレイジーかつ一本調子な感じで、お世辞にもうまいとはいえないが、ハープにはキラリと光るものがある。
アンプリファイせず、エコーをかけたサウンドには、独特の透明感がある。
(8)はアラバマ出身のハーピスト、ジェリー・マッケイン、61年の録音。
彼もご多分にもれず、リトル・ウォルターに強くインスパイアされたひとりだそうだが、そのアンプリファイド・サウンドにはウォルターの影響だけでなく、彼ならではの、イナたくも心やすらぐような"味"が感じられる。
初心者のコピーにも最適の、かっちりとよくまとまった佳曲といえるだろう。
(9)は大御所ハウリン・ウルフ、54年リリースのナンバー。
もちろんハープはウルフ自身。格別テクニック的にスゴいという演奏ではないが、ムダのないフレージング、そしていかにもブルースらしい「響き」を持ったプレイである。これまたコピーにうってつけ。
続く(10)はヤードバーズによる「アイ・ウィッシュ・ユー・ウッド」のカヴァーでロック・ファンにもおなじみとなったブルースマン、ビリー・ボーイ・アーノルド55年の録音。
ヘンリー・グレイ、ジョディ・ウィリアムスらを従え、歌とハープで熱演を聴かせてくれる。
彼のハープ・スタイルは、わりと「泣き」の要素が強いもの。ハートにじかに訴えてくるようなプレイだ。
(11)は、ロバジョンの「スウィート・ホーム・シカゴ」をその義理の息子、ロバート・ロックウッドが改作したナンバー。
ハープを演奏するのは、ビッグ・ジョン・レンチャー。このひともあまりおなじみではないが、ミシシッピ州出身、シカゴに出てロバート・ナイトホーク、ジョニー・ヤングらと共演している。
ここではヴォーカル、ギターのジョー・カーターと共演。レンチャ-のプレイは、あまりアクは強くなく、バンド・サウンドのワン・パートとして他とうまく協調・調和しているタイプだ。
(12)はジミー&ウォルター、すなわちジミー・ディベリー(g)とビッグ・ウォルターことシェイキー・ホートン(hca)のコンビによる53年の録音。
スロー・テンポのインスト・ナンバーだが、なんといってもビッグ・ウォルターの縮緬ビブラートがスゴい。
これまでのどのプレイヤーとも異なる、迫力あふれる響きに、ただただ圧倒される。
スローなのでメロディは拾いやすいが、この"響き"をコピーするのは至難の業だ。さすが、本物は違う!
(13)は、軽快なシャッフル・ビートが印象的なブギ。現役最高齢ブルースマンのひとり、スヌーキー・プライヤーの作品。
63年のリリース。歌、ハープともに彼が担当している。
彼の歯切れのいい元気な歌声もいいが、遠い汽笛を思わせるようなハープ・サウンドもまさにブルースそのもので、カッコいい。
(14)はケイ・ラヴをリーダーとするグループ「ホット・ショット・ラヴ」のナンバー。54年リリース。
この曲もブギのビートにのせ、ラヴのファンキーな語りとハープが披露される。
いきなり演奏の途中でとぎれて終わってしまうという、ヘンな曲なのだが、そのへんのテキトーさもブルースっぽくていい。
(15)はその名も、ジョージ・"ハーモニカ"・スミスなるシンガー/ハーピストが歌う、リトル・ウォルターのナンバー。68年録音。
スミスも「リトル・ウォルター命」のハーピストの一人。彼自身はスター・プレイヤーとはなりえなかったが、T・ボーン・ウォーカー、ビッグ・ママ・ソーントン、マディ・ウォーターズら多くのミュージシャンと共演している。
ここでは歌・ハープともに披露している。歌もそこそこ歌えるし(マディっぽい)、ハープのほうも百戦錬磨のつわものらしく、実に堂々としたプレイだ。
その力強いアンプリファイド・サウンドは、まさにリトル・ウォルター二世とよぶに、ふさわしい。
また、バックの顔ぶれが、オーティス・スパン、マディ・ウォーターズらベテラン揃いなのにも注目である。
(16)は、これもヤードバーズのカヴァー(「ベイビー・スクラッチ・マイ・バック」)によりその名が知られるようになったスリム・ハーポのナンバー。57年リリース。
彼のヴォーカル・スタイルは他に類例を見ないユニークなもので、そのあくまでもロー・テンションでクールな歌いぶりは、一度聴いたら忘れられないものがある。
ハープの方も、その歌に通じるものがあり、あくまでもクールなテイストだ。
まさにブルース界の異端児。でもこれもまたブルースのひとつのありかただという気がする。
(17)は、だいぶん時代が下がって、81年リリースの作品。ジミー・ヴォーン率いるブルース・ロック・バンド、「ファビュラス・サンダーバーズ」の登場である。
名ハーピスト、キム・ウィルスンをフィーチャーしたこのナンバーは、ペレス・プラドの大ヒットで知られるマンボの名曲。
全然ブルースでもなんでもないのだが、ハープというメロディ楽器をマンボに持ち込むことにより、新しいハイ・ブリッドなサウンドが生み出されているのが、なんとも面白い。
ラストの(18)は白人ハーピスト、チャールズ・マッセルホワイトによる67年リリースの作品。
曲はジャズ・ピアニスト、デューク・ピアスン作のバラード。たとえていえば、キャロル・キングの「イッツ・トゥー・レイト」のような曲だ。
ジョン・メイオールのバンドにもいたハーヴィー・マンデル(g)、フレッド・ビロウ(ds)など、ブルース系のミュージシャンを使って、コアなジャズの曲をやるという、なかなか面白い試みだが、これがけっこう成功している。
バターフィールドとわりと近い味わいをもつ、マッセルホワイトのハープのメロウな響きが、意外とマイナー・バラードにしっくりと合うのである。
(17)のケースと同様に、ブルースハープは音楽のジャンルを超えて、自由自在に活躍出来るってこと、である。
その構造は実に単純ながら、ハープという楽器は本当に「無限」の可能性を持っている。
あなたもこの一枚を水先案内人に、広大で底なしに深い「ハープ・サウンド」への航海をしてみてはいかがかな。
<独断評価>★★★★