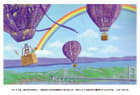「日本人が知らない日本語」の中で「しかとする」と言うのがありましたが、これは無視するという意味で、良く使われています。
「日本人が知らない日本語」の中で「しかとする」と言うのがありましたが、これは無視するという意味で、良く使われています。
これも花札からきたもので、十月の札である鹿の絵が横を向いているので、「鹿十(とう)」 「しかとう」
「しかとう」 「しかと」になったそうです。
「しかと」になったそうです。
「ぼんくら」と言うのも、博打(ばくち)用語で、盆の上の勝負(たぶんサイコロ)に暗い、つまり読みが悪い 頭の働きが悪い、のろまと言う意味になったそうです。
頭の働きが悪い、のろまと言う意味になったそうです。 悪い言葉が流行るのは、早いですね。
悪い言葉が流行るのは、早いですね。
知らないうちに「超」とか、「ださい」とかを、みんなが使うようになっていますね。
私は、きれいな言葉を使いたいと思っているのに、「じゃん」を時々使いますが、埼玉弁の「んだんべー」と言うのは、さすがに使えないですね。「んだんだ(そうだそうだ)」。






 今日は、教会の帰りにバスに乗りましたが、お向かいに座った若い女性と中年の男性の会話が大きく聞こえてきました。
今日は、教会の帰りにバスに乗りましたが、お向かいに座った若い女性と中年の男性の会話が大きく聞こえてきました。
私は、大きな声や音が苦手なので、イライラするよりもいつも耳栓を使います。 まったくシャツトアウトはできませんが、かなり遠くから聞こえているような感じになります。
まったくシャツトアウトはできませんが、かなり遠くから聞こえているような感じになります。
今日の二人は、キャバ嬢と知り合いと言う感じでしたが、しきりに「まどかさんは・・・。」と言うのが聞こえてきました。
 まどかさんは、キャバ嬢の先輩のようで、かなりいい方のようで、悪口でなかったのが、人ごとながらホッとしました。
まどかさんは、キャバ嬢の先輩のようで、かなりいい方のようで、悪口でなかったのが、人ごとながらホッとしました。
 私のペンネームの「まどか まこ」は、高校時代友人の家の近くの男子校の下にあった喫茶店の名前「まどか」から取ったのと、自分の好きな名前「まこ」をくっけただけです。
私のペンネームの「まどか まこ」は、高校時代友人の家の近くの男子校の下にあった喫茶店の名前「まどか」から取ったのと、自分の好きな名前「まこ」をくっけただけです。 どちらも大好きな名前ですが、ある出版者からおふろ絵本を出す時、水商売の源氏名ようだからというので、「加藤まどか」という名前にされてしまいました。
どちらも大好きな名前ですが、ある出版者からおふろ絵本を出す時、水商売の源氏名ようだからというので、「加藤まどか」という名前にされてしまいました。 ついでだから、この際全部変えようかと思いましたが、キリスト教では出版社からだめだと言われました。
ついでだから、この際全部変えようかと思いましたが、キリスト教では出版社からだめだと言われました。 美鈴も外国人には言いにくいようですが、まどかも言いづらいそうです。
美鈴も外国人には言いにくいようですが、まどかも言いづらいそうです。
 昨日、ライブに行く時、待ち合わせに時間があったので、本屋で立ち読みをしました。
昨日、ライブに行く時、待ち合わせに時間があったので、本屋で立ち読みをしました。
「日本人が知らない日本語」蛇蔵&海野凪子を読みましたが、面白かったです。
日本語教師が、いかに外国人の中で苦労しているのかが楽しく漫画で描かれています。
お土産に持って帰りたい物の中に食品サンプル がありましたが、たぶんそうだろうと思いました。
がありましたが、たぶんそうだろうと思いました。
あと、神社にある狛犬と言うのもありました。
また、任侠映画と時代劇で日本語を覚えた方々のやりとりも面白かったです。 それから、ボンクラなど花札がルーツの言葉がいくつもあったのにはびっくりしました。
それから、ボンクラなど花札がルーツの言葉がいくつもあったのにはびっくりしました。
今じゃーお金持ちの奥様が使っている「~ざます。」が吉原の遊女の言葉から来ているというのも、前に聞いたことがありましたがなるほどなーと思いました。 言葉は、時代とともに変化しますが、神の言葉は変わらないのです。
言葉は、時代とともに変化しますが、神の言葉は変わらないのです。