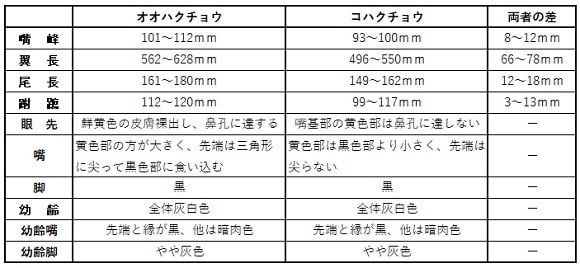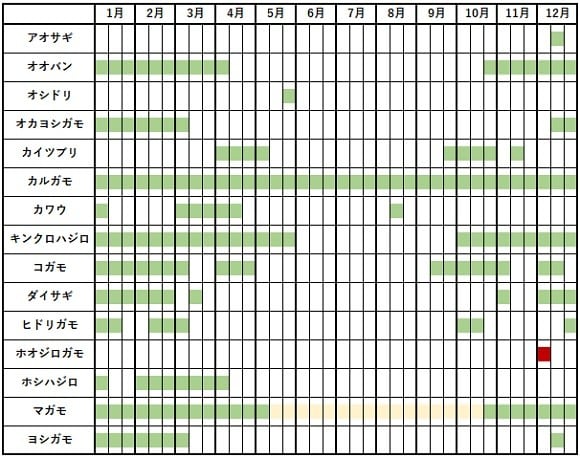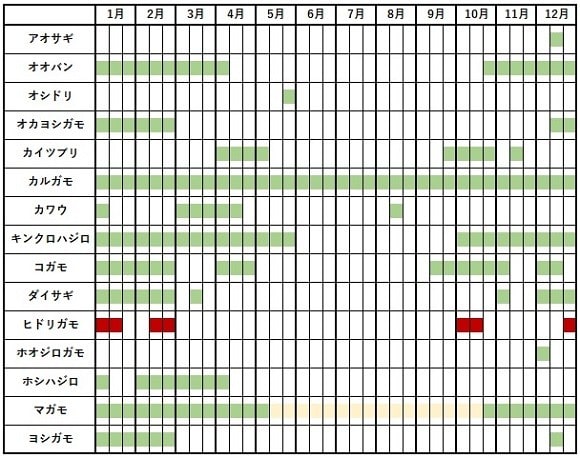今回はサンショウクイ。雲場池を散歩していると、思いがけない野鳥に出会うことがある。この種もそうした一つに数えられる。
池周辺には、ハクセキレイ、セグロセキレイ、キセキレイなどおなじみのセキレイの姿をよく見かける。この鳥を樹上に見た時にも、その長い尾の姿がハクセキレイによく似ているので、そう思ってカメラを向けたが、ファインダー越しに見た姿がどこか違っているとの印象を持った。
帰宅後、妻に写真を見せたところ、やはりハクセキレイではなさそうだということになり、図鑑であれこれ調べた結果落ち着いたのが、サンショウクイであった.
いつもの「原色日本鳥類図鑑」(小林桂助著 1973年保育社発行)でサンショウクイの項を見ると、
「体細長く上面灰青色。嘴峰12~13mm、翼長92~100mm、尾長88~98mm、跗蹠13~15mm、♂は頭の前半は白く、後半と頸とは藍黒色。以下の背面は青灰色。下面は灰白色。嘴は扁平で翼には白はんがある。♀は頭上も背と同じ青灰色で黒色部を欠く。
我国には春季渡来し主として低山帯で繁殖する。ヒリヒリッ、ヒリヒリッ なきながら波状に飛ぶ。冬季は南琉球・台湾・馬来諸島・印度支那半島に渡去、越冬。」とある。
少し変わったこのサンショウクイという名前の由来については、サンショウウオのことかなどと思ったりしたが、植物の山椒のことであった。上記のような鳴き声から、サンショウの辛い実を食べてヒリヒリすると鳴いているとの類推により名前が付けられたというから面白い話である。
別の図鑑には、「枝先にとまって昆虫やクモなどを捕食する・・・」とあるので、実際にサンショウの実を食べるわけではないようである。

サンショウクイ(2022.5.1 撮影)
翌日もまた高い枝先にとまっているところを見かけた。そして、それきりであってその後見ることがない。

サンショウクイ(2022.5.2 撮影)
2日間サンショウクイに出会うことができたのであったが、何か少し引っかかるところがあり、昨年の同じような時期に撮影した写真を見直してみたところ数枚の写真を見つけた。
遠くにいるところを撮影したものであり、当時まだ野鳥を写すための超望遠レンズを入手していなかったので小さく映っている写真だが、拡大してみると、サンショウクイだと判る。

サンショウクイ(2021.4.26 撮影)

サンショウクイ(2021.4.26 撮影)

サンショウクイ(2021.4.28 撮影)
昨年この鳥を撮影して帰宅した時、小さく姿が映っていたこの写真を見て、妻と何の鳥だろうかと話し合い、サンショウクイだろうかと話し合ったことがあるのを思い出した。しかし、そのまま忘れてしまっていた。
水鳥の写真、特にオシドリの鮮明な写真を撮りたいと思い入手した超望遠レンズであるが、その後は小型の野鳥の撮影にも威力を発揮してくれ、最近は雲場池周辺で見ることができる野鳥を多く撮影するようになっている。
しかし、あくまでも早朝散歩のときに偶然見かける種を撮影しているのであって、野鳥の撮影を目的にしているのではない。妻がツイッターでフォローしているある女性アマチュア写真家などは、目指す野鳥の撮影のために、各地に出かけ、一日中森の中に籠もることもある様だが、私にはとてもそんなことはできそうにない。
チョウの撮影となると、さまざまな情報を頼りに発生場所を探し、その季節になると現地に出かけているが、野鳥の場合にはまだそこまで熱心に取り組んでいないので、このサンショウクイ同様、偶然出会った種を撮影している段階にとどまっている。
先日、所用で小諸方面に車で出かけた時、道路わきの電線に1羽の鳥の姿を認め、スピードを落としながら走り抜けた。妻とあれは何の鳥だろうかという話になった。互いにあれこれ候補を挙げたが、きっとサンショウクイだということで、落ち着いた。